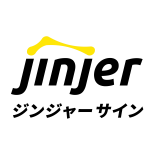「電子契約を導入したいが、自社に最適なサービスが分からない」とお悩みではありませんか?
電子契約は、安易に選ぶと「取引先の負担増」や「業務フローの混乱」を招く恐れがあります。
本記事では、電子契約サービス19選を徹底比較。
コスト・操作性・システム連携など、プロが重視する選定ポイントを詳しく解説します。
さらに、行政書士による専門的なアドバイスや、一目でわかる特徴別の図解も掲載!
自社の課題を解決できる電子契約サービスを見つけたい方は、ぜひ参考にしてください。
▼ おすすめサービスの比較を無料で! ▼

目次
電子契約サービスとは、Web上で契約を完結できるサービスのことです。
PDFなどの電子データに電子署名やタイムスタンプを付与し、契約当事者の「本人性」と、契約内容の「非改ざん性」を担保します。
印刷・押印・郵送といった契約業務を削減でき、契約締結までのリードタイム短縮やコスト削減につながります。
特に、遠方の取引先や複数拠点との契約でも、スピーディーな締結が可能です。
▼ 「電子契約の仕組み」や「電子署名の種類」について知りたい方は、こちらをご覧ください
電子契約サービスを利用した際の、契約締結から保管・管理までの基本的な流れは以下の通りです。
▼ 電子契約の一連の流れを自動化できる!ワークフロー機能の詳細は、こちらの記事をご覧ください
電子契約システムは、導入の目的や企業の規模、取引先の状況に合わせてサービスを選ぶことが重要です。
ここでは、以下の5つのタイプについて、具体的なサービス名も挙げながら解説していきます。

導入実績が豊富な電子契約サービスは、取引先も同じシステムを使っている可能性が高く、お互いの負担を抑えながら導入を進められます。
また、あらゆる企業での導入事例があるため、信頼性も高いのが特徴です。
350万社以上もの導入実績がある「電子印鑑GMOサイン」は、自社グループ内に電子証明書を発行する電子認証局「GlobalSign」を持つため、法的効力やセキュリティ面でも安心して利用できます。
契約書管理までできる電子契約サービスは、契約ライフサイクル全体の効率化を図りたい場合に最適です。
「ContractS CLM」では、契約書の作成から管理までのプロセスを完結できるのに加え、修正履歴のバージョン管理や法務担当者への相談機能なども搭載しています。
契約数が多く、契約内容の追跡やガバナンス強化を重視する企業におすすめです。
紙の契約書も一元管理できる電子契約サービスは、電子と紙の契約書が混在している企業におすすめです。
たとえば、「イースタンプ」なら、過去に締結した紙の契約書もスキャンして電子契約と一緒に保管・検索・管理することができます。
低コストの電子契約サービスは、電子契約を試験的に導入したい企業に最適です。
「契約大臣」では、月額固定費が安価に設定されており、月20件までなら月額4,400円(税込)といったプランで手軽に利用できます。
そのほか、初期費用と基本料金が0円の「ベクターサイン」もおすすめです。
多言語対応の電子契約システムは、海外企業との契約締結が多い企業や、グローバル展開を進めている企業に適しています。
たとえば、世界170万社で利用されている「Docusign eSignature」は、44もの言語に対応しており、海外の取引先とのスムーズな契約締結が可能です。
電子契約サービスを選ぶ際は、複数の視点から比較検討しましょう。
ここでは、特に重視すべき6つのポイントをわかりやすく解説します。
電子署名には主に「当事者型」と「立会人型」の2種類があり、いずれも電子署名法に基づいて法的効力が認められています。
「当事者型」は、契約者本人の電子証明書を利用して電子署名を行う方式です。
本人確認の信頼性が高く、より強い法的効力を求める契約に適していますが、取引先にアカウント作成の負担があったり、同じサービスを利用していないと契約できなかったりする場合があります。
一方、「立会人型」は、電子契約サービス事業者が契約締結の立会人となり電子署名を行う方式です。
取引先がアカウントを作成する必要がなく、スピーディーに契約を進められます。
どちらを選ぶかは、「法的効力の強さ」と「運用のしやすさ」のどちらを優先するかで判断しましょう。
最近では、どちらにも対応できる「ハイブリッド型」の電子契約サービスも登場しており、取引内容や相手に応じて柔軟に使い分けることが可能です。
| 立会人型署名 | 当事者型署名 | |
| 特徴 | 電子契約システムが契約締結の 立会人となり電子署名を行う |
契約者本人の電子証明書を 利用して電子署名を行う |
| 証拠力 | 十分にあるが なりすましリスクがある |
非常に強い なりすましリスクが低い |
| かかる時間 | メール認証のためスピーディ | 証明書取得に時間を要する |
| 取引先の負担 | 小さい 多くがアカウント登録不要 (費用負担なし) |
大きい 同じ電子契約システムの利用が必須 (費用負担あり) |
まずは自社の課題を洗い出し、電子契約サービスに何を解決してほしいのか、将来的にどのように業務を改善したいのかを具体的にしましょう。
たとえば、紙の契約書をなくすといったペーパーレス化が目的であれば、基本的な機能で十分なケースが多いです。
しかし、契約の締結から管理・更新まで一元的に効率化したい場合には、多機能でカスタマイズ性の高いサービスが必要になります。
電子契約を導入する際は、信頼性の高いサービスを選ぶことが重要です。
知名度が低いサービスの場合、取引先が不安に感じたり、導入の説明に時間がかかることもあります。
その点、「電子印鑑GMOサイン」のような導入企業数や累計送信件数を公表し、豊富な実績があるサービスであれば取引先の理解も得やすく、スムーズに契約を進められる可能性が高まります。
▼ 電子契約サービスのシェアランキングを知りたい方は、こちらの記事もご覧ください
自社の業種や契約形態に合った機能が備わっているかを確認しましょう。
たとえば、契約書の保管期限は会社法で10年と定められており、タイムスタンプの有効期限も最長10年です。
10年以上の長期契約を結ぶ場合は、有効期限を延長できる長期署名対応のシステムを選びましょう。
また、業種によって必要な書類が異なったり、企業ごとに契約承認のフローが違うこともあるため、カスタマイズの自由度もチェックしておくとスムーズに運用できます。

行政書士
石下貴大氏
業種によって契約書の形式は異なり、IT系では詳細の仕様書を添付することがあったり、建設業では許可証とのセットでの管理が必要となる場合も。自社の業務フローにあった使い方ができるかの確認は必須です。
電子契約サービスを選ぶ際は、APIを利用したシステム間連携が可能かをチェックしましょう。
たとえば、AI契約書レビューサービスと連携できるシステムであれば、リーガルチェックを自動化でき、ミスの防止や作業時間の短縮につながります。

行政書士
石下貴大氏
最近は契約周りだけでなく、顧客管理や支払いなど様々なワークフローのDX化が加速しているため、電子契約単体だけでなく「チャットシステムや経費精算システムと繋げるかどうか」によって将来的な使いやすさが左右されます。外部連携の自由度は必須確認項目。
高機能なサービスほど初期費用や月額料金が高くなる傾向がありますが、必ずしも高価なものが良いとは限りません。
重要なのは、自社にとって必要な機能がしっかり備わっているかどうかです。
無料トライアルやデモ画面を活用したり、他社の事例やレビューを参考にしたりしながら、納得のいく費用対効果の高いサービスを選びましょう。
電子契約システムの費用は大きく「基本料金」と「契約書送信料」の2つで構成されています。
| 基本料金 | + | 契約書送信料 |
| 月額固定 ※ユーザー数や機能などによって決定 →無料~数万円(おおむね10,000円前後) |
従量課金 ※契約書の送信件数によって決定 →100~200円程度/件 |
実際にかかる費用は、月当たりの契約件数やオプション利用によって変動するため、見積もりをたてておきましょう。
▼ 電子契約の費用や相場について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください
| ツール名 | タイプ | 月額基本料 | 電子署名 | 無料プラン | API連携 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
 電子印鑑GMOサイン
電子印鑑GMOサイン
|
導入実績が豊富
|
8,800円~ ※1
|
立会人型・当事者型
|
⭕️
|
⭕️
|
契約書ごとに署名方法が選べる
|
 クラウドサイン
クラウドサイン
|
導入実績が豊富
|
10,000円~ ※1
|
立会人型
|
⭕️
|
⭕️
|
サービス導入率No.1の圧倒的知名度
|
 CONTRACTHUB@absonne
CONTRACTHUB@absonne
|
導入実績が豊富
|
要問合せ
|
立会人型・当事者型
|
❌
|
要問合せ
|
法律のエキスパートが対応
|
 クラウドリーガル
クラウドリーガル
|
契約書管理までできる
|
11,000円~ ※2
|
要問合せ
|
トライアルあり
|
⭕️
|
専門家の法務サポートがある法務クラウドサービス
|
 LegalOn(旧LegalOn Cloud)
LegalOn(旧LegalOn Cloud)
|
契約書管理までできる
|
10,000円~ ※2
|
―
|
❌
|
⭕️
|
各法務体制の連携や、無限拡張が可能
|
 電子契約システム(日本情報クリエイト株式会社)
電子契約システム(日本情報クリエイト株式会社)
|
契約書管理までできる
|
要問合せ
|
立会人型
|
デモあり
|
要問合せ
|
不動産業界専用電子契約システム
|
※1 税抜 ※2 税表示なし ※3 税込
▼

「電子印鑑GMOサイン」は、導入企業数が350万社を超えるクラウド型電子契約サービスです。契約の締結から管理までをワンストップで行えるため、契約締結にかかる手間や時間の大幅に短縮できます。
また、国内最大手の電子認証局「GlobalSign」の技術を使っているため、安全性がとても高く、安心して契約を進められます。
| 電子署名方法 | 立会人型/当事者型 |
| おすすめ企業規模 | 中小企業から大企業まで |
| 主な導入実績 | 350万社以上、累計送信件数3,000万件超 |
| タイムスタンプ | あり |
| セキュリティ機能 | メールに電子署名、二要素認証、IPアドレス制限 |
| API連携 | 10カテゴリ以上の外部サービスと連携可能 |
| セキュリティ認証の 取得状況 |
ISO 27001、ISO 27017、ISMAP、SOC2 Type2、JIIMA認証 |
| 取引先のアカウント登録 | 当事者型を相手に求める場合は、取引先も電子印鑑GMOサインの利用が必要 |

行政書士
石下貴大氏
「電子印鑑GMOサイン」は、GMOの知名度、大手の信頼度が高いシステム。汎用的な分、カスタマイズの細かさがどこまでできるかを商談時にしっかり確認するようにしましょう。
| お試しフリープラン | 契約印&実印プラン | |
| 月額(税抜) | 0円 | 8,800円 |
| 登録ユーザー数 | 1 | 無制限 |
| 送信数 | 上限5件/月 | 無制限 |
| 署名方法 | 立会人型 | 立会人型/当事者型 |
| 送信料 | 0円 | 契約印タイプ:100円/件 実印タイプ:300円/件 |
詳しくは以下の資料を無料ダウンロードしてご確認ください。

IT/通信/インターネット
251〜500人
他社サービスと比較し圧倒的にコスパが高い





・立会人型と当事者型の電子署名を柔軟に使い分けられ、取引先の状況に応じて最適な契約方法を選択可能
・APIを活用した社内システムとの連携により、契約書作成から承認までの一連の流れを自動化できる
・セキュリティ面が充実しており、暗号化やバックアップ体制が整っているため安心感がある

小売/流通/商社
251人〜500人
高度なカスタマイズは難しい





・特定の業務フローに合わせた高度なカスタマイズが難しく、汎用的な設定に限られている。
・他のビジネスツールとの連携が限られており、特にSalesforceやMicrosoft Officeなど主要なツールとの深い統合が課題。
・大規模な組織で多くのユーザーを管理する際に、ユーザー権限の設定や管理が煩雑で手間がかかった。

「クラウドサイン」は、弁護士監修のもと開発された国内で圧倒的な利用実績を誇る電子契約システムです。立会人型電子契約システムとして初めて、電子署名法が定める「電子署名」に該当することを法務省・デジタル庁に認められています。
必要な機能が網羅されており、シンプルなUIで操作も簡単です。
| 電子署名方法 | 立会人型 |
| おすすめ企業規模 | 中小企業から大企業まで |
| 主な導入実績 | 250万社以上、累計送信件数1,000万件超 |
| タイムスタンプ | あり |
| セキュリティ機能 | 二要素認証や暗号化通信を採用 |
| API連携 | Microsoft Teamsやkintoneなど、多数の外部サービスと連携可能 |
| セキュリティ認証の 取得状況 |
ISO 27001、ISO 27017、ISMAP、SOC2 Type1 |
| 取引先のアカウント登録 | 高度な認証による署名では、取引先のアカウント登録が必要 |

行政書士
石下貴大氏
「クラウドサイン」は、大手である分、導入の安心度が高い。弁護士ドットコム社による弁護士監修があるという信頼度も強みです。実際はベンチャーなどでも多数導入されていますが、大企業での導入実績が目立ちますね。
月額に送信費用200円/1件を合わせた金額になります。
すべてのプランで「ユーザー数・送信件数」は無制限となります。
| Light | Corporate | Business | Enterprise | |
| プラン | 個人事業主や少人数の企業向け | 電子契約・書類管理の機能を備えた一般企業向け | 内部統制・セキュリティを強化する機能を追加 | 全社利用を想定された企業向けの書類管理機能を追加 |
| 月額 (税抜) |
10,000円 | 28,000円 | 要問合せ | 要問合せ |
| 送信料 (税抜) |
200円/件 | 200円/件 | 要問合せ | 要問合せ |
詳しくは以下の資料を無料ダウンロードしてご確認ください。

IT/通信/インターネット
11人〜30人
邱 世偉
業務効率化間違いなし!しかし、細部に難あり。





検索機能がある点は極めて便利だと感じました。これがあることによって書類を保存する手間、管理する手間、紛失するリスク、また必要なときに探す手間、全てなくなります。唯一残念なのは、文字が多くなると名前や住所といった基本情報が枠からはみ出たり、文章に被ってしまうことです。

IT/通信/インターネット
1人
鐘ヶ江由美
ペーパーレス化して本当に良かったです





ペーパーレスでネット上で完結できるのが何より業務しやすいと思いました。電子契約になれば時間のロスを減らすことが出来るのが魅力的です。メールを開いたら契約書をすぐ読めて、内容を承諾し、名前と住所を入力するだけで契約が出来ます。

画像出典元:「CONTRACTHUB@absonne」公式HP
「CONTRACTHUB@absonne(コントラクトハブ)」は、50万ユーザー以上が利用する電子契約サービスです。購買・販売・会計などの基幹システムと連携しやすいAPIも提供されており、既存の業務フローに組み込んで運用できます。
専門のコンサルティンググループと電子契約に関する法律・税務のエキスパートがこまめに対応してくれるので、電子契約導入に不安を抱えている企業におすすめです。
| 電子署名方法 | 立会人型/当事者型 |
| おすすめ企業規模 | 中堅企業から大企業まで |
| 主な導入実績 | 製造業、金融業、流通業など多岐にわたる |
| タイムスタンプ | あり |
| セキュリティ機能 | アクセス制御、操作ログ管理、データ暗号化など |
| API連携 | 基幹システムやワークフローシステムとのAPI連携が可能 |
| セキュリティ認証の 取得状況 |
電子取引ソフト法的要件認証 |
| 取引先のアカウント登録 | 当事者型を利用する場合には、取引先も電子証明書の登録が必要 |
署名タイプを自由に選択し、文書登録の分だけ料金が発生するシステムとなっています。
より選択ができます。詳しくは公式HPよりご確認ください。

不動産/建設/設備
31人〜50人
時間と費用の削減ができて嬉しい





収入印紙の関係での経費がかなり抑えられる。また、契約書類の郵送や、相手先まで直接持っていくなどの時間と費用が削減できるため、コスト削減が見込まれる。こうした面から是非お勧めしたい。

不動産/建設/設備
31人〜50人
バグにより作業できない時間が発生した





・午前中に使用するとなぜが表示にバグが生じ、午前中は使い物にならなかった。契約書の提出期限が迫っているときにこのバグが生じると、血の気が引く思いをした。
画像出典元:「クラウドリーガル」公式HP
「クラウドリーガル」は、専門家の法務サポートと生成AIの融合によって、企業の法務・労務の課題を効率的かつリーズナブルに解決へと導く法務クラウドサービスです。
弁護士監修のフォーマットを利用し契約書作成・電子契約・管理もワンストップ。得意領域の異なる複数の事務所の提携弁護士が在籍しているため、企業の多様な法務課題に対応可能です。
| 電子署名方法 | 立会人型 |
| おすすめ企業規模 | 中小企業から大企業まで |
| 主な導入実績 | 取扱い契約書数10,000通以上、利用者数5,000社以上 |
| 法的サポート | 企業法務の経験が豊富な弁護士に相談可能 |
| 契約書作成 | カスタマイズ可能で用途に合った契約書を自動作成 |
| 外部連携 | Slack |
| セキュリティ認証の 取得状況 |
ISO/IEC 27001:2022 |
| 取引先のアカウント登録 | 登録不要 |
クラウドリーガルには3つのプランがあり、いずれも年間契約での料金となっています。
プランに含まれていない作業については、作業所要時間×時間単価(税別3万円)で依頼することができます。
会社登記と商標出願は別途費用がかかります。
詳細はお問合せ下さい。
| ブロンズ | シルバー | ゴールド | エンタープライズ | |
| 月額料金 | 11,000円 | 55,000円 | 110,000円 | 要問合せ |
| サービス 内容 |
|
|
|
要問合せ |
| カスタム ワーク |
- |
2時間/月
|
5時間/月
|
要問合せ |
| 追加依頼 割引率 |
10% | 20% | 30% | 要問合せ |
※税表記なし

「LegalOn(リーガルオン)」は、AI技術を核とした法務支援プラットフォームです。AIが契約書の抜け漏れやリスク、法令遵守状況などを自動でチェックし、修正案を提示してくれます。各法務体制の連携や、無限拡張が可能なため、将来的に会社規模が拡大するという場合でも安心です。
また、LegalOn上で業務を行うことで自然とナレッジが蓄積され、それをAIが整理してくれます。欲しい時に欲しい情報をAIがレコメンドしてくれる環境が実現可能です。
| 電子署名方法 | ― |
| おすすめ企業規模 | 中小企業から大企業まで |
| 主な導入実績 | 多岐にわたる業種での導入実績があり |
| タイムスタンプ | ― |
| セキュリティ機能 | 第三者機関による脆弱性診断を実施など |
| API連携 | GMOサイン、ドキュサイン、クラウドサインとの電子契約と連携 |
| セキュリティ認証の 取得状況 |
― |
| 取引先のアカウント登録 | 要問合せ |
LegalOnは、利用するストレージ容量などに応じて基本プランを選択可能です。
基本プランのみの利用は不可で、強化したい機能やオプションによって料金が異なるため、詳細はお問い合わせが必要です。
選択できるオプション:契約審査・案件管理・契約管理・電子契約 など
また、強化したい機能によっては、基本プラン料金が発生しない場合もあります。
| 基本プラン | 基本料金(税抜) |
| Growth | 1万円 |
| Business | 3万円 |
| Enterprise | 10万円 |
※上記基本プラン料金に別途1アカウントにつき税込220円~330円かかります。
詳しくは以下の資料を無料ダウンロードしてご確認ください。

画像出典元:「電子契約システム(日本情報クリエイト株式会社)」公式HP
「日本情報クリエイト株式会社が提供する電子契約システム」は、不動産業界に特化した電子契約サービスです。
不動産業界特有の多岐にわたる関係者と、複雑な契約のステップをしっかりシステムに落とし込めます。全国30拠点のサポート拠点があるため、導入後も安心です。
| 電子署名方法 | 立会人型 |
| おすすめ企業規模 | 中小企業から大企業まで |
| 主な導入実績 | 約7,521社との取引実績 |
| タイムスタンプ | あり |
| セキュリティ機能 | 二要素認証、セキュアなクラウド環境 |
| API連携 | 要問合せ |
| セキュリティ認証の 取得状況 |
ISO/IEC 27001:2022 |
| 取引先のアカウント登録 | 登録不要 |
日本情報クリエイト株式会社の料金プランについては、問い合わせが必要です。
システムの概要については、以下の資料を無料ダウンロードしてご確認ください。

画像出典元:「ジンジャーサイン」公式HP
ジンジャーサインは、契約書の送付が最速1分で完了する、簡単操作で使いやすいクラウド型の電子契約サービスです。
賃貸契約をはじめ、雇用契約書、秘密保持契約書、社内用の誓約書、納品書、検収書など、多様な文書に対応。
紙で締結した契約書も、電子締結した契約書と共にフォルダや管理項目ごとの一元管理が可能です。
| 電子署名方法 | 立会人型 |
| おすすめ企業規模 | 中小企業から大企業まで |
| 主な導入実績 | シリーズ全体で高い導入実績 |
| タイムスタンプ | あり |
| セキュリティ機能 | TLS暗号化、第三者による脆弱性診断、不正アクセス防止対策、災害対策など |
| API連携 | ジンジャーAPIを使い外部システムやソフトウェアとの連携が可能 |
| セキュリティ認証の 取得状況 |
ISO/IEC 27001:2013、JIS Q 27001:2014 |
| 取引先のアカウント登録 | 登録不要 |
ジンジャーサインの料金は、要問い合わせになります。

「ContractS CLM(コントラクツ CLM)」は、電子契約締結だけでなく”契約の作成・相談・承認・締結・更新管理”をすべて1つのツールで対応できる契約管理ソリューションです。Word編集機能やナレッジマネジメント機能も備えており、契約プロセス全体の効率化を実現してくれます。
「システム導入によって契約関連業務すべてを効率化したい」という企業に向いています。
| 電子署名方法 | 立会人型 |
| おすすめ企業規模 | 中小企業から大企業まで |
| 主な導入実績 | 多様な業種・規模の企業で導入実績あり |
| タイムスタンプ | あり |
| セキュリティ機能 | アクセス権限の設計、契約プロセスの可視化、情報集約によるリスク回避 |
| API連携 | 他システムとの柔軟な連携が可能 |
| セキュリティ認証の 取得状況 |
ISO 27001 |
| 取引先のアカウント登録 | 登録不要 |

行政書士
石下貴大氏
「ContractS CLM」は、テンプレートの使いやすさが強み。ですが、実際の締結場面では、テンプレートそのままで利用できるわけではないので、ある程度の法務知識レベルをもった担当者におすすめのシステム。上位版を利用すればカスタマイズもかなり自由に行えます。
「初期費用」+「月額基本料金」+「オプション」という料金体系になっています。
「月額基本料金」は使用量に応じて変動する可能性があります。
詳細については公式HPよりお問い合わせが必要です。

サービス
11人〜30人
契約や承認業務が日常化している会社におすすめ





毎回PDFから紙に印刷をして承認をもらった後に、再度PDF化してから先方にメールで送るなど作業工程がとにかく多く、時間がかかっていました。操作方法に関してもマニュアルから動画解説まであるので、いままで2~3日かかっていた作業が当日で完了できるまでに効率化されました。

コンサル
51人〜100人
中小企業にはお勧めしない





ペーパーレス化することで、電子系に慣れていないクライアントが困惑するという事態が発生するので、一概にすべて電子化することがいいとは思いませんでした。
「freeeサイン」は、弁護士監修の契約書テンプレートが豊富に用意されている電子契約システムです。
kintone連携やSalesforce連携も可能で、契約情報の管理をさらに簡素化・自動化できます。使いやすさの点でも高評価を獲得しており、ITリテラシーがあまり高くない企業からも支持を得ています。
| 電子署名方法 | 立会人型 |
| おすすめ企業規模 | 中小企業から大企業まで |
| 主な導入実績 | 多業種で導入実績あり |
| タイムスタンプ | あり |
| セキュリティ機能 | 二要素認証、暗号化通信、アクセス制限機能 |
| API連携 | kintone、Salesforceなど、多数の外部サービスとも連携可能 |
| セキュリティ認証の 取得状況 |
ー |
| 取引先のアカウント登録 | 登録不要 |

行政書士
石下貴大氏
「freeeサイン」は、汎用性とカスタマイズ性のバランスが優れている。認知度の面でいっても一番強いシステムと言えます。ただし、freeeと連携しているため、現在マネーフォワードクラウドや弥生シリーズなどを利用している企業では連携のしづらさがネックになる可能性はあります。
| Starter | Standard | Advance / Enterprise | |
| 実質月額 年一括 (税表記なし) |
5,980円/月 71,760円/年 |
29,800円/月 357,600円/年 |
要問合せ |
| 基本ユーザー数 | 1 | 10 | 50~ |
| 電子サイン無料枠 | 50通/月 | 100通/月 | 300通/月~ |
Salesforceやkintoneと連携できるプランもありますので、詳しくは公式HPよりお問い合わせが必要です。

輸送/交通/物流/倉庫
51人〜100人
大森裕
人事労務管理と一緒に管理できる





お客さんに送付した際に、お客さんがわからないケースもサポートしてくれる。
対社外の問題は相手の協力が必要なのですぐ運用するのは難しいが、対社内の問題は比較的早く取り組める。入社時の書類や労働契約などを電子化するのは非常に良いので是非使ってみてほしい。

サービス/外食/レジャー
2人~10人
尾田聖也
送信相手側の入力項目もカスタマイズできる





主に顧客との売買契約書が中心だが、送信相手側の入力項目も自由にカスタマイズできるため、フォームに応じた項目設計が可能なのは嬉しい。紙面での契約書やりとりが基本となっている会社におすすめしたい。

プロトスター株式会社代表取締役
31人〜50人
前川英麿
月間で考えれば、約10時間のコスト削減につながっている





取引先から契約書の修正依頼があっても、全てfreeeサイン上で対応でき、毎契約書の送信が1、2分で完結できています。

画像出典元:「マネーフォワード クラウド契約」公式HP
「マネーフォワード クラウド契約」は、契約書の作成から管理までを完結できる電子契約サービスです。社内申請・承認のワークフロー機能を標準搭載しており、自社の運用ルールに合わせた承認ルートを設計できます。
また、他の電子契約サービスで締結した契約データも自動で取り込み、一元管理することが可能です。
| 電子署名方法 | 立会人型 |
| おすすめ企業規模 | 個人事業主から大企業まで |
| 主な導入実績 | 多業種で導入実績あり |
| タイムスタンプ | あり |
| セキュリティ機能 | 暗号化通信、サーバー自動監視、サーバーアクセス制限、IPアドレス制御 |
| API連携 | Slackなどと連携可能 |
| セキュリティ認証の 取得状況 |
ISO 27001、SOC 1 Type 2、SOC 2 Type 2 |
| 取引先のアカウント登録 | 登録不要 |
フル機能のプランと、まずは電子契約をはじめたい方向けに2,480円/月〜のプランがあります(法人向け)。
詳細については公式HPよりお問い合わせが必要です。

不動産/建設/設備
2人〜10人
わかりやすいデザインと定額制の料金体系で安心





・いくつかクラウド契約の会社を検討したが、他社に比べて安くわかりやすくサポートもよかった。
・契約書作成ー申請ー承認ー締結ー保存ー管理まで、サポートしてくれる。
・紙の契約書も電子契約もまとめて管理してくれる。
・マネーフォワードとの連携とUXが優れている使いやすい。

非公開
1001人以上
ユーザー数によって料金が変動する





・締結完了までいった契約書をフォルダで分けて管理できない。
・使用中に動きが悪くなってしまうことがある。
・ユーザー数によって料金が変動する。
・カスタマイズ性がちょっと低いところがある。
 画像出典元:「イースタンプ」公式HP
画像出典元:「イースタンプ」公式HP
「イースタンプ」は、契約作業や関連書類をすべてクラウド上で処理・管理できる電子契約サービスです。タブレットやスマートフォンなどで、契約締結の押印の代わりに手書きサイン機能を利用することもできます。
利用開始に必要な操作方法・疑問点・運用方法についての徹底したサポートがあり、初心者におすすめです。
| 電子署名方法 | 認印タイプ/実印タイプ |
| おすすめ企業規模 | 中小企業から大企業まで |
| 主な導入実績 | 多岐にわたる業種での導入実績あり |
| タイムスタンプ | あり |
| セキュリティ機能 | 手書きサイン機能、スキャン保存機能、画像添付機能など |
| API連携 | 要問合せ |
| セキュリティ認証の 取得状況 |
ISO 27001、SOC 2 Type2 |
| 取引先のアカウント登録 | 実印タイプの場合は必要 |
料金については公式HPよりお問い合わせが必要です。

IT
251人〜500人
印刷にかかる手間や費用を減らせる





従来使っていた紙の契約書は100枚近くあったのですが、スキャンするだけでデータ化できたので、紙の契約書をすべてデータ化することが5分程度の時間で完了できました。

建設業
1001人以上
クラウドサインの方が使いやすい





クラウドサインの方が、認知度も高く、他の会社も利用しているため、契約がすんなり行きます。他にも、クラウドサインはオプションが多く弁護士がバックについていることも心強いです。
画像出典元:「WAN-Sign」公式HP
「WAN-Sign(ワンサイン)」は、紙と電子の契約書を高セキュリティ環境下で一元管理できる電子契約・契約管理サービスです。
署名依頼メールの再送や文書テンプレートなど、電子契約をスムーズに行うための機能も豊富に用意されています。
| 電子署名方法 | 立会人型/当事者型 |
| おすすめ企業規模 | 中小企業から大企業まで |
| 主な導入実績 | 200社以上の上場企業で導入 |
| タイムスタンプ | あり |
| セキュリティ機能 | AATL(Adobe認定証明書)採用、IPアドレス制限 など |
| API連携 | 利用中のワークフロー・ CRM・基幹システムと連携可能 |
| セキュリティ認証の 取得状況 |
ISO 27001、ISO 27017 |
| 取引先のアカウント登録 | 当事者型の場合は必要 |
WAN-Signの料金体系は、初期費用や月額基本料が0円で、利用した分だけ費用が発生する従量課金制です。
| 署名タイプ | 項目 | 無料プラン | 有料プラン | |
| 当事者型 (実印版) |
電子契約締結 | 締結3件まで/月 | 300円/件 | |
| 電子署名* 利用料 |
8,000円/年 | |||
| 電子データ管理料 | 累計10件まで | 5,000件ごとに 10,000円/月 |
200GB(40万件)で 30,000円/月 以降100GBごとに 10,000円/月 |
|
| 立会人型 事業者署名 (認印版) |
電子契約送信 | 署名依頼送信 10件まで/月 |
100円/件 | |
| 電子データ管理料 | 累計10件まで | 5,000件ごとに 10,000円/月 |
200GB(40万件)で 30,000円/月 以降100GBごとに 10,000円/月 |
|
(税抜)
* 実印版利用には、無料プラン・有料プランともに電子証明書の発行が必要です(1署名者につき8,000円/年)
また、紙で保管している契約書を電子化し、WAN-Sign内で一元管理するためのオプションも提供しています。
全件電子化:75,000円〜/箱
オンデマンド電子化:30,000円〜/箱

メーカー
1001人以上
実印と同様の契約締結ができ、セキュリティー面も安心





自社独自の電子証明書を発行できる点が良かったです。なるべく法的効力の強い電子契約を結びたかったので、実印での契約と同様のスタイルで契約を結べるのは大きなメリットだと思います。

郵送/交通/物流/倉庫
31人〜50人
スマホでは扱いづらい





スマートフォンで作成する場合は扱いづらいです。画面をタップしても反応が鈍いことがあったり、実際に作成したデータを印刷すると文字がずれていたりと、この辺りの改善の必要性を感じました。
画像出典元:「BtoBプラットフォーム契約書」公式HP
「BtoBプラットフォーム 契約書」は、他のBtoBプラットフォームシリーズと連携させることで、契約書だけではなく、見積・受発注・請求の際の帳票類をすべて電子データ化できる電子契約サービスです。
契約書に関連する他の書類を紐付ける「関連付け機能」も備わっています。
| 電子署名方法 | 立会人型 |
| おすすめ企業規模 | 会社/従業員規模、業種を問わずすべての企業 |
| 主な導入実績 | 利用企業数は全体で110万社以上 |
| タイムスタンプ | あり |
| セキュリティ機能 | 最新のブロックチェーン技術を採用 |
| API連携 | 契約書の発行と受領がシームレスに連携可能 |
| セキュリティ認証の 取得状況 |
ISO 27001、ISO 27017 |
| 取引先のアカウント登録 | 無料会員としての登録が必要 |
BtoBプラットフォーム 契約書の具体的な料金プランや月額費用に関する詳細については問い合わせください。
取引先は無料会員のまま、さまざまな便利機能やセキュリティ機能が利用可能です。

不動産/建設/設備
101人〜250人
UIが非常に見やすくわかりやすい





・UIが非常に見やすくどこを触ればよいのか非常にわかりやすい
・マニュアルが適宜開ける位置にポップアップされている
・専属のシステム担当とメールでやりとりが可能であり、不明点が聞きやす

非公開
1001人以上
契約相手にも登録してもらう必要あり





・現在の契約書のステータスが(未処理、差し戻し、締結済み、終了、取り消し)それぞれタブに分かれて表示されており、いちいちそのタブに移動しないと現在どの契約書が進行済みなのかわからないので不便です。
・専用のメールアドレスをヒアリングするなど事前に準備が必要なので、そこは一手間かかるなと思っています。

画像出典元:「契約大臣」公式HP
「契約大臣」は、本格導入前に試してみたい中小企業やフリーランスにおすすめな電子契約システムです。
納得いくまで無料で試せるフリープランがあるので、電子契約の導入が初めての企業でも安心して始められます。
サービス契約中であれば、締結した契約書データはすべて自動的に無料で保存され、いつでも閲覧・管理が可能です。
| 電子署名方法 | 立会人型 |
| おすすめ企業規模 | 中小企業から大企業まで |
| 主な導入実績 | 弁護士事務所や各種コンサルティングなど多岐にわたる |
| タイムスタンプ | あり |
| セキュリティ機能 | 二要素認証・暗号化通信・アクセス制限 |
| API連携 | 利用中の外部システムと連携可能 |
| セキュリティ認証の 取得状況 |
電子取引ソフト法的要件認証 |
| 取引先のアカウント登録 | 登録不要 |
送信件数5件・ユーザー数1名までのフリープランがあります。
| フリープラン | スターター プラン |
ベーシック プラン |
プレミアム プラン |
|
| 年払い時の月額(税込) | 0円 | 4,400円 | 6,600円 | 9,900円 |
| 送信件数/月 | 5件 | 20件 | 50件 | 100件 |
| ユーザー数 | 1名 | 1名 | 無制限 | 無制限 |
年払い時は1ヶ月分がお得になります。
101件以上送信の場合は、公式HPにてお問い合わせが必要です。

画像出典元:「Shachihata Cloud」公式HP
「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」は、豊富なセットプランが用意されており、最も安価なプランでは220円(税込・利用者/月額費用)から利用できる電子決裁サービスです。
15日間のトライアルもあり、電子印鑑やワークフローをはじめ、多くの有料オプションを無料で利用できます。
| 電子署名方法 | 立会人型 |
| おすすめ企業規模 | 中小企業から大企業まで |
| 主な導入実績 | 導入数101万件 |
| タイムスタンプ | あり |
| セキュリティ機能 | 二要素認証、暗号化通信、アクセス制限 |
| API連携 | 他システムとのAPI連携が可能 |
| セキュリティ認証の 取得状況 |
電子取引ソフト法的要件認証 |
| 取引先のアカウント登録 | 登録不要 |
15日間の無料トライアルあり。
電子印鑑や保管の標準機能に加え、用途別にセットプランが用意されています。
| プラン名 | 月額料金/ユーザー(税込) |
| 業務の見える化・ナレッジを強化したい方 コミュニケーション満足セット |
220円 |
| 従来の運用方法のまま業務効率化したい方 ワークフロー充実セット |
330円 |
| 電帳法対策で書類保管を強化したい方 文書管理充実セット |
220円 |
| 人が増えてセキュリティを強化したい方 セキュリティ強化セット |
220円 |
詳しくは公式HPをご覧ください。

「SignTime(サインタイム)」は、気軽に始められる価格とコストパフォーマンスの高さが特徴の電子契約サービスです。ユーザー数に制限がないため、利用者が増えても追加の費用が発生しません。
電子契約に欠かせない多くの機能が基本料金に含まれており、オプション費用を抑えられます。
| 電子署名方法 | 立会人型 |
| おすすめ企業規模 | 中小企業から大企業まで |
| 主な導入実績 | 多様な業種・業界での導入実績あり |
| タイムスタンプ | あり |
| セキュリティ機能 | 二要素認証、アクセスコード設定、署名ページの有効期限設定 |
| API連携 | SalesforceやGoogle Driveなどの外部サービスと連携可能 |
| セキュリティ認証の 取得状況 |
ー |
| 取引先のアカウント登録 | 登録不要 |
無料・無期限で10通まで電子契約を締結できるフリープランもあります。
| 電子契約 | プライムスタート | プライムプラン | |
| 年払い時の月額 (税込) |
7,880円 | 25,600円~ | 55,600円~ |
| 電子契約書類 | 50通/月~ | 50通/月~ | 50通/月~ |
詳しくは公式HPよりお問い合わせが必要です。
 画像出典元:「ベクターサイン」公式HP
画像出典元:「ベクターサイン」公式HP
「ベクターサイン」は、導入時の金銭的なハードルがとても低い電子契約サービスです。基本料金が0円で、初期費用も一切かかりません。
また、他のサービスで締結した文書もまとめて管理・保管できるため、既存の業務プロセスからの移行もスムーズです。
| 電子署名方法 | 立会人型 |
| おすすめ企業規模 | 中小企業から大企業まで |
| 主な導入実績 | シリーズ累計8万社突破 |
| タイムスタンプ | あり |
| セキュリティ機能 | ワンタイムパスワード認証、二要素認証、認証コードによる認証、IPアドレス制限の設定 |
| API連携 | 要問合せ |
| セキュリティ認証の 取得状況 |
ー |
| 取引先のアカウント登録 | 登録不要 |
主要な機能を基本料金0円で利用でき、送信は1通あたり400円(税込440円)となっています。
月間または年間の送信数に応じたプランも用意されていますが、どのプランを選んでも機能差はありません。

マスコミ
11人〜30人
初めての導入に最適





元々は他社の電子契約システムを使用していましたが、契約書は月に数件レベルにも関わらずコストが発生していたので、導入したことでコスト削減に繋がりました。

不動産
2人〜10人
契約書の編集に手間がかかる





PDFファイルにしか対応しておらず、契約書の編集がある場合は一度Wordに落とし込み、編集したあとPDFに変換、アップロードしなくてはならない。
画像出典元:「Docusign eSignature」公式HP
「Docusign eSignature(ドキュサイン イーシグネチャー)」は、世界180か国以上・170万社以上で導入されている、世界No.1シェアを誇る電子契約サービスです。
世界最高水準の堅牢なセキュリティを備えており、安心して利用できます。署名に対応している言語は44言語、送信対応言語は14言語と、グローバルでの利用に最適です。
| 電子署名方法 | 立会人型/当事者型 |
| おすすめ企業規模 | 中小企業から大企業まで |
| 主な導入実績 | 世界中で10億人以上のユーザーが利用 |
| タイムスタンプ | あり |
| セキュリティ機能 | 国際的なセキュリティ認証を取得 |
| API連携 | 900以上のシステムと連携可能 |
| セキュリティ認証の 取得状況 |
ISO 27001、SOC 1 Type2、SOC 2 Type2 |
| 取引先のアカウント登録 | 登録不要 |

行政書士
石下貴大氏
「Docusign eSignature」は、スタートアップでの利用もありますが、大企業向けのイメージが強いシステムです。
一般的な企業の契約業務には、Standard(企業向け)がおすすめです。モバイルアプリの他、コメント機能や通知機能が利用でき、電子契約の推進という目的は充分達成することができます。
各プランに30日間無料トライアルがあります。初期費用は不要です。
| Standard (企業向け) |
Business Pro (企業向け) |
Enhanced Plans (拡張機能) |
|
| 月額 (年間一括) |
3,300円/ユーザー (年39,600円) |
4,400円/ユーザー (年63,600円) |
要問合せ |
| 月額 (月払い) |
6,050円/ユーザー | 8,700円/ユーザー | 要問合せ |
| 送信可能な契約件数 | 100件/年 | 100件/年 | 3件 (受信はOK) |
(税抜)

サービス/飲食/レジャー
1001人以上
お互いに紙を出さずパソコン上で契約手続きを完結できる





・動画があるので、初心者でも簡単に利用することができた。
・既存のシステムと連携ができているので楽。
・顧客にもわかりやすいような仕立てになっている。
・顧客がやり方わからなくても、申込書送付後に電話して、その場で3分もあれば完了できた。

メーカー/製造
251人〜500人
管理画面で契約書の全貌が見えない





・契約書リンク再送付時に自分で操作できず、送付依頼をする必要があり手間がかかる
・管理画面にて契約書最後の方が省略されており、見えないものがある

画像出典元:「Acrobat Sign」公式HP
「Acrobat Sign(アクロバットサイン)」は、年間80億回の取引処理件数の実績を誇るグローバル規模の電子契約システムです。企業版では、Microsoft製品とのシームレスな連携、その他Salesforceやkintoneなど他システムとの連携が可能で、営業活動や顧客管理などの業務効率化にも役立ちます。
時間や場所、使用するデバイスを問わず、契約書の送信や署名を安全に行える使い勝手の良さも魅力です。
| 電子署名方法 | 立会人型/当事者型 |
| おすすめ企業規模 | 中小企業から大企業まで |
| 主な導入実績 | Fortune 500企業をはじめ、世界中の多くの企業で導入 |
| タイムスタンプ | あり |
| セキュリティ機能 | エンタープライズレベルのセキュリティを提供 |
| API連携 | Dropbox、DocuWorks、Googleドライブなどと連携可能 |
| セキュリティ認証の 取得状況 |
ISO 27001、SOC 2 Type2 |
| 取引先のアカウント登録 | 基本的に不要 |
【個人版】では、基本機能がそろったAcrobat Standard(1,848 円/月)と豊富な機能が使えるAcrobat Pro(2,380円/月)のプランがあります。
| 【法人版】 | Acrobat Standard | Acrobat Pro | Acrobat Sign Solutions |
| 月額(税込)/ ライセンス |
1,848円 | 2,380円 | 要問合せ |
| 機能 |
|
|
|
詳しくは、公式HPよりご確認ください。

IT/通信/インターネット
251人〜500人
アクティビティ機能で顧客が開いたか確認できる





・単純でわかりやすいため、過去に電子契約ツールを使ったことがない人でも簡単に利用できる。
・アクティビティ機能で顧客が開いたかどうか確認できる。
・企業・お客様に契約書を開いてもらうまでに煩雑な作業がなくトラブルになったことがない。

メーカー
51人〜100人
シンプルなのはいいが・・・





・メールアドレスの設定を毎回行わなければならない。
・操作が簡素なため、ミスに気付きにくい。
・メールアドレスやパスワードの入力を間違えると自動でキャンセルとなり、また1からやり直さなければならない。
コストをかけずに契約業務を効率化したい場合は、無料で使える電子契約サービスを試してみるのも一つの方法です。
無料プランには送信数や機能に制限があるものの、まずは紙の契約書と併用しながら手軽に導入効果を確認できます。
▼ 無料で使える電子契約について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください
電子契約サービスは、製品によって標準機能が異なりますが、主に以下の機能があります。
| 契約書テンプレート | 知識が無くても分野別に契約書を作成できる |
| タイムスタンプ | 「いつ・誰が・何を」したかという証明。非改ざん性を証明できる |
| ワークフロー管理 | 契約書の申請~成立までの流れを管理。決裁ルートが正しいか確認できる |
| リマインド | 契約書送付後一定期間署名がない場合、メールなどでリマインドできる |
| インポート | 過去の紙の契約書も取り込み、電子契約書と一緒に保管できる |
| 保管・管理 | 契約書名/社名/金額などで検索し、過去の契約書を簡単に参照できる |
| 外部サービス連携 | 他の営業ツールやCRMツールと連携、契約書の作成がスムーズにできる |
ここでは、電子契約サービスを導入することで得られる5つの主なメリットについて解説します。
電子契約にすることで契約のスピードが劇的に早くなり、契約合意後の事務作業も効率化できます。
| 書面契約 | 電子契約 |
| 印刷・製本・郵送・保管など事務作業が多い | 作業は全てオンラインで簡単に行える |

行政書士
石下貴大氏
導入の現場での声を聞くと「電子契約は難しそう」というイメージがまだ残っていると感じます。でも実際はメールの送受信さえできれば問題なく使えるシステムがほとんど。現在では、相手方が同じシステムを使っていなくても締結できるものが大半なので、導入に踏み切りやすいです。
書面契約の場合は、費用が1通あたり約3,000円~5,000円かかるとも言われていますが、電子契約にすれば人件費と利用料以外は0円となるため、大幅なコスト削減につながります。
取り扱う契約書の件数が多い業界や、印紙税負担が高い業界(不動産・建設業・人材業など)では、さらにコストメリットを実感できます。

行政書士
石下貴大氏
印紙代は、初回の契約時だけでなく、内容変更の覚書などでも都度発生してくるものなのでこれが削減できると大きなコストカットに繋がります。また契約の種類によって印紙額がいくらなのか確認する時間的・作業的コストも削減できます。
電子契約システムを利用すれば、膨大な数の契約書をロッカーや倉庫などに保管する必要がなくなり、書類の整理などの作業も不要になります。

行政書士
石下貴大氏
会社法上、一般的な契約書の保管期間は10年間。契約件数が多い企業ではすぐに保管庫がいっぱいになりますが、データで保管できれば大幅なコストカットに繋がります。もしシステムを解約する場合はデータを別の場所に移す必要があるので、申込時に必ず方法を確認しておきましょう。
契約書を電子データ化すれば、契約終了後の契約書の検索や閲覧が簡単にできます。
書面契約の場合、膨大な契約書の中から探すのは大変ですが、電子データならキーワードを入力するだけですぐに書類を見つけることができ、類似の契約との比較も容易になります。

行政書士
石下貴大氏
膨大な紙の契約書から目的のものを見つけるのは非常に労力がかかります。電子契約であれば、検索機能ですぐに欲しい契約書が見つかる点がメリット。システムを選ぶ際に、検索機能が充実しているかどうかはチェックするようにしましょう。
電子契約システムを導入することで、契約書の紛失や改ざんリスクを大幅に軽減することができます。
データはクラウド上で厳重に管理され、アクセス権限の設定や操作履歴の記録により、不正な変更を防止可能。
さらに、電子署名やタイムスタンプ機能を活用すれば、契約の真正性を確保でき、法的証拠としての信頼性も向上します。
このように紙の契約書と比べてセキュリティレベルが高く、安心して契約業務を進められるのが大きなメリットです。
▼ 高セキュリティで多機能な電子契約サービスを知りたい方は、こちらの記事もご覧ください
ここでは、電子契約サービスをスムーズに導入するために、押さえておきたい3つの注意点について解説します。
一部には、電子化できない契約も存在します。
たとえば、公正証書の作成が必須とされている「事業用定期借地権設定契約」などは、電子契約に移行できません。
ただし、国の方針としてデジタル化が進められており、法改正によって電子契約が可能になるケースは増えています。
特定商取引法関連の契約のように、消費者から事前の承諾を得れば、電子化が認められる場合もあります。
自社で扱う契約が電子化に対応しているか不明な場合は、電子契約システムを導入する前に顧問弁護士や法務担当者に確認しておくと安心です。
初めて電子契約を利用する取引先にとっては、「手続きが難しそう」「法的に問題ないのか」など、不安を感じるケースもあります。
そのため、電子契約のメリットや操作方法を事前に説明し、安心して利用できる環境を整えることが大切です。
多くの電子契約サービスは、送信側(契約を締結する側)がシステムを利用すれば、受信側(契約を受ける側)はメールで契約を完結できる仕組みになっています。さらに、相手に費用負担がないタイプも多いため、取引先のハードルを下げる工夫も可能です。
導入した際には、相手側の負担が少ないことを伝え丁寧なサポートを行うことで、スムーズな運用につなげられます。

行政書士
石下貴大氏
取引先への説明や社内での説得が難しい場合は、いきなり複雑な契約書を使うのではなく、雇用契約やNDAなど簡単で汎用的な契約書などの締結時に、テストケースとしてまず1回利用してみるのもおすすめです。
▼ 電子契約の導入に向けた対策について知りたい方は、こちらの記事もご覧ください
書面契約から電子契約へと変更する場合、社内の業務フローが大幅に変わります。
現場が混乱し業務が止まることのないよう、事前に社内説明を行い社員の理解と協力が得られる体制を整える必要があります。
▼ 電子契約サービスの導入手順について知りたい方は、こちらの記事もご覧ください
電子契約サービスは、法的効力の強さ・セキュリティレベル・コスト・外部連携の柔軟性がサービスごとに異なるため、慎重な比較検討が欠かせません。
気になるサービスがあれば、資料請求や無料トライアルを活用し、実際の使いやすさを確かめてみましょう。
本記事でご紹介した情報を参考に、自社に最適な電子契約サービスを見つけ、契約業務の最適化を実現してください。
※2025年8月時点の情報をもとに作成しています。
画像出典元:「O-dan」公式HP
■あわせて読みたい





![[今さら聞けない]電子契約とEDIの違いは?1分でささっと理解](https://image-prod.kigyolog.com/contents/article/1c9813a5105a6ec9010da8afad5b08b9.jpg)