





Docusign eSignature(ドキュサイン イーシグネチャー)は、世界No.1の知名度を誇り、10億人以上が利用されています。
直感的な操作性に優れ、94%の利用者が「便利である」と回答しています。
PCやスマートフォンから簡単に署名でき、文書の本人性と非改ざん性を強固に保証し偽造が極めて困難なセキュリティと高い稼働率で、安心して利用できる点が評価されています。
Docusign eSignature(ドキュサイン イーシグネチャー)は、世界No.1の知名度を誇り、10億人以上が利用されています。
直感的な操作性に優れ、94%の利用者が「便利である」と回答しています。
PCやスマートフォンから簡単に署名でき、文書の本人性と非改ざん性を強固に保証し偽造が極めて困難なセキュリティと高い稼働率で、安心して利用できる点が評価されています。





目次
Docusign eSignature(ドキュサイン イーシグネチャー)は、契約書の署名・合意・管理をデジタル化する電子署名ソリューションです。
その最大の特徴は、世界180カ国以上、170万社を超える企業で導入されている圧倒的な実績にあります。グローバルな大企業から中堅・中小企業まで、あらゆる規模・業種で選ばれており、世界標準のツールとして高い信頼性を誇ります。
また、44言語をサポートし、14言語で文書を送信することが可能です。
また、単に電子署名ができるだけでなく、SalesforceやMicrosoft 365といった900種類以上の外部システムとの豊富な連携機能を備えている点も強みです。
これにより、契約業務を分断させることなく、既存の業務フローに組み込んでプロセス全体を自動化できます。
Docusign eSignatureは、企業の契約プロセスを根本から見直し、業務効率化とコンプライアンス強化を両立させる戦略的ツールとして、世界中で評価されています。
電子契約の導入で懸念されるのがセキュリティと法的有効性です。
Docusign eSignatureは、多要素認証(MFA)で不正アクセスを防止するだけでなく、GDPRやISO 27001といった世界的なセキュリティ基準にも準拠しており、客観的な安全性が大きな特徴です。
加えて、署名文書に自動発行される『完了証明書』は、「誰が・いつ」といった操作のすべてを記録するため、高い法的証拠力を確保できます。
さらに、契約書の閲覧権限や承認フローをシステム上で厳格に管理することで、不正な持ち出しや紛失といったリスクを未然に防ぎ、企業の内部統制強化にも繋がります。
Docusign eSignatureは、PCやスマートフォン、タブレットさえあれば、いつでもどこでも契約業務を行える環境を提供。
営業担当者は出張先からすぐに見積書や契約書を送付でき、承認者もオフィスにいる必要はありません。
相手方(署名者)はアカウント登録不要という手軽さも、世界で10億人以上が利用するDocuSignならではのスムーズな契約プロセスを後押ししています。

スマートフォンにも対応
Docusign eSignatureがもたらす高い効率性は、その多彩な機能によって支えられています。
例えば、頻繁に使う契約書をテンプレートとして保存すれば、次回から文書作成の手間を大幅に削減できます。
そうして作成された文書は、あらかじめ設定したワークフローに沿って、法務担当者や部長など、社内外の関係者へ自動で回付されるため、面倒な進捗管理や確認作業は不要です。
また、署名が完了したすべての文書には、「誰が・いつ・どこで」といった操作のすべてが記録された『完了証明書』(監査証跡)が自動で発行され、取引の透明性を確保します。

豊富な機能の一部
Docusign eSignatureは契約にまつわる業務全体を自動で処理することで、ビジネスの生産性を引き上げます。
SalesforceやMicrosoft 365をはじめとする、1,000種類以上の外部システムとシームレスに連携し、顧客情報を契約書へ自動で反映させることで、面倒な入力・転記作業や確認の手間を根本からなくします。
その上で、単なる電子署名に留まらず、契約書の作成から交渉、保管、更新管理まで、契約のライフサイクル全体を管理する「DocuSign CLM」も提供。
これにより、目に見えにくい管理コストまで削減することが可能です。
Docusign eSignatureは、グローバル基準の高度なセキュリティや豊富な連携機能を備えている分、国内のシンプルな機能の電子署名サービスと比較すると、月額料金が割高に感じられる場合があります。
特に、署名機能さえ使えれば良いという個人事業主や小規模なチームにとっては、多機能さゆえにコストパフォーマンスが見合わない可能性があります。
導入前には、自社にとって本当に必要な機能を見極め、費用対効果を慎重に検討することが重要です。
契約プロセス全体を自動化するワークフロー設定や外部システムとのAPI連携は、非常に自由度が高い反面、その機能を最大限に活用するには、導入初期の学習やIT部門との連携といった準備が必要になる場合があります。
日常的な署名や文書送付といった基本操作は直感的に行えますが、より高度な自動化を目指す場合は、あらかじめ学習のための時間を確保したり、社内の運用ルールを定めたりしておくことを推奨します。
Docusign eSignatureの海外での利用シェアは世界的に高いので、大企業・中小企業問わず「グローバルな取引を視野に入れている企業」には向いています。
44か国語の多言語対応が、追加料金なく標準搭載されているのはドキュサインだけです。
Docusign eSignatureはSalesforceと連携することで、契約の一元管理・契約プロセスの改善がされます。
「金額の算定」「契約書の発行」「署名の依頼」「電子署名」「締結済み契約書の管理」まで自動化することができ、圧倒的な効率化に期待ができます。
ただし設定が難しいとの口コミが寄せられていますので、当初は導入ベンダーなどの外部の力を借りることも視野にいれるとよいでしょう。
この記事では「Docusign eSignature」の特徴・評判・料金を解説しました。
Docusign eSignatureは契約を締結する上で必要な工程の大部分を行ってくれるため、時短や業務効率改善に役立ちます。
また、署名はネットに繋がっているデバイスであれば対応可能で、締結した契約はいつでも両者共に確認できることから署名者に負担をかけることもありません。
Docusign eSignature上のクラウドに保存されるため、契約書の保存・管理・検索も容易となります。海外でも多く使われているツールだからこそ、海外契約にも強いのが特徴です。
画像出典元:「Docusign eSignature」公式HP
各プランに30日間無料トライアルがあります。初期費用は不要です。
| Standard (企業向け) |
Business Pro (企業向け) |
Enhanced Plans (拡張機能) |
|
| 月額 (年間一括) |
3,300円/ユーザー (年39,600円) |
4,400円/ユーザー (年63,600円) |
要問合せ |
| 月額 (月払い) |
6,050円/ユーザー | 8,700円/ユーザー | 要問合せ |
| 送信可能な契約件数 | 100件/年 | 100件/年 | 3件 (受信はOK) |
(税抜)
一般的な企業の契約業務には、Standard(企業向け)がおすすめです。
モバイルアプリの他、コメント機能や通知機能が利用でき、電子契約の推進という目的は充分達成することができます。

押印や手書き署名の廃止のため。
2023年10月~2024年6月現在も使用中
・手書き署名や押印ではないため、いつでもどこでも、依頼先の人に署名を依頼できてとても便利。複数人に同時に依頼できるのも最高。
・いつ誰が確認したかなどの履歴が残る。履歴をサマリーとして残してくれる資料が別途あることでとても便利。
・資料をアップロードする時に、ドラッグドロップでできて使いやすい。
・パスワード入力やそれに伴う頻回な画面遷移があり、署名までに時間がかかる。
契約手続きの流れが履歴で残り適切な管理が可能なので、おすすめする。
不明

コスト削減プロジェクトの一環として、紙媒体での契約書締結を減らし、電子契約サービスを導入する必要があったため。
2022年4月~2023年9月現在も利用中
・ボリュームのある契約書だと読み込み時間が長く、UIが直感的に操作しづらかった。
・署名者が複数人の場合(ダブルチェック担当者や法務担当者など)、設定に手間がかかる。
・電子署名(サイン)が中心で、電子捺印(印影)にあまり向いていない。
・電子署名(サイン)の場合、契約締結完了後に書面から文字がはみ出しているのが分かるなど、後になってからでないと全体が把握できなくて不便。
不明

年間約20~30万円程度
2022年6月~2023年9月現在も利用中
・テンプレート機能があり、雛形を利用して大量に契約書を一括で送付できる。
・処理中の案件のステータスをすぐに確認できるため、どのステップで承認が滞っているか分かりやすい。
・導入企業数が多いため、契約先にも電子サインを抵抗感なく受け入れてもらえる。
毎月特定の形式の契約書を締結する必要がある会社におすすめ。テンプレートを設定することで、都度署名欄の設定をする手間が省けるため。
年間約20~30万円程度

【2026年最新】おすすめの電子契約サービス19選を特徴別に紹介!費用やシステム連携など、選定に欠かせないポイントを徹底比較。電子契約に詳しい行政書士のアドバイスも掲載しています。自社の課題を解決できる電子契約サービスを見つけたい方、必見です。

ContractS CLM(旧:Holmes)

freeeサイン(旧:NINJA SIGN by freee)

BtoBプラットフォーム契約書
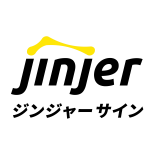
ジンジャーサイン

WAN-Sign

FAST SIGN

Great Sign(グレートサイン)

ONEデジDocument

おまかせ はたラクサポート

Shachihata Cloud

ラクラク電子契約

RAQCABI

eformsign

ConPass

DX-Sign

IMAoS

クラウドコントラクト

satsign

CMサイン

Zoho Sign

DottedSign(ドットサイン)

HelloSign

CONTRACTHUB@absonne

マネーフォワード クラウド契約

契約大臣

SignTime

Acrobat Sign

ベクターサイン(旧みんなの電子署名)

リーテックスデジタル契約

paperlogic電子契約

イースタンプ

クラウドスタンプ

エコドラフト

電子契約サービスのトップシェアは?市場や人気のサービスを徹底解説

電子契約の法的効力とは?法的根拠と改ざん防止を解説!

電子印鑑で業務効率化!印鑑を電子化する意味やおすすめツールも紹介

タイムスタンプとは?電子文書に欠かせないセキュリティの仕組み

電子署名の方法とは?仕組みや法的効力、メリットなど詳しく解説
![[今さら聞けない]電子契約とEDIの違いは?1分でささっと理解](https://image-prod.kigyolog.com/contents/article/1c9813a5105a6ec9010da8afad5b08b9.jpg)
[今さら聞けない]電子契約とEDIの違いは?1分でささっと理解

電子契約のやり方完全ガイド!具体的な方法や注意点まで全解説

e-文書法とは?電子帳簿保存法との違い、対象文書、要件、メリットを解説

ニューノーマル時代のバックオフィス課題発見イベント『 Less is More. 』参加レポート

【2026年最新】おすすめの電子契約サービス19選を特徴別に紹介!費用やシステム連携など、選定に欠かせないポイントを徹底比較。電子契約に詳しい行政書士のアドバイスも掲載しています。自社の課題を解決できる電子契約サービスを見つけたい方、必見です。

ContractS CLM(旧:Holmes)

freeeサイン(旧:NINJA SIGN by freee)

BtoBプラットフォーム契約書
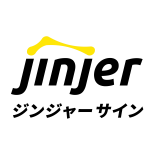
ジンジャーサイン

WAN-Sign

FAST SIGN

Great Sign(グレートサイン)

ONEデジDocument

おまかせ はたラクサポート

Shachihata Cloud

ラクラク電子契約

RAQCABI

eformsign

ConPass

DX-Sign

IMAoS

クラウドコントラクト

satsign

CMサイン

Zoho Sign

DottedSign(ドットサイン)

HelloSign

CONTRACTHUB@absonne

マネーフォワード クラウド契約

契約大臣

SignTime

Acrobat Sign

ベクターサイン(旧みんなの電子署名)

リーテックスデジタル契約

paperlogic電子契約

イースタンプ

クラウドスタンプ

エコドラフト

電子契約サービスのトップシェアは?市場や人気のサービスを徹底解説

電子契約の法的効力とは?法的根拠と改ざん防止を解説!

電子印鑑で業務効率化!印鑑を電子化する意味やおすすめツールも紹介

タイムスタンプとは?電子文書に欠かせないセキュリティの仕組み

電子署名の方法とは?仕組みや法的効力、メリットなど詳しく解説
![[今さら聞けない]電子契約とEDIの違いは?1分でささっと理解](https://image-prod.kigyolog.com/contents/article/1c9813a5105a6ec9010da8afad5b08b9.jpg)
[今さら聞けない]電子契約とEDIの違いは?1分でささっと理解

電子契約のやり方完全ガイド!具体的な方法や注意点まで全解説

e-文書法とは?電子帳簿保存法との違い、対象文書、要件、メリットを解説

ニューノーマル時代のバックオフィス課題発見イベント『 Less is More. 』参加レポート