





「SmartHR」は70,000社以上の導入実績を誇る労務管理システムです。
最大の特徴は質問に答えるだけで重要書類が作成できる簡単さ。Web上で書類作成や管理が行われるため、紙もハンコも使う必要がありません。
e-Gov APIと連携しているため、役所やハローワークへの書類提出もWEB上からできます。
実際にSmartHRを導入した企業では、「2人で1,700人分の給与計算が可能になった」「社員の60%の生産性が向上した」などの実績も出ています。
社労士がいなかったり従業員が多い企業には特におすすめです。
「SmartHR」は70,000社以上の導入実績を誇る労務管理システムです。
最大の特徴は質問に答えるだけで重要書類が作成できる簡単さ。Web上で書類作成や管理が行われるため、紙もハンコも使う必要がありません。
e-Gov APIと連携しているため、役所やハローワークへの書類提出もWEB上からできます。
実際にSmartHRを導入した企業では、「2人で1,700人分の給与計算が可能になった」「社員の60%の生産性が向上した」などの実績も出ています。
社労士がいなかったり従業員が多い企業には特におすすめです。





SmartHRは、70,000社以上の導入実績を持つ、労務管理クラウドの7年連続シェアNo.1システムです。
国内有名企業でも数多く導入されており、大規模処理やセキュリティの面でも信頼度十分です。
また、料金プランやUI/UXはスタートアップや中小企業にも対応できる使いやすさで、2名以上の小規模事業者からも幅広く導入されています。
他社製品からの乗り換えだけでなく、紙管理、エクセルから初めてシステム化を行う会社にもぴったりのツールです。

豊富な導入実績
SmartHRの機能の一番の肝は、幅広い人事書類を簡単・自動で作成できる点です。
まず雇用契約・入社手続きは、入社する従業員が直接入力するだけで完了するので、担当者の負担が激減します。
一度データ入力ができれば、退職や住所変更手続き等の書類も自動作成が可能になり、面倒な申請書やハンコが不要になります。
さらに、毎年の作業負担が大きい年末調整も、Web上の質問に答えるだけで自動作成。
「従業員へ通知 → 質問に答える → 自動で書類作成完了」この流れだけで書類ができあがります。
従業員はスマホからも入力可能なので使い勝手も抜群です。

SmartHRでは、Web上で書類作成、管理が行われるため、紙を使う必要がありません。その分時間や経費も抑えられます。
また、給与明細の配布にありがちな、各従業員の机に回ってわざわざ配布する必要もなく、どこでも給与明細を確認できるのも嬉しいところです。
また、e-Gov API(政府が運営する電子申請システムに、直接申請できる窓口の役割をするもの)と連携しており、役所やハローワークへの書類提出もWEB上からできます。
無駄を削減し、時間のかかる手続きなどを代わりに行ってくれるので、本来業務に集中でき、生産性の向上につながります。

SmartHRでは、これまで散らばりがちだった従業員の情報を一元管理することができます。
入退社・扶養の追加・住所の変更など、従業員が多くなるにつれて膨大な量となる情報を、管理、連動させ、簡単に使えるようにしてくれます。
例えば、社会保険、雇用保険などの労務管理は、ミスがあると従業員と雇用主との信頼関係にもかかわってくるため、データの更新漏れなどの心配なく取り扱うことができるのは魅力的な機能です。
また、一部プランではオプション機能となりますが、人事情報を様々なチャートで見える化する分析機能も搭載しています。
主要な指標はあらかじめセットされているため、面倒な初期設定なく、分析初心者の担当者でも簡単に利用できる点も安心です。

SmartHRは、120以上もの外部サービスと連携しており、拡張性高く利用することが可能です。
給与、勤怠、採用やタレントマネジメントなどの人事領域のソフトと繋げれば、ワンクリックで従業員情報を連携でき大変便利です。
また、slackやchatworkなどのチャットツールとの連携で、従業員の更新や申請通知をタイムリーに受信し対応漏れを防ぐこともできます。
なお、Open APIを公開しているため、既存の連携ツールだけでなく、人事データベース等を内製で作成している企業でも連携可能な点も好評価ポイントです。
SmartHRのさらなる特徴は、その使いやすいUI/UXです。
"人事労務の手続きをカンタン・便利にする"というビジョンの元こだわって作られたUIはシンプルで非常に見やすいです。
また、サービス継続率も99%と非常に高く、管理する側だけでなく、使う側にとっても、使い続けやすいシステムであることがわかります。
起業ログの独自アンケートの声でも、UI/UXを評価する声が多く聞かれました。

デザインがシンプルで、色合いも白とブルーで目に優しく有難いです。年末調整の質疑応答に答えていく際、質問の文言がとてもわかりやすかったので、今後も使いたいなと思いました。(コンサルティング業・101〜250人)

とにかく操作が簡単なので使いやすいと思いました。他の労務管理システムだと結局どのように操作すれば良いのか中途半端な指示があったりするのですが、SmartHRは指示もデザインも分かりやすいので、大変ありがたいです。(メーカー・51〜100人)

紹介した特徴などを踏まえると、「SmartHR」は次のような企業におすすめです。
紹介のとおり、SmartHRには国内シェア7年連続No.1の信頼の実績があります。
また、大企業から信頼されるに足るセキュリティ対策も万全で、暗号化や認証はもちろんのこと、重要な操作履歴の保存などいざというときに有り難い機能も搭載しています。
労務クラウドシステムは新出のサービスも多いですが、SmartHRであれば金融機関も含む豊富な導入事例を参考に、安心して導入を進めることができるでしょう。
SmartHRのさらなる特徴は、そのシンプルで見やすいUI/UXです。
特に年末調整メニューは、わかりづらい書類への記入項目を、YES/NOの問いに答えるだけで自動作成してくれるのでユーザーにも高く評価されています。
どんな方にとっても使いやすいデザインなので、従業員のITリテラシー、労務ルールへのリテラシーにばらつきがある企業でも安心して導入できます。
使いやすいUIとコスパに定評のある「SmartHR」ですが、一方で次のようなデメリットもあります。
SmartHRは、人事情報管理と労務手続きについて幅広い機能を持っていますが、付随して管理したい「勤怠」「有給休暇」「給与計算」などについては、外部サービス連携させて使用する必要があります。
勤怠だけでも11システムの連携が可能ですし、その企業独自のシステムとも繋ぐことは可能ですが、1つのシリーズ商品内で労務・勤怠・給与などをいっぺんに処理したいという場合には不向きかもしれません。
SmartHRサポート体制は、チャット・FAQページのみとなり、電話での受付窓口はありません。
また、SmartHRスクールという導入者用のeラーニングコースも充実しているため、そちらで調べても十分疑問は解決できると思いますが、どうしても電話サポートが欲しいという場合には物足りなく感じるかもしれません。
ただし、電話サポートのついたサービスは基本料金が高くなる傾向があるため、コスト面を考慮した上で最適なサービスをお選びください。
編集部では、日本で初めてのハイジーンファクターに特化した調査・改善サービスを開発している株式会社OKAN代表取締役の沢木恵太氏に取材を敢行しました。

多様な働き方支援の専門家 株式会社OKAN 代表取締役 CEO
多様な働き方支援の専門家 沢木 恵太によるSmartHRの総評
2012年に個人向け総菜配送サービスで起業。「株式会社OKAN」として法人向けサービスにシフトし、急成長を遂げている。2019年には、ハイジーンファクターに特化した、日本で初めての調査・改善サービス『ハイジ』をリリース。

このように、SmartHRは非常に使いやすいUXを強みに、労務管理全般をオンラインで完結できるサービスです。
この記事では、SmartHR(スマートHR)の特徴・評判・料金を解説しました。
労務に特化した使い勝手のよいUIと優れた機能が評価され、7年連続シェアNo.1、顧客の継続率も高い、信頼のおけるシステムです。
運営会社である株式会社SmartHRも、業績の拡大に伴い、国内6社目のユニコーン企業ともなり(日経新聞記事)、ますます勢いを増しています。
労務に関する仕事は、従業員が増えるにつれて管理が難しくなりますが、SmartHRの導入で、「生産性が60%向上した」などの事例もあり、どんな業種・規模の企業でもコスト削減や効率化への効果を実感できるでしょう。
労務の作業をシンプルにし、企業全体の生産性の向上を図りたい企業におすすめです。
画像出展元:「SmartHR」公式HP
初期費用・サポート費用は無料。
従業員数と課題に合わせた月額プランを提供しており、詳細についてはお問い合わせが必要です。

特にかかった費用はなし
2020年12月に利用
初心者でも使いやすいツールだったから。
基本的に自分で記入する必要がなく、質問に対して回答を選択する方式だったので、年末調整を初めて行う自分でも簡単にできた。
また、字が大きくて明るいデザインで、本来面倒な作業のはずなのに負担に感じることなく行えたところがよかった。
特にここが不便という点はなかったが、強いていうなら作業が完了したかどうかが分かりにくく、これで本当に大丈夫なのかと担当者に聞いてしまった。もっと、やるべきタスクはありませんという目立つ表示を入れるなど、完了したことが明確にわかるようになっているといいと思う。
おすすめする。年末調整というと面倒な作業であるイメージがあるが、SmartHRを使ったらすぐに完了したので、どなたでも年末調整に苦手意識を持つことなくできると思うから。

給料明細の確認、源泉徴収票の確認、申請の為。
2021年10月~2022年8月現在も利用中
・給料明細が確定後にメールでお知らせがくる為、すぐに確認が出来る。
・源泉徴収票が必要な際に、人事部に依頼せずにいつでも自分で印刷が出来る。
・源泉徴収の申請がこれまでは書類で申請を行っていたが、WEB上での申請が可能な為、自宅でも出来る。
おすすめ出来ます。
従業員が多い会社は、従業員が簡単に利用出来る為、取り入れて良いと思います。
不明

2019年3月頃~2022年7月現在も利用中。
・全体を通して見やすいレイアウトで表示されている。
・住所・口座情報など個人情報の変更がしやすい。
・交通費の入力がしやすい。
・給料明細もパソコンで確認・印刷ができ、過去の明細も見やすい表示になっているので見返すのが簡単。
・会社に提出している自分の自宅の住所や給料振込先、交通費、自分の等級なども含めて一つのツールで見ることができ、一元化できている。
・どこになにがあるかを早く探せて、見失うことがない。
・経費精算や支払い精算は別のツールを使用するので、使い方が異なるため多少不便を感じることがある。
・自分側の問題かもしれないが、給与の振込口座を変更したのに反映されないことがあった。いつから変更になり反映されるのかがわかるようになれば、より不安要素がなくなると思った。
会社の規模が大きい場合、個人情報をいろいろなところで保有していると手続きが大変だったりする。一元化することでミスも少なくなるし、何か問題があったときに発見しやすい。
比較的まとまった仕様で使いやすいのでおすすめしたいと思う。
不明

【入社手続き】会社側の対応チェックリストを段階ごとに分かりやすく説明!

会社側の行う退職手続きの流れと必要書類は?保険や年金手続きも解説!

【2023年最新】賞与に必要な手続きと社会保険料の計算方法を簡単解説

社員管理とは?従業員管理のコツやメリット、おすすめ管理システムも

社会保険の電子申請義務化とは?全法人が利用可能!対応届出も解説

労務費とは?人件費との違いや計算方法・内訳・労務費率をサクッと解説

雇用契約書の電子化に要件はある?雇用関連書類電子化のメリットとは
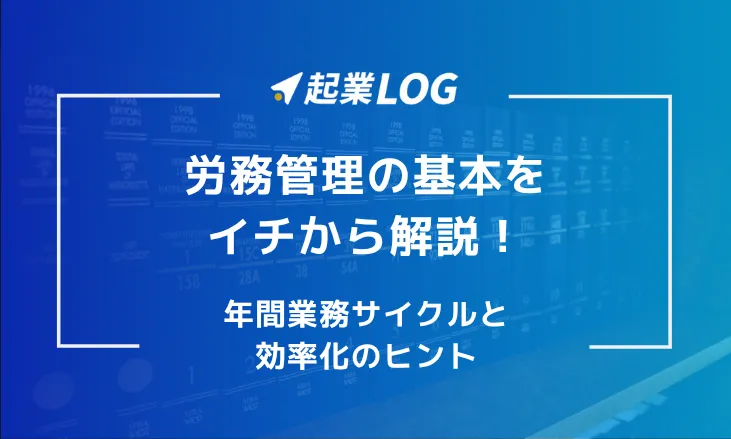
労務管理の基本をイチから解説!年間業務サイクルと効率化のヒント

従業員入社時に必要な社会保険手続きを解説!5日以内の手続き必須です

会社が行う雇用保険の加入と喪失の手続きを解説!電子申請の活用を!

労務管理システムを比較!選び方のポイントやおすすめ16選を比較表で紹介
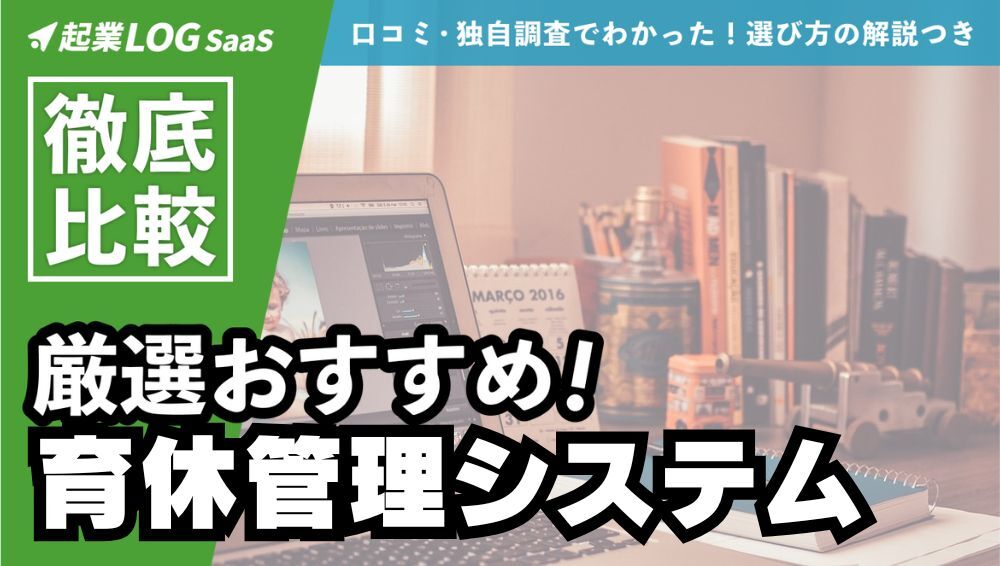
【2026年版】育休管理システム比較6選|法改正・タスク管理・従業員ケアまで解決する選び方

【2026年最新】無料で使える労務管理システムおすすめ8選!有料システムとの違いと選び方を徹底解説

【25年版】飲食業界向け採用管理システム(ATS)比較12選!選び方も解説

ハイブリッドワークのおすすめツール比較26選!カテゴリ別に紹介

スキル管理システムおすすめ比較14選!選び方・メリットも解説

Web給与明細アプリ比較7選!無料含めたおすすめや選び方のコツを解説

【最新比較】従業員エクスペリエンス管理ツールおすすめ9選!

【最新比較】バックオフィス業務効率化におすすめサービス厳選61選!

【最新比較】経理担当者におすすめ業務効率化ツール49選!選び方は?

【入社手続き】会社側の対応チェックリストを段階ごとに分かりやすく説明!

会社側の行う退職手続きの流れと必要書類は?保険や年金手続きも解説!

【2023年最新】賞与に必要な手続きと社会保険料の計算方法を簡単解説

社員管理とは?従業員管理のコツやメリット、おすすめ管理システムも

社会保険の電子申請義務化とは?全法人が利用可能!対応届出も解説

労務費とは?人件費との違いや計算方法・内訳・労務費率をサクッと解説

雇用契約書の電子化に要件はある?雇用関連書類電子化のメリットとは
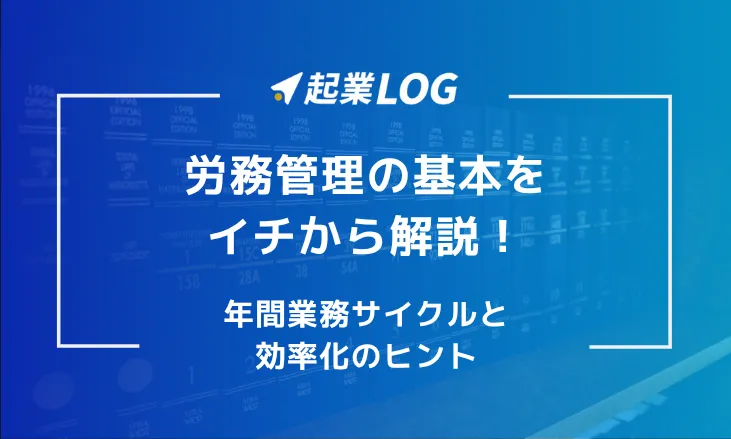
労務管理の基本をイチから解説!年間業務サイクルと効率化のヒント

従業員入社時に必要な社会保険手続きを解説!5日以内の手続き必須です

会社が行う雇用保険の加入と喪失の手続きを解説!電子申請の活用を!