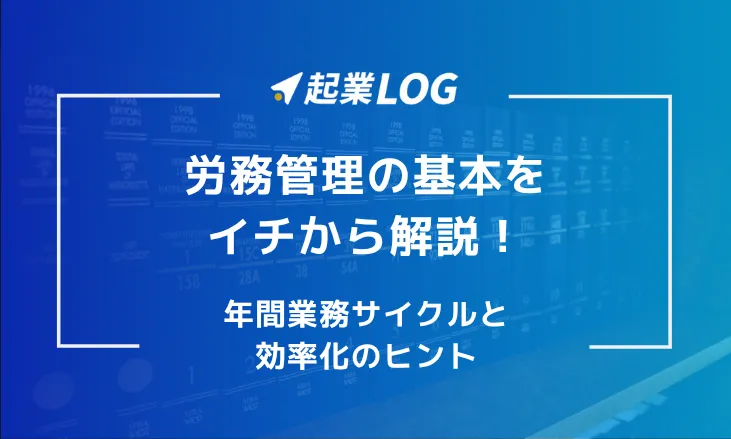
「会社で労務を担当することになったけれど、結局、労務管理の基本って何なんだろう?」 と漠然とした不安を抱えていませんか?
労務管理の基本は、法令を正しく理解し、遵守したうえで適切な管理体制を構築することです。
入退社手続きや社会保険対応、帳簿管理など、年間を通じて多岐にわたる実務が発生する一方で、対応漏れや運用の属人化などの課題もつきものです。
本記事では、年間スケジュールに沿って発生する実務内容を軸に、労務担当者が押さえておくべき法定帳簿や関係法令、見落としやすい業務のポイントまでを解説!
基礎知識とあわせて、効率化と法令遵守を支援するおすすめの労務管理システムもご紹介します。
目次

労務管理の基本は、労働関連法令を正しく理解し、法に沿った手続きと管理を行うことです。
労働基準法、安全衛生法、労災保険法、健康保険法、労働契約法など、関係する法律は多岐にわたります。
適切に対応するためには、「どんな法令があるか」「どんな管理や手続きが必要か」を把握し、自社の実務に落とし込むことが欠かせません。
この章では、初心者にもわかりやすい労務管理の基本を解説!
労務管理の基礎知識を学び、業務の見直しや効率化のきっかけにしてみてください。
労務管理とは、「労働法に基づいて、従業員の労働条件や職場環境を適切に整える業務」であり、企業の成長や安定的な運営のために欠かせない経営の土台を支える役割を担っています。
こう聞くと難しく感じるかもしれませんが、本質は「ヒト」に関するあらゆる業務をルールに則って整えること。
働く人が安心して働き続けられる環境をつくることが、労務管理の最も重要な目的です。
そのためには、以下のような多くの労働関係法令を理解し、遵守する必要があります。
これらに違反した場合は、罰金や損害賠償・行政指導・企業の信用失墜といったリスクにつながります。
特に、残業代の未払いや労働災害の隠蔽(いわゆる労災かくし)は、重大な問題としてメディアでも取り上げられるケースがあるため、知っている方も多いでしょう。
では、この「労務管理」とよく混同されがちな「人事」「総務」「勤怠管理」とはどう違うのか?
似ているようで役割が異なるそれぞれの違いについて、整理してみましょう。
人事・総務・勤怠管理業務と細かく分かれすぎて、どこまでが自分の担当なのか不安になることはありませんか?
実際、これらの業務は重なり合う部分が多く、明確な線引きが難しいのが現実です。
ですが、全体像を整理して理解することで、役割分担や業務の最適化がしやすくなります。以下の表でそれぞれの役割を確認してみましょう。
| 業務領域 | 主な役割 |
| 労務管理 | 勤怠・給与・社会保険・安全衛生など、従業員の労働環境を法令に基づき管理 |
| 人事 | 採用・異動・評価・教育研修など、組織戦略に基づく人材マネジメント |
| 総務 | 備品管理・施設管理・文書対応など、会社全体の運営を支える庶務的業務 |
| 勤怠管理 | 打刻・出退勤・休暇・残業の記録とチェック。労務管理の一部に含まれる |
特に労務管理は、給与計算や入退社手続き・勤怠チェックといった表面的な作業だけではなく、労働法や社会保険制度の正しい理解と運用が求められる業務です。
こうした背景から、人事や総務と比べても専門性が高く、より難易度の高い領域といわれています。
では、なぜ労務管理はここまで「難しい」と感じるのでしょうか?
その理由は以下のような要因が複雑に絡み合っているためです。
このようにただ業務をこなすだけではなく、背景の知識・運用の工夫・リスク管理すべてが求められるのが、労務管理の難しさといえるでしょう。
法律は労働者の権利を守り、企業が健全に運営されるための基盤を築きます。
労務管理の業務を担う担当者にとって、労働関連法規の理解は欠かせません。
一方で、これらの法律に違反すると、企業は罰則だけでなく信用失墜や訴訟リスクなど深刻な問題に直面します。
ここではまず、労務担当者が押さえるべき主要な法律について整理し、違反してしまった際の具体的なリスクを解説します。
労務管理に深く関係する法律は多岐にわたりますが、ここでは特に押さえておきたい代表的な法律とその役割を解説します。
労働基準法は、労働者の生活を守るために労働条件の最低基準を定めています。
労働時間・休憩・休日・賃金・解雇などの基本的なルールが盛り込まれ、過重労働や不当な解雇から労働者を保護します。
労働契約法は、企業と従業員間の労働契約に関するルールを明確にし、労働条件の明示や契約の適正な履行を義務付けます。
労使間のトラブル防止に不可欠な法律です。
企業が従業員に支払うべき賃金の最低額を定めています。
地域別最低賃金と特定最低賃金があり、毎年改定されるため注意が必要です。
特にこれらの法律は日々の労務業務の基盤となるため、内容を正確に理解しておきましょう。
これらの法律に違反した場合、企業経営に多大な悪影響を及ぼします。
主なリスクは以下の通りです。
労働基準法をはじめとする各種労働関連法には、違反に対して罰則や罰金が科される規定があります。
例えば労働基準法に違反した場合、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」といった刑事罰が科されることもあります。
法定三帳簿を正しく整備・保存していなかったり、虚偽の内容を報告する「労災かくし」も罰則の対象です。
これらの違反は、重大な事故やトラブルが発覚した際に企業責任を問われる要因となり、結果として刑事処分や企業評価の低下につながる恐れがあります。
法令対応を他人事にせず、日々の業務に落とし込むことが重要です。
労災の隠蔽やハラスメント問題・個人情報の漏洩など、法令違反が明るみに出ると企業の社会的信用は一気に低下し、ブランドイメージにも深刻なダメージを与えます。
その影響は一過性ではなく、「顧客や取引先の離脱」「採用活動への悪影響」「長期的な売上・成長へのブレーキ」といった経営リスクにつながる可能性があります。
一度失った信頼を取り戻すには、多くの時間とコストが必要です。
「うっかり」が通用しない領域であることを常に心がけましょう。
企業が法令に違反し、その結果として従業員に損害を与えた場合、損害賠償請求や労働審判・訴訟に発展する可能性があります。
よくある事例としては、
・長時間労働や不当解雇などによる労働契約の不履行
・割増賃金の未払い
・労働安全衛生法上の義務違反による健康被害・労働災害
などが挙げられます。
労務管理の不備は企業経営に直結する重大リスクになり得るため、企業として責任ある行動が問われる場面です。
法令違反があった場合、労働基準監督署などの行政機関から行政指導や是正勧告を受けることがあります。
さらに、悪質なケースや改善が見られない場合には、企業名が公表されることもあり、企業のレピュテーション(社会的評価)に深刻な影響を及ぼします。
企業名の公表はニュースやネットで拡散され、「採用活動が困難になる」「既存取引の停止や新規契約の減少につながる」といった二次的な経営リスクを招く恐れもあります。
たとえ一時的な違反であっても社会的な信用の回復には時間とコストがかかるため、日頃から法令に即した対応を心がけましょう。
これらの法律を理解し日々の業務に活かすことは、企業を守る予防線として極めて重要です。
万が一知らずに法律違反をしてしまうと、罰則や損害賠償だけでなく従業員の信頼喪失や社会的信用の低下にもつながりかねません。
「知らなかった」では済まされないのが労務管理の現場。
特に、法律で作成・保存が義務付けられている帳簿類は、労務担当者が最初に押さえておくべき必須の管理項目です。
次章では、そうした法定三帳簿(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿)について、わかりやすく解説していきます。
▼法改正自動対応・データ集計を効率化!ヒューマンエラーのリスクを減らすシステムを導入しよう
法定三帳簿とは、労働基準法で企業に作成・保存が義務付けられている3つの基本的な帳簿のことです。
法定三帳簿は、次の3つになります。
これらは、従業員の労働条件や勤務状況を正確に把握・記録するためのものであり、労務管理の「土台」となる書類です。
もっと詳しく知りたい方は下記よりご覧ください。
従業員一人ひとりの人事情報をまとめた基本台帳です。
会社が従業員の情報を正確に把握し、いざという時に連絡が取れたり、過去の勤務状況を確認したりするために使われます。
記載内容:氏名・住所・生年月日・性別・雇入れ日・退職日などの人事情報
保管期間:退職・解雇・死亡の日から3年(原則5年)
管理方法:個人情報が多く含まれるため、紛失・漏洩防止に配慮した厳重な管理が必要。記載内容や保存期間は労働基準法で定められており、違反すれば法的リスクあり。
従業員に支払った給料の明細書をまとめたものです。
会社が従業員に適切に給料を支払っているかを証明するため、また給料計算に間違いがないかを確認するために使われます。
記載内容:給与計算期間・労働日数・労働時間・基本給・手当・控除額などの給与支払い情報
保管期間:3年(原則5年)
管理方法:ミスがあれば信頼損失や労使トラブルに発展する恐れもあるため、正確に計算・管理し、安全に保管する。
従業員の勤務記録です。
従業員がどれくらい働いたかを正確に把握し、適正な給料を支払うため。また、残業時間の上限など労働基準法を守って働かせているかを確認するために使われます。
記載内容:出勤日・退勤時刻・労働時間・休憩時間・休日などの勤怠情報
保管期間:3年(原則5年)
管理方法:タイムカード・ICカード打刻・PCログ管理など、従業員の出勤・退勤時間を自動で記録できる仕組みを活用。改ざん防止のためできるだけ電子化が望ましい。
労務管理は年間を通じて多岐にわたる業務が発生し、タイミングを逃すとトラブルの原因にもなります。
特に初めて担当する方にとっては「何をいつすればいいのか」がわかりづらいもの。
そこでこの章では、労務管理の基本的な業務を4月から翌年3月までの年間スケジュールに沿ってわかりやすくまとめました。
労務管理初心者も経験者も、ぜひ保存版としてご活用ください。
■主な月別年間業務スケジュール(4月~翌3月)
| 月 | 主な労務管理業務 |
| 4月 | 新卒・中途入社手続き、労働保険料の年度更新準備、就業規則の見直し |
| 5月 | 労働保険料の年度更新(準備含む)、36協定の提出期限(労基署) |
| 6月 | 健康診断(定期)、就業規則の改定対応、労働保険の申告・納付 |
| 7月 | 社会保険の定時決定(算定基礎届)、夏季賞与対応 |
| 8月 | 算定基礎届の結果確認、保険料の改定確認と通知 |
| 9月 | 賃金改定・人事異動の反映、福利厚生制度の見直し |
| 10月 | 健康保険・厚生年金保険料の改定(月変対応)、育児介護関連制度の確認 |
| 11月 | 年末調整準備、扶養控除申告書の回収、マイナンバー確認 |
| 12月 | 年末調整本番、源泉徴収票の発行、冬季賞与対応 |
| 1月 | 法定調書合計表の作成、労働者名簿や賃金台帳の整備 |
| 2月 | 就業規則の見直し、来年度の体制検討、人事評価の集計 |
| 3月 | 来期人員計画、昇給・異動対応準備、退職者手続きの増加傾向 |
次章より、4月~3月の流れを上半期・下半期に分けて、ポイントをわかりやすくまとめました。
1年間の業務を「見える化」することで、準備や引き継ぎがしやすくなり、対応漏れの防止にもつながります。
労務管理の基本業務を理解し、自社の運用体制も見直してみましょう。
4月:新年度のスタートと新入社員対応
・新入社員の受け入れ・入社手続き
雇用契約書の締結、社会保険・雇用保険の加入、住民税特別徴収の開始、雇い入れ時健康診断などを実施
・給与改定
昇給などに伴い、給与計算システムや社会保険料率(健康・介護・雇用保険)を更新
・労働保険の年度更新準備
6~7月の申告に向けて、労災保険・雇用保険料算定に必要な賃金総額の集計を開始
・就業規則の見直し
法改正や社内制度の変更にあわせて、就業規則や各種規程の内容をチェック・修正
5月:住民税と年度更新の準備月
・住民税特別徴収税額通知の確認
市区町村から届く「税額決定通知書」に基づき、6月からの住民税天引きに備えた給与システムを設定
・労働保険の年度更新申告書作成
前年の賃金総額を集計し、6月以降に提出する労働保険の年度更新書類を作成
・社会保険算定基礎届の準備開始
7月提出に向け、4月~6月の給与データを正確に集計するための事前準備
6月:年度更新と算定基礎届の本格準備
・労働保険の年度更新を実施
前年度の賃金に基づき労働保険料を確定し、申告・納付(7月10日締切)
・社会保険算定基礎届の準備を本格化
4月~6月の報酬月額をもとに、標準報酬月額の算定基礎届を作成
・住民税の特別徴収を開始
5月に届いた通知書をもとに、新しい住民税額を給与から天引き
・夏季賞与の計算と支給を実施
就業規則や業績評価に基づき、賞与を支給。社会保険料・所得税も精算
・熱中症対策の義務化に対応
2025年6月施行の法改正に備え、対象作業のある職場は対策を整備
7月:算定基礎届の提出と法定報告
・社会保険の算定基礎届を提出
4月〜6月の報酬に基づき作成した算定基礎届を、7月10日までに提出。9月からの社会保険料が決定
・高年齢者・障害者の雇用状況報告を提出
6月1日時点の雇用状況を取りまとめ、7月15日までにハローワークへ提出
・月額変更届の対象者を確認
昇給・降給などによって報酬が大きく変動した場合は、随時改定として月額変更届を提出
8月:落ち着いた時期に制度見直しと情報収集
・法改正や制度変更の情報を収集
育児・介護休業法、副業・兼業制度、労働基準法などの最新動向を確認し、必要に応じて就業規則や社内制度を見直す
・有給休暇の取得状況を確認・促進
取得状況を把握し、計画的な取得を促進。有給休暇の適切な管理は、年次を通じて重要な業務の一つ
9月:社会保険料の改定と健康診断準備
・社会保険料の改定
7月に提出した算定基礎届に基づき、9月支給分の給与から新しい保険料を適用。従業員への通知や給与計算システムの更新を実施
・健康診断の実施準備
秋に実施する定期健康診断に向けて、医療機関との調整や社内案内を開始。従業員の健康管理は、労働安全衛生法に基づく企業の義務
新年度が始まる4月~9月は労務管理が特に忙しく、法で定められた重要手続きが集中する時期です。
期限厳守は当然ですが、これらの業務は従業員の給与や生活に直結するため正確な処理と計画的な準備が不可欠です。
小さなミスが大きなトラブルにつながることもあるため、余裕を持ったスケジュールで確実に進めましょう。
10月:社会保険適用拡大と年末調整の準備
・社会保険の適用拡大への対応
2024年10月以降の法改正により、パート・アルバイトにも社会保険が適用されるケースが増加。対象となる従業員の確認と加入手続きを実施
・年末調整の準備開始
扶養控除申告書や保険料控除申告書など、必要書類の配布準備を行い、従業員への案内も開始
11月:年末調整の本格化とストレスチェック対応
・年末調整書類の回収と確認
扶養控除申告書や保険料控除申告書などを従業員から回収し、記入内容を確認
・年末調整の計算業務
提出書類をもとに、1年間の所得税を再計算し、毎月の源泉徴収との差額を精算
・ストレスチェックの実施(従業員50人以上)
常時50人以上の事業場では、年1回のストレスチェックを実施。従業員のメンタルヘルス対策として義務付けられている
12月:賞与支給と年末調整の締めくくり
・冬の賞与支給と届出
賞与を支給する場合、支給日から5日以内に賞与支払届を提出。賞与は就業規則や評価結果に基づいて計算・支給
・年末調整の完了
調整結果に基づき、12月または1月の給与で所得税の過不足を精算。1年間の給与計算を締めくくる重要業務
・源泉徴収票の作成準備
翌年1月の提出に向け、源泉徴収票の作成を進める。税務署や市区町村への法定調書としても使用
1月:年末調整後の各種提出と36協定更新準備
・法定調書合計表の作成・提出
支払調書などをまとめ、1月末までに税務署へ提出。年末調整後の重要な税務手続き
・給与支払報告書の提出
従業員の居住市区町村に1月末までに提出。退職者・休職者も対象
・再年末調整
追加控除等が判明した場合、1月給与で再調整を実施
・36協定の更新準備
有効期間満了前に新協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る準備を行う。
2月:次年度に向けた労務管理の準備
・労働条件の見直し
賃金・労働時間・休日などの条件や評価制度の運用状況を確認し、改善点を検討
・人員計画の検討
次年度の採用計画や人員配置について検討を開始
・36協定の提出
有効期間満了前に労働基準監督署へ提出。時間外労働の法定上限(月45時間・年360時間、特別条項付きは年720時間以内)を遵守
3月:年度末処理と新年度準備の最終確認
・年度末処理
未消化の有給休暇確認や退職者の手続きを実施。年10日以上の有給付与労働者には年5日の取得義務があり、年次有給休暇管理簿の作成と3年間の保存も必須。退職者対応では健康保険・雇用保険・厚生年金の脱退手続き、退職金支払い、源泉徴収票の発行を迅速かつ正確に行う。
・新年度準備の最終確認
4月からの新年度に備え、給与改定の最終チェック、新入社員受け入れ準備、就業規則変更点の周知を完了。労働条件通知書の交付や雇入時健康診断、労働者名簿作成も基本業務として重要。常時10人以上の事業場では就業規則の作成・届出・周知が義務。
10月~3月は、年末調整や社会保険適用拡大、年度末処理と、従業員の税金や保険料に直結する重要業務が集中する時期です。
特に年末調整は従業員の生活に大きく影響するため、書類回収から計算、提出まで抜け漏れなく正確に進めることが肝心です。
計画的に進めて、新年度を余裕をもってスタートさせましょう!
年間を通じて、特定の時期だけでなく常に発生する重要な労務管理業務もあります。
| 業務分類 | 内容 |
| 勤怠管理 | 出退勤の確認、残業・休暇管理、36協定範囲内の労働時間の把握 |
| 給与計算 | 月次の給与計算、残業代・手当の計上、給与明細の発行 |
| 社会保険手続き | 入退社に伴う資格取得・喪失届、扶養変更、保険証の交付、育休・産休など |
| 入退社手続き | 雇用契約書・誓約書の整備、離職票の発行、年金手続きなど |
| 労務相談対応 | ハラスメント、勤務時間、制度に関する問い合わせへの対応 |
| 書類管理 | 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿(法定三帳簿)の更新・保存 |
| 安全衛生活動 | 衛生委員会の開催、メンタルヘルス対応、災害時対応ルール整備 |
| 情報管理 | 個人情報(マイナンバー・住所・口座情報など)の適正管理と更新、情報漏洩防止など |
| 法改正対応 | 労働法や社会保険法などの改正内容の把握と社内制度への反映 |
通年業務は、テンプレートやクラウドツールの活用で定型化・自動化を図ることで、担当者の負担を大幅に軽減することができます。
また、担当変更時もスムーズに引き継げるよう業務マニュアルや年間カレンダーでの運用管理が鍵となります。
▼労務管理がグッとラクに!厳選ツール紹介はこちら
日々の業務に追われているとどうしても緊急度の高いものから処理しがちですが、本当に大切なのは長期的な視点でのリスク回避と、従業員からの信頼を確保することです。
「どれから手をつければいいのか」「何が一番重要なのか」と悩みがちな労務管理業務の中から、特に「ここだけは押さえておきたい!」という優先すべきポイントと、具体的な業務を分かりやすくご紹介します!
労務管理で優先すべき業務を判断するうえで、特に重要なのが次の2つの視点です。
法令遵守の必須性: 法律で義務付けられているか、違反した場合に罰則や企業の信頼低下といった重大なリスクがあるか
従業員への影響度: 従業員の生活や健康、働く意欲に直接関わるか
どちらも、企業の安定運営や従業員のパフォーマンスに深く関わる要素です。
見落とすと気づかぬうちにリスクが大きくなり、後々多大なコストやブランドの信用失墜につながるおそれがあるため注意が必要です。
これらの業務は、企業のコンプライアンスや従業員の信頼にも直結するため、後回しにせず、確実かつ優先的に対応することが求められます。
| 業務カテゴリ | 理由 | 業務例 |
| 社会保険・労働保険の手続き | 法令で義務付けられており、遅延や漏れは従業員の不利益に直結。企業の信頼を損ない、行政指導や罰則の対象にも。 | ・入社時の健康保険 ・厚生年金加入 ・退職時の資格喪失手続き ・産前産後休業や育児休業の保険料免除申請など |
| 給与計算と賃金台帳の管理 | 従業員の生活に直結するデリケートな業務。ミスはトラブルにつながりやすく、正確な管理が必須。 | ・残業代 ・深夜手当の計算 ・各種控除(社会保険料、住民税など) ・賃金台帳の保管 |
| 勤怠管理(労働時間・休憩・休日) | 長時間労働は健康被害・過労死リスクに直結。未払い残業や法違反につながり、企業リスクも高い。 | ・労働時間の正確な記録 ・休憩時間の付与 ・36協定の遵守 |
| 労働者名簿・出勤簿の作成と保存 | 労働基準監督署の調査対象。不備があると是正指導・指摘を受ける恐れがある。 | ・最新の従業員情報の記録 ・欠勤、遅刻の出勤状況の管理 |
従業員が安心して働ける環境を整え、企業としてのリスクを減らすためにも、これらの業務には優先的に取り組む必要があります。
| 業務カテゴリ | 理由 | 業務例 |
| 就業規則の整備と周知徹底 | 企業のルールブックとして労使トラブル防止に不可欠。法改正に伴う見直しと従業員への周知が義務付けられている。 | ・労働時間、賃金、退職などの基本ルールを整備 ・就業規則を改定し、全従業員にメールや掲示で周知 |
| 健康診断の実施と結果管理 | 従業員の健康リスクを早期に把握し対処するため、労働安全衛生法により企業に実施義務がある。 | ・全従業員に定期健康診断を実施 ・診断結果を管理し、再検査や産業医面談など必要な対応を行う |
| ハラスメント対策と相談体制の整備 | パワハラ・セクハラ等の防止措置は企業の義務。適切な対策により安心して働ける職場づくりと法的リスク回避に貢献する。 | ・年1回以上のハラスメント研修の実施 ・社内相談窓口を設け、従業員に周知徹底する |
| 育児・介護休業制度の周知と運用 | 育児・介護休業の取得は法的権利。両立支援により定着率向上と多様な働き方の推進につながる。 | ・制度内容を社内イントラやマニュアルで周知 ・取得希望者への説明や申請手続きのサポート |

労務管理は多岐にわたるため、時に見落としがちな業務やトラブルに繋がりやすいポイントがあります。
会社を健全に運営し、従業員が安心して働ける環境を作る上で欠かせないものなので、理解しておきましょう。
「タイムカードがあるから大丈夫」と思いがちですが、実際に労働者が休憩をきちんと取っているか、サービス残業が発生していないかなど、実態を把握することが重要です。
特に休憩時間は労働時間の途中に与える義務があり、その会社の全従業員が同時に一斉にとるのが基本的なルール(例外もあり)です。
テレワークの場合も休憩時間の取得状況を確認し、適正な管理を心がけましょう。
2019年から、年10日以上の有給休暇が付与される従業員には、年5日の有給休暇を会社が時季を指定して取得させることが義務化されています。
対象者を把握して計画的に取得を促す仕組みを導入し、有給休暇管理簿で取得状況を記録することが必須です。
労働関連法規は頻繁に改正されます。
例えば、2025年4月1日からは育児・介護休業法の改正により、育児・介護休業の取得状況に関する従業員への情報提供が義務化されるなど、企業の対応が必要となる改正がありました。
常に最新情報をキャッチアップし、就業規則や社内規定を速やかに見直す習慣をつけましょう。
パワハラ・セクハラ・マタハラなど、各種ハラスメント対策は企業の義務です。
相談窓口を設置するだけでなく、その存在を従業員に周知徹底し、相談しやすい環境を整えることが重要です。
相談があった際の適切な対応方法も事前に定めておきましょう。
労務管理は単なる手続き業務だけでなく、従業員との信頼関係構築も重要です。
従業員が抱える悩みや不満を早期に察知し、定期的な面談やアンケート実施などで対応できる体制を整えることは、潜在的なトラブルの未然防止に繋がります。
結果として、従業員エンゲージメントの向上や離職率の低下といった企業経営における好影響が期待できるでしょう。
労務管理は企業の安定運営に不可欠ですが、多くの担当者が共通の悩みを抱えています。
ここでは、特に頻繁に見られる課題とその具体的な解決策をご紹介します。
労務管理は、給与計算や社会保険手続きなど細かい数字や期限が伴う業務が多く、手作業や古いシステムを使っているとヒューマンエラーや提出遅延が起こりがちです。
特に繁忙期は担当者の負担が増えミスがさらに発生しやすくなります。
これにより従業員の給与や保険料に影響が出たり、会社が罰則を受けたりするリスクが高まります。
例えば、自動計算機能やアラート機能により入力ミスや期限の見落としを防ぐことが可能になる労務管理システムの導入を検討してみましょう。
業務の正確性と効率を大幅に向上させることができます。
勤怠はタイムカード、給与計算は表計算ソフト、人事情報は紙や別のデータベース…と、複数のツールや記録方法が混在している会社は少なくありません。
これでは必要な情報がすぐに引き出せず、データ連携の際に手間やミスが発生しやすくなります。
情報がバラバラの場合全体の状況把握も困難になり、非効率な状態に陥ります。
情報が一元管理できる統合型の労務管理システムへの移行が有効です。
勤怠・給与・人事情報などを連携させることでデータの二重入力や転記ミスをなくし、作業の手間を大幅に削減することができます。
労務管理の知識やノウハウが特定の担当者しか持っていない「属人化」は、多くの企業で共通の課題です。
担当者が急に休んだり退職した場合、業務が完全にストップしてしまい会社全体に大きな影響が出てしまいます。
新しく担当者が決まっても、不十分な引き継ぎでは業務を覚えるのに時間がかかり、ますます負担が大きくなるでしょう。
マニュアル作成はもちろん重要ですが、業務プロセス自体をシステムで標準化することが最も効果的です。
システムを導入すると誰が操作しても同じ手順で業務が進められるため、担当者の変更があってもスムーズに引き継ぐことができます。
労働基準法や社会保険関連の法律は頻繁に改正されるため、労務管理担当者は常に最新の情報をキャッチアップし、社内制度や手続きを更新していく必要があります。
しかし、通常業務に追われていると法改正の情報収集や対応が後手に回り、知らず知らずのうちに法令違反を犯してしまうリスクがあります。
法改正に自動で対応する機能を持つ労務管理システムの導入が有効です。
システムが自動で最新の法律に合わせて更新されるため、担当者が個別に法改正の内容を調べる手間を省き、法令遵守を確実にサポートしてくれます。
多くの課題に対する解決策として「システム導入」を挙げてきましたが、「結局システム頼みなのでは?」と感じた方もいるかもしれません。
たしかにシステムは便利なツールですが、それだけで労務管理がすべて解決するわけではありません。
労務管理の本質は、煩雑な作業を効率化し、担当者が本来注力すべき従業員とのコミュニケーションや制度改善といった人にしかできない業務に時間を割けるようにすることです。
労務管理システムは、そうした本質的な業務に集中するための土台を整える、心強いサポート役といえるでしょう。
次章よりおすすめのシステムを厳選してご紹介しますので、次の一手の参考にしてみてください。

画像出典元:「オフィスステーション 労務」公式HP
「オフィスステーション 労務」は、社会保険労務士や税理士も納得の118種類の帳票作成に対応したクラウド型労務管理システムです。法令改正や様式変更にも自動で対応し、常に最新の状態を維持してくれます。
他社の給与・勤怠システムとのAPI・CSV連携やマイページ機能による業務効率化と正確性が魅力。利用継続率は99.7%を誇り、多くの企業から信頼を得ています。
| おすすめ企業規模 | 中小企業 |
| こんな方におすすめ | コストを抑えたい企業 |
| 機能 | ・従業員情報の一元管理 ・充実したセキュリティ ・機能拡張が可能 |
| 提供形態 | クラウド |
| 無料トライアル | 30日間の無料トライアルあり |

社会保険労務士 金山杏佑子
「オフィスステーション 労務」は100人規模の大企業や社労士向けのシステム。 対応帳票が他システムと比べてもかなり多いので玄人向けのシステムですね。逆に人数がそこまで多くないような企業では、そこまでの機能が必要ないとなるパターンが多いです。
オフィスステーション 労務の料金プランは1種類。
初期費用は登録料の11万円(税込)、そこから製品利用料:従業員ひとりあたり440円(税込)/月がかかります。
| 製品利用料 | |||
| 従業員数 | 100名 | 500名 | 1,000名 |
| 月額利用料 | 従業員1名あたり440円 | ||
| 年額利用料 | 528,000円 | 2,640,000円 | 5,280,000円 |

商社
251~500人
管理者向けにおすすめ





色々なシステムを検討して最後にスマートHRとオフィスステーションの2択になり、価格面をみてオフィスステーションに決めました。管理者にとってはオフィスステーションの方が使いやすいと感じました。

コンサルティング
11〜30人
社会保険の手続きの一部には対応しておらず





簡単な手続きはオフィスステーションで十分でしたが、オフィスステーションでは申請できない社会保険の手続きもありました。そこにも完全に対応したら、完璧なツールだったと思います。

「マネーフォワード クラウド人事管理」は、従業員情報のオンライン収集と一元管理を実現するクラウド型サービスです。フォームの作成から回収までをWeb上で完結することができます。
従業員情報は他のマネーフォワード クラウドサービスと連携し、データの一貫性と業務効率化を実現。柔軟な承認設定やカスタム項目の追加が可能で、企業のニーズに合わせた運用が可能です。
| おすすめ企業規模 | 大~中小企業 |
| こんな方におすすめ | スムーズな連携をしていきたい企業 |
| 機能 | ・入社手続き自動化 ・従業員情報が自動でデータ化 ・雇用契約書の作成から締結もWeb上で完結 |
| 提供形態 | クラウド |
| 無料トライアル | なし |
法人向け(50名以下)の料金プランは下記になります。
| ひとり法人プラン | スモールビジネスプラン | ビジネスプラン | |
| 基本料金 (年払い) |
2,480円/月 (29,760円/年) |
4,480円/月 (53,760円/年) |
6,480円/月 (77,760円/年) |
| アカウント数 | 1名 | 3名 | 10名 |
| アカウントの追加 | ✕ | ✕ | 11名以上から600円/名 |
51名以上の場合、豊富なラインナップから必要なサービスを選択し、利用人数に応じてサービスごとに定額の利用料金が発生します。設定人数を超えた場合に超過料金がかかります。

「SmartHR」は、70,000社以上の導入実績を誇る7年連続シェアNo.1の労務管理システムです。国内有名企業でも数多く導入されており、大規模処理やセキュリティの面でも信頼度十分です。
e-Gov APIと連携しており、役所やハローワークへの書類提出もWeb上から可能。あらゆる手間を省くことで本来の業務に集中することができ、生産性の向上につながります。
| おすすめ企業規模 | 全ての規模に対応可能 |
| こんな方におすすめ | 社労士がいなかったり従業員が多い企業 |
| 機能 | ・従業員情報の一元管理 ・Web上で給与明細、年末調整など自動で作成 ・入退社・社会保険・雇用保険などの手続きや管理が可能 |
| 提供形態 | クラウド / SaaS |
| 無料トライアル | 15日間の無料トライアルあり |

社会保険労務士 金山杏佑子
「SmartHR」は、幅広い規模の企業にオススメしているシステムです。 30名未満の会社では無料で利用できる点から中小企業にも導入されている印象。勤怠管理や給与計算の機能はないが、API連携させれば他システムと組み合わせて問題なく使えるので総合的におすすめできます。

株式会社OKAN 代表取締役 CEO 沢木 恵太
「SmartHR」は生産性の観点から、非常に役に立つサービスです。例えばUXが悪く人事総務や労務に問合せが殺到してしまうと、せっかく生産性を上げるために導入したのに本末転倒になってしまいます。そこでSmartHRのように、UI/UXが良いサービスを導入すればしっかりと生産性を向上させることができます。
| HRストラテジー プラン |
人事・労務 エッセンシャルプラン |
タレントマネジメント プラン |
|
| 月額料金 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| 機能 | 従業員データベース・労務管理・タレントマネジメントの全ての機能 | 入社手続き・雇用契約・給与明細・年末調整・スキル管理など | タレントマネジメント機能すべて |
他にも、従業員50名以下企業向けの「労務管理プラン(労務管理機能のみ)」、小規模事業者向けの「¥0プラン(30名までの従業員情報を登録可)」があります。
どのプランでも初期費用はなし。15日間無料トライアルあり。

コンサルティング
101~250人
間違いやすい部分にコメントがあるのでわかりやすい





年末調整をこのSmartHRで行うようになって今年で2回目でしたが、間違いやすい部分は補足のコメントがあるのでとてもわかりやすいです。いつでもオンラインでパパっと作成・申請できるので大変便利でした。

メーカー
51〜100人
初期設定に時間がかかった





操作こそ簡単でしたが、初期設定に時間がかかりました。もっと簡単なマニュアル等があれば初期の稼働がスムーズにいったと思います。

画像出典元:「ジョブカン労務HR」公式HP
「ジョブカン労務HR」は、入退社手続きや社会保険手続きの電子申請を一元管理できるクラウド型労務管理システムです。ジョブカンシリーズと連携することで、一元管理が可能。
| おすすめ企業規模 | 中小企業~スタートアップ |
| こんな方におすすめ | 丁寧なサポート体制が必要な企業 |
| 機能 | ・従業員情報の一元管理 ・あらゆる手続きの自動化 ・TODOリストによる進捗管理等、各種機能で業務効率化をサポート |
| 提供形態 | クラウド / SaaS |
| 無料トライアル | 30日間の無料トライアルあり |

社会保険労務士 金山杏佑子
ジョブカンは費用が安く、従量課金制なので「かかる費用」が分かりやすいので、導入コスト・ハードルが低いのが良い点。シリーズ化されているので単品導入が可能、知名度も高いので人気のシステムという印象です。一方で、初期設定が少し難しいです。ヘルプページだけでは苦労する企業もあると思います。
中小企業向けのプランは下記になります。初期費用・サポート費用はかかりません。
また、月額最低利用料金は2,000円(税抜)となります。(電子契約料は除く)
| 無料プラン | 有料プラン | |
| 月額料金/ユーザー | 0円 | 400円 |
| 電子契約機能 | なし | +200円/1送信(1件) |
| 従業員数 | 5名まで | 無制限 |

小売
101~250人
膨大な社員情報がスムーズに管理できる





膨大な社員情報を管理しているような職種や部署におすすめできます。正確に、そして必要なときに目的のデータをすぐに出せるなど、情報管理がスムーズにできるようになります。

サービス
51〜100人
旧姓と新姓の管理がしづらいのがデメリット





「結婚をしたあとの旧姓と新姓を使い分けての管理」が少々しにくいというのは気になる大きなデメリットであり、不便な箇所だと思います。女性社員も多い会社からするとこの箇所は強く改善を希望します。

「freee人事労務」は、幅広い労務管理業務を効率化し、企業の成長ステージにあわせた使い方が可能な労務管理システムです。これだけで、勤怠管理や給与計算、年末調整に助成金の申請までカバーできます。
設立したての企業から中堅以上まで規模にあわせたプランが用意されているので、業種規模問わず使いやすいシステムです。
| おすすめ企業規模 | 中小企業 |
| こんな方におすすめ | 幅広い労務業務を一元化したい企業 |
| 機能 | ・社内の勤怠管理を自動で集計 ・年末調整や労務保険・住民税の更新などを管理・サポート ・入社情報など労務管理機能 |
| 提供形態 | クラウド / SaaS |
| 無料トライアル | あり |

社会保険労務士 金山杏佑子
「freee人事労務」は、勤怠管理・給与計算・入退社時の対応など一連の業務が全て完結します。その分、料金はジョブカンなどと比較すると少し高いですし、カスタマイズの幅は狭まります。 とりあえず一連の労務管理を全体的に楽にしたい!という企業には合うと思います。
| ミニマム | スターター | スタンダード | アドバンス | |
| 最小5名分料金/月 (年払い) |
2,600円 (2,000円) |
3,900円 (3,000円) |
5,200円 (4,000円) |
7,150円 (5,500円) |
| 従業員料金/人 (6名以降〜) |
400円/月 | 600円/月 | 800円/月 | 1,100円/月 |
※上記は全て税抜価格です。
どのプランでも初期費用はかかりません。

IT
1001人以上
労務まわりを一つに統合できる点が魅力





勤怠管理システムだけではなく給与計算や年末調整、労務手続き(入退社手続き)等を一つのシステムに統合できる点は、大きな魅力だと思います。一つに統合することでコストメリットが生かせました。

コンサルティング
11〜30人
電話対応が付かないプランがある





選んだ料金プランによっては電話によるヘルプデスク機能が付いてこない点が不便だと感じました。最初は一番価格の安いプランを選択していたが、人事、経理から電話で聞かないとわからないことがあると報告が上がってきたため、プランを変更しました。
▼システムをもっと比較検討したい方はこちら!資料もダウンロードできます
本記事では、労務管理の基本的な知識から、人事総務部の皆さまが日々直面する「処理ミス」「情報分散」「属人化」「法改正への対応」といったリアルな課題、そしてその解決策までを網羅的に解説しました。
年間を通じた業務スケジュールで全体像を把握し、見落としがちな業務や法律知識を整理することで、自社の労務管理は格段に安定するでしょう。
労務管理の「基本」とは、法令遵守だけでなく、効率的な業務で従業員の信頼を築き企業を強くすることです。
こうした課題には、労務管理システムの導入が非常に有効です。
労務管理システムはこれらの課題を一元的に解決し、業務負担を軽減する強力なツールとなりますので、もし現状に課題を感じているようでしたら、一度導入を検討してみてください。
画像出典元:O-DAN

【2023年最新】賞与に必要な手続きと社会保険料の計算方法を簡単解説

社員管理とは?従業員管理のコツやメリット、おすすめ管理システムも

労務費とは?人件費との違いや計算方法・内訳・労務費率をサクッと解説

SmartHRとジョブカン労務HR徹底比較!料金・機能・使いやすさでわかる違いとは?
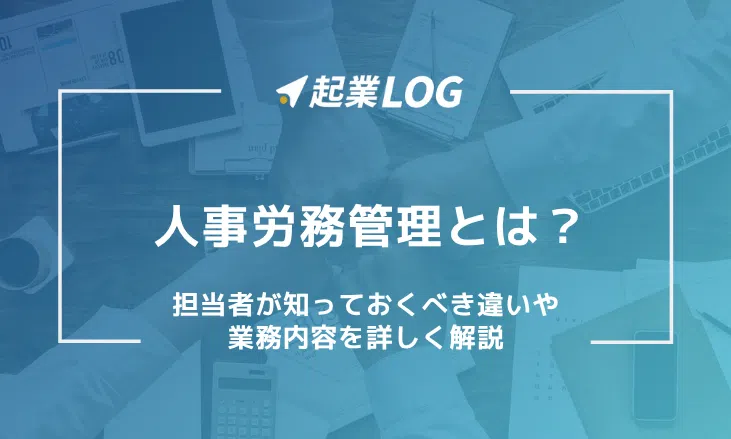
人事労務管理とは?担当者が知っておくべき違いや業務内容を詳しく解説
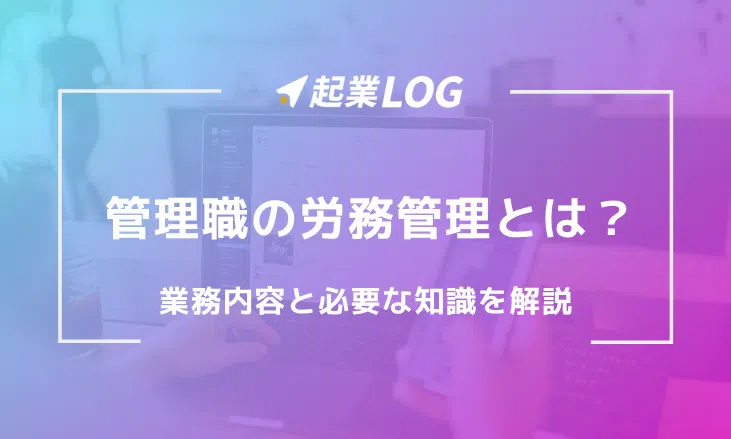
管理職の労務管理とは?業務内容と必要な知識を解説

労務管理システムとは?導入メリットや自社に合った選び方を解説

所定労働時間と法定労働時間とは?違いや残業代について簡単に解説

労務とは?人事との違いや社内での役割・仕事内容を大公開!

就業規則を変更する!変更が必要なケースと手順とは?