
新しい社員を迎える際、会社側で行う入社手続きにはさまざまな準備が必要です。
必要書類の作成や行政手続き、備品の準備まで、スムーズな手続きが求められます。
本記事では、会社側が行うべき入社手続きの全体的な流れと、注意点について解説します。
これを読めば、会社側で行う入社手続きの進め方をしっかり理解でき、スムーズに準備が進められるようになります!
目次
会社側で進めるべき入社手続きのチェックリストです。
不備や漏れが発生しないよう、上から順に行ってください。
次の章からは、入社手続きチェックリストに沿って、それぞれの内容について詳しく解説します。
新入社員の入社手続きを進めるにあたり、会社側で準備すべき書類は以下の通りです。
内定者が決定したら、まずは採用通知書(内定通知書)・入社承諾書・誓約書の3点を作成し、採用の通知と、内定者の入社意思の確認を行います。
採用通知書(内定通知書)は、内定者に対し、採用する旨を通知する書面で、交付は法律上の義務ではありません。
採用通知書(内定通知書)には、
などを記載します。
採用通知書を出した後の雇用者都合による採用取り消しは労働契約法第16条によって違法となるので注意しましょう。
入社承認書・誓約書は、採用通知書(内定通知書)を受けて、内定者の入社意思を書面に残すためのもので、記載内容に決まりはありませんが、署名・捺印の欄を設けるのが一般的です。
入社承認書の返送をもって、内定承諾となります。
雇用契約書・労働条件通知書は、2つとも「労働条件を内定者に明示する書類」のことです。
労働条件通知書は、会社の決定した労働条件を「通知」する書面で交付が法律で義務付けられています。
雇用契約書は「通知」に加え記載した労働条件に対し内定者の「合意」がなされたことを証明するものであり、交付は義務ではありません。
ただし、トラブル回避のためにも書面で雇用契約書を作成し、署名・捺印を行って契約を締結しておくのが無難です。
雇用契約書には、以下の内容を盛り込むのが一般的です。
雇用契約書・労働条件通知書については、こちらの記事で詳しく解説しています。
扶養控除等申告書は、年末調整を行う際に必要な書類です。
扶養する家族の有無に関わらず提出してもらわなければなりません。
初回の給与を支払う際に必要になるため、入社前に提出を依頼しましょう。
健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届は、社会保険に加入する際の手続きに必要な書類です。
内定者に扶養家族がいる場合のみ、提出してもらいます。
入社時に回収する書類関係も、事前に通知し、準備を促すようにしましょう。
入社時に回収する書類の代表的なものは、以下です。
| 必要書類 | 詳細 |
| 年金手帳 | 厚生年金保険の加入手続きに必要な基礎年金番号を確認できる書類として年金手帳か基礎年金番号通知書を提出。 |
| 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 扶養者がいる・いないに関わらず納税のため提出が必須。 |
| 健康保険被扶養者 (異動)届 |
配偶者・子供などがいる場合、新たに転職先の健康保険に加入する際に必要。 |
| マイナンバー | 社会保険や雇用保険の手続きで必要。 マイナンバーカードがない場合は、身分証明書+通知カード、 もしくはマイナンバー記載の住民票の提出が必要。 |
| 給与振込先申請書 | 給与振り込み用の銀行口座の指定に必要。 |
以下は、対象者だけであったり、企業ごとに異なるものになります。
| 必要書類 | 詳細 |
| 各種手当支給届出書 | 通勤手当、住宅手当、子供手当などの各種手当の設定がある場合は支給に必要。 |
| 雇用保険被保険者証 (中途入社者のみ) |
雇用保険に加入した際に発行される証明書。 最初に就職した企業から発行されており、退職時に返却される。 前職がある場合は、雇用保険加入のために必要なので提出必須。 |
| 国民年金第3号被保険者 資格取得届 (該当者のみ) |
第3号被保険者=扶養されている人の国民年金保険料を免除するための書類。 |
| 源泉徴収票 (中途入社者のみ) |
入社年に給与所得があった場合は提出必須。 年末調整後に入社した場合は、提出不要。 |
| 健康診断書 | 直近、もしくは入社後3カ月以内に受診したもの。 |
| 雇用契約書、入社承諾書 | 署名・捺印をしたもの。 (事前に郵送で返送を求められる場合もあり) |
| 住民票 | 個人情報の観点から企業によっては回収しないこともあり。 |
| 身元保証書 | 社員の過失があった際に、身元保証人に損害賠償請求を行うことができる。 |
| 個人情報保護法に基づく 誓約書 |
職種によって必須。 |
| 資格免許証、合格証明書類 | 職種によって必須。 |
| 卒業証書 | 職種によって必須。 |
入社に関する書類の多さにうんざりしてしまった、より効率的に入社手続きを行いたいと思った方には、労務管理システムがおすすめです。
入社手続きを含む労務周りの業務を一元管理することのできるシステムで、導入する企業も増えています。
詳細を先にご覧になりたい方は、以下からご確認ください。
新しい従業員が入社し、必要書類を回収した後は、早急に以下の手続きを行いましょう。
厚生年金と雇用保険、住民税の手続きは、電子申請、郵送、窓口持参のいずれかで行えます。

画像出典元:日本年金機構
社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)の加入手続きは、従業員に健康保険証を早く手渡すため早急に行います。
社会保険の加入手続きは、従業員の扶養家族の状況によって3つうちいずれかを、健康保険組合、厚生年金基金または年金事務所に入社後5日以内に提出します。
1. 被保険者資格取得届
2. 健康保険被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者関係届
3. 国民年金第3号被保険者関係届
社会保険は、以下に該当する企業は、必ず加入する必要があります。
また、該当企業のうち社会保険に加入させる必要がある従業員は、次の通りとなります。
1 週の所定労働時間が20時間以上あること
2 雇用期間が1年以上見込まれること
3 賃金の月額が8.8万円以上であること
4 学生でないこと
5 特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤めていること
なお、次に該当する従業員は、加入義務はありません。

画像出典:『ハローワークインターネットサービス』公式HP
雇用保険の手続きは、企業の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、雇用保険被保険者資格取得届を翌月10日までに提出します。
その際に、法定三帳簿(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿)の添付が義務付けられているので、準備が必要です。
雇用保険の加入の義務がある従業員は、以下の通りです。
次の(1) 及び(2) のいずれにも該当するとき
具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
住民税は、
の2つの徴収方法があります。
特別徴収する場合は、会社側が従業員が住む市区町村へ切り替え手続きを翌月10日までにしなければなりません。
前職でも特別徴収をしていた場合は「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出します。
普通徴収から特別徴収に切替える場合は「特別徴収への切替申請書」を提出します。
住民税の届け出書類は、各市区町村のホームページからダウンロードします。
入社してきた従業員の情報を「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿等」に記載します。
法定三帳簿の作成は労働基準法で義務付けられており、記載内容と対象者が決められています。
法定三帳簿は、紙台帳のようなアナログ管理とExcelや労務管理システムのなどのデジタル管理どちらでも構いません。
| 帳簿の内容 | 帳簿の対象者 | |
| 労働者名簿 | 氏名、生年月日など個人情報を管理する | 日雇い以外の雇用形態(正規、非正規、パートタイムなど) |
| 賃金台帳 | 労働時間、給与の支給額など労働者の給与に関して記録する | すべての雇用形態 |
| 出勤簿 | 入・退社時間や休憩時間などを記録する | すべての雇用形態 |
法定三帳簿は、こちらの記事で詳しく解説しています。
下記のような備品を支給している場合は、従業員の入社日前に用意します。

入社手続きには様々なものがあり多岐にわたります。
では、どのような点に注意すればいいのでしょうか。
人を雇用する場合に守るべき法律にはどんなものがあるのかを、きちんと確認し、遵守するようにしなければなりません。
特に、労働関係に関する法律には、重い罰則規定が課されているものもありますので、会社としては安易に違法することがないように、内容を把握しておく必要があります。
社会保険・雇用保険・納税に関する入社手続きは、提出期限に注意しましょう。
特に社会保険は入社から5日以内なので、従業員には入社前に必要書類を伝えておきます。
マイナンバーや住所など従業員個人の情報も必要ですし、添付書類として前の会社から取り寄せておかなければならない書類もあります。
会社側がしっかりと必要書類と期限を理解しなければなりません。
入社手続きは、従業員の重要な個人情報を扱うため、閲覧する者の制限や、書類の取り扱いができる権限なども明確に決めておく必要があります。
最近は、紙でのアナログな管理ではなく、セキュリティの面で様々な規制のかけられる労務管理システムを導入し、情報管理を徹底している企業も増えています。
従業員に安心して入社手続きに必要な書類を提出してもらえる労務管理体制が求められます。
ここまで入社手続きについて解説してきましたが、作成・提出書類が多く、人数が10名以上いる企業だと紙ベースでの管理がかなり煩雑な業務になるでしょう。
そこで最近は、労務管理システムを導入し、入社手続きを含む労務周りの業務を一元管理する企業が圧倒的に増えています。
労務管理システムとは、法定三帳簿はもちろん、入退社手続き、申請書類の自動作成、年末調整、電子申請など様々な業務が1つのシステム内で完結できます。
また、クラウド型の労務管理システムであれば、従業員に直接システム上で情報入力してもらうことができるので、人事担当者の負担は大きく削減されます。
労務管理システムで自動化・効率化できる業務には、以下のようなものがあります。
| 業務 | 業務内容 |
| 帳票自動作成 | 従業員データや手続きの情報を基にして帳票を自動作成します。 |
| 入退社手続き | 社会保険・雇用保険の資格取得書類や扶養控除申告書等の作成・提出を効率化します。 |
| 年末調整 | 年末調整に必要な書類を自動作成をします。 |
| 電子申請 | 役所まで足を運ばずにクリック1つで手続きが完了します。 |
| マイナンバー管理 | 各種提出書類に必要なマイナンバー管理もクラウド上で可能です。 |
上記以外にも、各社様々な機能や特徴を持った労務管理システムがあり、入社手続きだけでなく労務に関する様々な業務の効率化に役立てることが可能です。
自社に必要な機能や検討する上でのポイントなどをまとめた無料の資料や記事がありますので、以下もご参照ください。
入社手続きは、流れと必要書類をきちんと理解し、法令を守って事前準備を行えば、比較的扱いやすいルーチン業務です。
また近年は、労務管理システムなどのシステムの導入によって、より業務効率を上げ、情報管理もしやすくなっています。
スムーズな入社手続きを行い、従業員が働きやすい環境を整えて信頼関係を構築できると良いでしょう。
画像出典元:pixabay

【2023年最新】賞与に必要な手続きと社会保険料の計算方法を簡単解説

社員管理とは?従業員管理のコツやメリット、おすすめ管理システムも

労務費とは?人件費との違いや計算方法・内訳・労務費率をサクッと解説

SmartHRとジョブカン労務HR徹底比較!料金・機能・使いやすさでわかる違いとは?
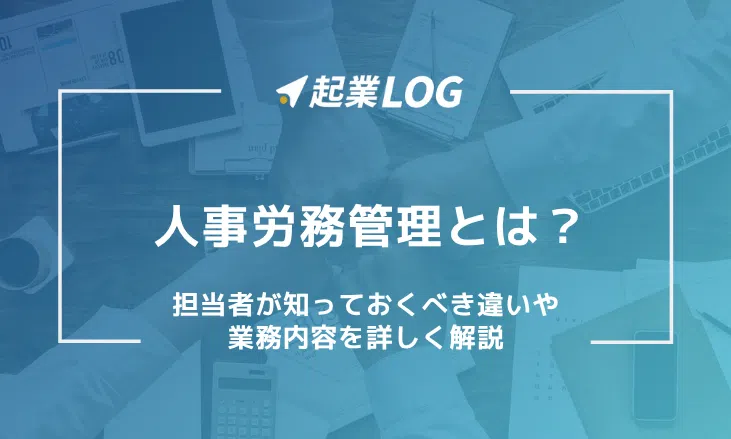
人事労務管理とは?担当者が知っておくべき違いや業務内容を詳しく解説
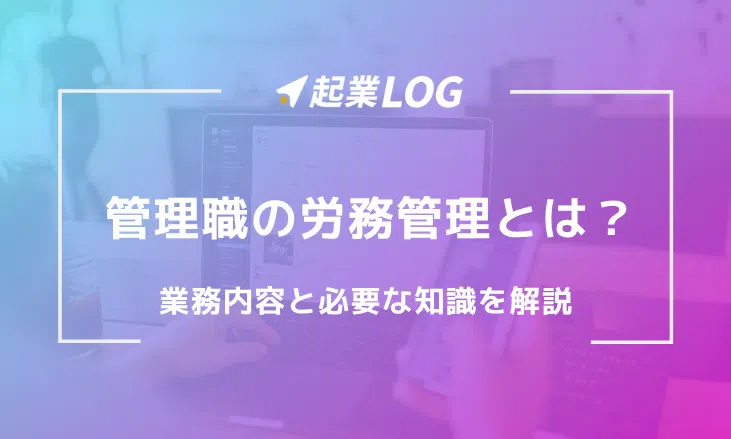
管理職の労務管理とは?業務内容と必要な知識を解説

労務管理システムとは?導入メリットや自社に合った選び方を解説

所定労働時間と法定労働時間とは?違いや残業代について簡単に解説

労務とは?人事との違いや社内での役割・仕事内容を大公開!

就業規則を変更する!変更が必要なケースと手順とは?