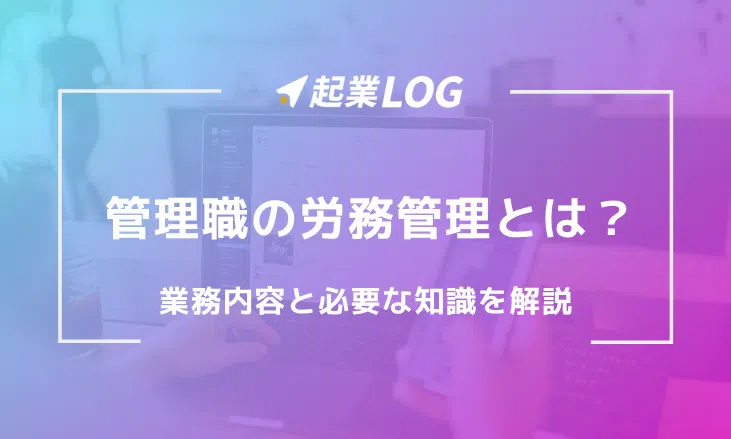
管理職の労務管理は、従業員のモチベーションや生産性の向上に直結する、非常に重要な業務のひとつです。
しかし、近年では、多様化する働き方への対応やハラスメント防止、メンタルヘルスケアの強化など、管理職に求められる役割は一層複雑化しています。
労務管理の方法を誤ると、社内外からの信頼を損ねるだけでなく、法的リスクや企業イメージの低下にもつながりかねません。
本記事では、管理職が行うべき労務管理の内容や目的、直面しやすい課題と対策について詳しく解説します。
労務管理を効率化したい方はこちら
このページの目次
管理職が行うべき労務管理とは、従業員の勤怠や労働環境、メンタルヘルス、福利厚生といった労働に関わる事項を管理・運営する業務を指します。
従業員と健康的で良好な関係を構築し、生産性を向上させるためには、適切な労務管理が欠かせません。
また、近年では、コンプライアンスやハラスメント防止、ワークライフバランスの実現といった観点からも、労務管理の重要度は増しています。
労務管理の主な目的は、以下の3点です。
それぞれの項目について解説します。
すべての労働人材を、適所に配置することによって生産性の向上を図ります。
従業員のスキルや知識、技能に応じて最適な部署や職種に配置できれば、成果が出やすくなり、企業価値も向上します。
こうした取り組みが従業員の働きやすさに反映され、生産性の向上→満足度の向上→社会的信用の獲得といった好循環を生み出すことができます。
労働環境が適切に整備され、福利厚生や勤怠管理が充実すると、従業員のモチベーション向上につながります。
企業から大切にされていると感じられれば、従業員に安心感が生まれ、心身の健康やワークライフバランスが維持しやすくなります。
愛社精神も育まれるため、仕事への集中力も高まるでしょう。
結果として各業務の成果が上がりやすくなり、業績アップに寄与します。
労働基準法や労働安全衛生法など、企業には遵守すべき労働関係法令が複数存在します。
それらに沿った労働環境を整備することは、企業の社会的責任であり、違反した場合には行政指導や罰則の対象にもなり得ます。
たとえば、長時間労働や休暇不足、不衛生で危険な労働環境を放置していると、従業員の健康リスクが増し、労災や訴訟といった深刻な問題に発展する可能性もあります。
こうした事態を回避するためにも、法令に基づいた適切な労務管理は欠かせません。
管理職が行うべき労務管理の主な業務は、以下の5つになります。
それぞれについて解説します。
部下が、労働基準法や就業規則で定められた範囲内で勤務しているかを管理します。
具体的には、以下のような項目があります。
遅刻や早退、有給休暇の取得、時間外労働については、その都度理由も把握し、記録に残しておきます。
部下が、雇用契約で定められた労働条件に沿って働けているかを把握・管理します。
具体的には、以下のような項目があります。
労働基準法(第15条)では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と規定されています。
契約内容と実際の勤務実態が一致していなければ、労働基準法違反の恐れがあるため注意しなければなりません。
部下のワークライフバランスを調整するのも管理職の大事な労務管理です。
ワークライフバランスを充実させるには、まず部下一人ひとりの状況やニーズによく耳を傾ける必要があります。
その上で、以下のようなサポートを適切に行えば、従業員の満足度や業務パフォーマンスの向上が期待できます。
これらを管理職自身が率先して活用・推進し、チームで協力し合う風土作りを行うことが、全体のワークライフバランス向上には不可欠です。
近年、多様化かつ複雑化しているハラスメントへの予防策を講じたり、発生した場合に対応したりするのも管理職の役割です。
ハラスメントに関する研修を実施し、どのような言動がハラスメントに該当するかを共有・啓発することで、未然に防ぐ体制を構築します。
相談窓口の設置や、日頃からの丁寧な声かけ・観察を通じて、問題の早期発見につなげる工夫も重要です。
実際にハラスメントが発生した場合は、速やかに事実確認を行い、被害者の保護を最優先に対応します。
同時に加害者には企業としての方針に基づき、毅然とした対応と処分を行い、再発防止に努めることが管理職の責任です。
怪我や病気と違って、メンタルの不調は外見から気づきにくいのが一般的です。
そのため、部下とのコミュニケーションを密にとり、人間関係や仕事に不満やストレスがないか、無理をしすぎていないかといった状態を把握するように努めなければなりません。
問題があれば、配置転換や業務量の調整を行い、自身の対応では難しいと感じた場合は、早めに産業医や社内の相談窓口、外部の専門機関へつなぐことも必要です。
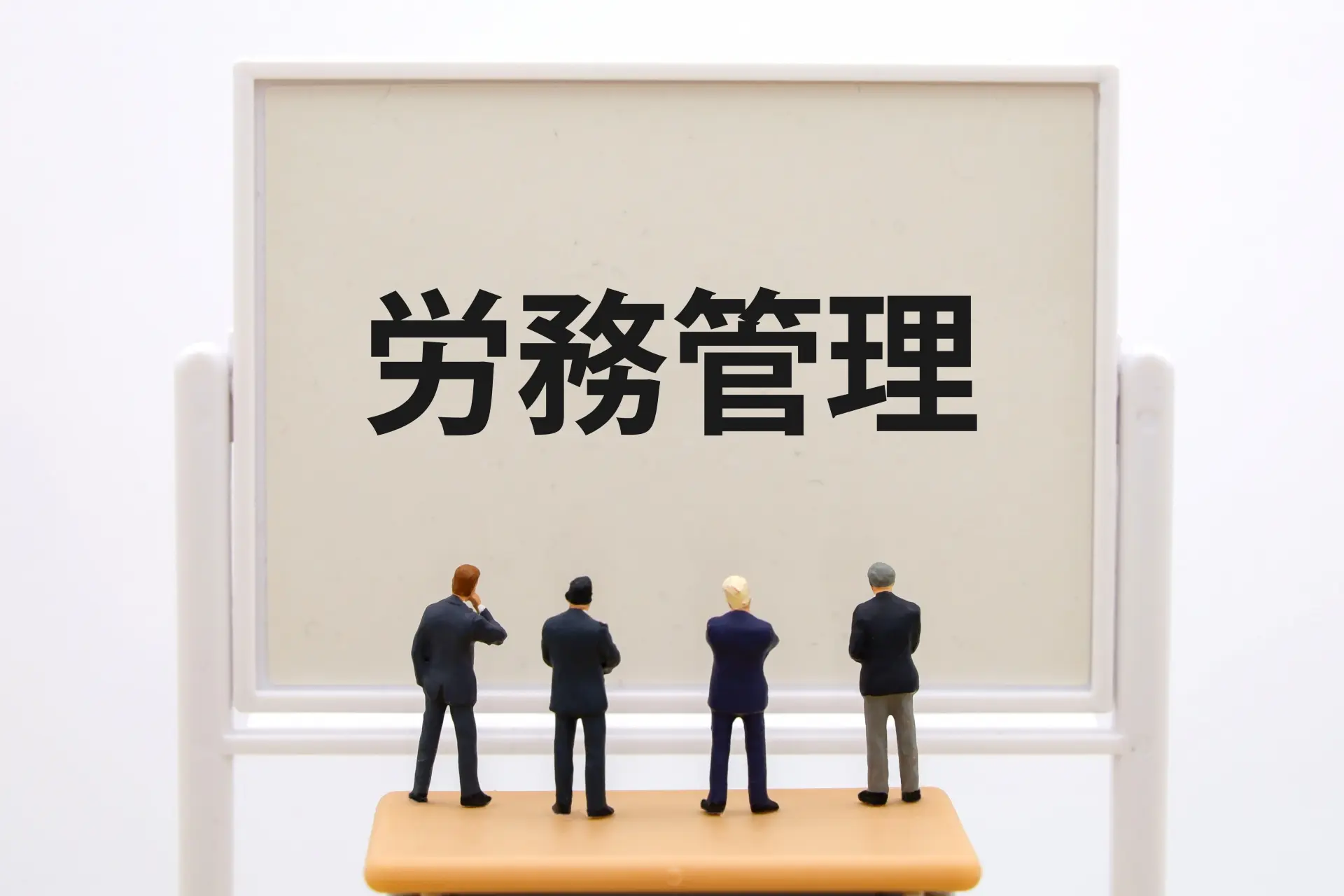
管理職が労務管理を行う上で必要な知識とスキルについて解説します。
具体的には、以下の3つになります。
それぞれについて解説します。
労務管理に関する法令は複数ある上、その中身も頻繁に変更されるため、常に知識をアップデートしておく必要があります。
労働基準法は、労働条件の最低基準を定めた法律です。
主に次のような項目が定められています。
例えば、時間外労働について定めているのが「36協定(サブロク協定)」です。
1日8時間、週40時間を超えて働かせる場合は、労使間で36協定を締結の上、労働基準監督署への届出が必要です。
例外も含めて、労働時間の上限や手続きは細かく規定されているので、管理職は正確に把握して管理しなければなりません。
労働安全衛生法は、労働災害や健康障害から従業員を守ることを目的とした法律です。
安全衛生管理体制の確立、危険・健康障害の防止措置、機械や有害物の規制などが、細やかに定められています。
職種や事業規模によって、安全管理者や衛生管理者、衛生委員会の設置などが義務付けられています。
これらを怠った場合の罰則規定もあるため、管理職には厳密な管理が求められます。
労働契約法は、労働契約の基本的なルールや考え方を定めた法律です。
労働契約の締結、労働条件の変更、解雇などに関する民法の補完的役割を担っています。
例えば、「労働契約法(第3条)」は、雇用契約において企業側の立場が強くなりがちな現実を踏まえつつも、あくまで労働者と使用者は対等であり、力関係の不平等があってはならない、という考え方を明文化したものです。
使用者が一方的に条件を変更したり、不利益な対応を行ったりすることは原則として認められず、労働条件の変更にも合理性や合意が求められます。
男女雇用機会均等法は、性別を理由に雇用における差別があってはならないことを定めた法律です。
これは、あらゆる業種・業態で生じやすく、慣習化している例が少なくないため、とくに注意が必要です。
例えば、出産や育児を理由にした降格・解雇は法令違反となります。
また、時間外労働や夜勤を男性にのみ限定するのも違反行為に該当します。
管理職は、「女性だから」「男性だから」という固定観念を排除して、機会を平等に与える考え方を持つ必要があります。
違反した場合、すぐに罰則が科される訳ではありませんが、厚生労働大臣や都道府県労働局長への報告を求められたり、助言・指導・勧告を受けたりする可能性があります。
法定三帳簿や労務管理で必要な書類について知りたい方はこちら
従業員のプライバシーと個人情報は、企業や、それを知りうる管理職、外部関係者(産業医・顧問弁護士)などによって固く保護されるべきものです。
これは個人情報保護法によって定められています。
ただし、健康状態などの情報は、仕事内容や立場を配慮する上で共有しなければならないケースもあります。
その際は、必ず本人の承諾を得た上で、関係者のみに必要最低限の範囲で共有することが求められます。
管理職は、こうしたセンシティブな情報を慎重に取り扱うことで、部下からの信頼を得るよう努めなければなりません。
管理職と部下との間で精神的な壁があったり、関係が表面的で希薄だったりすると、労務管理はうまくいきません。
部下からの信頼が得られていなければ、ハラスメントやメンタルヘルス、仕事への不満や不安を本音で打ち明けてはもらえないからです。
こうした事態を回避するためにも、管理職には以下のようなコミュニケーションスキルが求められます。
コミュニケーションスキルは、一朝一夕で身につくものではなく、そして完璧もありません。
日々の仕事の中で、表情を意識したり、挨拶を心がけたり、目を見て話しかけたりといった地道な努力を継続していく姿勢が大切です。
管理職にありがちな労務管理上の課題と、その対策について整理します。
具体的には、以下の項目への留意が必要です。
コンプライアンスへの取り組みが甘いと、労務管理に支障をきたします。
労働関係法令、就業規則、社会的倫理など、遵守すべきコンプライアンスの範囲は非常に広いです。
特に労働関係法令は近年頻繁に改正されるため、常に最新の情報を把握しておく必要があります。
管理職自身が遵守するのはもちろん、部下にも研修を実施したり、マニュアルを共有したり、相談窓口を設置したりするなどの対策が必要です。
働き方改革関連法が施行されたことにより、近年、働き方が多様化しています。
在宅勤務やノマドワーク、フレックスタイム、副業、みなし残業、育児・介護休暇など、さまざまな働き方への柔軟な対応が求められます。
社内で新たな働き方が根付くには、これらについて、従業員が納得できるような運用ルールや社内インフラを整備することが重要です。
管理職には、ハラスメントに対する高い理解と、その防止および発生時の的確な対応力が求められます。
ハラスメントは多様化しており、現在では以下のような種類が存在します。
| パワーハラスメント | 相手に精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為 |
| セクシャルハラスメント | 相手の意に反する性的言動により、精神的苦痛を与えたり、働きにくくさせたりする行為 |
| モラルハラスメント | 相手の人格を傷つけたり、精神的苦痛を与えたりする嫌がらせ行為 |
| マタニティ / パタニティハラスメント | 妊娠・出産・育児に関連づけて降格・解雇したり、休暇を取ることを批判したりする行為 |
| アルコールハラスメント | 望まない相手に飲酒を強要する行為 |
| アカデミックハラスメント | 教職員が、部下や学生に行う嫌がらせ行為 |
| カスタマーハラスメント | 顧客や取引先からの過度な嫌がらせ行為 |
こうしたハラスメントを根絶すべく、具体例を挙げた社内マニュアルを作成したり、研修を行ったりする必要があります。
相談窓口の設置や、風通しの良い職場環境作りを通じて、ハラスメントを見逃さない風土を構築することが強く求められます。
労務管理は、勤怠管理、法令遵守、福利厚生対応といった広範な実務だけでなく、部下を思いやる人間味あるコミュニケーション力も求められる業務です。
しかし、過度に属人化すると、その担当者が異動・退職した際に適切な労務管理が行えなくなる恐れがあります。
そのため、個人情報やプライバシー保護を徹底しつつも、重要な情報については共有できるシステムを整備し、研修やマニュアルによって管理職を育成できる体制を構築することが必要です。
労務管理を効率化したい方はこちら
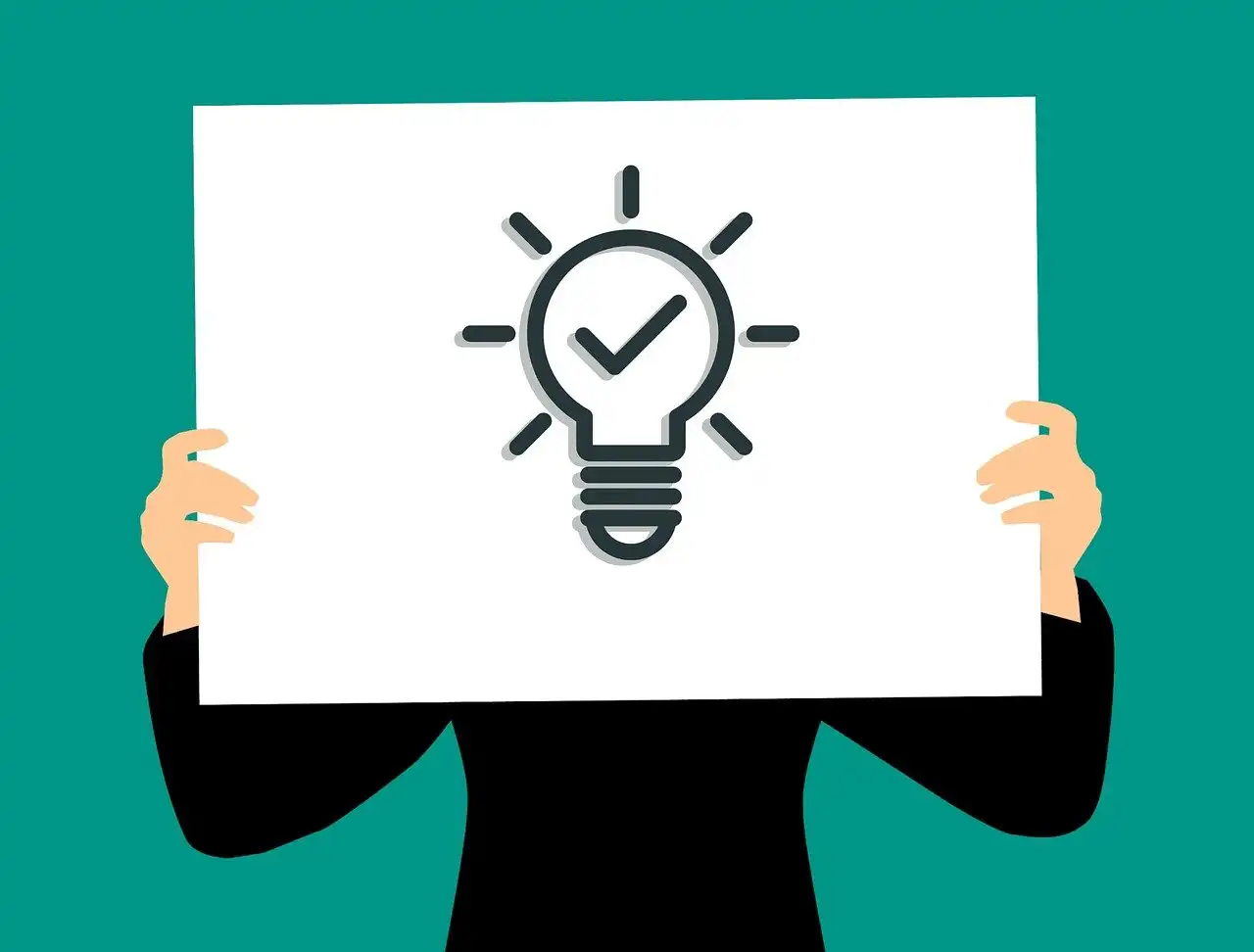
労務管理は広範囲に渡るため、正しく行うには相応の準備が必要です。
企業の規模や、管理職のスキル・知識によって、取り組むべき内容は異なるので、以下を参考にして必要な取り組みから着手できるよう検討してください。
それぞれについて解説します。
労務管理にあたっては、社内全体で共通認識を持ち、間違った管理が起きないようにしなければなりません。
そのためには、最新の法令や必要な知識を、マニュアルや社内研修を通じて従業員に共有する仕組みが求められます。
特にハラスメントへの対応やコミュニケーションスキルについては、専門家から最新の手法を学び、質疑応答やグループワーク、実地研修を通じて、現場での対応力を高めていく体制づくりが必要です。
労務管理について解説された書籍は数多く出版されているため、それらを活用して知識を深めることも有効な手段です。
企業規模や業種、経験値によって取り入れるべき知識は異なるので、自社の状況に見合った書籍を選んでください。
一冊だと偏りが出る恐れがあるため、複数の書籍を参考にするのがおすすめです。
また、最近では、専門業者が配信しているeラーニングで学ぶ方法もあります。
インターネット経由で場所を選ばす、いつでも何度でも受講できる上、オンラインで質問できるサービスもあるので、必要に応じて活用してみるのもよいでしょう。
労務管理の一部を、労務管理システムを使って効率化する方法もあります。
専門業者と契約してシステムを導入すれば、入社情報の入力、勤怠管理、給与計算、社会保険の電子申請、人事情報の管理・分析などが可能になります。
労務管理は業務量が多いため、可能な業務はデジタル化・自動化した方が生産性が高まります。
システムによって料金や機能が異なるので、複数のサービスを比較し、自社に最適なものを選ぶことが大切です。
労務管理システムについて詳しく知りたい方はこちら
管理職の労務管理は、部下のモチベーションを向上させ、生産性を高める上で非常に重要な業務です。
労務管理を正しく行うためには、部下とのコミュニケーションを深め、コンプライアンスを遵守し、多様な働き方へ柔軟に対応するといった取り組みが欠かせません。
労務管理の実効性を高めるには、社内研修を充実させ、関連書籍を参考にしたり、労務管理システムを導入したりする方法がおすすめです。
管理職のスキルや意識によって労務管理の質は大きく変化します。
企業の健全な運営と従業員の働きやすい職場作りのためにも、ぜひ積極的に取り組んでみてください。
画像出典元:photoAC、Pixabay

【2023年最新】賞与に必要な手続きと社会保険料の計算方法を簡単解説

社員管理とは?従業員管理のコツやメリット、おすすめ管理システムも

労務費とは?人件費との違いや計算方法・内訳・労務費率をサクッと解説

SmartHRとジョブカン労務HR徹底比較!料金・機能・使いやすさでわかる違いとは?
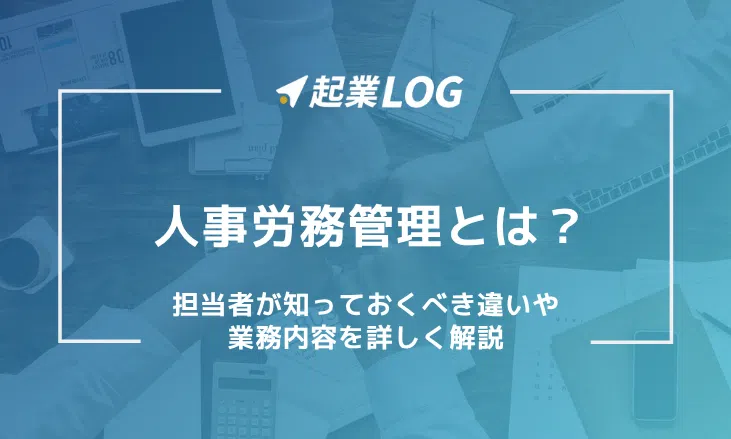
人事労務管理とは?担当者が知っておくべき違いや業務内容を詳しく解説

労務管理システムとは?導入メリットや自社に合った選び方を解説

所定労働時間と法定労働時間とは?違いや残業代について簡単に解説

労務とは?人事との違いや社内での役割・仕事内容を大公開!

就業規則を変更する!変更が必要なケースと手順とは?

労務管理のオフィスステーション 労務とSmartHRを比較解説!特徴は?

勤怠管理システム

Web給与明細システム

シフト管理システム

人事システム

マイナンバー管理システム
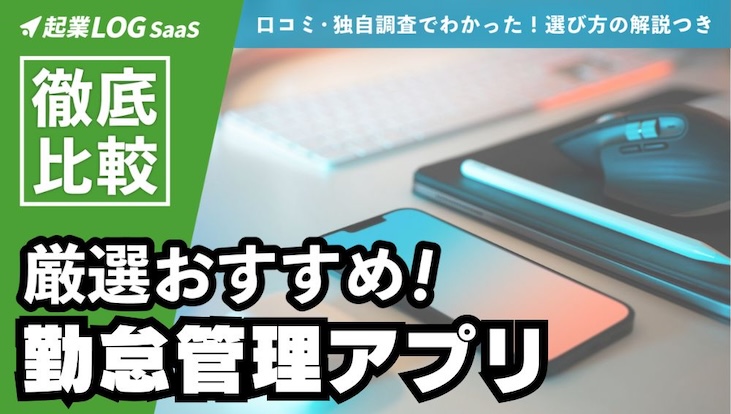
勤怠管理アプリ

営業職向け勤怠管理システム

青色申告ソフト

無料勤怠管理システム

製造業向け勤怠管理システム

運送業向け勤怠管理システム

建設業向け勤怠管理システム

人事管理システム

年末調整支援システム

中小企業向け勤怠管理システム

飲食店向け勤怠管理システム

サービス業向け勤怠管理システム

介護業向け勤怠管理システム

病院向け勤怠管理システム

シフト管理アプリ

有給管理ソフト

人事アウトソーシングサービス

無料労務管理ソフト

パッケージ型労務管理システム
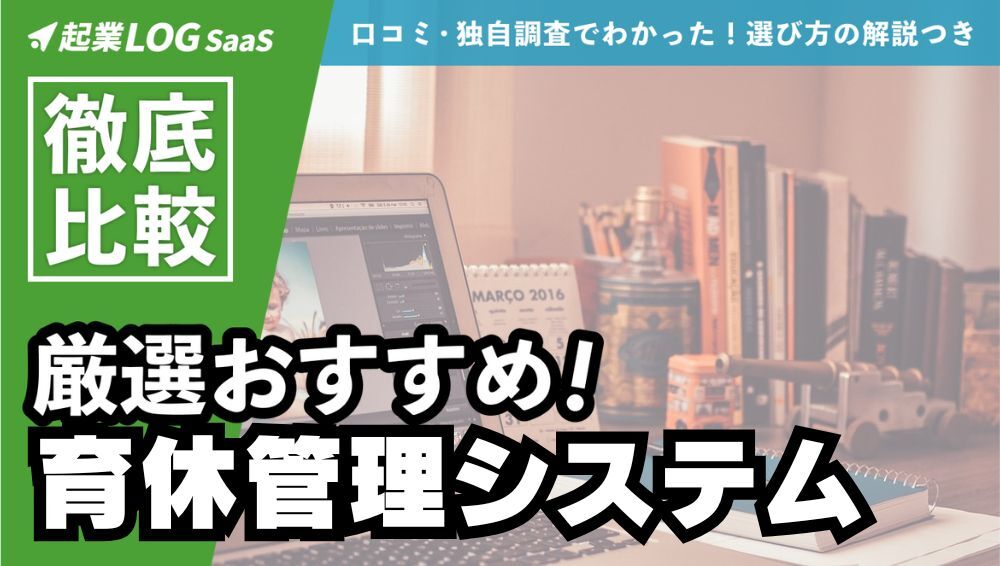
育休管理システム

電子契約サービス