
厚生年金の保険料は企業と従業員で折半して納める決まりです。
厚生年金に加入する義務があるのは、すべての法人事業所と5人以上の従業員がいる個人事業所。会社負担金が発生する事業所は必要経費として予算を確保する必要があります。
また、厚生年金以外の社会保険料も会社が負担しなくてはなりません。経営者の方は社会保険全般についての知識を持っておきましょう。
今回は、厚生年金保険を始めとした社会保険全般の基礎知識や加入義務の要件、未加入のリスク、会社負担の割合、保険料の具体的な計算方法について解説します。
社会保険に関する業務を効率化したいなら労務管理システムがおすすめです。
各サービスの特徴も併せて紹介するので、あなたの会社に合ったシステムを見つけましょう。
このページの目次

厚生年金の会社負担割合は50%で企業と社員が折半して保険料を納めるルールです。
保険料は標準報酬月額(月給)に保険料率18.3%をかけて算出します。
例えば、月給300,000円の従業員の厚生年金保険料は54,900円、その内、会社負担分は27,450円です。
同じ条件の社員が5人いたら、毎月137,250円を厚生年金保険料として納めないといけません。
こんなにも厚生年金保険料が高いのは、超高齢社会により公的年金が財源不足に陥っているからです。国民年金も厚生年金も保険料(率)が段階的に引き上げられています。
また、厚生年金の適用範囲が徐々に拡大していますが、その理由は「加入者を増やして年金の財政難を解消するため」という意見もあります。
令和2年度の国民年金保険料は一律16,540円ですが、厚生年金は収入が高ければ保険料も高くなる仕組み。保険料が16,540円以上の人が増えれば、それだけ徴収できる金額が増えます。
それに加えて、平均寿命まで生きた場合の年金受給額を単純計算すると、国民年金は納めた保険料以上の年金が受け取れるのに対し、厚生年金は納付した保険料の全額が戻ってくるわけではありません。
でも、被保険者の納めた半額分の保険料よりは多くの年金が受け取れるので、不満が出にくいのです。※ねんきん定期便の”これまでの保険料納付額”には、被保険者負担分の保険料しか記載されていません。
では、会社が納めた残り半分の保険料はどこに行ってしまったのでしょう?
日本の年金制度は現役世代が納めた保険料で賄う賦課方式なので、会社負担分は現在の高齢者への年金給付の不足分を穴埋めするために使われています。
「赤字を埋めるために会社負担金が国家に没収されている」と言われているのも、あながち間違いではないでしょう。
そんな裏事情を知ると、余計に「会社負担金を納めたくない!」と思いますよね。でも、理不尽だと感じても、法律で義務付けられているので厚生年金保険料を節約することはできません。
そして、厚生年金は「社会保険」のひとつ。厚生年金保険料だけでなく、健康保険料や労災保険料などの社会保険全般で会社負担金が発生します。
経営者の方は、社会保険に関する基礎知識をつけておきましょう。

社会保険とは、病気、ケガ、障害、加齢、死亡などのリスクに備える保険制度で、国民の生活を守ることを目的としています。
経営者の方に関係があるのは、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5種類です。
”広義の社会保険”は会社員などが加入する『被用者保険』と自営業者などが加入する『一般国民保険』の両方を意味します。
『被用者保険』をさらに分類すると、”狭義の社会保険”と”労働保険”に分けられます。
”狭義の社会保険”は「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」を指し、”労働保険”は「雇用保険」と「労災保険」を指します。

狭義の社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険)への加入義務があるのは、以下の強制適用事業所です。
法人として会社を設立したら必ず健康保険、厚生年金保険、介護保険に加入しなければなりません。個人事業所でも従業員が5人以上いる場合には、業種によって加入義務が生じます。
新規で社会保険に加入する事業所は、日本年金機構(年金事務所)に「新規適用届」を提出しましょう。
そして、強制適用事業所は従業員の社会保険の加入手続きも行わないといけません。加入対象は正社員だけではないので注意してください。
(1)週の所定労働時間が20時間以上
(2)勤務期間が1年以上見込まれる
(3)月額賃金が8.8万円以上
(4)学生以外
(5)従業員501人以上の企業に勤務している、または従業員500人以下でも労使で社会保険加入の合意がある
これらの条件を満たす従業員を雇用している場合は、年金事務所や各健康保険組合で手続きを行いましょう。
なお、健康保険と介護保険はセットになっているので、健康保険に加入すれば自動的に介護保険の手続きも完了します。
労働保険である雇用保険と労災保険に関しては、労働者を1人でも雇ったら強制適用事業所となります。業種や規模に関係なく労働保険に加入しなければなりません。
ここでの労働者は、賃金を支払う必要がある者(常勤、パート、アルバイト、派遣等の勤務形態に関わらずすべて)を指します。
パートやアルバイト等の短時間労働者は労災保険の対象になっても、雇用保険の対象にならないことがありますが、それでも届出は必須です。
従業員を雇用したら「労働保険の保険関係成立届」を労働基準監督署かハローワークに提出してください。
それに加えて、雇用保険の対象となる従業員がいる場合には「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出する必要があります。
雇用保険対象となるのは、以下の条件のいずれにも該当する従業員です。

加入義務があるのに未加入のまま事業を行うと数々のリスクがあります。
社会保険の強制適用事業所には日本年金機構から加入を促すお知らせが届きますが、無視し続けると、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。
それに、社会保険に加入していないことが見つかったら、遡って保険料を納めなくてはなりません。最大で2年分の保険料を徴収されるので、かなりの出費になるでしょう。
遡及徴収に応じないと日本年金機構から企業の資産を差し押さえられるリスクがあります。
従業員が病気やケガをしたり死亡した時に保険金が出ないので、労働者から損害賠償請求される危険があるのも問題です。
また、ハローワークに求人を出しても、不正な理由で社会保険に未加入だと求人が取り消されます。ブラック企業だという噂が広まれば、経営に悪影響を及ぼすのは間違いありません。
会社負担分の保険料を捻出するのが難しい場合には、未加入ではなくあらかじめ社会保険料を予算に組み込んでおく方法がおすすめです。

強制適用事業所は社会保険への加入義務があるので「会社がいくらぐらい負担するのか?」が気になるところですよね。
従業員を雇う時や賃金を決める際には、必要となる保険料も計算することが大切です。
| 社会保険の会社負担割合 | |
| 健康保険 | 企業:社員=5:5 |
| 厚生年金保険 | 企業:社員=5:5 |
| 介護保険 | 企業:社員=5:5 |
| 雇用保険 | 企業>社員 |
| 労災保険 | 企業:社員=10:0 |
社会保険料の会社負担割合は種類ごとに違います。
狭義の社会保険である「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」は企業と社員で折半しますが、労働保険の「雇用保険」と「労災保険」は会社負担割合が高い仕組みです。
また、厚生年金保険とセットになっている「子ども・子育て拠出金」は企業が全額を負担する決まりです。※扶養している子供の有無に関わらず、厚生年金の加入対象であるすべての従業員が対象になります。
次は、5種類の社会保険+「子ども・子育て拠出金」で必要になる会社負担金額を計算してみましょう。

健康保険料は健康保険組合(協会)ごとに設定された標準報酬月額に保険料率をかけた額で、給与によって保険料が変動する仕組みです。
毎月の保険料に加えて、ボーナス月には標準賞与額に健康保険料率をかけた額の保険料も納めます。
全国健康保険協会の東京都を例にすると、令和2年9月からの保険料率は9.87%(企業負担分は4.935%)です。
法人化した際には、企業や団体が設立した「健康保険組合」または「全国健康保険協会」に加入しますが、保険料率は各健康保険組合(協会)が財政状況に応じて独自に決めます。
健康保険組合は保険料率だけでなく負担割合を変更することも可能で、様々な特典が用意されていることがあります。
新規設立会社の場合でも業界団体が運営する組合に入れるケースがあるので、調べてみてください。保険料率や保障内容を比較して加入先を決めましょう。
赤枠で囲んだ部分が該当箇所で、緑枠で囲んだ部分が保険料率です。

画像出典元:全国健康保険協会HP
報酬月額が290,000円~310,000円の人は標準報酬月額300,000円として計算します。
標準報酬月額×保険料率=健康保険料
300,000円×9.87%=29,610円
29,610円×0.5=14,805円
会社負担5割:14,805円
社員負担5割:14,805円
厚生年金保険料は標準報酬月額に保険料率をかけた額です。
厚生年金の標準報酬月額は基本給に残業手当、通勤手当などを含めた税引き前の給与を、1等級(88,000円)から32等級(650,000円)に分けたもの。
毎年9月に4月~6月の報酬月額を基にして標準報酬月額の見直しを行います。
ボーナスを支給した際には、税引き前の賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた標準賞与額に保険料率をかけた保険料を納めます。
支給1回あたりの標準賞与額の上限は1,500,000円です。
厚生年金保険の保険料率は段階的に引き上げられてきましたが、平成29年9月に引き上げが終了し18.3%(企業負担分9.15%)で固定されています。
厚生年金保険とセットになっている「子ども・子育て拠出金」の拠出金率は、令和2年4月1日から0.36%(令和3年1月時点)です。
赤枠で囲んだ部分が該当箇所で、緑枠で囲んだ部分が保険料率です。

画像出典元:日本年金機構HP
報酬月額が290,000円~310,000円の人は、標準報酬月額300,000円(19等級)として計算します。
標準報酬月額×保険料率=厚生年金保険料
300,000円×18.3%=54,900円
54,900円×0.5=27,450円
会社負担5割:27,450円
社員負担5割:27,450円
標準報酬月額×保険料率=子ども・子育て拠出金
300,000円×0.36%=1,080円
会社負担10割:1,080円
社員負担0割:0円
介護保険料は40歳以上60歳未満の人が納めるルールで、該当する従業員は健康保険料に介護保険料が加わります。
介護保険料は、健康保険組合(協会)ごとに設定された標準報酬月額に保険料率をかけて算出します。
全国健康保険協会の東京都を例にすると、令和2年9月からの保険料率は1.79%(企業負担分は0,895%)です。
赤枠で囲んだ部分が該当箇所で、緑枠で囲んだ部分が健康保険料と介護保険料を合わせて納める場合の保険料率です。

画像出典元:全国健康保険協会HP
健康保険料率(9.87%)+介護保険料率=11.66%
介護保険料率=11.66%-9.87%=1.79%
標準報酬月額を300,000円、保険料率1.79%として介護保険料を計算します。
標準報酬月額×保険料率=介護保険料
300,000円×1.79%=5,370円
5,370円×0.5=2,685円
会社負担5割:2,685円
社員負担5割:2,685円
標準報酬月額×健康保険と介護保険を合わせた保険料率=健康保険料と介護保険料を合わせた額
300,000円×11.66%=34,980円
34,980円×0.5=17,490円
会社負担5割:17,490円
社員負担5割:17,490円
雇用保険料は基本給に残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の総支給額(賞与も含む)に保険料率をかけた額です。
雇用保険料率は事業の種類によって若干違いますが、農林水産・清酒製造・建設以外の一般の事業は0.9%(9/1,000)に設定されています。

画像出典元:厚生労働省HP
総支給額×保険料率=雇用保険料
300,000円×0.9%=2,700円
300,000円×0.6%=1,800円
300,000円×0.3%=900円
会社負担0.6%分:1,800円
社員負担0.3%分:900円
労災保険料は、基本給に残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の総支給額(賞与も含む)に保険料率をかけた額です。労災保険料率は事業の種類によって細かく分けられています。
参考:労 災 保 険 率 表
例えば、金融業、保険業または不動産業は0.25%ですが、金属鉱業、非金属鉱業または石炭鉱業は8.8%です。そして、労災保険料は企業が全額負担します。
総支給額×保険料率=労災保険料
300,000円×0.3%=900円
※卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業の保険料率は0.3%
会社負担10割:900円
社員負担0割:0円

社会保険料をひとつずつ計算すると手間がかかるので、おおよその予算を立てるために目安を知っておきましょう。
社会保険料の総額を出せば、給与の何%くらいが会社負担割合になるかが分かります。
| 社会保険の種類 | 賃金に占める会社負担割合 | 保険料 |
| 健康保険料の会社負担 | 4.935% | 14,805円 |
| 厚生年金保険の会社負担 | 9.15% | 27,450円 |
| 子ども・子育て拠出金の会社負担 | 0.36% | 1,080円 |
| 雇用保険料の会社負担 | 0.6% | 1,800円 |
| 労災保険の会社負担 | 0.3% | 900円 |
| 社会保険に関する会社負担金の合計 | 15.345% | 46,035円 |
| 社会保険の種類 | 賃金に占める会社負担割合 | 保険料 |
| 健康保険料の会社負担 | 4.935% | 14,805円 |
| 厚生年金保険の会社負担 | 9.15% | 27,450円 |
| 子ども・子育て拠出金の会社負担 | 0.36% | 1,080円 |
| 介護保険料の会社負担 | 0.895% | 2,685円 |
| 雇用保険料の会社負担 | 0.6% | 1,800円 |
| 労災保険の会社負担 | 0.3% | 900円 |
| 社会保険に関する会社負担金の合計 | 16.24% | 48,720円 |
事業の種類によって社会保険に関する会社負担割合が変わりますが、モデルケースと同じ条件なら目安は従業員の給与の15%~16%にあたる額です。
会社負担金を大まかに知りたい時には、賃金の15%~16%で計算しましょう。
概算見積もりを出すだけなら15%~16%だと予測を立てて計算すれば事足りますが、事業をスタートさせて社会保険に加入したら正確な値を出さなくてはいけません。
それに、たびたび行われる法改正にも対応する必要があります。
間違った手続きを行うと会社の責任になるので、対象者を見逃さずに届出を出す、保険料の納付手続きを忘れない、など適切に管理することが大切です。
しかし、業務を手作業で行っている限りヒューマンエラーを減らすのは難しく、細かな計算をするためには膨大な時間がかかります。
それらの問題を解決するために、正しく効率的に業務が行える労務管理システムを導入しましょう。
労務管理システムとは、従業員情報や社会保険などの諸手続きをweb上で管理するシステム。
保険料計算の自動化だけでなく、電子申請もできるので年金事務所に出向かなくても手続きが完了します。
ただ、導入費用や月額利用料金、機能、サポート体制などがサービスごとに違うので「どれにすれば良いのか分からない…」と迷うことが珍しくありません。
そこで、選びやすいように各サービスの特徴をまとめました!比較検討する時の判断材料にしてくださいね。


「freee人事労務(フリー人事労務)」は勤怠管理・給与計算・年末調整・助成金の申請など、幅広い労務管理をカバーしてくれるシステムです。
複数の労務管理において共通で使用する情報は、freee人事労務がデータベースとなり入力を1回で済ませることができるので業務が効率化するでしょう。
社内では多くの労務管理に関する業務が散らばりがちですが、人事労務freeeであれば一気通貫で行って対応コストを削減可能です。
| プラン | 月額料金 | 機能 | 従業員追加 |
| ミニマムプラン | 1,980円~ (3名まで一律料金) |
基本的な労務管理全般 | 月額300円 /ユーザー |
| ベーシックプラン | 3,980円~ | 従業員による勤怠打刻等追加 | 月額500円 /ユーザー |
| プロフェッショナルプラン | 8,080円~ | フレックス制などに対応 | 月額700円 /ユーザー |
| エンタープライズプラン | お問合せ | 従業員情報のカスタム項目 | お問合せ |
月額料金は年額プランの場合の金額です。どのプランでも初期費用はかかりません。

IT
1001人以上
労務まわりを一つに統合できる点が魅力





勤怠管理システムだけではなく給与計算や年末調整、労務手続き(入退社手続き)等を一つのシステムに統合できる点は、大きな魅力だと思います。一つに統合することでコストメリットが生かせました。

コンサルティング
11〜30人
電話対応が付かないプランがある





選んだ料金プランによっては電話によるヘルプデスク機能が付いてこない点が不便だと感じました。最初は一番価格の安いプランを選択していたが、人事、経理から電話で聞かないとわからないことがあると報告が上がってきたため、プランを変更しました。

「SmartHR(スマートエイチアール)」は2万社以上の導入実績を誇る労務管理システムです。
最大の特徴は質問に答えるだけで重要書類が作成できる簡単さです。Web上で書類作成や管理が行われるため、紙もハンコも使う必要がありません。
e-Gov APIと連携しているため、役所やハローワークへの書類提出もWEB上で完結します。
実際にSmartHRを導入した企業では、「2人で1,700人分の給与計算が可能になった」「社員の60%の生産性が向上した」などの実績も出ています。
従業員情報を一元管理するクラウド人事労務ソフトなので、社労士がいなかったり従業員が多い企業には特におすすめです。
| プラン | 月額費用 | 機能 | 従業員数 |
| ¥0プラン | 0円 | 一部利用できない機能あり | 30名まで |
| スモールプラン | お問合せ | 労務手続きや情報管理の効率化 (小規模の企業向け) |
50名以下 |
| スタンダードプラン | お問合せ | 人事・労務の効率化と従業員情報の一元管理(あらゆる規模の企業に対応) | 50名以上 |
どのプランでも初期費用はかかりません。

コンサルティング
101~250人
間違いやすい部分にコメントがあるのでわかりやすい





年末調整をこのSmartHRで行うようになって今年で2回目でしたが、間違いやすい部分は補足のコメントがあるのでとてもわかりやすいです。いつでもオンラインでパパっと作成・申請できるので大変便利でした。

メーカー
51〜100人
初期設定に時間がかかった





操作こそ簡単でしたが、初期設定に時間がかかりました。もっと簡単なマニュアル等があれば初期の稼働がスムーズにいったと思います。

画像出典元:「ジョブカン労務HR」公式HP
「ジョブカン労務HR」は、初めて労務管理システムを利用するという方に絶対的におすすめしたいシステムです。
導入実績はシリーズ累計で100,000社以上とかなり多くの会社で使われてて、とにかく使いやすく労務業務に不慣れな人でも書類作成から申請まで簡単に行うことができます。
たった1分で無料アカウントが発行できて、即日簡単に始められるという導入ハードルの低さも初心者にお勧めしたい理由です。
帳票は自動的に作成され、ボタンひとつで主要な社会保険・労働保険の書類を提出することができるため、役所まで足を運ぶ必要もありません。
「システム導入の際の初期設定が面倒だ」という方でも、初期設定を代行してくれるオプションプランもあるので安心です。
| プラン | サポート&初期費用 | 月額費用 | 従業員数 |
| 無料プラン | 0円 | 0円/ユーザー | 5名まで |
| 有料プラン | 0円 | 400円/ユーザー | 無制限 |

小売
101~250人
膨大な社員情報がスムーズに管理できる





膨大な社員情報を管理しているような職種や部署におすすめできます。正確に、そして必要なときに目的のデータをすぐに出せるなど、情報管理がスムーズにできるようになります。

サービス
51〜100人
旧姓と新姓の管理がしづらいのがデメリット





「結婚をしたあとの旧姓と新姓を使い分けての管理」が少々しにくいというのは気になる大きなデメリットであり、不便な箇所だと思います。女性社員も多い会社からするとこの箇所は強く改善を希望します。

画像出典元:「オフィスステーション 労務」公式HP
「オフィスステーション 労務」とは、大手企業を含む35,000社以上に導入(※)されている実績豊富な労務管理システム。
他社と比べて機能も充実しており、人事・労務における幅広い業務の効率アップ・ペーパーレス化に役立ちます。
勤怠や給与、年末調整、マイナンバー管理などの外部ソフトとの連携やe-GOVへの対応、セキュリティの高さなども魅力。
無駄な出費を抑え、低額で利用することができるのも大きな特徴です。
※「オフィスステーション」利用実績数
オフィスステーション 労務の料金プランは1種類。
初期費用は登録料の11万円(税込)で、毎月従業員ひとりあたり440円(税込)がかかります。
| 名目 | 費用 |
| 登録料 | 110,000円(税込) |
| 従業員ひとりあたりの月額利用料 | 440円(税込) |
| ユーザー数 | 無制限 |

商社
251~500人
管理者向けにおすすめ





色々なシステムを検討して最後にスマートHRとオフィスステーションの2択になり、価格面をみてオフィスステーションに決めました。管理者にとってはオフィスステーションの方が使いやすいと感じました。

コンサルティング
11〜30人
社会保険の手続きの一部には対応しておらず





簡単な手続きはオフィスステーションで十分でしたが、オフィスステーションでは申請できない社会保険の手続きもありました。そこにも完全に対応したら、完璧なツールだったと思います。


「クラウドハウス労務」は労務に関わる業務をペーパーレスにすることで、コストや手間の大幅削減が可能。
使いやすさにこだわった操作画面や充実したヘルプ機能で、スマホやパソコン上で誰でも簡単に操作ができます。
導入前・導入後のサポート体制も充実しているので安心して運用スタートできるでしょう。
ただし、労務業務に特化しており、給与計算や勤怠管理には対応していないため、検討の際には注意が必要です。
月数万円から利用可能。課題を踏まえた上で見積もり・提案をしてくれます。
社会保険は「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5種類があります。
前者3つは社員と企業が折半して保険料を納める仕組み、後者2つは保険料の会社負担割合が高いのが特徴です。
会社を経営する際には、社会保険にまつわるルールを熟知することが大切です。忘れてはならないのは、加入義務が生じたら必ず加入手続きを行うこと。
未加入だと様々なリスクがあり事業の継続が困難になる恐れがあります。
会社負担金額は従業員1人あたりの賃金の約15~16%です。後で困らないよう、保険料をあらかじめ予算に組み込んでおきましょう。
画像出典元:O-DAN

【2023年最新】賞与に必要な手続きと社会保険料の計算方法を簡単解説

社員管理とは?従業員管理のコツやメリット、おすすめ管理システムも

労務費とは?人件費との違いや計算方法・内訳・労務費率をサクッと解説

SmartHRとジョブカン労務HR徹底比較!料金・機能・使いやすさでわかる違いとは?
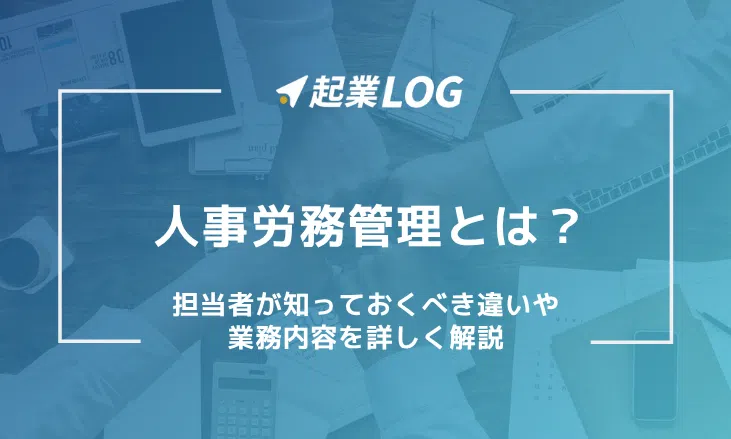
人事労務管理とは?担当者が知っておくべき違いや業務内容を詳しく解説
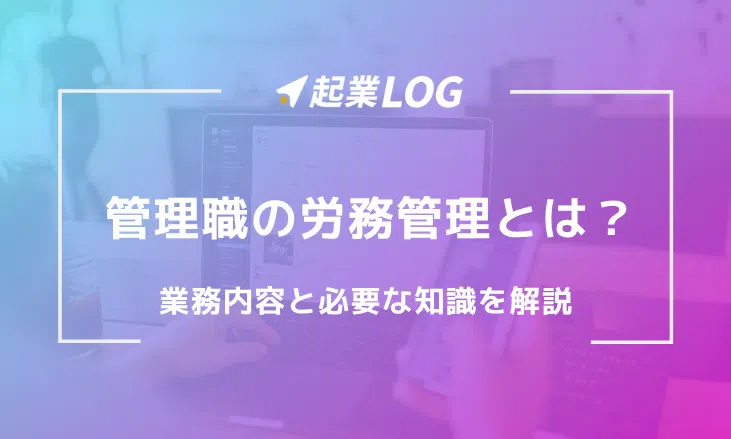
管理職の労務管理とは?業務内容と必要な知識を解説

労務管理システムとは?導入メリットや自社に合った選び方を解説

所定労働時間と法定労働時間とは?違いや残業代について簡単に解説

労務とは?人事との違いや社内での役割・仕事内容を大公開!

就業規則を変更する!変更が必要なケースと手順とは?