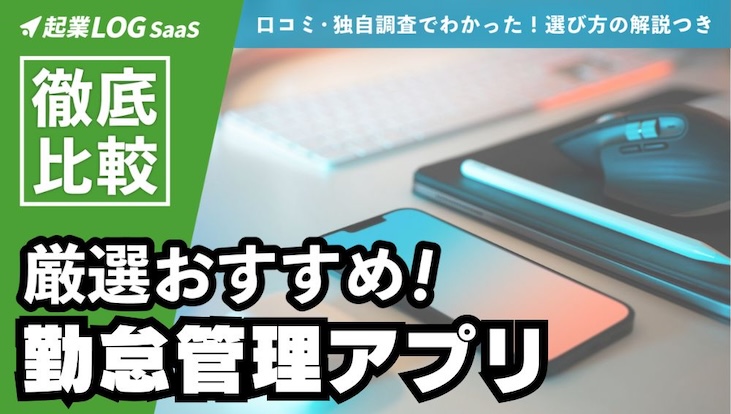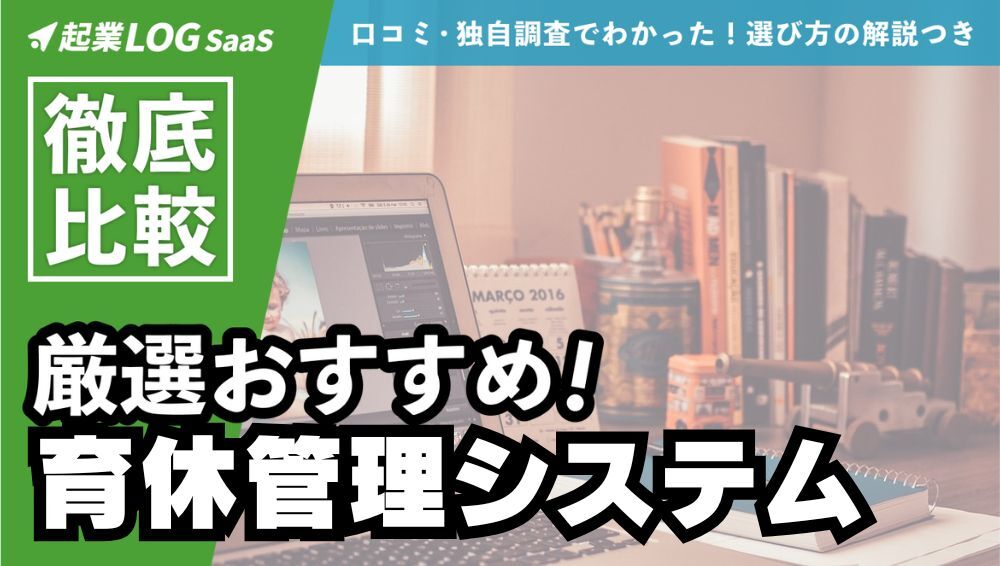
育児・介護休業法改正の施行が2025年4月・10月と続き、育休管理業務は年々複雑さを増しています。
そこで本記事では、おすすめの育休管理システム6選を比較しながら解説します。
単なる機能比較に留まらず、「煩雑な管理業務からの解放」と「従業員が安心して休める環境づくり」を両立できる、本当に価値のあるシステムの選び方を徹底解説します。
おすすめサービスの比較を無料で!
目次
育休管理システムとは、育児や産前産後休業(以下、産休)に関する業務を支援する専門ツールです。
各種申請手続き、休業期間中の情報共有、復職支援のためのコミュニケーションなどを一元的に管理し、人事労務担当者の業務効率化と、休業を取得する従業員のスムーズな制度理解職場復帰を目的としています。
またサービスによっては、人事労務担当者だけでなく従業員にとっても喜ばれる機能を提供することで、育休取得環境の整備に繋げようとするものもあります。
育休関連業務は、従業員ごとに異なる対応が必要です。
出産予定日や休業期間、延長の有無、提出書類の種類と期限、社会保険や給付金の手続きなど、管理項目は多岐に渡ります。
これを複数の担当者がExcelやスプレッドシートで手動管理しようとすると、管理が煩雑になるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクが常に付きまといます。
さらに、特定の担当者の経験や知識に依存する「属人化」が進みやすく、担当者の異動や退職が業務の停滞に直結する恐れもあります。
特に近年、男性育休が増えたことによる対応数の増加や、短い取得期間に合わせたスピーディな対応も求められています。
休業中の従業員は、まずは取得に対する「お金」「キャリア」「配置」などの懸念がありますが、出産がある年代は管理職になる可能性も多い年代なので、結果「育休を取りにくい」と言う課題があります。
また取得した後も職場との接点が大幅に減るため、復職時に「浦島太郎状態」への不安を抱きがちです。
組織の変化や業務内容のアップデートについていけない懸念に加え、キャリア中断による焦りやスキルの陳腐化への不安も大きな心理的負担となります。
育休管理システムと労務管理システムは、目的と強みが異なります。
前者は休業者の管理とケアに特化し、後者は人事労務全般の効率化を目的としています。
育休管理システムは、育休取得者の管理に特化した機能と休業中の従業員のエンゲージメント維持に重点を置いています。
代表的なサービスとして「workingU」 や「アドバンテッジハーモニー」 「armo」があり、育休取得者管理としては対象者の産育休期間の一眼管理や出産日の変更、関連タスク管理、育介法改正への対応した機能などが主です。
また、従業員エンゲージメントに関する機能としては、ガイドブック等の情報提供、休業者同士の交流コミュニティ、スキルアップを支援するeラーニング、会社との双方向コミュニケーション機能など、従業員の心理的・キャリア的な不安を和らげる機能が充実しています。
一方、労務管理システムは勤怠管理や給与計算、年末調整といった人事労務業務全体の効率化を目指す中で、育休管理機能を一つのモジュールとして扱います。
「SmartHR」「freee人事労務」「ジョブカン労務HR」 などが代表例で、各種手続きの自動化や電子申請といった管理業務の効率化に強みを持っています。
育休手続きは、個々の従業員の状況によって必要なタスクや期限が全く異なります。
この個別対応が業務を煩雑にする最大の要因です。
誰がいつから休業に入り、どの手続きがどこまで進んでいるのかをダッシュボードなどで一覧表示できるかが非常に重要です。
Excelの複数シートを行き来する管理から卒業し、ダッシュボードで直感的に全体像を把握できるようにしましょう。
優れたシステムは、出産予定日などを入力するだけで、法規定に基づくタスクリストが自動生成されます。
「誰が・何を・いつまでに」実施すべきかが明確になり、担当者と従業員双方に適切なタイミングでリマインド通知が送られます。
この機能により、手続きの抜け漏れを防ぐことが可能です。
育児・介護休業法は、近年特に改正が頻繁に行われています。
担当者が常に最新情報をキャッチアップし、実務に反映させるのは大きな負担です。
2022年に創設された「産後パパ育休」は、2回までの分割取得が可能です。
こうした複雑な取得パターンにもシステムが標準で対応しているかは、必ず確認しましょう。
手計算やExcelでの管理では、ミスが発生するリスクが非常に高くなるため、システムを使って簡単に管理できることが重要になります。
信頼できるシステムは、法改正に合わせてクラウド上で自動的にアップデートされます。
これにより、企業は常に最新の法令を遵守した労務管理が可能になります。
システムの選定時には、アップデートの頻度や費用についても確認しておくと安心です。
育休管理のゴールは、手続きを完了させることではありません。
従業員が安心して仕事と育児を両立できる環境を整え、エンゲージメントを高めることが目的です。
「育休中の給付金はいくらもらえる?」「社会保険料はどうなる?」といった質問は頻繁に寄せられます。
システム内にFAQや情報提供機能、ガイドブック等のコンテンツがあれば、従業員が自分で疑問を解決でき、担当者の問い合わせ対応工数も大幅に削減できます。
特に男性の育休取得を促進する上で、休業期間中の収入減少は大きなハードルです。
システム上で世帯収入のシミュレーションができたり、最適な育休プランを提案してくれたりする機能は、従業員が主体的に育休を計画する上で強力な後押しとなります。
これは、単なる管理ツールを超えた、戦略的な人材定着施策としても有効です。
| サービス名 | タスク管理の自動化 | 法改正への対応力 | 従業員の不安解消 | 育休からタイプ復職支援 | こんな企業に最適 |
|---|---|---|---|---|---|
 workingU
workingU
|
◎
|
◎
|
◯
|
休職者管理特化
|
企業や従業員の状況に合わせて効率化したい企業
|
 armo
armo
|
◯
|
◯
|
◎
|
休職者管理特化
|
従業員のエンゲージメントを最優先する企業
|
 アドバンテッジハーモニー
アドバンテッジハーモニー
|
◎
|
◎
|
◯
|
休職者管理特化
|
あらゆる休業者を包括的に管理したい企業
|
 ジョブカン労務HR
ジョブカン労務HR
|
◎
|
◯
|
△
|
汎用労務管理
|
コストを抑えたい中小企業
|
 freee人事労務
freee人事労務
|
◯
|
◯
|
△
|
汎用労務管理
|
バックオフィス全体を効率化したい企業
|
 SmartHR
SmartHR
|
◯
|
◯
|
◯
|
汎用労務管理
|
コンプライアンスを重視する中堅・大企業
|
画像出典元:「workingU(ワーキングユー)」公式HP
「workingU (ワーキングユー)」は、育休業務の圧倒的な効率化と、従業員が育休を取得しやすい環境の向上を同時に実現することを目指す育休支援システムです。
「育休増加に対応する業務負荷」「法改正への運用上の対応」「従業員が情報不足により自己解決できない」という3つの課題を解決することを目的としています。
| おすすめポイント | 企業毎のカスタマイズと、独自のAI育休プラン提案機能 |
| 主な機能 |
|
| 無料トライアル | あり |
詳細については、お問い合わせが必要です。

画像出典元:「armo (アルモ)」公式HP
「armo (アルモ)」は、eラーニング事業を主力とする株式会社プロシーズが提供する、育休・産休中の社員フォローに特化したシステムです。休業者の不安解消とスキルアップ支援を両立させることをコンセプトとしています 。
| おすすめポイント | 休業者同士が情報交換できるコミュニティ機能 |
| 主な機能 |
|
| 無料トライアル | 要問合せ |
詳細については、お問い合わせが必要です。

画像出典元:「アドバンテッジハーモニー」公式HP
「アドバンテッジハーモニー」は、メンタルヘルスケアや組織開発コンサルティングを手掛ける株式会社アドバンテッジリスクマネジメントが提供するクラウドサービスです。育休だけでなく、介護休業や私傷病による休職など、あらゆる理由で休業している従業員を一元管理できる点が大きな特徴です 。
| おすすめポイント | 自動生成されるリマインド機能が充実 |
| 主な機能 |
|
| 無料トライアル | 要問合せ |
詳細については、お問い合わせが必要です。

画像出典元:「ジョブカン労務HR」公式HP
「ジョブカン労務HR」は、株式会社DONUTSが提供する「ジョブカン」シリーズの一つです。シリーズ全体で25万社以上の導入実績を誇り、特に中小企業から高い支持を得ています。直感的な操作性とコストパフォーマンスの高さが魅力です 。
| おすすめポイント | 従業員がスマホから出産報告等をすると必要な手続きが自動生成される |
| 主な機能 |
|
| 無料トライアル | あり(30日間) |
初期費用は無料で、有料プランは1ユーザーあたり月額400円(税抜)から利用できます。
※月額最低利用料金2,000円
従業員5名までであれば、一部機能制限付きの無料プランも提供されています。

画像出典元:「freee人事労務」公式HP
「freee人事労務」は、freee株式会社が提供する人事労務システムです。
会計、勤怠管理、給与計算といったバックオフィス業務全体をfreeeのサービス群で統合管理できる点が最大の強みです 。
| おすすめポイント | 従業員情報画面内で、産休・育休期間を登録管理可能 |
| 主な機能 |
|
| 無料トライアル | 要問合せ |
初期費用は無料で、1ユーザーあたり月額400円で利用可能です。

画像出典元:「SmartHR」公式HP
「SmartHR」は、労務管理クラウド市場でトップシェアを誇るサービスです。入社手続きから年末調整まで、あらゆる労務業務のペーパーレス化と、従業員データベースを活用したタレントマネジメント機能に強みを持っています 。
| おすすめポイント | 育休申請フォームを柔軟にカスタマイズ可能 |
| 主な機能 |
|
| 無料トライアル | 無料プランあり |
初期費用とサポート費用は無料ですが、複数の料金プランが用意されているため詳細についてはお問い合わせが必要です。従業員30名以下の企業向けに一部機能を無料で利用できる無料プランも提供しています。
育休管理システムを導入することで、書類作成や進捗確認、リマインドなどの定型業務を自動化できます。
担当者は戦略的な業務に集中でき、業務品質が個人のスキルに依存しなくなるため、組織全体の対応力が向上します。
また、法令要件に基づいたタスクの自動生成・管理は、手続き漏れや法令違反のリスクを低減し、企業の信頼性と安定経営を強化します。
育休支援の質は、人材の定着やパフォーマンスに大きく影響します。
さらに手厚いフォローは、ダイバーシティやエクイティ&インクルージョンの推進を示し、「アドバンテッジハーモニー」のようなシステムは育休データを集計し、「くるみんマーク」等の認定申請に役立ちます。
これにより、投資家や求職者からの企業評価を高め、ブランド価値向上に貢献します。
これまでExcelや紙で管理していた場合、システムの導入には新たなコストが発生します。導入前の提出書類のリマインド・問い合わせ対応・面談など組織全体で掛かっていた時間と、導入後に得られる、効率化や従業員満足度の向上と比較して、費用対効果が十分かどうかを事前に検討することが必要です。
また現在の稼働時間だけでなく、育児・介護休業法の改正対応や男性育休増加など、今後どの程度まで取得数や対応に掛かる稼働が増える可能性があるのかも含め、中長期的に想定されると数年後に再検討する手間も削減できます。
システムの導入は、ボタン一つで完了するわけではありません。
初期設定や従業員への操作教育、運用ルールの整備など、軌道に乗るまでには一定の労力と時間が必要です。
検討時には、誰にとってどの様な工数が発生するのかを確認しておきましょう。
多機能なシステムが必ずしも自社にとって最適とは限りません。
実際に使うのは一部の機能だけで、管理画面が複雑すぎると、かえって運用が面倒になることもあります。
逆に、機能がシンプルすぎたり、カスタマイズの柔軟性が低かったりすると、自社の独自のルールや複雑な勤務形態に対応できず、結局Excelでの補助的な管理が必要になることがあります。
A. 多くのシステムが対応していますが、導入前の確認が必須です。
システムによって、育児・介護休業法に対応している部分が異なります。企業によって現状の管理フローに懸念を持っている部分は異なります。特に「選択的措置の確認」は対象従業員の抽出や、子供の年齢に応じて連絡すべきタイミングが異なるため、システムとして効率化に対応しているか確認しておけば安心です。
A. 電話、メール、チャットなど、ベンダーによって様々です。
システムの導入初期は、操作方法などで不明点が出やすいものです。
迅速に疑問を解決できるサポート体制があるかは、安心して運用を続ける上で重要なポイントです。
FAQやマニュアルの充実度と合わせて、無料トライアル期間中にサポートの対応品質を実際に試すことをお勧めします。
A. 「なぜ導入するのか」という目的の共有が成功の鍵です。
新しいツールの導入には、背景にある制度をどう従業員に理解してもらうかと、従業員による運用上協力が不可欠です。
「手続きが楽になる」「スマホでいつでも申請できる」といった従業員側のメリットを丁寧に説明し、導入への理解を得ることが大切です。
また、誰でも直感的に使える、分かりやすいデザインのシステムを選ぶことで、スムーズな定着につながります。
本記事では、育休管理システムの選び方から具体的なサービス比較までを詳しく解説しました。
優れた育休管理システムは、手続きの煩雑さを軽減し、法改正にも自動で対応できるだけでなく、従業員が安心して休業できる環境を支援します。
人事・労務担当者の負担を減らしつつ、従業員一人ひとりに向き合う時間を生み出すためにも、この記事を参考に自社に合ったサービスを選んでみてください。
※料金はプランや従業員数によって変動します。詳細は各サービスの公式サイトをご確認ください。