TOP > SaaS > 人事評価システム > 人事評価ナビゲーター
TOP > SaaS > 人事評価システム > 人事評価ナビゲーター






人事評価ナビゲーターは、業界トップクラスの低価格で導入できる、シンプルで使いやすいシステムです。人事評価制度の活用の幅を広げ、運用の効率化を実現できます。
人事コンサルを通じてこれまで培ってきた経験やノウハウを詰め込み、様々なクラウドサービスと比較してもサービスの質・価格・フォロー体制において、確かな価値を提供しています。
本当に必要な機能を適正な価格で届け、中小企業、さらには日本を元気にしていきたいという想いが、人事評価ナビゲーターのサービスには込められています。
人事評価ナビゲーターは、業界トップクラスの低価格で導入できる、シンプルで使いやすいシステムです。人事評価制度の活用の幅を広げ、運用の効率化を実現できます。
人事コンサルを通じてこれまで培ってきた経験やノウハウを詰め込み、様々なクラウドサービスと比較してもサービスの質・価格・フォロー体制において、確かな価値を提供しています。
本当に必要な機能を適正な価格で届け、中小企業、さらには日本を元気にしていきたいという想いが、人事評価ナビゲーターのサービスには込められています。

当社では「スタンダードプラン(月額55,000円)」を導入しました。初期費用としては20万円程度を支払い、導入支援やカスタマイズ設定のサポートを受けました。
これまでExcelと紙ベースで評価を行っており、各部門のフォーマット差や提出遅延が常態化していました。管理職が評価対象を誤認するケースもあったため、評価の透明性や公平性を重視してツール導入を検討しました。複数のツールを比較する中で、「人事評価ナビゲーター」はUIがシンプルで教育コストが少なく済むこと、評価期間の設定やリマインド機能が自動化できることが魅力でした。特に導入の決め手となったのは、目標管理(MBO)と評価管理が1つの画面で完結できる統合性の高さです。
2025年4月〜2025年7月現在も利用中
①評価スケジュールの自動通知が便利
評価の開始・締切が自動でリマインドされるため、提出遅延が激減しました。以前使っていた「カオナビ」では、メール通知はあってもリマインドの柔軟設定ができず、Slack通知も非対応でした。
②コメント入力がしやすく、入力中の自動保存あり
評価コメントの途中入力が自動保存され、通信エラーで消えることがないのは地味にありがたい機能です。前に使用していた「スマレビ」では保存忘れによる入力やり直しが多発していました。
③評価シートのカスタマイズ自由度が高い
部署ごとに異なるコンピテンシー項目を設定でき、部署ごとの職務特性を反映させやすいです。「カオナビ」ではこの点で制約があり、全社統一の評価軸しか選べませんでした。
①スマホからの操作性がいまひとつ
レスポンシブ対応はしているものの、スマホ画面だと評価コメント欄が小さく、入力しにくいです。過去に使った「HRMOS」はスマホUIに最適化されていたため、外出先での操作性が高かった印象です。
②初期設定に時間がかかる
評価項目や社員データのインポートに手間がかかり、慣れるまではサポートを仰ぐ必要がありました。導入時のテンプレートはあるものの、自社仕様に調整する工程が多く、改善の余地ありです。
③コメント欄の文字数制限がやや厳しい
評価者として詳細に書きたい場合、入力制限文字数に引っかかるケースがあります。「カオナビ」ではコメントフィールドの拡張ができたので、もう少し柔軟にしてほしい点です。
コスト面では、毎期の評価テンプレートを一から作るのではなく、前年のデータを「複製機能」で再利用しています。また、評価者ごとの進捗をExcel出力で一覧化し、部門責任者が早期介入できるようにすることで、リマインド回数を減らしました。加えて、評価時期の直前に簡易マニュアルを全社配布しておくことで、サポート対応の工数も削減できました。Slack連携を自前で設定して通知を自動化するのもおすすめです。
Slackとの連携が可能で、評価開始・締切・未入力のアラートをSlackチャンネルで通知できるのは非常に便利でした。また、Google Workspaceとの連携でGoogleスプレッドシートに評価結果を自動エクスポートし、役員会議用の資料作成に活用しています。ただし、kintoneなどの業務アプリとの連携には若干設定の手間がかかりました。API連携の自由度はあるものの、知識が必要なので中小企業ではややハードルがあるかもしれません。
従業員数50〜300名程度の中堅企業で、部門ごとに独自の評価指標を使いたい会社には特におすすめです。評価制度が属人化しており、透明性を持たせたい場合には有効に機能します。一方で、従業員数10名以下で人事制度が簡素な会社にはオーバースペックかもしれません。また、スタートアップ企業のように変化が激しい組織では、都度テンプレート修正が煩雑に感じる可能性があります。
スタンダードプラン(月額55,000円)初期費用としては20万円程度

初期費用は約15万円 月額は約4万円だったと思う
従業員数が約200人と多く、人事評価を行うための一定のツールが無かったため。
2019年4月~2023年1月現在も利用中
・中企業~大規模組織でみたときに価格が安いと感じた。コストパフォーマンスが良い。
・当院はPC操作が苦手な年配者が多いが、操作は基本的にシンプルなので、そのような方でも分かりやすかった。
・ログイン手続きもクラウド上で簡単に行えるため、どこでも自己評価を入力できる。
・どこをクリックしてから入力するのが良いか、また、入力がちゃんと終わっているかなどについては、インターフェイスがやや分かりづらい。
・自己評価ではD~Sまであるが、特にB~Sの文章では同じような文面が並んでおり、違いが分かりづらい。読みこまないと違いが分からない点がストレスに感じる。
・単独で使いやすい反面、外部ツールとの連携はしづらいように感じた。
連携はしづらそうなので、外部ツールとの連携はなく、単独で使用しています。
当方は中型の病院だが、大企業でもかなり値段が安いようなので、コストパフォーマンスが気になる企業にはオススメしたい。
初期費用は約15万円 月額は約4万円

初期費用101,200 月額料金 おすすめプラン 35,420円
料金プランが人数ごとに明確に提示されている点がわかりやすいと思い、決め手になりました。それまで行っていたエクセルによる管理では煩わしかったので、利用者の話や導入事例などが多数あるツールということにも背中を押されました。
経営者向けの総括資料をボタン一つで自動生成できる機能については、仕上がった資料が理想の資料とは違うので不満がありました。
是非推奨したいと思います。多くの福祉施設や事業所で採用されていて、そちらでの評価も高いです。エクセル等の管理に限界を感じておられる担当者には検討してほしいです。

月額6000円ぐらい 初期費用不明
2018年末ぐらいから現在に至るまで。
評価に関する資料作成や集計がシステム上でできるようになり、人員配置や役職を複数人で決めていく際に一元化できるようになりました。
作成データを出力するときのファイル形式が限られているのが若干気になりました。だからといって作業が滞るなどの事が発生したわけではありませんが、もっと様々なファイル形式を選べることで様々な使い方ができるようになると思いました。
「評価する側」にあたる人にオススメできるツールだと思います。利用することで必要なときに必要なデータを瞬時に確認することができるので、仕事が円滑になると思います。

総務
Dのベーシックプランを初期費用15万円以下で月額3万円弱くらいで利用していたと思います。
2020年4月~2021年3月
今まで煩雑になっていた人事評価を一元管理して組織を強固にするため、試験的に導入にいたったと思います。
入力した過去のデータと照らし合わせて、現在のデータを管理できる点は使いやすく感じました。利用料金もお手軽なことも、使いやすい点といえるのであれば該当します。
過去にこの手のツールは利用したことがなかったため、不慣れだったということも要因としてあるかもしれませんが、直感的に利用できる機能が少なかったです。コンサル面からのサポート機能があるからかもしれませんが、操作になれるまで1~2ヶ月手探り状態でした。
金額をとるか、操作方法を習得するまでの時間をとるかというとろでしょうか。安くても、一番は使い勝手の良さだと思いますので、あまりオススメしません。

利用ユーザー(営業事務)
2018年9月~2020年12月
人事評価システムがうまく構築できず、市販ツールを使用することになった為。
スマートフォンからログインができるため場所を選ばず、電車での長距離移動中に作業することができた。
操作が簡単で過去の評価結果の振り返りが容易。
またシステム化によって評価の公平化も図れ、従業員の納得度が以前よりも上がった。
文字が小さい。スマートフォンで操作すると、全体を見る事ができ、スクロールになってしまい非常に見ずらい。
退勤管理や業務アンケートなどほかの外部ツールと連携ができないのでツールがいくつにも分かれてしまい、管理も従業員への告知も不便。
低価格で導入しやすいので、人事評価のみが希望ということであればお勧めします。ただ現在活用しているほかの外部ツール等を連携したいのであれば、あまりお勧めではないかもしれません。

利用ユーザー(人事)
2017年5月~2021年10月現在も利用中
プロジェクト進行などに関して結果とその過程での取り組みを見える化してシステムに落とし込んでいけるので、適切で正しい人事評価できるようになりました。
スマホ対応しているのが便利なのですが、スマホの場合文字がかなり小さく、スクロールもしづらく必要な場所に必要なアイコンなどがないのが不便です。文字を大きくしてもらったり画面上の配置を自分たち好みになるようにカスタマイズできる機能性が伴えばより便利になると思います。
個人やチームなどの評価を見える化し、根拠を伴う正しい人事評価をしていきたい場合にオススメ出来るツールです。特にシステム上で一元管理できるので、評価を元にした人員配置を瞬時に組めるのが特徴的です。

月額5000円
2019年11月〜2021年11月現在も利用中
評価基準に対しての細かな数字や達成度など「評価の見える化」をすることが可能になります。そのため人員配置や役職推薦など人事に関する配置を関係者で共有し、的確にそして迅速に判断していけるようになりました。「業務の効率化」は確実にできました。
それまで利用していたEXCEL上にまとめていた評価シートのデータをそのまま移行することができないのは不便でした。また1から作成しなければならない手間が発生しました。
人事や管理職など人の評価や人員配置をする立場にある人にオススメしたいツールです。「なぜその評価や人員配置にするか」ということを決定づけることができる明確な判断基準を可視化することができます。
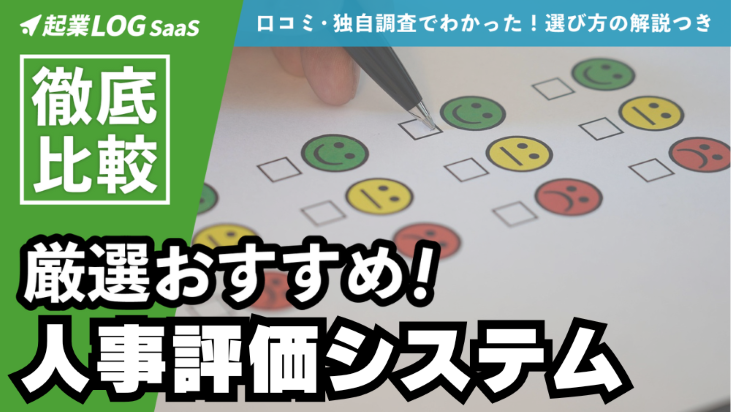
中小企業・自治体向けにおすすめ&人気の人事評価システム・ツール21選を評判・口コミ・料金・機能の面から徹底比較。専門家の意見をふまえた選び方やメリットもわかりやすく解説します!

HRBrain

あしたのクラウドHR

SmartHR

ヒトマワリ

クアルトリクス XM for Employee Experience

SAP SuccessFactors

シナジーHR

JobSuite TALENTS

スキルナビ

WiMS

モノドン
](https://image-prod.kigyolog.com/contents/tool/5eaba00b7aad78ea0f3174e844799d63.png)
One人事[タレントマネジメント](旧スマカン)

BizForecast HR

HRMOSタレントマネジメント

HiManager

評価ポイント

識学

Wistant

COMPANY Talent Managementシリーズ

sai*reco

HR-Platform 人事評価

HITO Talent

カオナビ

MINAGINE人事評価システム

MIRAIC

【職種別】人事考課コメントの例文と書き方を本人・上司別でポイント解説!

人事制度の目的と役割|仕組みや種類・課題点・改革時の注意点も解説

【絶対評価と相対評価とは】違いやメリット・デメリットを分かりやすく解説!

コンピテンシー評価とは?必要性や評価項目や基準、具体例を解説

成果主義を成功させるには?事例・導入のポイント・デメリットを解説

給与体系のモデル作成方法から見直し手順までをやさしく解説

中小企業にも人事評価は必要?制度導入で得られる効果や作り方を紹介

【人事必見】モチベーションマネジメントとは?社員の意欲を上げる方法

人材育成とは?基本的な考え方や具体的な方法を解説!

組織開発とは?使えるフレームワーク9選!進め方も解説
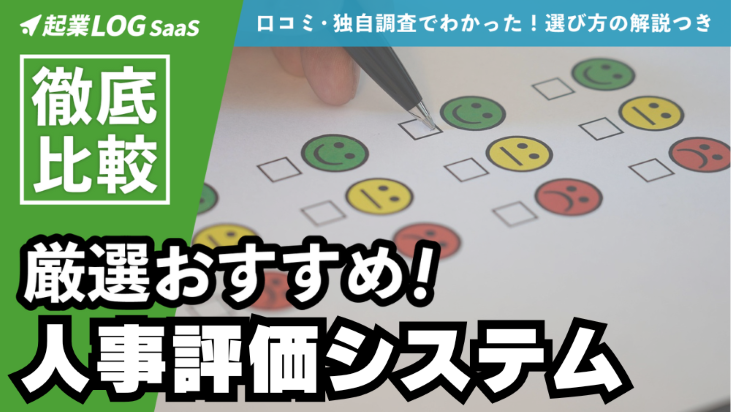
中小企業・自治体向けにおすすめ&人気の人事評価システム・ツール21選を評判・口コミ・料金・機能の面から徹底比較。専門家の意見をふまえた選び方やメリットもわかりやすく解説します!

HRBrain

あしたのクラウドHR

SmartHR

ヒトマワリ

クアルトリクス XM for Employee Experience

SAP SuccessFactors

シナジーHR

JobSuite TALENTS

スキルナビ

WiMS

モノドン
](https://image-prod.kigyolog.com/contents/tool/5eaba00b7aad78ea0f3174e844799d63.png)
One人事[タレントマネジメント](旧スマカン)

BizForecast HR

HRMOSタレントマネジメント

HiManager

評価ポイント

識学

Wistant

COMPANY Talent Managementシリーズ

sai*reco

HR-Platform 人事評価

HITO Talent

カオナビ

MINAGINE人事評価システム

MIRAIC

【職種別】人事考課コメントの例文と書き方を本人・上司別でポイント解説!

人事制度の目的と役割|仕組みや種類・課題点・改革時の注意点も解説

【絶対評価と相対評価とは】違いやメリット・デメリットを分かりやすく解説!

コンピテンシー評価とは?必要性や評価項目や基準、具体例を解説

成果主義を成功させるには?事例・導入のポイント・デメリットを解説

給与体系のモデル作成方法から見直し手順までをやさしく解説

中小企業にも人事評価は必要?制度導入で得られる効果や作り方を紹介

【人事必見】モチベーションマネジメントとは?社員の意欲を上げる方法

人材育成とは?基本的な考え方や具体的な方法を解説!

組織開発とは?使えるフレームワーク9選!進め方も解説