
タイムカードでの勤怠管理は導入しやすい一方で、集計・計算の手間や改ざんのリスクなどがあります。
また、業務負担を感じており、勤怠管理システムの利用を検討している担当者の方は多いのではないでしょうか。
本記事では、タイムカードによる勤怠管理のデメリット・課題を解説します。
勤怠管理システムの導入メリットや選定ポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
まずは、タイムカードで勤怠管理を行う3つのメリットは以下の3つです。
デメリットや課題とあわせてチェックしておきましょう。
タイムカードは、タイムレコーダーに差し込むだけで現在の時刻が打刻される仕組みです。
難しい操作が不要で、入社したての従業員でもスムーズに打刻できます。
また、タイムカードを確認すれば誰でもすぐに出勤者を把握できるなど、管理しやすいことがメリットです。
タイムカードでの勤怠管理に必要なのはタイムレコーダーと人数分のタイムカードだけです。
機種によって異なりますが、タイムレコーダーは2万円から購入できます。
さらに維持費はタイムカード更新時の用紙代やインク代、レコーダーの電気代しかかかりません。
タイムカードによる勤怠管理は、タイムレコーダーと人数分のタイムカードさえ用意すればすぐに導入できます。
オフィスの入口にタイムレコーダーを設置して、出勤時と退勤時にタイムカードを差し込むように口頭で指導するだけで済み、教育の手間や時間が不要です。

次に、タイムカードによる勤怠管理の課題を明らかにするために、5つのデメリットについて解説します。
タイムカードによる勤怠管理では、従業員の勤怠情報をタイムカードから転記して集計・計算しなければなりません。
目視で確認しながら管理者が手作業でパソコンに入力するため、従業員が多いほど膨大な業務量です。
また、手入力なので集計や計算ミスが発生しやすく、確認や修正にも手間がかかります。
さらに、ミスに気づかないまま誤った勤怠情報を給与計算に反映させてしまい、給与の未払いが発生する可能性もあります。
労働基準法第109条では、タイムカードの保管期限は5年間と定められています。
保管義務を怠ると罰則が科せられるため、適切に保管しなくてはいけません。
特に従業員数が多い企業では、タイムカードを参照する際に手間や時間がかかるだけでなく、保管に必要なスペースが大きくなるため、管理も難しくなります。
タイムカードでの勤怠管理は、正しい出退勤時間が記載されているかの証明が難しいため、簡単に不正ができてしまいます。
たとえば、「本人以外が代理で打刻する」「上司が残業時間を記録しないように指示する」などの不正が発生しやすいです。
また、改ざんや不正を放置すると、法的リスクが高まるだけでなく、企業の信頼性にも深刻な影響を及ぼします。
さらに、実際の労働時間とは異なる過剰な給与支払いが発生すれば、経済的な損失も避けられません。
タイムカードによる勤怠管理では、オフィスに出社してタイムレコーダーで打刻する必要性があります。
そのため、従業員のニーズに合わせて労働時間や勤務場所を自由に選べる多様な働き方には適していません。
また、タイムカードをタイムレコーダーに差し込む作業は単純ですが、急な対応に追われて打刻を後回しにしてしまいがちです。
さらに、一度打刻してしまうと修正やキャンセルができず、打刻ミスがあった場合は担当者に申告し、修正を依頼する必要があります。
タイムカードによる勤怠管理は、集計するまで正確な労働時間がわからない点がデメリットです。
日々の労働時間や残業状況をすぐにチェックできず、月末になって長時間労働が発覚するリスクが発生します。
また、労働基準法によって義務付けられている有給休暇の取得・消化についても、リアルタイムでの管理が難しいのが現状です。
このようにタイムカードでは、適切な管理体制を構築しにくく、意図せず労働基準法を逸脱するリスクがあります。
タイムカードによる勤怠管理の課題解決には、勤怠管理システムがおすすめです。
ここでは、勤怠管理システムの基礎知識と主な機能、タイムカードとの費用比較をまとめました。
勤怠管理システムとは、従業員の出退勤を正確に記録・管理できるシステムです。
出退勤時間や休憩時間、残業時間、欠勤、休日出勤などの勤務状況を、リアルタイムで把握できます。
WEBサイトやスマホアプリなどから打刻でき、記録した出退勤時間を自動で集計することが可能です。
勤怠管理システムの主な機能を、従業員と勤怠管理者に分けてまとめました。
従業員向けの主な機能は以下の通りです。
| 打刻機能 | デバイスから出退勤の時間を記録する |
| ワークフロー機能 | 打刻時間の修正・残業・休暇などの申請ができる |
| 通知機能 | 打刻忘れ・超過勤務・休暇取得不足などを通知する |
従業員が勤怠管理システムを使用する機会は多く、使いやすいものを導入することが大切です。
勤怠管理を行う労務管理者(勤怠管理者)向けの機能を紹介します。
| 勤怠情報の集計機能 | 従業員が入力した情報をもとに勤怠時間を集計する |
| スケジュール管理機能 | 勤務体系や雇用形態にあわせて従業員のスケジュールを管理する |
| シフト管理機能 | 希望シフトをもとにシフト表を自動で作成できる |
| 帳票出力機能 | 集計した勤怠データをCSVやPDF形式で出力できる |
| 他システムとの連携機能 | 給与管理システムなど他のシステムとの連携できる |
勤怠管理システムには、担当者の業務負担を軽減できるさまざまな機能が備わっています。
ただし、連携が可能な他システムは勤怠管理システムによって異なるため、事前に確認しましょう。
勤怠管理システムには、オンプレミス型とクラウド型がありますが、現在の主流はインターネット上のサービスを利用するクラウド型です。
以下に、タイムカードとクラウド型勤怠管理システムの費用をまとめました。
| タイムカード | タイムレコーダー | 印字のみ:2~5万円 USBでデータ出力が可能:5~7万円 本体で自動集計が可能:15~20万円 |
|
| ランニングコスト | タイムカード(100枚):1,000~2,000円 インクカセット:1,500~2,000円 |
||
| 勤怠管理システム | 初期費用 | 0~50万円 | |
| 月額費用 | 200〜500円/人 | ||
料金体系は勤怠管理システムによって異なりますが、管理する従業員1人ごとに月額費用が発生するのが一般的です。
また、利用する人数によって料金は変わるため、見積もりをとって確認しておきましょう。

ここでは、タイムカードから勤怠管理システムに移行するメリットをまとめました。
タイムカードでの勤怠管理に課題を抱え、勤怠管理システムの導入を検討している担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
勤怠管理システムでは、労働時間や残業時間、休暇の取得状況など、リアルタイムで確認できることがメリットです。
従業員が入力した情報は自動で集計されるため、改修や転記、計算といった業務が必要ありません。
また、特定の期間や時間帯を限定して閲覧や集計が可能なので、労務管理の担当者は必要な情報をいつでも参照できます。
さらに、給与計算システムとの連携で勤怠管理と給与計算が一元管理でき、さらなる業務効率化につながります。
勤怠管理システムには、パソコンのログオン・ログオフや入退室記録と連携できる機能を備えたものがあります。
また、打刻漏れを通知する機能もあるため、より正確かつ確実に打刻できることがメリットです。
もし、打刻ミスがあった場合には管理者による承認が必要なので、改ざんの心配もありません。
さらに、スマートフォンのGPSを活用して打刻できるシステムもあり、テレワークや直行直帰、出張でもより正確な打刻が可能です。
生体認証システムによる打刻なら、第三者による不正な打刻の心配もありません。
勤怠管理システムでは、以下のような打刻方法から選択できます。
複数の打刻方法を組み合わせることができ、就業形態や条件にあわせて打刻できます。
ただし、対応する打刻方法は勤怠管理システムによって異なるため、あらかじめ確認しておくことが重要です。
一般的なクラウド型の勤怠管理システムでは、勤怠管理に関する法改正があれば自動でアップデートされます。
また、出退勤時間や残業時間、有給の取得状況を把握でき、一定の時間を超過した従業員がいれば一覧や通知で把握が可能です。
法改正のたびに管理体制や手順を見直す必要がなくなり、労務管理担当者の負担を軽減できます。
自社の働き方や管理体制に合わない勤怠管理システムを選んでしまうと、かえって業務負担が増えたり、勤怠管理が難しくなってしまいます。
ここでは、勤怠管理システムを選ぶ際に押さえておきたい5つのポイントについて解説します。
まずは自社の勤怠管理で抱えてる課題から、どのような業務をシステム化したいのかを明確にします。
絶対に必要な機能やあると便利な機能など、重要度で分けると自社に最適な勤怠管理システムが選べるはずです。
また、雇用形態や勤務形態にあった打刻方法が搭載されているかどうかも、あわせて確認しておきましょう。
勤怠管理システムが、すでに導入しているシステムとの連携に対応しているか、あらかじめチェックしておきましょう。
給与計算システムや労務管理システムと連携できれば、情報を別々に入力する必要がなくなり、業務効率化にもつながります。
勤怠管理システムは、労務管理担当者だけではなく、打刻するすべての従業員が利用するため、誰でも使いやすい勤怠管理システムを選ぶことが重要です。
画面の見やすさや操作のシンプルさはもちろん、必要な情報にすぐアクセスできるか、打刻や申請がスムーズにできるかといった点も確認しましょう。
デモンストレーションや無料トライアルがある場合は、実際に使って試してみることをおすすめします。
労働基準法など勤怠管理に関わる法改正は定期的に行われます。
また、法改正は業界や企業規模によって適用タイミングや内容が異なることもあります。
そのため、法改正の際に自動でアップデートされる勤怠管理システムを選ぶと、法令違反や労務トラブルを未然に防ぐことが可能です。
さらに、サポート体制が整っているシステムであれば、法改正に関する情報提供も受けられるので、安心して利用できます。
勤怠管理システムの料金体系は、月額制や従量課金制などさまざまで、複数のプランが用意されてるものもあります。
必要な機能や利用人数をふまえたうえで、導入費やランニングコストがどれくらいかかるか調べましょう。
また、打刻の方法によっては機器の購入やレンタルが必要なので、あわせてチェックが必要です。
複数の勤怠管理システムから見積もりをとれば、より正確な料金を比較できます。
タイムカードによる勤怠管理は集計・計算に時間や手間がかかり、打刻の改ざんなども発生する可能性があります。
タイムカードでの勤怠管理に限界を感じ、発生するさまざまな課題を解決したいなら、勤怠管理システムの導入がおすすめです。
法律に則った正確な勤怠管理や業務の効率化につながります。
選定ポイントも紹介したので、自社にあった勤怠管理システムを選ぶ際にぜひ役立ててください。
画像出典元:O-DAN

時間外労働の種類や改正前後のポイント|36協定についても徹底解説!

勤怠管理のやり方を徹底解説!基本的な流れから管理方法の比較まで

管理職も勤怠管理は必須?管理監督者の定義・労働時間のルールも解説

Web打刻とは?勤怠管理システムを導入すべき企業・メリット・おすすめツールも詳しく解説

【法令遵守】正確な残業時間の管理に最適な方法!上限規制や法律もわかりやすく解説

社長の勤怠管理は不要?理由や勤怠管理が必要となるケースについても解説します

ノーコードツールを使って勤怠管理システムを自作できる?作る手順や費用を解説!

【生体認証で勤怠管理】4種類の特徴を解説|おすすめシステムも紹介

労働時間の上限は1日8時間・週40時間!違反が発覚したらどうなる?

労働基準法に基づいた正しい休憩時間のルールを解説!無自覚な違法も?

Web給与明細システム

労務管理システム

シフト管理システム

人事システム

マイナンバー管理システム
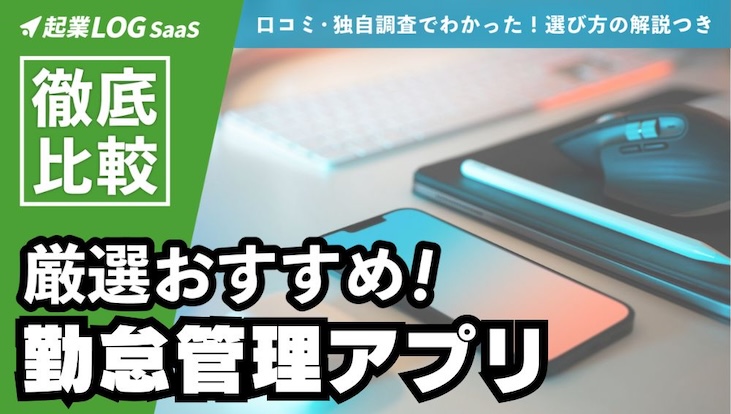
勤怠管理アプリ

営業職向け勤怠管理システム

青色申告ソフト

無料勤怠管理システム

製造業向け勤怠管理システム

運送業向け勤怠管理システム

建設業向け勤怠管理システム

人事管理システム

年末調整支援システム

中小企業向け勤怠管理システム

飲食店向け勤怠管理システム

サービス業向け勤怠管理システム

介護業向け勤怠管理システム

病院向け勤怠管理システム

シフト管理アプリ

有給管理ソフト

人事アウトソーシングサービス

無料労務管理ソフト

パッケージ型労務管理システム
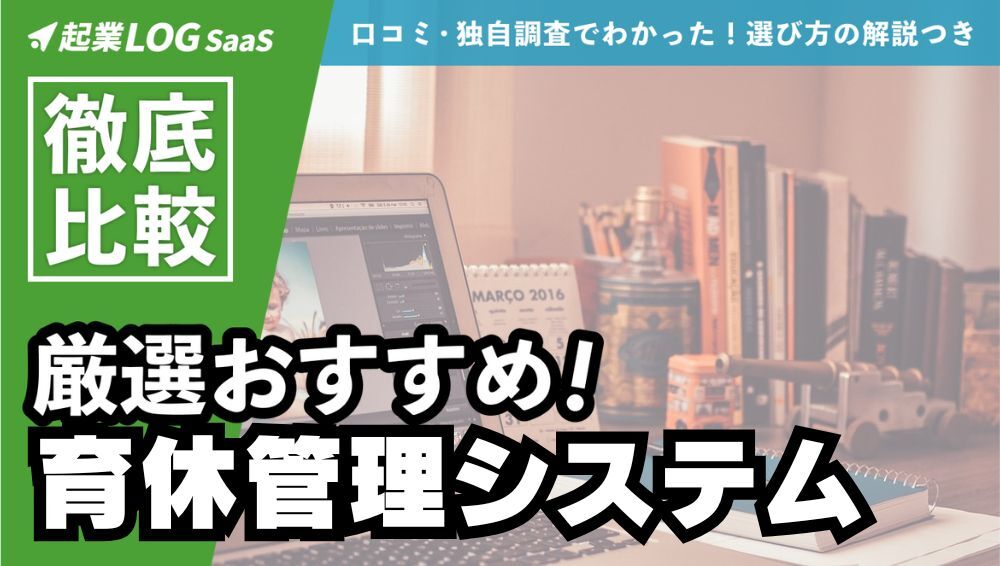
育休管理システム

電子契約サービス