
人事管理の目的は「従業員の能力を活かすこと」、労務管理の目的は「法令に基づいて従業員の職場環境を整えること」です。
企業にとって重要な経営資源である「ヒト」の管理に関わる点は同じですが、両者の業務内容は異なります。
人事管理領域と労務管理領域とを正しく区別し、柔軟かつ効率的な人材管理を実現させましょう。
本記事では、人事管理と労務管理の違いやそれぞれの業務内容、両者を効率化するためのポイントをご紹介します。
目次
人事管理:戦略的な人材マネジメントを実現するための業務
労務管理:法令に基づいて企業の労働条件を整備・維持するための業務
人事管理と労務管理の役割や目的は異なりますが、「ヒト」を管理する点では同じです。
両者は複数の業務が重複することから線引きが難しく、実務の境界が曖昧になる傾向があります。
「組織運営が非効率化している」「従業員満足度が低い」といった課題を抱える企業は、人事管理と労務管理の役割分担や業務プロセスの違いを理解して、見直しを検討することが必要です。
ここでは、人事管理と労務管理の違いについて詳しくご紹介します。
人事管理は、従業員の能力を最大化したり適材適所を実現したりするために必要な業務です。
企業の経営戦略に関わる、以下の領域が含まれます。
人事管理を適切に行うことにより、「従業員が成果を上げやすくなる」「従業員のモチベーションや成長を促せる」などのメリットがあります。
適切な人事管理は、組織全体の活性化や競争力の強化、継続的な成長を実現する上で必須です。
労務管理は、従業員の働く環境や労働条件を、法令に基づき適切に管理するための業務です。
労働環境の安全性や法令遵守、勤務状況の整備に関わる、以下の領域の業務が含まれます。
適切な労務管理が行われることにより、企業は法令違反のリスクを低減したり、従業員の働きやすさを向上したりできます。
従業員が不安なく能力を発揮できる環境を構築することは、企業の健全な経営や生産性の向上を実現するためには欠かせません。

人事管理は、戦略的に人材を活用するために必要な業務です。
ここでは、人事管理で特に重要な4つの業務をご紹介します。
採用活動とは、企業が人材を採用するために行うプロセス全般です。
企業が経営理念やビジョンを実現するためには、自社にとって必要なスキルや価値観を持った人材をそろえることが必要となります。
長期的な成長戦略に基づいて適切な採用計画を策定し、組織文化に合った人材を獲得し育成していかなければなりません。
採用活動の主な業務には、以下のものがあります。
企業の競争力強化や継続的な成長に直結する採用活動は、人事管理の重要な一部です。
人材育成・研修計画とは、企業戦略に即した体系的な教育や訓練プログラムを策定・実施することです。
企業が主体的に従業員の能力向上やキャリア形成を支援することで、組織全体の競争力向上と継続的な成長を目指します。
具体的な業務内容は、以下のとおりです。
人材育成計画や研修、キャリアプランニングは、企業の経営戦略や将来ビジョンに合わせて「どのような人材をどう育てていくか」を中長期的に考えるためのものです。
従業員のキャリアアップ・スキルアップはもちろん、組織文化や企業の価値観を根付かせるためにも、重要な人事管理業務といえます。
人材配置は、事業戦略や事業プランに合わせ、従業員を最適な部署や役割に配置する業務です。
人材配置では、従業員それぞれのスキル、経験、適性はもちろん、キャリア志向まで考慮して最適な部門や職務を決定しなければなりません。
人事管理における人材配置には、以下の業務が含まれます。
適切な人材配置により従業員が活躍できる場が増えれば、組織全体の活性化・組織力の強化を実現できます。
人事評価は、従業員が一定期間内に達成した業績や能力を評価する業務です。
人事評価の結果が給与や昇進、教育訓練などの人事施策に影響することから、透明かつ信頼性の高い評価システムが求められます。
人事評価の設計・運用に関する具体的な業務は、以下のとおりです。
評価基準に企業のビジョンを適切に組み込めば、従業員は企業が求める行動や価値観を理解しやすくなります。
業務においてどのような行動を取るべきかが明確になり、従業員1人ひとりが企業の戦略・文化に即した働き方を実現することが可能です。
適切な人事評価の設計・運用は、戦略的な人材育成や適材適所の実現、さらには組織全体の活性化にもつながるため、人事管理において非常に重要な要素です。
労務管理は、従業員が安心して働ける環境を整えるために必要な業務です。
労務管理に関係する業務として、特に重要な4つの業務をご紹介します。
勤怠管理は、従業員の出勤状況や労働時間を正確に記録して管理するための業務です。
勤怠データは給与計算の基礎となるため、ミスや曖昧さは許されません。
従業員が不満や不安を感じることなく働ける環境を構築するためには、適切な勤怠管理が必須です。
勤怠管理業務には、以下の内容が含まれます。
なお従業員の労働時間や休憩、休日、残業時間の記録と管理は、労働基準法により定められた雇用者の義務です。
法令遵守の観点からも、詳細かつ正確な勤怠管理が求められます。
給与計算は、従業員に正確かつ公平な給与支払いを実現するための業務です。
支払いの遅延や計算ミスは、従業員の生活に大きな影響を及ぼします。
わずかなミスが不満や不安を招くこともあるため、給与計算には正確さと迅速さが求められます。
また従業員への給与は、企業経費の中でも「人件費」として大きな割合を占めます。
労働コストの適切な管理や、実態に即した予算および経営戦略の立案を行うためにも、給与データは適切に管理されなければなりません。
入社・退職の手続きは、新たに入社する従業員と退職する従業員に対し、必要な事務処理や対応を行う業務です。
| 入社手続き |
|
| 退職手続き |
|
従業員の入社および退職時には、法令で定められた処理が必要です。
トラブルの発生を抑制し法的リスクを回避するためには、各種手続きや対応を迅速かつ正確に行う必要があります。
職場環境の整備は、従業員が不自由なく働ける環境を構築するための業務です。
職場環境の整備に関わる業務には、以下のものがあります。
| 業務内容・作業方法の見直し | テレワークやフリーアドレス制の検討、作業量のバランス調整など |
| 安全衛生対策 | 労働安全衛生法に基づく安全衛生管理体制の構築 |
| 衛生・健康管理 | 衛生設備の整備・メンタルヘルス対策 |
| 作業環境の最適化 | 温度や空気環境の整備、照明やレイアウトの最適化など |
| 休憩・リフレッシュスペースの整備 | 快適な休憩室やリフレッシュエリアの設置など |
| コミュニケーション環境の整備 | 意見交換や情報共有がしやすい仕組みづくりなど |
職場環境の整備は、従業員の安全と健康を守り、生産性を向上させるために必要な業務です。
従業員が安心して働ける環境を計画的に整えることで、「事故や健康被害のリスク低減」「従業員の満足度やモチベーションの向上」をスムーズに実現できます。

人事・労務管理では、属人化や法令対応など、避けて通れない課題が存在します。
ここでは、企業が直面しやすい3つの課題について、それぞれ詳しく解説します。
人事・労務管理業務の中には、専門性や機密性の高い業務が少なくありません。
そのため、業務の標準化や業務内容の共有が難しく、属人化しやすい傾向があります。
例えば給与計算は、企業会計の知識や労働基準法をはじめとする法令への理解が必要です。
これらを理解している担当者に業務が集中しやすく、属人化してしまいます。
業務が特定の担当者に依存してしまうと、担当者が不在時に業務が滞るリスクがあります。
人事・労務管理業務は、労働基準法や男女雇用機会均等法、個人情報保護法、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)などの定めに従って行う必要があります。
担当者の理解が浅く法令違反が発生した場合、重い罰金や訴訟に発展するかもしれません。
顧客からの信頼性も失われ、企業価値が損なわれるリスクもあります。
また近年は労働者の権利意識の高まりに加えて、社会からの目も厳しくなっているため、「ただ法令を守るだけ」の姿勢ではよいイメージを持たれません。
企業としての信頼性を高めるには、社会的規範や倫理も含めてコンプライアンスを遵守することが必要です。
人事・労務管理業務には、より慎重な姿勢と高い倫理観が求められることから、担当者への負担は増大しています。
働き方改革の推進により、多様な働き方を認める企業が増えています。
各雇用形態に応じた人事・労務管理が必要となることから、担当者には以下のような負担が増えているのが実情です。
担当者が適切な人事・労務管理を実現できない場合、「法令違反が発生する」「人材の採用・定着が難しくなる」「従業員のモチベーションが低下する」などのリスクが高くなります。
企業の労働生産性を向上させるためには、人事・労務管理を効率化することが必要です。
管理業務が効果的に機能していない企業が実行すべき2つの方法について詳しくご紹介します。
人事・労務管理の業務範囲は多岐にわたっており、機密性の高いものや個別対応が必要なものが少なくありません。
業務が複雑になるほど無駄な手順や重複作業が発生しやすく、業務全体の非効率化を招きます。
早急に業務プロセスの詳細な見直しを行い、無駄な工程や作業を排除することが必要です。
以下の手順に従い、人事・労務管理業務プロセスの見直しを行いましょう。
| 現状の把握 | 現状業務の洗い出しを行い、課題を抽出する |
| 課題の抽出と優先順位の設定 | 抽出した課題に優先順位をつけ、改善すべきポイントを明確にする |
| 目標設定 | 改善の目的やゴールを設定する |
| 改善策の検討 | 課題に応じた改善策を検討する |
| 改善策の実行 | 検討した改善策を実行し、効果を検証する |
業務のプロセスを見直すときのポイントは、現場の声を反映することです。
現場の改善要望を積極的に取り入れれば、より実践的な改善策が生まれやすくなります。
人事管理システム・労務管理システムを導入すれば、煩雑な業務を自動化できます。
勤怠管理や給与計算、採用管理といった負担の大きい定型業務について、大幅な業務効率化が可能です。
それぞれのシステムの目的や機能は、以下を確認してください。
| 人事管理システム | 労務管理システム | |
| 目的 | 人材情報の管理・活用 | 勤怠管理、給与計算、社会保険などの手続き管理 |
| 機能 | 従業員情報管理、評価、配置、育成 | 勤怠管理、給与計算、入退社・年末調整手続き |
| 管理対象 | 人材データ、人事異動、評価、研修 | 労働時間、給与、雇用契約、社会保険 |
人事・労務管理システムの選定と導入では、現行の業務プロセスと課題を明確にし、必要な機能、カスタマイズ性、セキュリティ、サポート体制などを見極めましょう。
自社に最適なシステムを選ぶことで、業務効率の向上はもちろん、コンプライアンス遵守や戦略的な人事施策の推進が可能になります。

人事・労務管理業務が煩雑化している企業は、人事管理システムや労務管理システムの導入がおすすめです。
ここからは、システム導入によって得られる3つのメリットをご紹介します。
管理システムを導入することにより、手作業や紙ベースの作業を削減できます。
担当者が無駄な業務に手をかける必要がなく、作業効率が向上するのがメリットです。
また手作業の工程がなくなれば、入力や計算、転記のミスといったヒューマンエラーも発生しません。
ミスが許されない給与計算や勤怠集計などの業務において、正確性が大幅に向上します。
管理システムを導入すれば、業務がシステムのルールやプロセスで実行されます。
担当者の独自ノウハウや経験、直感などに頼る必要がなく、誰が業務を担当しても決まった手順で正確に遂行することが可能です。
加えて、管理システムで処理した業務データはシステム内に蓄積されるため、業務手順やノウハウを簡単に共有できます。
業務が特定の担当者に依存しにくく、担当者不在時の代行や担当者変更時の引継ぎがスムーズです。
管理システムは、分散しがちな従業員情報や給与、勤怠データを一元管理できるのも大きなメリットです。
重要な情報に対して厳格なアクセス制限を設けたり、アクセス権限を適切に振り分けたりすることで、不正アクセスや情報漏洩のリスクを低減できます。
また管理システムの多くは、個人情報保護法や各種労働関連法規に準拠して設計されているのが一般的です。
データの変更履歴やアクセスログを記録する監査機能が搭載されており、不正行為についての追跡や調査が容易になります。
クラウド型のサービスなら、セキュリティパッチやアップデートが定期的に自動で実行されるというメリットもあり、常に最新のセキュリティ対策を維持できます。
人事管理は人材の採用や育成、評価などの「人材活用」に関する業務であり、労務管理は従業員の契約や労働環境、労働条件の管理、法令遵守に関する業務です。
両者の線引きが曖昧になると、業務の非効率化や法令違反、組織全体のパフォーマンス低下などを引き起こすリスクがあります。
企業の担当者は人事管理業務と労務管理業務の違いを正しく理解し、適切な業務分担を行いましょう。
人事・労務管理業務が効果的に機能していないと思われる場合は、システムの導入で作業効率の向上やセキュリティ強化を図ることも検討してください。
画像出典元:O-DAN

勤怠管理システム

Web給与明細システム

労務管理システム

シフト管理システム

人事システム

マイナンバー管理システム
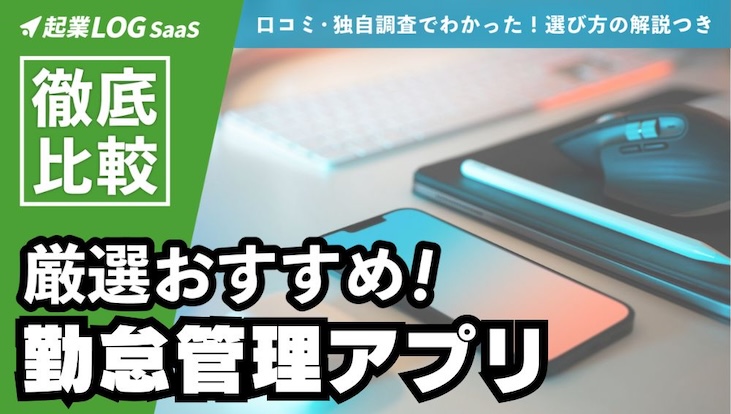
勤怠管理アプリ

営業職向け勤怠管理システム

青色申告ソフト

無料勤怠管理システム

製造業向け勤怠管理システム

運送業向け勤怠管理システム

建設業向け勤怠管理システム

年末調整支援システム

中小企業向け勤怠管理システム

飲食店向け勤怠管理システム

サービス業向け勤怠管理システム

介護業向け勤怠管理システム

病院向け勤怠管理システム

シフト管理アプリ

有給管理ソフト

人事アウトソーシングサービス

無料労務管理ソフト

パッケージ型労務管理システム
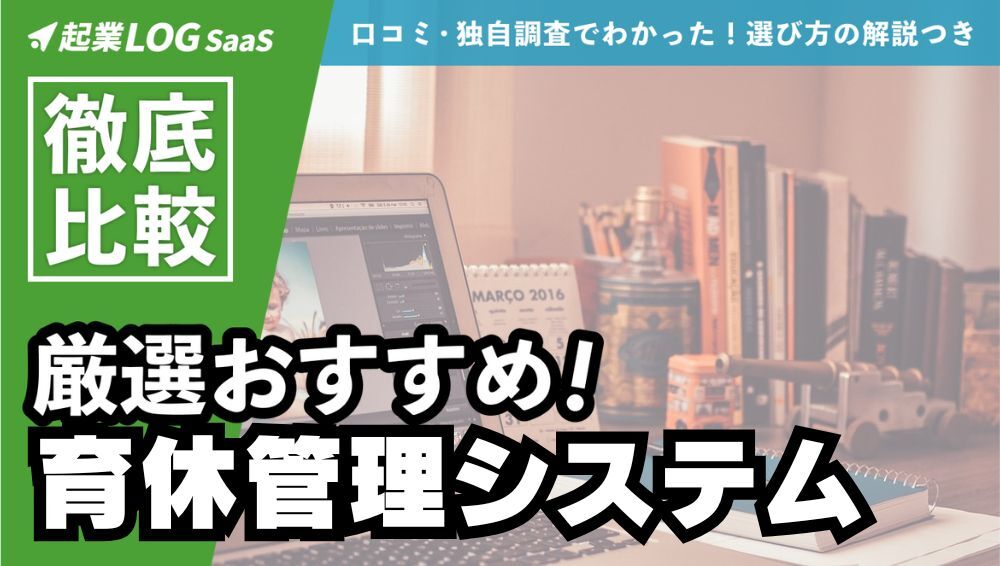
育休管理システム

電子契約サービス