
AIの進化が、SaaSのあり方を根本から変えつつある。単なる業務効率化ツールにとどまらず、より自律的で高付加価値なプロダクトへと進化しているのだ。こうした変化に対応すべく、SaaS企業各社はAIを中核に据えた製品戦略を次々と打ち出している。
では、実際にどのような企業が、どのようなアプローチでAIを実装しているのか。本記事では、日米SaaS企業の取り組みを紹介する。
監修記事
監修:プロトスター株式会社 代表取締役 前川英麿
早稲田大学政治経済学部政治学科卒業後、ベンチャーキャピタルのエヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ(現、大和企業投資株式会社、SMBCベンチャーキャピタル株式会社)に入社。 シードからレイターまで幅広いフェーズ、領域の企業への投資育成に関与した。 その後、常駐の経営再建支援に特化したフロンティア・ターンアラウンドに入社し、地方における小売・製薬・メーカー等の経営再生に従事する。 2015年2月よりスローガン株式会社に参画し投資事業責任者として、Slogan COENT LLPを設立し、20社以上の企業に投資。 2016年11月に起業家支援インフラを創るべくプロトスター株式会社を設立。 その他、経済産業省 先進的IoTプロジェクト選考会議 審査委員・支援機関代表、ネイティブ株式会社社外取締役、株式会社サイトビジット(現:freeeサイン株式会社)社外監査役など複数の企業の経営に関与している。 青山学院大学「アントレプレナーシップ概論」非常勤教員。
目次
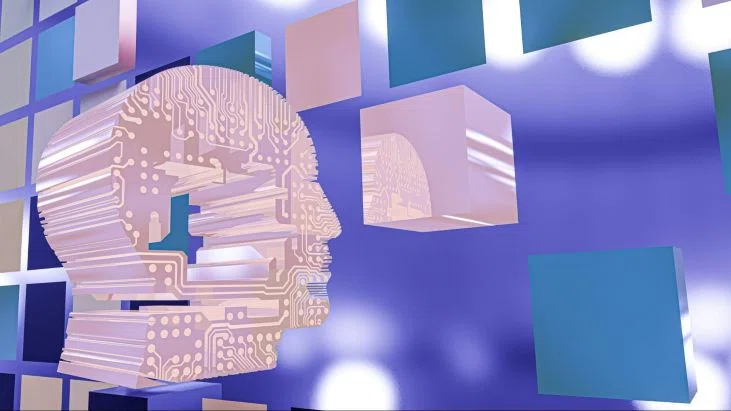
2024年、業界で「SaaS is Dead」という議論が巻き起こった。その背景には、ユーザーの指示で複数のアプリを横断し、自律的にタスクをこなす「AIエージェント」の台頭がある。これにより、業務プロセスそのものが再定義されつつある。
結果として、限定的な機能しか持たず、外部と連携できないSaaSは選ばれにくくなるだろう。AIはもはや単なる付加機能ではなく、あらゆるプロダクトの「前提」となり始めている。
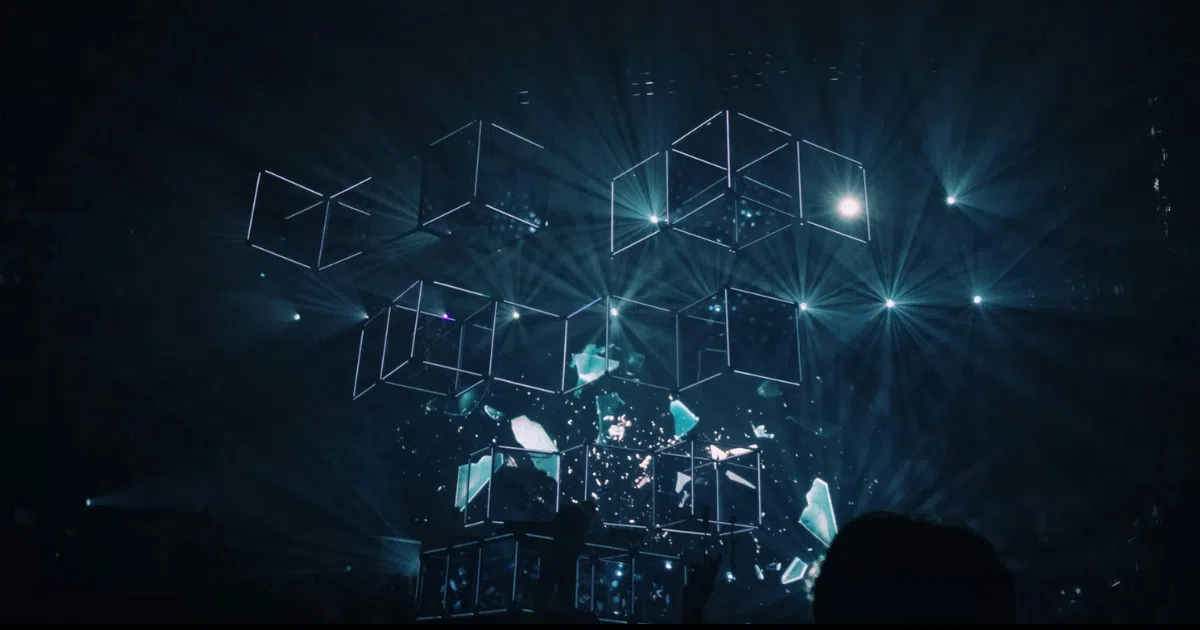
「SaaS is Dead」を背景に、米国のSaaS企業は、AIを中核に据えたプラットフォーム戦略を加速している。営業、マーケティング、サポートなど全領域でAIを統合し、プロダクトの付加価値を高めることが今後の競争力確保の鍵となる。
以下の3社は実際にAI導入を進めている事例だ。
CRM大手のSalesforce(セールスフォース)は、AI機能群「Einstein(アインシュタイン)」を自社のCRMプラットフォームに統合した。AIが顧客データを統合・分析し、営業提案やサポート対応の精度を向上させている。
さらに、自律型AIエージェント「Agentforce(エージェントフォース)」を発表。これは、顧客からの問い合わせ対応やスタッフの教育といった、従来は人が担ってきた業務を自動化するものである。
同社がこれらのAI機能で目指すのは、単なる作業の自動化にとどまらない。データに基づき、企業の意思決定そのものを支援することである。
Adobeの取り組むAI施策は、主に生成AI「Firefly(ファイアフライ)」とマーケティングAI「Agent Orchestrator(エージェント・オーケストレーター)」の2点だ。
「Firefly」は著作権的にクリーンな素材を学習データとすることで、企業が安心して生成物を商用利用できるAIである。PhotoshopやIllustratorなど、Creative Cloud製品群と統合され、コンテンツ制作の効率化を図る。
一方、「Agent Orchestrator」は、顧客データに基づき、マーケティング施策を自動で最適化するAIエージェントだ。
同社はこれらの取り組みにより、制作から体験提供まで、ビジネスプロセス全体をAIで一貫して支援する基盤を形成している。
HubSpotは、AI機能を搭載したマーケティング支援ツール「HubSpot Breeze(ハブスポット・ブリーズ)」を提供している。
「HubSpot Breeze」は操作性に優れたUIと、外部ツールとの連携しやすさが特徴で、専門的なAI人材を持たない中小企業でも活用しやすい。
さらに同社の自律型AIエージェント「Breeze Agents」は、マーケティング、営業、カスタマーサポートといった幅広い業務の自動化を実現する。これにより、人的リソースが限られる組織の生産性向上と持続的成長を後押しする。

編集部
米国のSaaS企業のAI戦略について、どのように考えていらっしゃいますか?

監修:前川氏
米国のSaaS企業が展開するAI戦略の本質は、顧客の「業務フローの起点」を誰が握るか、という競争だと考えています。
自社のプラットフォームを起点としてAIエージェントが自律的に業務を遂行するようになれば、顧客はもはや、そこから離れることが困難になります。
これは、他社サービスへのスイッチングコストを極めて高くし、顧客を自社エコシステム内にロックインするという、明確な戦略的狙いがあると言えるでしょう。
日本市場では、大手SaaS企業が顧客基盤と蓄積データを活用し、AIによるサービスの高度化を進めている。加えて、日本独自の業務課題に対応するスタートアップも台頭しており、多様な進化が見られる。
バックオフィスのDXを牽引してきたマネーフォワードは、2025年4月に「AIエージェント」「AIエージェントプラットフォーム」「AXコンサルティング」の三本柱を発表した。業務自動化に加え、AIによる意思決定支援に踏み込んでいる。
AIエージェントは、次のアクションの提案やリマインドなどを自律的に実行するものだ。経費精算、会計、HRといった主要領域での適用を進めており、日本企業における生産性向上の新たな基準を提示しつつある。
2017年創業のRevCommは、これまで紹介してきた企業とは異なり、既存のSaaSにAIを追加するのではなく、AI活用を前提としたプロダクト開発を行っている。
同社が提供する、音声解析AI電話「MiiTel(ミーテル)」は、AIによって営業活動を最適化するサービスだ。「MiiTel」は電話、Web会議、さらには対面での会話まで、あらゆるビジネスコミュニケーションの可視化を実現する。
感覚的・属人的になりがちな会話というブラックボックスを、データドリブンな改善領域へと変革させる。
法律相談ポータルサイトや、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」を提供する弁護士ドットコム。同社は法律・税務分野のDXを推進するリーディングカンパニーである。
近年、その豊富なリーガルデータとAI技術を融合させ、新たなリーガルテックの開発を加速。その中核をなすのが、法律特化のAIコアテクノロジー「リーガルブレイン」だ。これは、同社が独自に構築したデータベース「Legal Graph(リーガルグラフ)」に生成AIを組み込んだものである。
Legal Graphは、判例、法律専門書、過去の法律相談記録といった膨大なデータを、その関係性を含めてグラフ化した独自のナレッジベースだ。この構造により、生成AIの課題であるハルシネーション(誤情報の生成)を大幅に抑制。情報の正確性が絶対条件である弁護士業務と極めて高い親和性を持つ。
同社のような特定領域に特化したバーティカルAIへの取り組みは、今後のSaaS市場における重要な潮流となるだろう。

編集部
国内のSaaS企業のAI戦略について、どのように考えていらっしゃいますか?

監修:前川氏
日本は業界特有の商習慣が多いため、「広く浅く」の水平分業型SaaSよりも、「狭く深く」課題を解決する垂直統合型(バーティカル)SaaSが浸透しやすい市場と言えます。 そのため、AIの登場は、この「深さ」の価値をさらに高める強力な触媒となるでしょう。

編集部
日米のSaaS企業で、AI戦略に違いはあるのでしょうか?

監修:前川氏
アプローチに明確な違いが見られますね。
米国企業は、様々なサービスを繋ぎ込む「水平的なプラットフォーム」として、市場全体を覆うエコシステム戦略を得意としています。
一方、日本企業は、業界の課題を「狭く深く」解決する「垂直的な(バーティカル)特化」と、これまでの顧客基盤といった既存資産の活用に強みがあると言えるでしょう。

編集部
今後のSaaS×AIの潮流や、経営者が持つべき視点についてお聞かせください。

監修:前川氏
今後の潮流としては、「脱テキスト(音声対話など)」「脱エンジニア(ノーコード化)」、そして「超パーソナライゼーション」といった、これまでの常識を覆すような変化が加速すると見ています。
こうした中で経営者が持つべき視点は数多くありますが、特に重要なのは2つです。
一つは、データ戦略こそが企業の生命線になるという再認識。もう一つは、単なる「AIツールの導入」ではなく、「AIネイティブな組織への変革」を目指すという覚悟です。後者は、業務プロセスから企業文化に至るまでの変革を意味します。
SaaS企業はAIの導入により大きく進化している。米国ではプラットフォーム化、日本では既存資産の活用や特定領域への特化などアプローチは様々だが、目指す方向は共通している。それは、作業の自動化にとどまらない、付加価値の提供だ。
今後のSaaSは「機能の多さ」のみでは選ばれない。「いかにAIが事業課題の解決と成長に直結するか」という視点こそが、顧客の決め手になるだろう。
そのような取り組みを行なっている企業に注目していきたい。
画像出典元:O-DAN
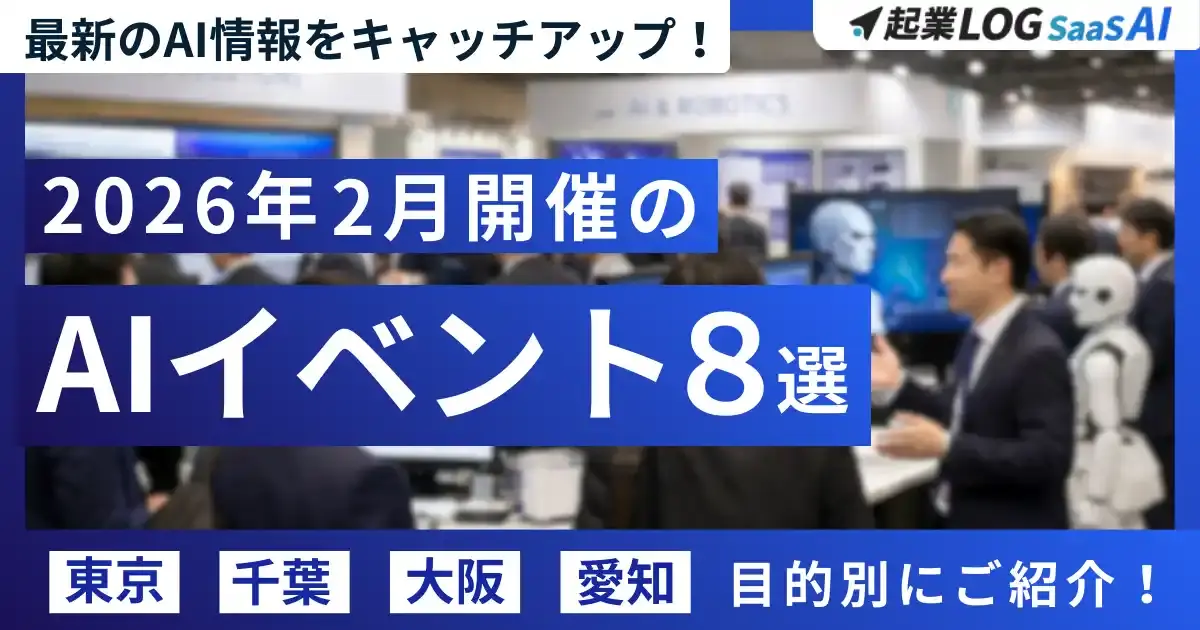
2026年2月開催!注目のAIイベントを目的別に紹介
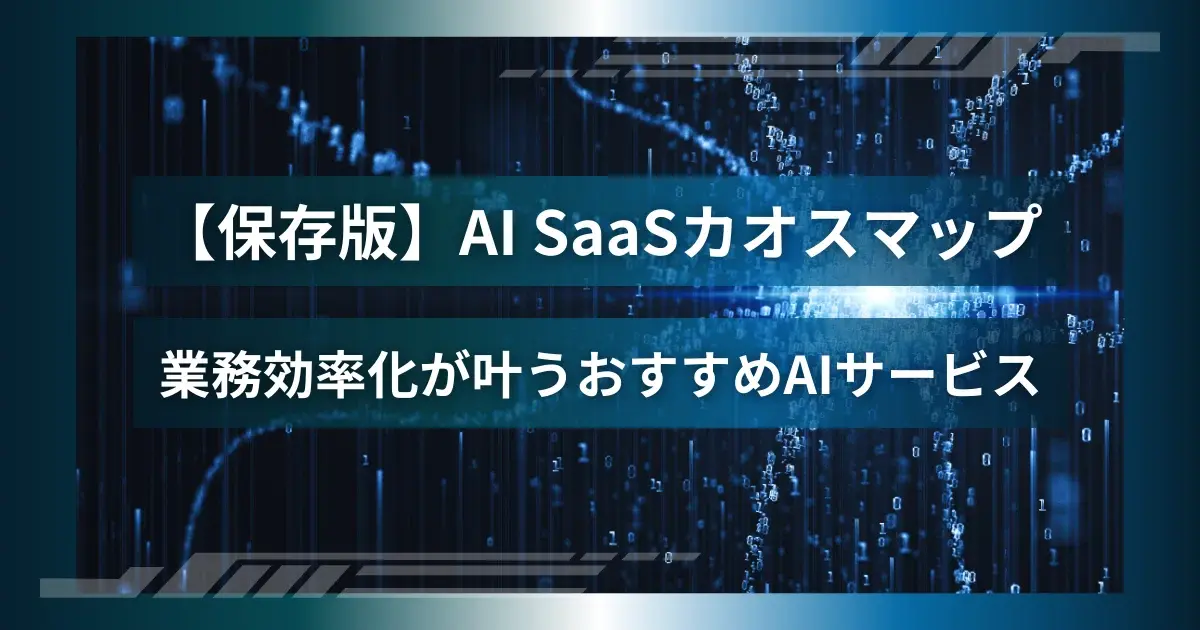
【保存版】AI SaaSカオスマップ|業務効率化が叶うおすすめAIサービス
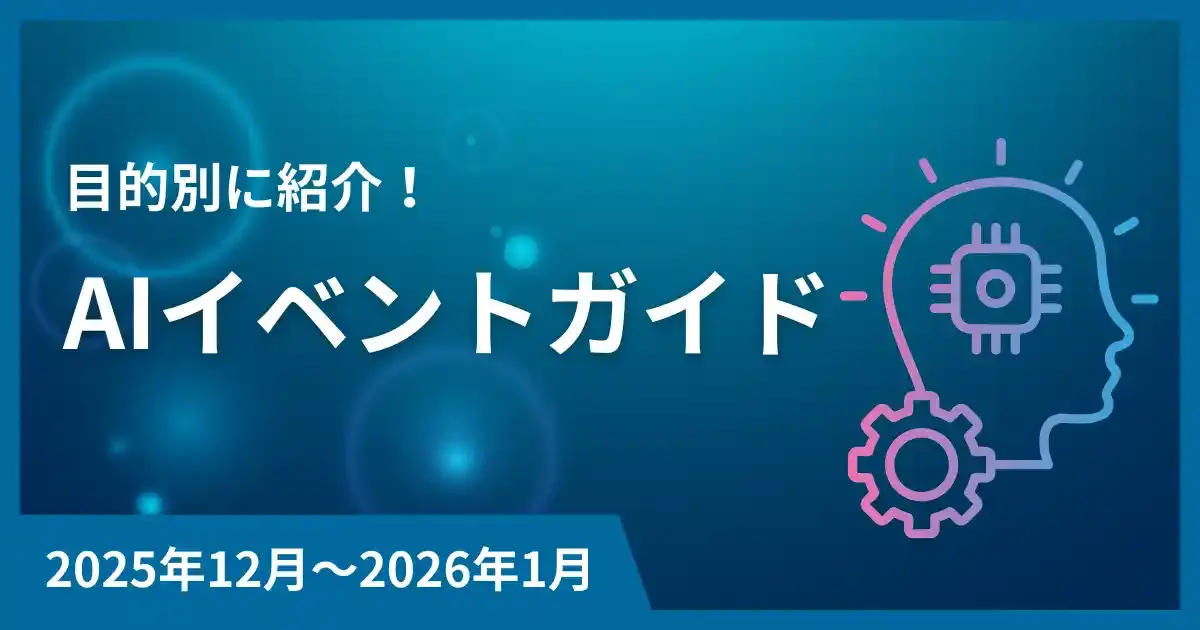
2025年12月~2026年1月開催!注目のAIイベントを目的別に紹介

建築業界のDXはどう変わる?アンドパッド代表・稲田氏が明かす「AI戦略の現在地」

コンプラ遵守は“無理ゲー”?労務課題を社労士とAIが解決したワケ

契約を「守る」から「活かす」へ、AI時代の経営を「データの正確性」で革新するContract Oneの挑戦
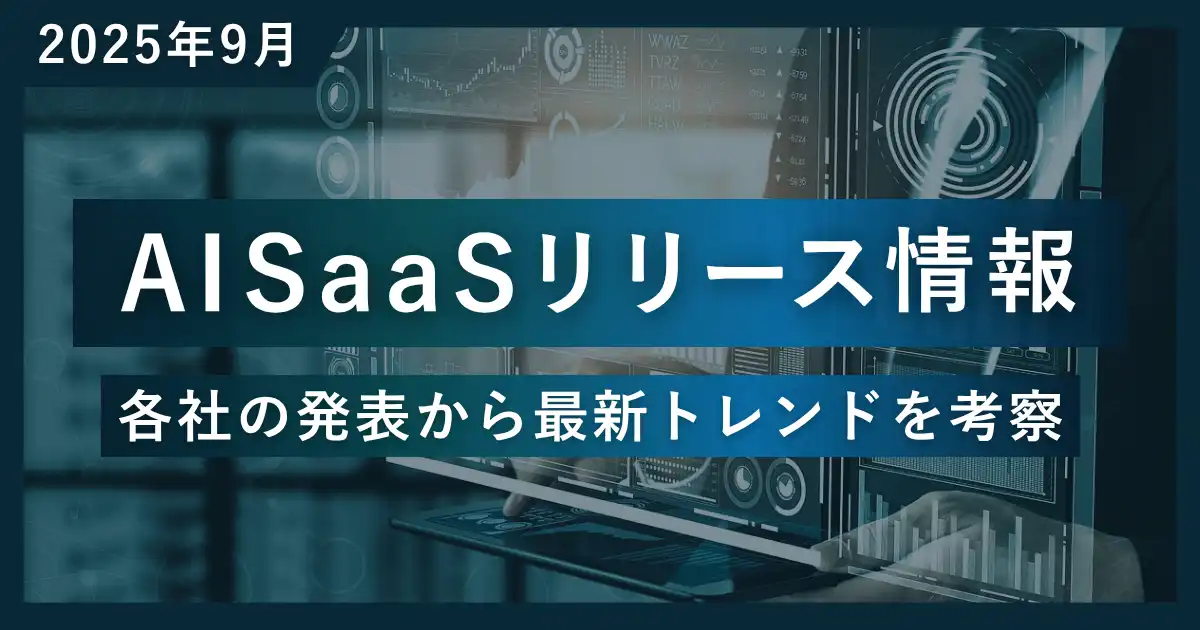
【速報】AI SaaSリリースラッシュ!2026年9月に見る最新トレンド
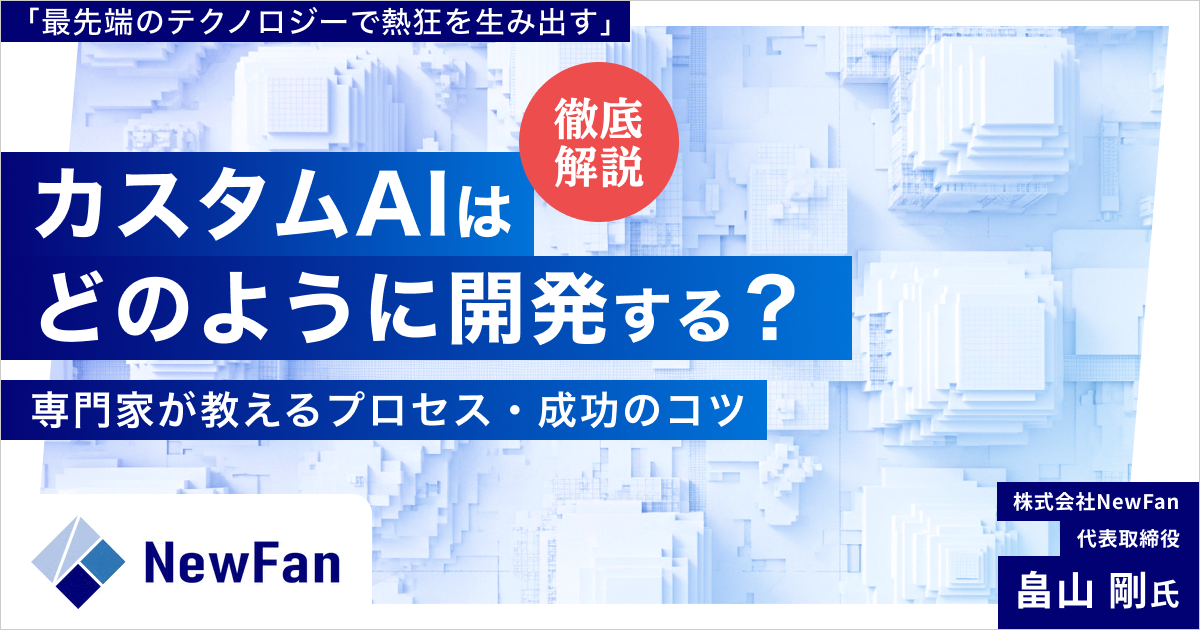
AI開発の進め方を専門家が解説!業務効率化・ナレッジ活用に役立つ、カスタムAIの第一歩
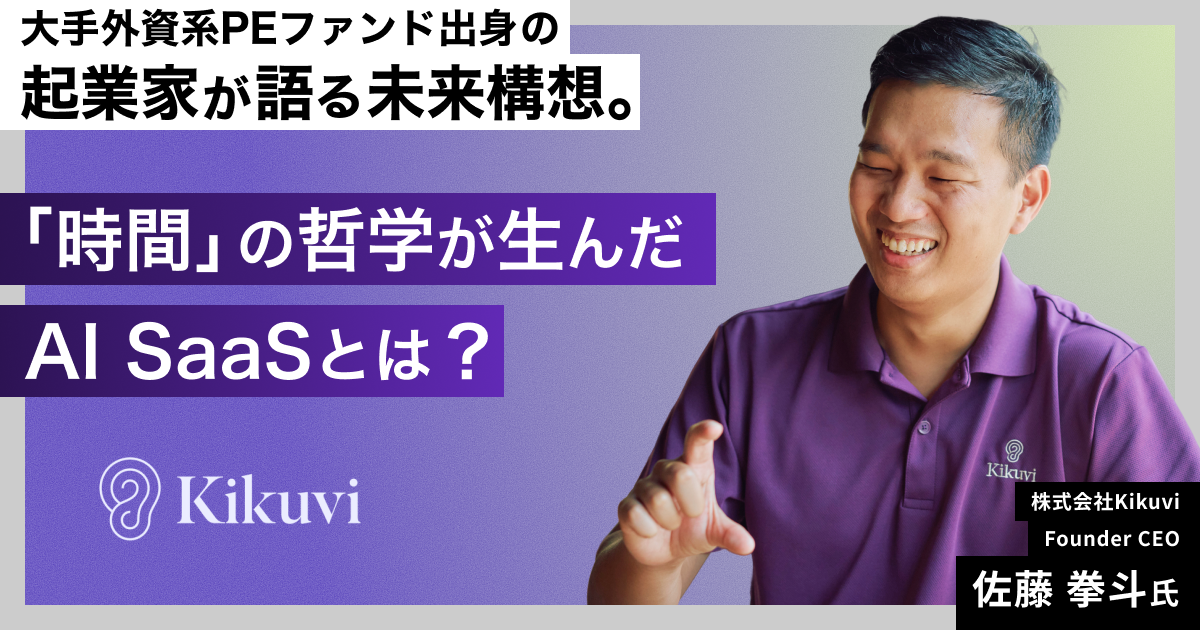
大手外資系PEファンド出身の起業家が語る未来構想。「時間」の哲学が生んだAI SaaSとは?

AIでSaaS営業の働き方は変化する。業界を俯瞰して「営業担当の未来」を考察