TOP > SaaS AI > SaaSの未来 > SaaS is Deadの真実とは?米国の事例から、国内SaaS企業の動向を予測

AI技術の急速な進化により、SaaS業界はかつてない転換期を迎えている。
2024年には、Microsoftのサティア・ナデラCEOが「SaaS is Dead(SaaSは死んだ)」と発言し、業界関係者の間に大きな波紋が広がった。
「SaaS is Dead」論は、SaaSモデルの終焉を意味するものなのか。それとも、新たなビジネスモデルへの進化を示唆するものなのか。
本記事では、ナデラ氏の発言の背景に加え、アメリカ市場で起きている変化を踏まえながら、日本のSaaS市場が今後どのように変化していくのかを考察する。
監修記事
監修:プロトスター株式会社 代表取締役 前川英麿
早稲田大学政治経済学部政治学科卒業後、ベンチャーキャピタルのエヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ(現、大和企業投資株式会社、SMBCベンチャーキャピタル株式会社)に入社。 シードからレイターまで幅広いフェーズ、領域の企業への投資育成に関与した。 その後、常駐の経営再建支援に特化したフロンティア・ターンアラウンドに入社し、地方における小売・製薬・メーカー等の経営再生に従事する。 2015年2月よりスローガン株式会社に参画し投資事業責任者として、Slogan COENT LLPを設立し、20社以上の企業に投資。 2016年11月に起業家支援インフラを創るべくプロトスター株式会社を設立。 その他、経済産業省 先進的IoTプロジェクト選考会議 審査委員・支援機関代表、ネイティブ株式会社社外取締役、株式会社サイトビジット(現:freeeサイン株式会社)社外監査役など複数の企業の経営に関与している。 青山学院大学「アントレプレナーシップ概論」非常勤教員。
目次
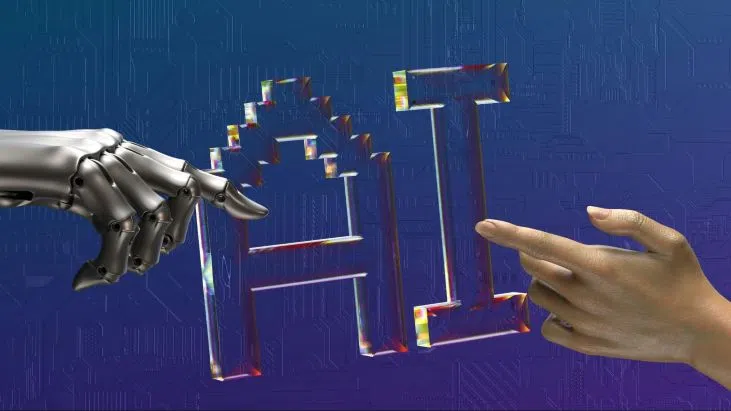
「SaaS is Dead」とは、AIの導入を前提としない従来型のSaaSでは、もはや通用しないという主張だ。これを受け「SaaSは終わるのか?」といった業界内の動揺も見られたが、これは終焉を意味するものではなく、進化を求める議論である。
とはいえ、SaaSの存在意義が問われつつあるのも事実だ。AIによる業務の自動化が進み、システム構成もより柔軟になった今、必ずしも「SaaSである必要」がないケースが増えている。
こうした背景を踏まえると、「SaaS is Dead」という言葉は、単なる警鐘ではなく、業界の転換点を示す象徴ともいえる。
では、Microsoftのサティア・ナデラCEOは、どのような文脈でこの言葉を発したのか。真意を探るために、まずは彼のコメントに注目していきたい。
ナデラ氏は2025年1月、起業家バルン・マイヤ氏が運営するYouTubeに出演し、SaaSの未来について見解を語った。ナデラ氏はAIエージェントの登場によってSaaSの役割が抜本的に変化しつつあることを強調した。変化とは以下の通りである。
リレーショナルデータベースの登場やWebの普及といった技術革新のたびに、アプリケーションの設計や構造は大きく変化してきた。
ナデラ氏は、今起きている変化もそれと同等、あるいはそれ以上のインパクトがあり、今回はアプリケーション内部の「処理の仕組み」そのものが変わろうとしていると指摘する。
変化の背景には「AIエージェント」の急速な進化がある。
AIエージェントは、複数のSaaSサービスを横断しながら、自律的に業務を実行できる能力を備えている。これにより、従来はユーザーが個別のSaaS上で行っていた業務が、エージェントによって“アプリの外側”から一括で制御・遂行される形へと移りつつある。
ナデラ氏は、こうした変化を受けて、SaaSの本質が今後「CRUDデータベース」へとシフトしていくと指摘する。
つまり、SaaSの役割は、データの作成(Create)、取得(Read)、更新(Update)、削除(Delete)を行う、これらが中心になるというわけだ。
実際にナデラ氏自身も、CRMやMicrosoft 365といったアプリに直接ログインすることはほとんどなく、AIアシスタント「Copilot」を通じて、業務の完結までを行っているという。

編集部
SaaSの役割はどのように変化していくとお考えですか?

監修:前川氏
SaaSの価値の源泉は、「操作性(UI)」から「データの信頼性(API)」へとシフトしています。これからは表面的な使いやすさ以上に、APIによる接続性や、蓄積されるデータの正確性・トレーサビリティが求められるようになるでしょう。
ここで重要になるのが、「データベース」としてSaaSをどう捉えるか、という視点です。SaaSを単なる「データ置き場」と考えるのは、その本質を見誤ることになります。これからのSaaSは、人間が画面を操作するためのアプリではなく、AIが自律的に業務を遂行するための「土台」そのものになるのです。
その意味で、「SaaSがAIのデータベースになる」という表現は、まさに的を射ていると言えます。
ナデラ氏は「SaaSは形を変える」との見解を示しているが、SaaSそのものの終焉を明言したわけではない。
一方で、すでに従来型SaaSへの依存から脱却しようとする企業も現れている。
その象徴的な事例が、欧州のフィンテック大手Klarna(クラーナ)だ。2024年、同社はSalesforceやWorkdayなどの主要SaaSの利用を停止し、AIを活用した内製システムへの移行を発表した。
実際にAI導入により、約700人分にも及ぶカスタマーサービス業務の自動化を実現。年間4,000万ドル規模の営業利益改善が見込まれているという。
汎用的なSaaSの利用を停止し、自社の業務フローに最適化された内製AIに置き換えるという同社の決断は、SaaSの存在意義やビジネスモデルに再考を促す象徴的な動きといえる。

ここまで、ナデラ氏の発言やKlarnaの事例からSaaSの変化の兆しを見てきたが、米国のSaaSベンダーは、この変化にどう対応しているのだろうか。
コンサルティングファームPwCによれば、米国のSaaSベンダーの約75%が、2026年までに主要サービスへのAI実装を予定しているという。
実際に以下のような取り組みが進んでいる。
事例1:Oracle(オラクル)
Oracleは、自社SaaSアプリケーションへのAIエージェントの導入を実施。これにより、データ入力や処理といった定型業務を自動化し、業務プロセスの効率化を図っている。
さらに、ユーザー自身が独自のAIエージェントをカスタマイズ・運用できるプラットフォームを提供している。これにより、顧客ごとに最適化された業務フローの構築が可能になり、AIによる業務支援がより柔軟かつ実践的に展開されつつある。
事例2:Adobe(アドビ)
Adobeは、クリエイティブ領域でのAI活用に加え、マーケティング分野にも本格的にAIを導入している。
同社は、複数のAIエージェントを構築・管理・連携させる基盤として「Adobe Experience Platform Agent Orchestrator」を発表。これにより、Adobe製品および外部パートナー製品間でのAI連携が容易になり、より複雑な業務フローにも対応可能な環境が整いつつある。
このように、米国のSaaSベンダーは「AIを前提としたアプリケーション設計」へと大きく舵を切っている。単なる機能強化ではなく、AIを中核とするプラットフォームシフトが進行中だと言えるだろう。
ここまではSaaSベンダー側の取り組みを見てきたが、導入企業の視点ではどうか。KlarnaのようにAIによるシステムの内製化を進める動きは、今後も加速していくのだろうか。
米国のベンチャーキャピタル、Andreessen Horowitz(アンドリーセン・ホロウィッツ)が発表したレポートによれば、AI分野における企業のソフトウェア投資は、「自社開発」から「外部購入」への大きな転換点を迎えているという。
背景にあるのは、AIの圧倒的な進化の速さだ。変化の激しい分野において、一度構築したツールを自社で継続的に維持・改善していくには、膨大なコストを要する。汎用性が高く、常に最新の技術を取り込んだ外部ツールを活用する方が、多くの企業にとって実用的だ。
このような傾向を踏まえると、AI導入によって既存SaaSが一斉に解約されるといった可能性は、限定的と見られる。むしろ今後の脅威となるのは、AI実装を前提にゼロから設計された「AIネイティブ」なプロダクトの存在だ。
AIネイティブ製品は、開発スピードや最適化の度合いにおいて既存SaaSよりも優位に立つ。既存のSaaSベンダーにとっては、こうした新興勢力との差別化こそが、今後の競争環境を左右する重要な課題となるだろう。

ここからは日本国内の状況について注目していく。米国に追随する形でAI導入が進む一方、日本企業ならではのアプローチも見られる。
国内のSaaSベンダーを見ると、欧米のようにAIを中核に据えた劇的な変化は、まだ限定的だ。
それでも、足元では現実的なAIの実装が着実に進みつつある。その方向性は、大きく二つに分けられる。
一つは、既存プロダクトにAIを組み込む「組み込み型アプローチ」。もう一つは、業務負荷の高い作業に絞って導入する「即効性重視の業務効率化」だ。
以下では、この二つの方向性を体現する事例を紹介する。
事例1:freee
会計SaaSを提供するfreeeでは、経費精算や年末調整といった定型業務にAIを活用。
申請内容をAIが自動で判定・補助することで、ユーザーの手間を大幅に削減している。
AI導入事例2:SmartHR
SmartHRは、人事・労務に関する問い合わせ対応に生成AIを導入。
社内規程などの情報をもとにAIが質問に自動回答する機能を提供し、社内の業務負荷軽減と応答品質の均一化を図っている。
AI導入事例3:Sansan
名刺管理から発展したB2Bプラットフォームを展開するSansanは、AIによる名刺情報の自動入力補完機能や、営業文脈を読み取ったレコメンド機能などを導入。
ビジネスデータ活用の精度向上に取り組んでいる。
このように、日本では「既存サービスの改善・効率化」を目的とした段階的なAI導入が中心だ。
“AIを前提とした再設計”には至っていないものの、ユーザーの業務負荷を軽減し、サービス価値を高めるという点では、着実な進展が見られる。
導入企業側の動きも活発だ。JUAS(日本情報システム・ユーザー協会)の調査では、言語系生成AIの導入企業(準備中含む)は41.2%に達し、特に大企業では7割以上が導入済みである。

この日米の動向の違いは、どこから生まれるのであろうか。そこには、各国の市場環境や社会課題を背景とした、明確な戦略の違いが存在する。

編集部
日米のAI戦略の違いについて、「攻めの米国、守りの日本」という見立ては的確だと思いますか?

監修:前川氏
はい、基本的に的を射ていると考えます。
アメリカは従来からイノベーションを“ディスラプションの武器”として活用する傾向があり、日本は“事業継続の盾”として位置づける傾向が見られます。
ただし、この構図は固定的ではありません。特に日本のスタートアップレベルでは、独自のデータや技術を武器に、世界市場を狙う「攻め」のプレイヤーが台頭する可能性も十分にあります。
SaaS特化型VCであるALL STAR SAAS FUNDの前田ヒロ氏と、湊雅之氏は、同社の対談記事で、日本において「SaaS is Dead」はほとんど当てはまらないと語った。
なぜなら、米国と比べ、日本のSaaS普及率は低く、成長の余地があるためだ。
さらに人手不足に直面する日本では、KlarnaのようにAIでSaaSを完全に内製化する動きは限定的だと指摘する。
ただし、これは一時的な時間に過ぎない。AIの進化により、海外の強力なSaaSが言語の壁を越えて参入してくる未来も見据え、国内ベンダーは独自の価値を磨く必要がある。

編集部
Klarnaのように、日本でもSaaSを解約してAIによる内製化を進める企業は増えるでしょうか?

監修:前川氏
いえ、その動きが日本市場において短期間で主流となるのは、現時点では考えにくいでしょう。
背景には、AIを自社で開発・運用する、いわゆるAI内製化に伴う高額なコストとビジネス上のリスクがあります。多くの日本企業がその投資判断に慎重になるのは当然であり、一気に踏み込むには依然としてハードルが高いのが現状です。
したがって、短期的には、これまで使い慣れた既存のSaaSと、目的に特化した様々なAIツールを併用・連携させていく形が、現実的な選択肢となるのではないでしょうか。
AIによる転換期において、国内SaaSベンダーが生き残るために取り組むべき課題は次の3つだ。
もはやAIは「追加機能」ではない。AIをサービスのOSと捉え、「AIを搭載すること」を前提に、全てのプロダクトロードマップをゼロから見直す必要がある。AIを搭載していないSaaSは、やがて「レガシーシステム」として扱われることになるだろう。
汎用的なAI機能は、いずれコモディティ化する。本当の価値と競争優位性は、特定の業界(医療、建設、法務など)の専門知識とデータを深く学習させた「バーティカルSaaS」から生まれる。これこそが、グローバル勢にも負けない強力な堀となる。
関連記事:情報資産でバーティカルAI SaaSを構築 弁護士ドットコムの取り組み
これからのSaaSは、単に「業務が楽になる」だけでは不十分だ。「このAIを使えば、売上がこれだけ上がる」「解約率がこれだけ下がる」といった、ビジネスの成果(アウトカム)に直結する価値を定義し、顧客に提供しなければならない。
これらの課題に共通するのは、独自のデータ、深いワークフローへの統合、そして明確なROIという「AI時代の競争優位性」を持っている点である。

編集部
記事で提案した「国内ベンダーが取り組むべき3つの課題」は的確だと思いますか?

監修:前川氏
はい、3つの課題は的確であり、多くの国内ベンダーにとって重要な指針になると考えます。
その上で、あえてもう一つ視点を加えるならば、「データ戦略の深化」が挙げられるでしょう。なぜなら、特に日本で強みを発揮するバーティカルSaaSにおいて、その競争力の源泉は、各業界に特化した「プロプライエタリデータ(独占的なデータ)」に他ならないからです。
これは、記事で提示された課題『AI搭載前提でプロダクトを見直す』を、データの観点からさらに深掘りする、重要な視点とも言えます。

編集部
他に重要な視点はありますか?

監修:前川氏
「収益モデルの抜本的な見直し」は避けて通れない論点になると考えます。
SaaSの役割が、人間が使う「UI」中心の世界から、AIが利用する「データベース」へと変化していくのであれば、その価値の提供形態も変わらざるを得ません。従来の「ユーザーID数に応じた月額課金」モデルは、AIが主体となる世界では必ずしも最適とは言えなくなるでしょう。
今後は、AIの処理量に応じた「従量課金」や、AIが創出したビジネス価値に基づく「成果報酬型モデル」といった、新たな収益モデルをめぐる議論が、今後活発化していくことも考えられます。
「SaaS is Dead」という言葉は、SaaSの終焉ではなく、AIの登場によってその役割が「アプリケーション」から「AIが利用するデータベース」へと進化するという、歴史的な転換点を示している。
SaaSは死なない。しかし、進化できなければ、いずれ本当に“死ぬ”だろう。
この変化の本質を捉え、AIを前提とした新たな価値を提供することこそ、これからのSaaSベンダーに求められている。
画像出典元:O-DAN
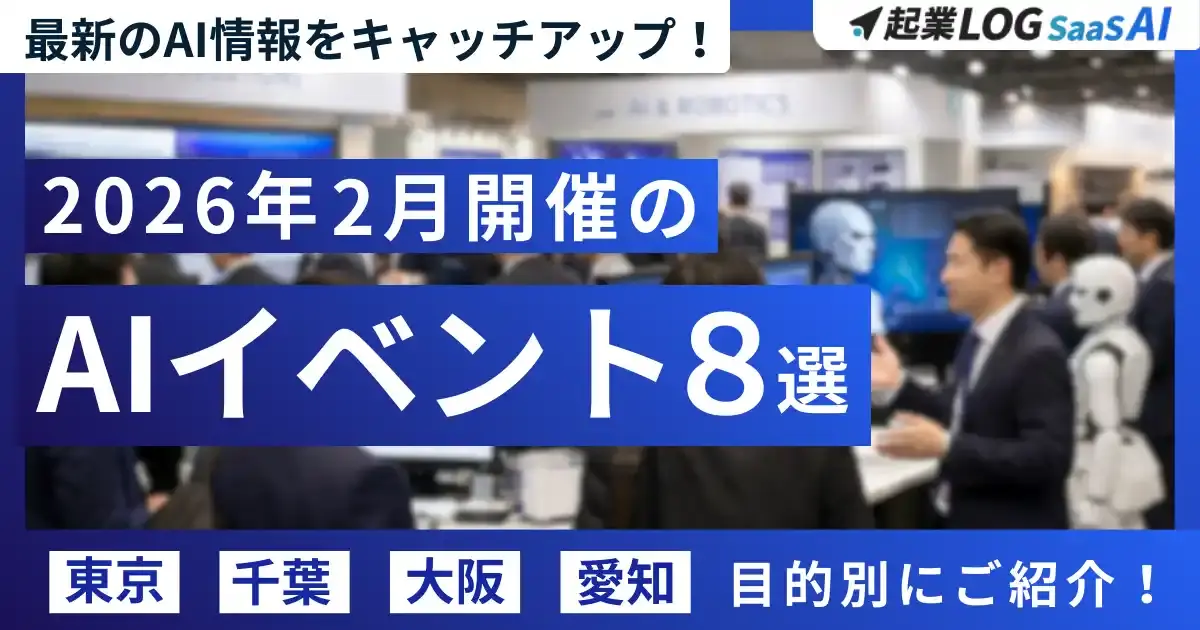
2026年2月開催!注目のAIイベントを目的別に紹介
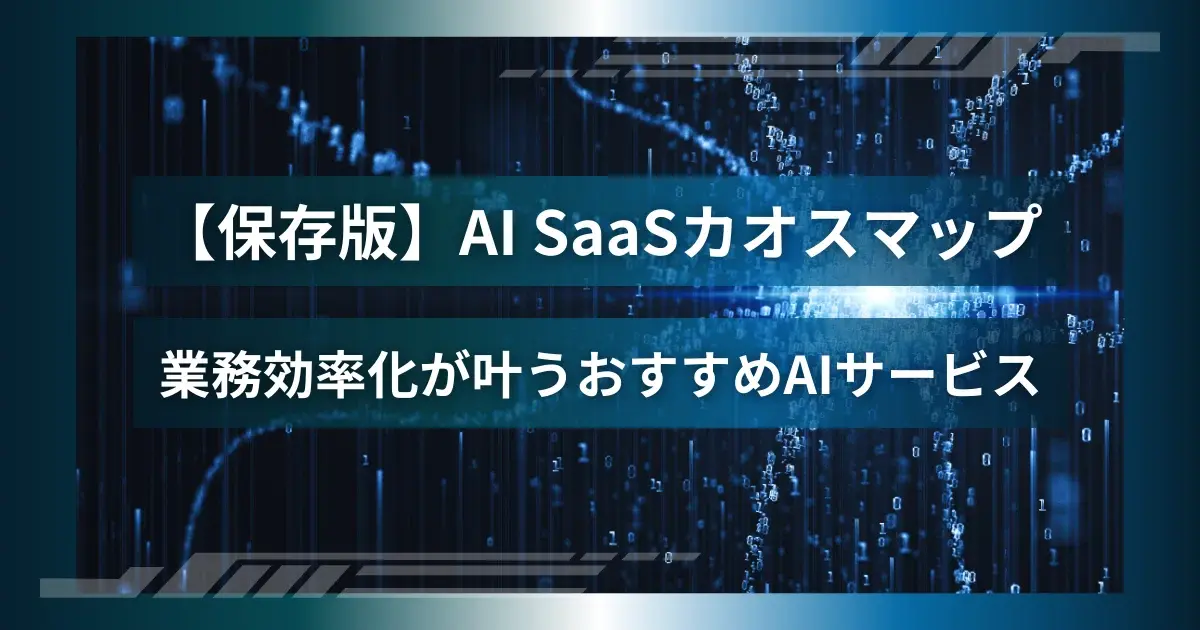
【保存版】AI SaaSカオスマップ|業務効率化が叶うおすすめAIサービス
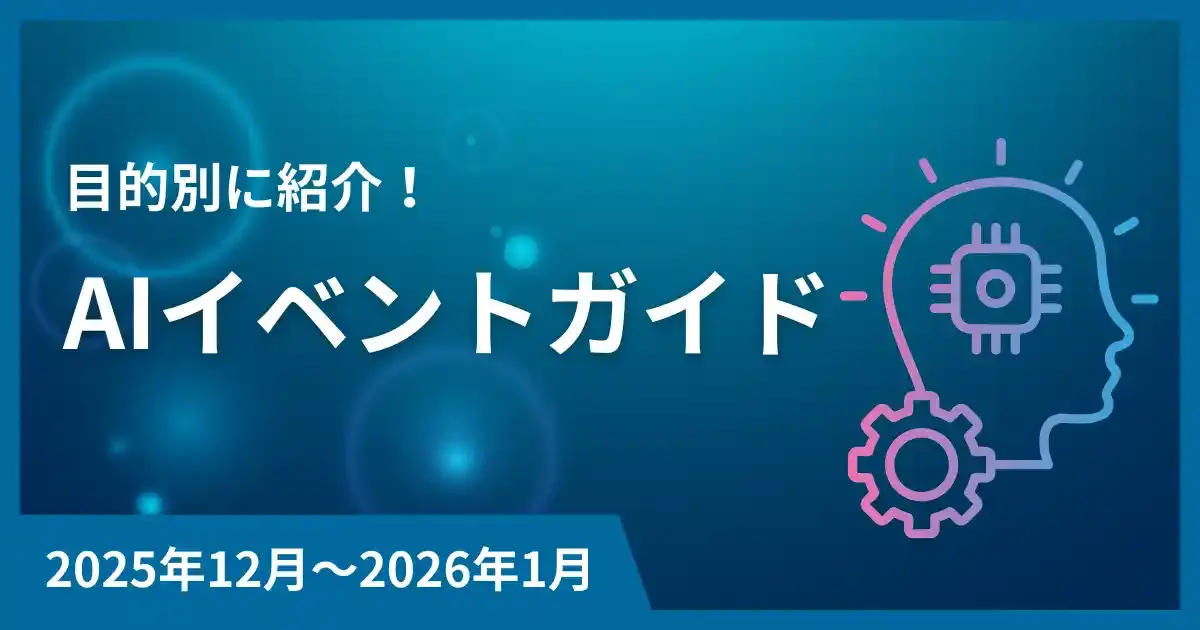
2025年12月~2026年1月開催!注目のAIイベントを目的別に紹介

建築業界のDXはどう変わる?アンドパッド代表・稲田氏が明かす「AI戦略の現在地」

コンプラ遵守は“無理ゲー”?労務課題を社労士とAIが解決したワケ

契約を「守る」から「活かす」へ、AI時代の経営を「データの正確性」で革新するContract Oneの挑戦
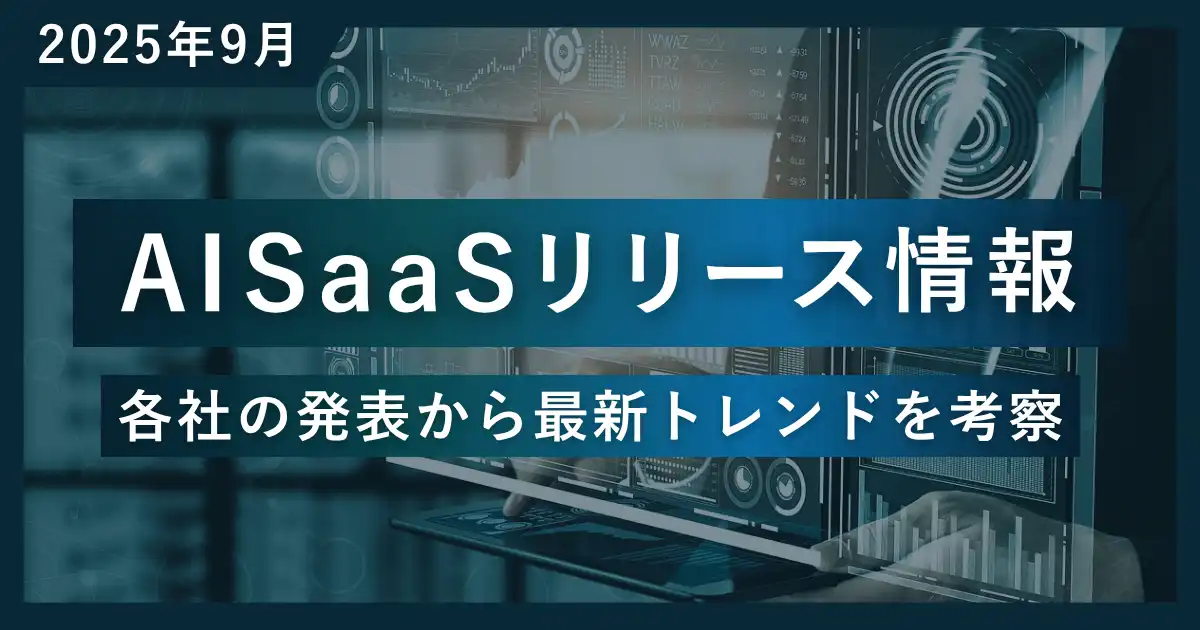
【速報】AI SaaSリリースラッシュ!2026年9月に見る最新トレンド
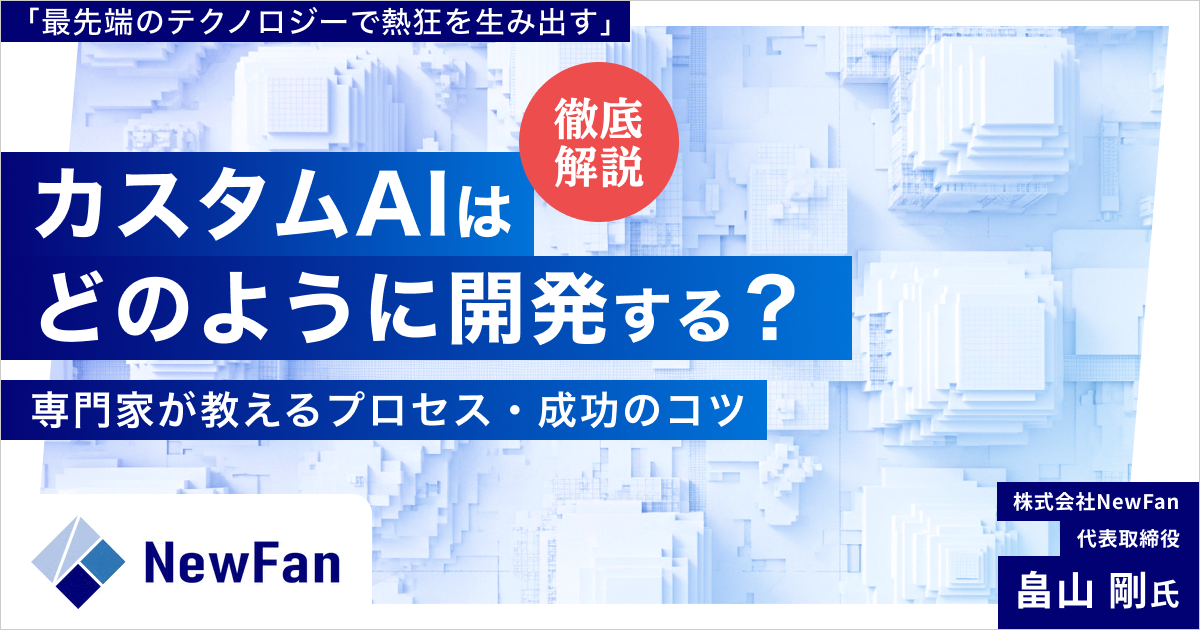
AI開発の進め方を専門家が解説!業務効率化・ナレッジ活用に役立つ、カスタムAIの第一歩
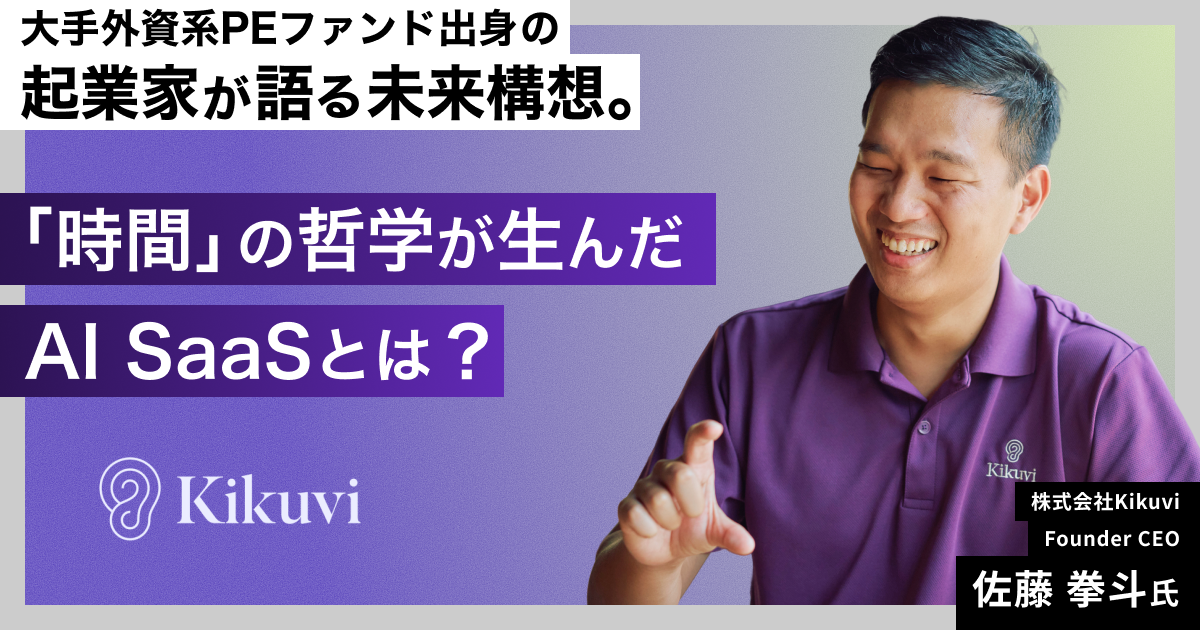
大手外資系PEファンド出身の起業家が語る未来構想。「時間」の哲学が生んだAI SaaSとは?

AIでSaaS営業の働き方は変化する。業界を俯瞰して「営業担当の未来」を考察