





企業の成長ステージにあわせた使い方が可能
クラウド会計サービスとして知名度の高いfreeeが提供する労務管理サービスです。
これだけで、勤怠管理や給与計算、年末調整に助成金の申請までカバーできます。
設立したての企業から中堅以上まで規模にあわせたプランが用意されているので業種規模問わず使いやすいです。
労務に関する管理をひとまとめにできる点が便利と評価する声がある一方、勤怠管理や給与計算を単体で導入することはできないので注意が必要です。
企業の成長ステージにあわせた使い方が可能
クラウド会計サービスとして知名度の高いfreeeが提供する労務管理サービスです。
これだけで、勤怠管理や給与計算、年末調整に助成金の申請までカバーできます。
設立したての企業から中堅以上まで規模にあわせたプランが用意されているので業種規模問わず使いやすいです。
労務に関する管理をひとまとめにできる点が便利と評価する声がある一方、勤怠管理や給与計算を単体で導入することはできないので注意が必要です。

2024年1月~2024年7月現在も利用中
基本勤務体制
・毎日の打刻さえ忘れなければ自動で集計される。
・スマホ一つで完結できて楽。
・紙ベースでの提出が無くなり、コピー代や紙代のコストがカットできる。
・位置情報システムにより、打刻した時の位置情報がデータとして残る。
・スマホに慣れていない高齢の社員には扱い辛いようである。
・出勤、退勤以外にも外始、外終などの機能があり、うまく使いこなせれば良いが、会社には多様な人間がいるので少々混乱が起きた。
現場での仕事が多く直行直帰が多くあり事務所へ行く回数が少ないような業種の会社にとって、スマホ一つで管理でき便利だと思うので、おすすめする。
不明

2024年4月~2024年7月現在も利用中
正社員、基本勤務体制、シフト制
・入力した日までの月の労働時間や時間外労働時間、休日日数が見てすぐ分かるため、残業調整などがしやすい。
・スマホで操作する時に、ウェブだけでなくアプリでもできる。
・アプリが重くない。
・打刻の画面がアナログ時計の針やデジタル入力のため、現在時刻と位置情報で記録できる他のツールの方が圧倒的にラク。
・カレンダー表記にしかできないため、1週間や1-15日の打刻時間を確認したくても1日ずつ日付をタッチして確認するしかなくとても不便で手間がかかる。
・他ツールと違い、打刻時に位置情報を要求されない為不正打刻が可能。
・給与明細を印刷した時に文字しかなく、どの項目がどの金額になるのか見づらかったため表を取り入れて欲しい。
おすすめはできない。
見た目が使いにくく、位置情報などで打刻していないため不正もできてしまうので。
不明

2023年6月~2024年1月
退職したため
シフト制
・以前は紙媒体だったので、導入により人事部の手間が減った。
・シンプルなので打ち間違いなどすることがほぼなく、使いやすかった。
・難しい操作がなく、高齢の社員でも簡単に使えた。
・有給の申請は複数日分まとめて入力できず、1日ずつ申請しないとならない。
今もタイムカード等を使っている会社があれば、かなりお勧めできる。
シンプルなので高齢の社員やバイトでも簡単に操作でき、人事部が毎月行う勤務時間の計算や有給申請書をまとめる手間も軽減されるので。
不明

年額 26,400円
従業員が少なく社労士に給与計算を頼んでいたが、コストがかさんでいくため自身で給与計算しようと思ったため。
2022年7月~2024年7月現在も利用中
・他社と比べて安い。
・スケジュール管理がしやすい。
・勤怠管理もできる。
・更新手続きも簡単。
・最初の導入の段階で説明がなく、自力で考えなければならなかった。
・サポートやヘルプを見るが、わからないことが解決しづらかった。
価格が安いのでオススメはできるが、社会保険料や算定、基礎等のある程度業務的な知識がないとわからず、中級者向けのシステムだと思う。
年額 26,400円

スタンダードプラン 月額800円/人
経理がfreee会計をもともと使っていたため、勤怠管理も同じ会社のソフトで統一することになった。
2020年9月~2024年7月現在も利用中
フルタイム、正社員
・slackやLINEで勤怠の打刻ができ、いちいちPCを開かなくてもよい。
・freee会計と連携ができ、給与仕分けの登録が簡単にできる。
・不明点があったときのヘルプページが充実していて、何か分からないことがあったときにすぐに自力で調べることができる。
・画面の遷移が遅いのが気になる。特に、勤怠→給与明細のメニューに切り替えるときの処理が重い。
・外国語に対応していないので、外国人従業員が操作を覚えるのに時間がかかる。
・スマホアプリだと特に処理が重く、確認に時間がかかる。
・freee会計との連携機能が優れているので、すでにfreee会計を導入済みの会社は、こちらも導入するべきだと思う。
・freee人事労務一つで勤怠も給与計算もできるので、バラバラにツールを導入したくないという企業におすすめする。
スタンダードプラン 月額800円/人

2023年4月~2024年7月現在も使用中
シフト制
・シンプルな画面で、誰もが苦手意識なく使用出来る。
・休みの申請がシステムからできるので、紙申請だった頃と比べると経費削減になっている。
・出勤している社員や外出者を表示する画面などがあればもっと便利だと思う。
在籍社員が大勢いる企業に、おすすめしたい。大きな会社になればなるほど全社員の勤怠管理には負担があると思うが、それを代わりの管理ツールが全て補ってくれると多少なりとも負担が減ると思うので。
不明

ミニマムプラン
2023年3月~2024年7月現在も利用中
・Webベースの画面で各項目毎(勤怠、休暇等)にカテゴリ分けされていて見やすく、初めてでも簡単に利用できた。
・サポート体制がしっかりしている。メールとチャットの2つで対応してくれる。
・年末調整の準備もこのソフトで対応できる。
・疑問点について問い合わせする際、電話サポートになると有料になる。
・各従業員の給与計算の際にブラウザ画面上で「給与計算」のボタンを押下するが、何故かWebブラウザ画面上は「計算中」のまま固まってしまうため、再度ログインしなければならない。
ミニマムプラン

・人事データを一元管理し、ペーパーレス化を進めるため
・勤怠管理や年末調整業務を効率化するため
・法改正などにも柔軟に対応できる信頼性の高いサービスだと感じたため
2020年4月〜2023年7月現在も利用中
・直感的な操作性で、人事担当者の教育コストを削減できる。
・エクセルなどでバラバラに管理していた情報を一元化でき、業務効率が大幅に向上した。
・法改正などにも迅速に対応してくれるので、コンプライアンス面でも安心。
・以前使用していたソフトに比べて、機能が充実していて使い勝手が良い。
・カスタマイズの自由度がやや低い。もう少し柔軟にカスタマイズできると良い。
・同期間で大量の処理をすると、たまにレスポンスが遅くなることがある。
勤怠管理システム「AKASH」と連携することで、勤怠データを自動で取り込めるようになり、さらに業務がスムーズになった
人事業務のDXを推進したい企業、人事データの一元管理とペーパーレス化を進めたい企業、働き方改革関連法への対応に追われている企業におすすめする。

2022年12月〜2024年6月現在も利用中
・月毎に従業員管理ができるため、先に予定してる給与変更や手当をあらかじめ支給月に設定ができる。
・従業員管理、勤怠管理、給与計算までfreee人事労務内で完結することができるため、情報の連携漏れが起きづらい。
・SmartHR、KING OF TIMEなどの労務系クラウドサービスとAPI連携も可能なため容易に情報連携できる。
・徐々に管理できる情報が増えていっている(雇用契約、健康管理)。
・従業員情報として社会保険の資格取得日、資格喪失日を登録しても、自動で同月得喪の処理が行われないため社会保険料を手直しする必要がある。
・所得税区分『丙』の計算に対応していないため、所得税額を手計算し修正する必要がある。
・アップデートが頻繁にありすぎて、設定の見直しを頻繁に行う必要がある。
・サポートの応答は、早いが細かい内容の場合に質が低い。こちらの方が仕様について詳しい場合が多い。
比較的感覚的に使いやすいツールで、チャットサポートの応答も早いため、比較的小規模で導入経験があまりない会社にはおすすめできる。
不明

プラン:アドバンス
2020年8月~2024年5月現在も利用中
シフト制、正社員
・どこからでも確認できたり、変更があってもすぐ把握することができたりして使いやすい。
・シフトのパターンをいくつも作成でき、柔軟に使用できた。
・色で出勤パターンを登録できて見やすい。
・不備があるとエラーで登録できず、分かりやすかった。
・クリックで打刻でき、IDとパスワードを共有しておけば代理で打刻できてしまう。
・問い合わせの電話がつながりにくかった。
・管理する際の権限が制限され、シフトを調整するときや勤怠を確認する際に不便なことがあった。
・初のツール導入でも、従業員側は操作に戸惑うことなく使用でき導入しやすいと思うので、どのような会社にもおすすめできる。
・特に、シフト制で管理者と顔を合わせる機会が少ない職場では、電子でやり取りでき効率的で良いと思うので、おすすめする。
プラン:アドバンス

【入社手続き】会社側の対応チェックリストを段階ごとに分かりやすく説明!

会社側の行う退職手続きの流れと必要書類は?保険や年金手続きも解説!

【2023年最新】賞与に必要な手続きと社会保険料の計算方法を簡単解説

社員管理とは?従業員管理のコツやメリット、おすすめ管理システムも

社会保険の電子申請義務化とは?全法人が利用可能!対応届出も解説

労務費とは?人件費との違いや計算方法・内訳・労務費率をサクッと解説

雇用契約書の電子化に要件はある?雇用関連書類電子化のメリットとは
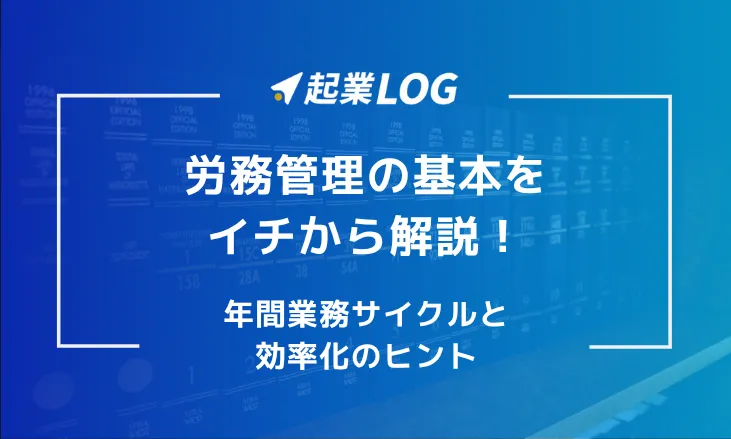
労務管理の基本をイチから解説!年間業務サイクルと効率化のヒント

従業員入社時に必要な社会保険手続きを解説!5日以内の手続き必須です

会社が行う雇用保険の加入と喪失の手続きを解説!電子申請の活用を!

【入社手続き】会社側の対応チェックリストを段階ごとに分かりやすく説明!

会社側の行う退職手続きの流れと必要書類は?保険や年金手続きも解説!

【2023年最新】賞与に必要な手続きと社会保険料の計算方法を簡単解説

社員管理とは?従業員管理のコツやメリット、おすすめ管理システムも

社会保険の電子申請義務化とは?全法人が利用可能!対応届出も解説

労務費とは?人件費との違いや計算方法・内訳・労務費率をサクッと解説

雇用契約書の電子化に要件はある?雇用関連書類電子化のメリットとは
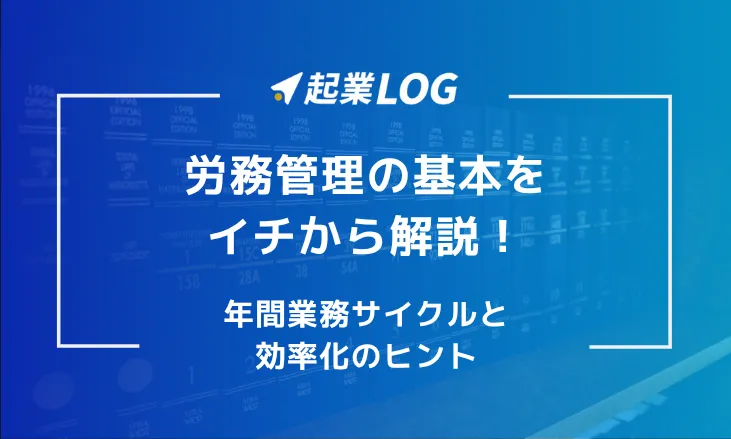
労務管理の基本をイチから解説!年間業務サイクルと効率化のヒント

従業員入社時に必要な社会保険手続きを解説!5日以内の手続き必須です

会社が行う雇用保険の加入と喪失の手続きを解説!電子申請の活用を!