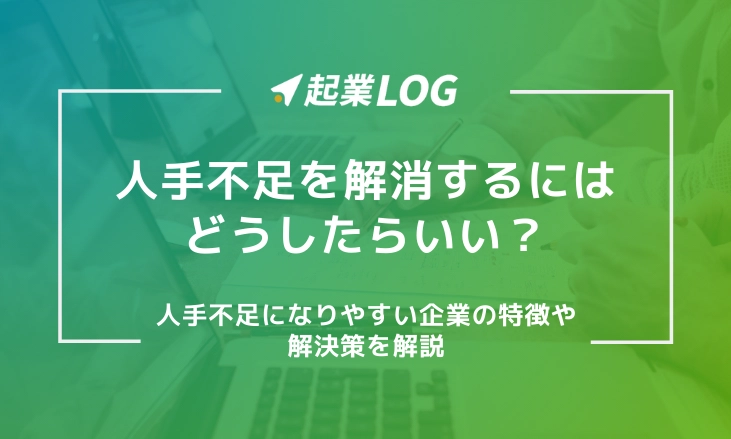
近年、少子高齢化や需給のアンバランスなどが影響し、多くの企業で長期的な人手不足が深刻化しています。
本記事では、まず人手不足の原因や深刻化している業種を解説し、人手不足になりやすい企業の特徴を探ります。
具体的な解消方法や、実際に課題を克服した企業事例、国による支援施策についても解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
目次

参考:帝国データバンク|人手不足に対する企業の動向調査(2025年1月)
上記グラフにあるように、とくに2020年以降、正社員、非正社員ともに人手不足と感じている企業は増え続けています。
人手不足の深刻化の原因として、以下の4つが挙げられます。
内閣府の「令和6年版高齢社会白書」によると、国内の生産年齢人口(15〜64歳)は、1995年の8,716万人をピークに、2023年には7,395万人と減少傾向にあります。
同時に65歳以上の人口は明らかに増加しており、少子高齢化によって慢性的な人手不足が顕著になっています。
業界や業種によっては、労働需要に対して労働供給が追いつかない、または逆に労働供給に対して労働需要が不足している場合もあります。
このような需給のアンバランスにより、「希望する仕事に就けない人」と「働き手を見つけられない企業」が存在し、構造的失業が人手不足の一因となっているのです。
近年では、20〜30代の若年・中堅労働者を中心に、早期離職や転職を希望したり、起業を目指したりする例が増えています。
かつての様に終身雇用や長時間労働を良しとする考えが希薄になり、将来を見越したスキルアップやワークライフバランスの向上、自由度の高い働き方が重視されるようになりました。
そのため、業種によっては新卒や第二新卒などの若者の獲得が困難となり、たとえ確保できても定着率が上がらず人手不足に陥るケースがあるのです。
地方は都市部に比べて人手不足が生じやすい傾向にあります。
労働人口は東京や大阪といった大都市に集中しており、地方ではニーズに合った人材を見つけるのが難しいことがよくあります。
また、採用活動には求人広告や人材紹介サービスの利用など、一定のコストがかかりますが、とくに中小企業では予算確保が難しい場合もあります。
こうした背景から、地方における人手不足が深刻化しています。

人手不足は多くの企業にとって共通の課題ですが、業界や業種によって程度は異なります。
本章では、とくに人手不足が深刻な5つの業種を紹介します。
とくに、医師・ドライバー・建設業については、2024年4月より時間外労働の上限規制が適用されたことで、労働時間の短縮による人手不足も懸念されています。
社会のデジタル化に伴い、IT人材の需要が急速に高まっています。
さらに、AIをはじめとする最新技術の進歩も目覚ましく、これらの変化に対応するための人材が求められています。
しかし、技術の進展があまりにも速いため、エンジニアが大幅に不足しているのが現状です。
加えて、多くの企業でITシステムのレガシー化が進んでおり、その保守や運用に多くのエンジニアが時間を取られているため、新しいスキルの習得が後回しになりがちです。
このような背景から、IT業界の人手不足が一層深刻化しています。
経済産業省の調査によれば、このままいくと、2030年にはIT人材が40~80万人不足する可能性があるとされています。
これにより、IT業界の人手不足は非常に重大な課題となっています。
地域医療や救急医療、産婦人科、小児科、麻酔科などの診療科では、医師不足が深刻な問題として取り上げられています。
また、福祉業界では、2019年度と比較して、2025年には約32万人、2040年には約69万人の介護職員の増員が必要です。
しかし、給与水準の低さや待遇への不満などが原因で多くの離職者が発生しており、これらの目標達成は困難だと予測されています。
参考:厚生労働省「第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」
近年、EC需要の急増に伴い、宅配便の取扱量は増加していますが、ドライバーの数は増えておらず、人手不足が続いています。
さらに、ドライバーの平均年齢は50歳を超えており、全産業の中でも高齢化が顕著です。
若年層のドライバー離れとベテランドライバーの退職が進み、ドライバー不足の解消は極めて困難な状況です。
建設業では、労働人口が1997年の685万人をピークに、2023年には483万人にまで減少しています。
現場での仕事は、体力的な負担や安全面でのリスクが伴うというイメージがあり、若年層の就業が進みにくい状況です。
さらに、2025年には団塊の世代が75歳を迎えることにより、大量の退職者が発生すると予測されています。
人手不足に加え、技術継承が進まないことも危惧されています。
参考:4. 建設労働 | 建設業の現状 - 日本建設業連合会
国内旅行やインバウンド需要の回復により、宿泊業の需要は急増していますが、それに伴い人手不足が深刻化しています。
長時間労働や不規則なシフト勤務、低い給与水準など、労働環境の課題が離職を引き起こし、慢性的な人手不足の一因になっています。
人手不足に陥りやすい企業には以下のような共通した特徴があります。
業界を問わず、これらの要素を意識的に改善しなければ離職や採用難リスクが増すため、注意が必要です。
労働負荷に対して待遇が見合わない場合、離職者が増え、新規採用も困難になるため、人手不足を招く原因となります。
これらの状況に対して、十分な報酬や適切な人事評価が伴わない場合、社員はやり甲斐や納得感が得られず、人材流出のリスクが高まります。
時代の経過とともに新たなテクノロジーやツールが開発され、仕事の進め方や慣行も変化していきます。
とくに若者は、企業がデジタル化による業務効率の改善や、次世代に向けた価値創出にどれだけ前向きかを重視する傾向にあります。
昔ながらの方法に固執し、変革に後ろ向きな場合は、魅力が感じられないため敬遠される要因となります。
人事評価においては、業績・成果・能力・情意の4つの視点から公平に評価することが求められます。
しかし、評価基準が曖昧だったり、評価者によって判断にばらつきがあると、社員のモチベーションが低下しかねません。
会社や上司、他の社員への不満などから職場の雰囲気が悪化し、将来有望な若手社員や優秀な社員の離職を招く恐れもあります。

人手不足を解消するには、以下の6つの方法が有効です。
人手不足を迅速に解消したい場合は、アウトソーシングの利用が有効です。
例えば、オンラインアシスタントを活用すると、経理、スケジュール管理、メール業務、カスタマー対応などの業務を委託できます。
社員を雇うより安価な上、育成や研修の手間が省けるため、効率よく人手不足を解消できます。
労働者が仕事を決める際に基準とするのが、給与と仕事内容です。
そのため、スキルアップやキャリアパスに役立つ、やり甲斐のある業務かどうかを精査する必要があります。
また業務内容や成果に見合った給与基準や昇給制度を整備できているかを見直すことも重要です。
福利厚生も人手不足解消に寄与します。
上記のような福利厚生が充実していれば安心して働けるため、入社希望者や定着率の向上が期待できます。
働きやすさを向上することも人手不足解消に有効です。
快適な空間や人間関係の中で仕事ができると、モチベーションがアップして成果が上がりやすいだけでなく、愛社精神も育成できます。
その結果、離職リスクが低減し、定着率向上につながります。
採用のミスマッチがあると、やり甲斐や生産性を見出せず、早期退職リスクが高まります。
こうした事態を回避するには、面接内容や募集プロセスの見直し、リファラル採用の導入、研修内容の整備といった施策が有効です。
採用人材の幅を広げる方法も人手不足解消につながります。
外国人や経験豊富なシニア人材の採用、過去に社員であった人材を呼び戻すアルムナイ採用などを導入すれば、企業にとって貴重な戦力になる可能性が十分にあります。
また、バックオフィスの人手不足を解消するなら、オンラインアシスタントの活用もおすすめです。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
実際に人手不足を解消した企業の事例を2つ紹介します。
宮城県の「株式会社こだま」は、地元で知名度の高い「こだまのどら焼き」などを製造販売しています。
商品への馴染みが深すぎるために会社のイメージに偏りが生まれ、業務内容が伝わりにくいことがが課題でした。
そこで同社では、採用前に職場見学を実施し、実際の業務を見せることでこの課題を解消。
また、コミュニケーション力があれば年代に拘らない方針で募集をかけ、就職氷河期世代人材の採用にもつなげています。
また、説明会で面談した人事担当者が入社後もフォローすることによって、定着強化にも取り組んでいます。
和歌山県で創業70年以上の旅館を経営する「株式会社むさし」では、社員の高齢化と次世代を担う若手社員不足が課題でした。
こうした課題を解消するために、合同企業説明会や就職説明会に積極的に参加し、地元高校や関西圏内の大学にもPRを行うことで、継続的な新卒採用に成功。
就職氷河期世代特化型マッチング会で中途採用もでき、外国人も全体の1割を占めるまでに採用数を増やすことができています。
このほか、社員寮をリフォームして土日も使用できる食堂やWi-Fi環境を完備したり、社員表彰制度を設けて、受賞者には同温泉のスイートルームに宿泊できるようにしたりと、福利厚生の充実にも注力。
こうした取り組みで社員の定着をはかり、次世代のリーダー育成を目指しています。
厚生労働省が中心となり、以下の施策を通じて企業の人手不足解消を支援しています。
これらの施策について概要を解説します。
参考:人材確保対策|厚生労働省
人材確保を進めるべく、「魅力ある職場づくり」を実現するために事業主を支援する施策です。
具体的には、以下のような項目があります。
| ポータルサイト | 仕事と家庭の両立や、働き方・休み方の改善に役立つ情報を提供 |
| 相談支援 | 各都道府県労働局において「働き方・休み方改善コンサルタント」を配置し、労働時間制度や年次有給休暇取得などに関する相談支援を無料実施 |
| 雇用管理制度の導入支援 | 専門的知見や分析による雇用管理改善方策の整理・普及・啓発など |
| 各種助成金 | 人材確保等支援助成金や働き方改革推進支援助成金など、条件を満たす事業主に対して助成 |
以下のような求人と求職のマッチング支援にも注力しています。
| ハローワーク | 全国550以上の窓口で、求職者と求人者に対して細かな相談・職業紹介・情報提供などを実施 |
| 人材確保対策コーナー | ハローワークに「人材確保対策コーナー」を設け、人手不足が顕著な福祉・建設・警備・運輸などの関係団体と連携した人材確保支援を実施 |
特定のスキルや資格を持った人材を育成して企業の戦力とするために、以下のような支援事業を行っています。
| 事業主が社員の能力を高める場合の各種支援策 | 職業能力開発に関する情報提供やキャリア支援、相談など |
| 人材開発支援助成金 | 社員に専門スキルを習得させる訓練を実施する事業主に、訓練経費や訓練期間の賃金の一部を支援 |
| 認定職業訓練 | 建築、金属・機械加工、情報処理、和洋裁、調理などの職種で、都道府県知事の認定のもと実施される職業訓練 |
非正規雇用で働く社員が、希望に応じて正社員へ転換できるよう、企業に対して支援制度が設けられています。
| キャリアアップ助成金 | 非正規社員のキャリアアップのために、正社員化や処遇改善に取り組む事業主に対して助成 |
| 多様な人材確保で輝く企業応援サイト | 非正規雇用労働者のキャリアアップに取り組んでいる企業の事例紹介サイト |
| その他事業主が利用できる支援策 | トライアル雇用助成金など |
企業にとって人手不足は何より先に解消すべき重要課題です。
待遇と労働負荷のミスマッチや、不公平な人事制度など、人手不足を招く要因がないか注意を払う必要があります。
すでに人手不足に陥っていたり、その兆候が見られたりする場合は、アウトソーシングの利用や職場環境の見直し、国の支援を検討するなどして、早急に解消策を講じる必要があるでしょう。
画像出典元:Pixabay、photoAC