
スクラム採用は、採用担当者だけでなく現場の社員も積極的に採用に関わり、チーム全体で人材確保に取り組む手法です。
人材獲得競争の激化や働き方の多様化が進む中、企業にとって重要な採用戦略となっています。
本記事では、スクラム採用のメリットや成功ポイント、具体的な事例などを詳しく解説します。

まずはスクラム採用とは具体的にどのようなものなのかを解説していきます。
スクラム採用とは、採用目標の達成というゴールに向けて、社員全員が一丸となって取り組む採用方式のことを指します。
スクラム採用では、現場を把握している人たちが主体となって採用活動を行うため、業務により適した人材を取り入れることができます。
また、スクラム採用を提唱した株式会社HERPによると、インターネット・IT系企業で取り入れられているチームで開発を進める手法「スクラム開発」から着想を得たとのことです。
つまり、スクラム採用とは、全社員が一つの目標に向かって協力し、プロジェクトに取り組むことを意図したネーミングなのです。
スクラム採用を行う目的は、採用活動の精度を向上させ、ミスマッチのリスクを減らすことにあります。
近年、労働人口の減少や売り手市場による人材獲得の競争激化により、従来の採用方法だけでは十分な成果が得られなくなりました。
さらに、採用チャネルの多様化によって、従来の画一的な選考では適切な人材を見極めるのが難しく、ミスマッチが発生してしまうケースも少なくありません。
スクラム採用では、現場の社員が採用活動に積極的に参加することで、応募者のスキルや経験だけでなく、企業文化へのフィット感やチームへの貢献度などを多角的に評価し、より適切な人材の採用が可能になります。
スクラム採用を成り立たせるためには以下の条件が必要不可欠とされています。
権限移譲とは、採用活動において必要な意思決定や対応の権限を、現場社員に与えることを指します。
現場主導で採用活動を進めるためには、全ての権限を一人の採用担当に与えるのではなく、現場の社員一人ひとりに適切な権限を付与することが重要です。
権限移譲をしなければ、スクラム採用の本質である「チームで取り組む」採用活動は成立しません。
スクラム採用では、採用活動での成果を社員全員にフィードバックすることが重要です。
フィードバックにより、定期的な振り返りを行うことでPDCAサイクルを効率よく回せるようになります。
改善点をいち早く見つけ、現場と人材のミスマッチを防ぐことも可能です。
スクラム採用では、採用担当者が採用活動というプロジェクトの責任を負うマネージャーとしての役割を持っていることが必要です。
採用担当者がフロント業務のみを行うのではなく、プロジェクトのマネージャーとして動くことで、採用活動全体の統括がしやすくなります。
上記の権限移譲や成果の可視化によって採用担当者の負担を軽減し、採用担当者がマネジメントに集中できるようにしましょう。

スクラム採用の主なメリットは3つあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
会社での業務に関して熟知している社員が採用を行うため、より業務にマッチした人材の確保ができるようになります。
従来の人事部が主体となって行う採用活動では、実際の現場の様子を把握しないまま新しい人材が配属されていました。
この採用活動では、人物像と業務の間にズレが生じてしまいます。
しかしスクラム採用で現場が主体となることで、現場の事情を把握した上での採用活動が可能になります。
実際の業務と人材の間にズレがなく、双方にとって満足のいく採用ができるのです。
スクラム採用では、求人票やスカウト文面の作成を通じて、社員が自社の魅力を再認識し、言語化する機会が生まれます。
こうした言語化が自社への理解を深め、社員のエンゲージメント向上につながるのです。
採用活動に関する業務を細分化してそれぞれの部署や社員に振り分けることで、採用担当者の負担が軽減されます。
また、スクラム採用では採用担当者がプロジェクトマネージャー化することが重要になってきます。
負担が軽減することで、採用担当者は全体のマネジメントに集中できるようになり、効率よく業務を進められるようにもなります。
スクラム採用は、採用活動を全社的に取り組むことで多くのメリットをもたらしますが、課題も存在します。
ここでは、スクラム採用に取り組む際に注意すべき3つのデメリットについて解説します。
スクラム採用では、現場の社員が採用活動に時間や労力を割く必要があり、特に通常の業務量が多いチームでは負担が増加する可能性があります。
たとえば、スカウトメールの送信や候補者との面談、社内での採用ミーティングなど、採用活動が増えると通常業務に支障をきたします。
負担を軽減するためには、タスクの分担や時間配分の調整を行う仕組みづくりが必要です。
スクラム採用では、全社的な取り組みが求められるため、社員全員の採用に対する意識統一が重要です。
しかし、部門ごとの業務優先度や採用に対する熱量の違いにより、全員が同じ目標を共有し、同じ基準で採用活動に関わることが難しい場合があります。
特に、業務がひっ迫する状況下では、「採用活動に時間を割けない」という不満を抱く社員が出てくる可能性もあります。
こうした状況を防ぐためにも、事前に採用の目的や目標を明確にし、全社員で共有しておくことが重要です。
さらに、採用基準や評価ポイントを定期的にすり合わせ、役割分担を共通認識として持つことで、社員の不満を軽減し、協力体制を強化しましょう。
スクラム採用では、多くの社員が採用活動に関わるため、候補者の情報や面接の進捗状況を正確に管理しないと、候補者とのやりとりが重複したり、スケジュールが混乱します。
さらに、採用活動では求職者の個人情報を扱うため、セキュリティ対策や情報の取扱ルールの徹底が欠かせません。
この問題を解決するには、情報を一元化できる採用管理ツールの導入や、社員向けのコンプライアンス研修、セキュリティ対策の強化などが必要となり、その分管理コストは増大する可能性が高くなります。
しかし、採用管理ツールを活用すれば、候補者情報の共有がスムーズになり、意思決定が迅速化されるだけでなく、データに基づいた採用戦略の立案も可能になります。
スクラム採用をスムーズに導入するには、計画的な準備と実施後の振り返りが重要です。
ここでは、スクラム採用を導入する際の具体的な4つのステップを解説します。
まずは、採用活動のビジョンや目的を明確にし、全社員に共有します。
現場の社員が採用に関わる意義や期待する役割を伝え、全社員が一丸となって協力体制を築くことが重要です。
採用方針や基準についても共有し、社員一人ひとりが「採用活動の一員」であるという意識を持つよう促しましょう。
定期的なミーティングや社内研修を通じて、認識の統一を図ることが大切です。
次に、スクラム採用を実現するための具体的な体制を整備します。
まず、採用プロセスを整理し、各ステップでの担当者や役割分担を決定しましょう。
特に、現場の社員がどのくらい採用活動に関わるのかを明確にし、役割や責任、権限の範囲を定め、人事部門とのコミュニケーション方法やサポート体制も整備します。
たとえば、人事部門にスクラム採用全体の統括責任者を置き、部門ごとに採用責任者を配置すると効果的です。
また、情報の共有や進捗管理を効率化するため、採用管理ツールの導入も検討しましょう。
ツールを活用することで、候補者の情報やタスクの進行状況を一元管理でき、重複した作業や進行の遅れを防げます。
体制が整ったら、いよいよ採用活動をスタートさせます。
リファラル採用やSNSを活用した情報発信、イベントへの参加など、さまざまな手法を組み合わせ、社員一人ひとりが主体的に採用活動に関わる環境づくりをしましょう。
現場の社員が候補者との接点を持つ際には、企業の魅力を伝える「企業の顔」としての役割を意識してもらうことが大切です。
また、採用プロセスの進行中には、各ステップでの進捗を共有し、必要に応じて柔軟に対応しましょう。
採用活動が終了したら、全社で振り返りを行い、改善点を明確にします。
候補者の質や採用プロセスの効率、現場社員の関与度などを評価し、データを基に次回の採用活動につなげましょう。
採用活動の評価や数値データの分析には、採用管理システムの活用がおすすめです。
分析ツールを上手に利用できれば、どの施策が効果的だったのか、改善すべき点はどこなのかを具体的に把握し、PDCAサイクルをスムーズに回していけます。
また、成功事例や課題を共有することで、社員全員の理解を深め、次回の採用活動への意欲を高められます。
特に、現場社員の意見を積極的に取り入れると、より実践的な改善策の立案が期待できます。
株式会社HERPはスクラム採用を成功させるためには以下のポイントが重要だと語っています。
スクラム採用を導入する際、多くの企業が直面するのが、社員の理解不足や抵抗です。
中には新たな業務やスキルの習得が必要になることに対して、戸惑いや不安を感じる社員もいます。
スクラム採用を成功させるためには、経営陣が積極的にコミットメントし、全社的な理解と協力体制を築く必要があります。
経営陣は、なぜスクラム採用が必要なのか、そして社員一人ひとりの役割がいかに重要なのかをわかりやすく伝えることが大切です。
また、採用活動への貢献が評価される仕組みづくりをして、社員のモチベーションを高めましょう。
スクラム採用では、採用に関わる情報が一元管理されており、必要に応じて社員が情報にアクセスできる環境が整っている必要があります。
採用管理システムなどを活用して、社員全員がプロジェクトの進捗を確認できるようにしましょう。
情報の共有がスムーズに行われるため、より効率的な連携が可能になるだけでなく、社員の主体的な活動を促すことができます。
社員が積極的に参画するための工夫として、まず、採用計画の段階から社員の意見を聞くことが重要です。
ワークショップ形式で、部門ごとに求めるスキルや経験などを話し合うと、多様な意見を取り入れることができます。
さらに、採用基準を一緒に考えることで、社員は自社の求める人物像を深く理解し、自らの言葉で説明できるようになります。
また、社員が疑問に思うことを解消するため、採用に関するFAQを公開するのも効果的です。
採用活動の透明性を確保し、社員が安心して採用活動に関わることができる環境をつくりましょう。

実際にスクラム採用を導入している企業は数多く存在します。
導入事例を3つ紹介するので、参考にしてみましょう。
ヘイ株式会社では、スクラム採用を効果的に運用するために、採用管理システム「HERP Hire」を導入しました。
このツールにより、応募者情報を一元管理し、採用業務の効率化を実現。
面接に関わる社員間のコミュニケーションが円滑になり、社員全体の採用意識向上にもつながっています。
さらに、「HERP Hire」のレポート・データ分析機能も活用し、経営陣との採用定例会議で確認するデータの出力作業を簡略化し、戦略的な採用施策の土台を整備しました。
参考:ヘイ株式会社でスクラム採用プラットフォーム「HERP Hire」が導入されました。
freee株式会社では、創業当初からエンジニアが自ら採用活動に参加する文化が根付いていました。
そこに普段開発プロセスとして採用しているスクラム開発手法を取り入れ、さらに効率的な採用を推進しています。
具体的には、チームごとにスプリント計画を立て、採用候補者の進捗状況を振り返る「スプリントレトロスペクティブ」を実施。
これにより、採用活動の課題を明確化し改善を繰り返すことで、採用数やカジュアル面談の件数を増加させています。
また、スカウト活動を楽しむ工夫として「スカウト返信王決定戦」も導入し、メンバーのモチベーション向上にも成功しました。
参考:スクラム採用をチームに取り入れてみた話 - freee Developers Hub
株式会社スマートバンクは、「社員全員で採用を進める」スクラム採用を創業初期から実践しています。
職種ごとにプロジェクトを組み、課題分析やスカウト送信を各チームで行う体制を構築、選考プロセスでは「構造化面接」を導入し、評価基準の統一を徹底しました。
これにより、面接クオリティを担保しつつ、効率的かつ的確な採用活動を実現しました。
さらに、採用広報ブログを通じて求職者に具体的な情報を発信し、企業の魅力を伝える取り組みも行っています。
参考:「負担なく理想が叶うATSは奇跡」独自のスクラム採用体制を支えたHERP Hire導入事例
現場が主体となって採用活動を行うスクラム採用を導入することで、実際の業務と人材のミスマッチを防ぐことができます。
メリット・デメリットを把握した上で導入していきましょう。
画像出典元:pixaday、Unsplash

採用管理をスプレッドシートで行う方法は?項目例・注意点も解説
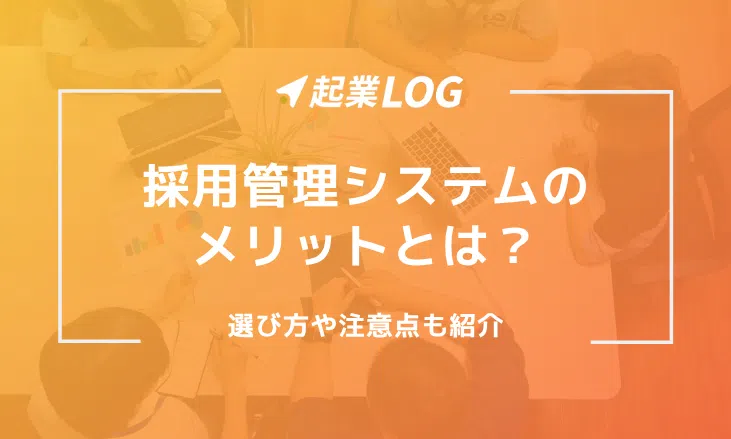
採用管理システムのメリットとは?選び方や注意点も紹介

通年採用とは?新卒一括採用との違いや企業・学生のメリットを解説

採用担当業務がつらい理由4つ!あるあるな悩みと解決策を解説

【採用トレンド】ジョブ型雇用とは?メンバーシップ型との違いやメリットも解説

中途採用が難しい5つの理由と解決策を解説!失敗を避けるためのコツも伝授

内定辞退の原因ランキング|辞退を防ぐためにすべきこと・頼れるサービスを紹介

優秀な人材の見分け方とは?12の特徴と企業が取るべき行動を解説

採用計画の立て方を5つの手順で分かりやすく解説!新卒・中途採用計画の違いも紹介

【成功事例多数】AI面接とは?仕組み・メリットや導入のポイントを解説