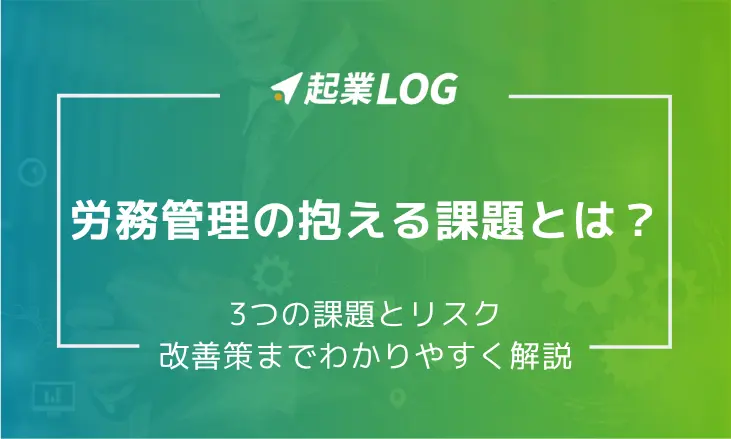
「月末の給与計算、時間かかるから憂鬱…」
「多様な働き方に対応しきれておらず、トラブルのリスクを感じる」
「法改正のたびに、対応漏れがないかヒヤヒヤ」
こんな、もやっとした不安を抱えながら業務を行っていませんか?
近年、働き方の多様化や法改正の加速などにより、労務管理業務は複雑化しています。
労務管理の課題は、企業の信頼と生産性に直結する重要な経営課題です。
本記事では、多くの企業が直面する労務管理の課題を解き明かし、放置が招くリスクを徹底解説!
実践的な解決策まで紹介するので、従業員が安心して働ける環境を築くための第一歩をスタートさせましょう。
労務管理とは、従業員の雇用や労働環境を適切に維持するために「労働に関する全般を管理」する業務をさします。
具体的には、入退社手続き、社会保険・労働保険の手続き、年末調整、給与計算、勤怠管理などが含まれます。
これらの業務は、従業員を守り、企業が健全に運営されるための基盤となりますが、昨今の働き方の多様化や、働き方改革関連法、育児・介護休業法の改正といった法改正により、管理業務は複雑化しています。
結果として、多くの企業で「見えない課題」が生まれており、放置するほど大きなリスクへと発展しかねません。
▼ 労務管理の具体的な業務内容をさらに深く知りたい方は、こちらをお読みください。
雇用形態が多様化し、契約内容・労働時間・社会保険の管理がブラックボックス化していませんか。
様々な働き方が社会的に認められるようになってきた昨今、従来のサラリーマンのような正規雇用だけでなく、派遣社員やアルバイトなどの非正規雇用、フリーランスなどの個人事業主との業務契約など、雇用形態は多様化が進んでいます。
雇用形態の多様化の背景には、インターネットの発達や企業の慢性的な人材不足、人員コストの削減、個人のQOL(生活の質)向上など、複合的な要因があると考えられます。
これに伴い、企業の労務管理も従来型の固定的な方法では通用しなくなってきているのです。
雇用形態の多様化に伴う課題の1つ目は、就業規則の未整備です。
就業規則は、労働基準法にもとづき一定の条件を満たす会社に作成義務が課される書類です。
就業規則を作成することにより、会社側が示す労働条件や職務上のルールが明確になるため、会社と従業員、双方の利益保護の観点からも重要な書類となります。
<雇用の多様化によって、あらたに整備が必要な例>
コンプライアンスが強く求められる上場企業であれば、すでに対応済の企業も増えていますが、中小企業では就業規則の整備に着手出来ていないケースも多いでしょう。
未整備だと、従業員とのトラブルに発展し、訴訟リスクや企業の信用失墜に繋がりかねません。
雇用形態の多様化に伴う課題の2つ目は、労働契約への未対応があげられます。
従来であれば、サラリーマンを前提とした労働契約を労使間で締結すれば良かったのですが、現在では、状況に応じた労働契約を各関係者と結ぶ必要が出てきています。
適切な労働契約を締結しないと、後々の賃金トラブルや解雇問題に発展するリスクがあり、多額の賠償金や企業のイメージダウンに繋がる恐れもあります。
日本ではアメリカに比べて訴訟件数は相対的に少ないですが、労働者との労働トラブルを防ぐ観点からも適切な労働契約を締結することを心がけましょう。
雇用形態の多様化に伴う課題の3つ目としては、雇用形態による不平等があげられます。
雇用形態には、大きく分けて正規雇用と非正規雇用がありますが、企業側はコスト削減の観点から非正規雇用者への待遇を(正規雇用者と比べて)下げる傾向にあります。
2020年4月からは「同一労働同一賃金」の施行が始まっていますが、実質的に非正規雇用者と正規雇用者が平等な扱いを受けているかは不透明なのが現状*です。
不適切な待遇は、従業員のモチベーション低下や離職に繋がり、結果として採用コストの増加や生産性の低下を引き起こします。
報酬面だけでなく、労働環境も含めて、双方が納得のいく労働環境を整備し、雇用形態に関わらず適切に労働者を評価する制度を構築しましょう。
*参照:厚生労働省「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況」
月末の勤怠集計、アナログ作業に時間を取られていませんか。
また、残業時間の上限規制などの法改正への対応が追い付かず、「労務リスク」を抱え込んでいませんか。
企業は、従業員の労働時間を、的確に管理・把握する必要があります。
徹底管理が求められる背景には、長時間労働による過労死や、働き方改革関連法によって設けられた時間外労働時間の上限が関係しています。
働き方改革関連法の施行により、残業時間の上限が法律に明記され、罰則付きの規制が導入されました。
具体的には、週40時間を超える場合は残業とみなし、時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として月45時間・年360時間と定められています。
残業に対する細かな労働時間の把握が必要となるため、企業側は各従業員の時間外労働への意識を強く持つ必要があります。
日本企業の場合、長時間労働に加えて問題となっているのが、有給取得率の低さです。
企業には、今まで以上に有給休暇の取得奨励が求められるようになっています。
年10日以上の年次有給休暇が与えられている労働者に対しては、最低でも年5日分を時期を指定して取得させることが、企業の法的義務となりました。
多様化な働き方を促進し、労働生産性を向上させることが目的ですが、企業としても、従来以上に各従業員の有給取得状況を把握・管理する必要性が出てきたと言えます。
働き方改革関連法とも深く関連する内容にはなりますが、従来以上に「労務面」でのコンプライアンス徹底が強く求められるようになってきています。
「時間外労働への対応」や「有給休暇の未消化解消」に加え、「残業代未払」といったコンプライアンス上の問題を抱えている企業には、行政指導や企業の社会的信用の失墜のリスクがあります。
場所にとらわれない働き方が普及する一方で、従業員の勤怠管理や労働環境の把握など、見えにくい部分での労務管理が手薄になっていませんか。
テレワーク導入が進んでいる背景には、働き方の多様化やオンラインツールの進歩に加え、新型コロナウイルス流行が大きく影響しています。
出社で業務管理していた企業にとって、テレワークは、「従業員が必要業務を適切に対処できているか、わかりづらい」という課題があります。
また労働状況の不透明さは、サービス残業・過労・メンタルヘルス不調などの従業員の健康問題や、生産性低下に繋がるリスクもはらんでいます。
テレワークでも適切な成果を生み出すための工夫が企業には求められています。
新型コロナウイルスの影響により、テレワークの導入率が全体的に高まっていた時期もありますが、業種別の導入率は大きく異なっているのが現状です。
本来テレワークが出来る業種にも関わらず、社内フローが未整備のため、スムーズにテレワークに移行出来ていない企業も多く存在します。
また、ITリテラシーの不足により、業務効率の低下だけでなく、情報漏洩などのセキュリティリスクの可能性もあります。
従業員への教育研修も含めた社内プロセスの整備・運用が重要になってきていると言えます。
会社によってテレワークの導入方法や体制は異なるため、一概には言えませんが、一般的に経理や法務といったバックオフィス系の部署は、オフィス出社が必要となるケースが多いです。
一部の部署のみオフィス出社が必要という状況は、不満を感じる従業員のエンゲージメント低下、離職といった問題に繋がっていきます。
リモート経理や電子契約の導入といった改革案が企業には必要となるでしょう。
参考:厚生労働省「テレワーク総合ポータルサイト」
参考:厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
まずは、自社が抱えている労務面の課題を明確にすることが重要になります。
労務面での課題は多岐に渡るため、「何が企業の課題になっているか」は会社によって異なります。
企業と従業員、両者の悩みや困りごとを具体的に洗い出したリストを作成してみるなど、労使間の環境を改善するためにも、自社の課題を明確にしましょう。
自社の課題が明確になったら、ITシステムの利用を積極的に検討しましょう。
労務管理に特化したシステムを導入することで、勤怠状況の正確な把握が可能となるなど、労務リスクの低減や、労務課題の解決につながります。
労務管理システムの導入メリット
労務管理システムの導入は、積極的にトライアルなどを活用して、費用対効果を含めて検証することをおすすめします。
労務コンプライアンスを徹底したい会社は、企業戦略の一環として、IT活用を推進しましょう。

「SmartHR」は70,000社以上の導入実績を誇り、高いシェア率を維持する労務管理システムです。
国内有名企業でも数多く導入されており、大規模処理やセキュリティの面でも信頼度も十分です。
e-Gov APIと連携しており、役所やハローワークへの書類提出もWEB上で可能。
あらゆる手間を省くことで本来の業務に集中することができ、生産性の向上につながります。
従業員情報を一元管理するクラウド人事労務ソフトなので、従業員が多い企業にもおすすめです。

社会保険労務士 金山杏佑子
「SmartHR」は、幅広い規模の企業にオススメしているシステムです。 30名未満の会社では無料で利用できる点から中小企業にも導入されている印象。勤怠管理や給与計算の機能は、有料オプションでの提供となるが、API連携させれば他システムと組み合わせて問題なく使えるので総合的におすすめできます。
すべてのプランで初期費用なし、15日間無料トライアルあり。
| HRストラテジー プラン |
人事・労務 エッセンシャルプラン |
タレントマネジメント プラン |
|
| 月額料金 | 要問合せ | ||
| 機能 | 従業員データベース・労務管理・タレントマネジメントの全ての機能 | 入社手続き・雇用契約・給与明細・年末調整・スキル管理など | タレントマネジメント機能すべて |
他にも、従業員50名以下企業向けの「労務管理プラン(労務管理機能のみ)」、小規模事業者向けの「¥0プラン(30名までの従業員情報を登録可)」があります。

コンサルティング
101~250人
間違いやすい部分にコメントがあるのでわかりやすい





年末調整をこのSmartHRで行うようになって今年で2回目でしたが、間違いやすい部分は補足のコメントがあるのでとてもわかりやすいです。いつでもオンラインでパパっと作成・申請できるので大変便利でした。

メーカー
51〜100人
初期設定に時間がかかった





操作こそ簡単でしたが、初期設定に時間がかかりました。もっと簡単なマニュアル等があれば初期の稼働がスムーズにいったと思います。

画像出典元:「ジョブカン労務HR」公式HP
「ジョブカン労務HR」は、入退社手続きや社会保険手続きなどのあらゆる労務手続きを、帳票作成から提出までサポートできるクラウド型労務管理システムです。
ジョブカンシリーズと連携することで、採用や勤怠管理も含めたバックオフィス業務の一元管理が可能。
従業員自身が情報を入力できるマイページ機能や、マイナンバー管理などもあり、安全性と利便性も兼ね備えています。
「システム導入の際の初期設定が面倒だ」という方向けに、初期設定を代行してくれるオプションプランもあるので安心です。

社会保険労務士 金山杏佑子
ジョブカンは費用が安く、従量課金制なので「かかる費用」が分かりやすいので、導入コスト・ハードルが低いのが良い点。シリーズ化されているので単品導入が可能、知名度も高いので人気のシステムという印象です。一方で、初期設定が少し難しいです。ヘルプページだけでは苦労する企業もあると思います。
中小企業向けに、下記のプランが提供されています。
初期費用・サポート費用は不要、簡単申し込みで30日間の無料トライアルが利用できます。
| 無料プラン | 有料プラン | |
| 月額料金/ユーザー | 0円 | 400円 |
| 電子契約機能 | なし | +200円/1送信(1件) |
| 従業員数 | 5名まで | 無制限 |
(税抜)
※月額最低利用料金は2,000円(税抜)(電子契約料は除く)

小売
101~250人
膨大な社員情報がスムーズに管理できる





膨大な社員情報を管理しているような職種や部署におすすめできます。正確に、そして必要なときに目的のデータをすぐに出せるなど、情報管理がスムーズにできるようになります。

サービス
51〜100人
旧姓と新姓の管理がしづらいのがデメリット





「結婚をしたあとの旧姓と新姓を使い分けての管理」が少々しにくいというのは気になる大きなデメリットであり、不便な箇所だと思います。女性社員も多い会社からするとこの箇所は強く改善を希望します。

画像出典元:「オフィスステーション 労務」公式HP
「オフィスステーション 労務」は、利用社数45,000超えの実績を誇り、他社を圧倒する124種類の帳票作成に対応したクラウド型労務管理システムです。
e-Gov完全対応、他社の給与・勤怠システムとのAPI・CSV連携にも柔軟に対応しているため、既存のシステムをそのまま利用できます。
オフィスステーションシリーズで年末調整・給与明細・有休管理などの機能を好きなタイミングで拡張して利用することも可能です。
利用継続率は99.7%を誇り、金融機関並みの高いセキュリティ、24時間365日の監視体制で多くの企業から信頼を得ています。

社会保険労務士 金山杏佑子
「オフィスステーション 労務」は100人規模の大企業や社労士向けのシステム。 対応帳票が他システムと比べてもかなり多いので玄人向けのシステムですね。逆に人数がそこまで多くないような企業では、そこまでの機能が必要ないとなるパターンが多いです。
30日間の無料トライアルで機能を確認できます。
| 費用 | |
| 登録料 | 110,000円(税込) |
| 従業員ひとりあたりの月額利用料 | 440円(税込) |
| ユーザー数 | 無制限 |
※従業員数が10名以下の場合、月額利用料は一律4,400円(税込)

商社
251~500人
管理者向けにおすすめ





色々なシステムを検討して最後にスマートHRとオフィスステーションの2択になり、価格面をみてオフィスステーションに決めました。管理者にとってはオフィスステーションの方が使いやすいと感じました。

コンサルティング
11〜30人
社会保険の手続きの一部には対応しておらず





簡単な手続きはオフィスステーションで十分でしたが、オフィスステーションでは申請できない社会保険の手続きもありました。そこにも完全に対応したら、完璧なツールだったと思います。


「freee人事労務」は、幅広い労務管理業務を効率化し、企業の成長ステージにあわせた使い方が可能な労務管理システムです。
これだけで、勤怠管理や給与計算、年末調整に助成金の申請までカバーできます。
設立したての企業から中堅以上まで規模にあわせたプランが用意されているので、業種規模問わず使いやすいシステムです。

社会保険労務士 金山杏佑子
「freee人事労務」は、勤怠管理・給与計算・入退社時の対応など一連の業務が全て完結します。その分、料金はジョブカンなどと比較すると少し高いですし、カスタマイズの幅は狭まります。 とりあえず一連の労務管理を全体的に楽にしたい!という企業には合うと思います。
どのプランでも初期費用はかからず、30日間の無料トライアルが利用できます。
| ミニマム | スターター | スタンダード | アドバンス | |
| 月額費用 (年払い/ 最小5名分料金) |
2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,500円 |
| 従業員料金 (6名以降〜) |
400円/人 | 600円/人 | 800円/人 | 1,100円/人 |
(税抜)
※上記費用は、年額プランの場合の金額

IT
1001人以上
労務まわりを一つに統合できる点が魅力





勤怠管理システムだけではなく給与計算や年末調整、労務手続き(入退社手続き)等を一つのシステムに統合できる点は、大きな魅力だと思います。一つに統合することでコストメリットが生かせました。

コンサルティング
11〜30人
電話対応が付かないプランがある





選んだ料金プランによっては電話によるヘルプデスク機能が付いてこない点が不便だと感じました。最初は一番価格の安いプランを選択していたが、人事、経理から電話で聞かないとわからないことがあると報告が上がってきたため、プランを変更しました。

「クラウドハウス労務」は、大手企業向けに特化したセミオーダー型の労務管理システム。
大手企業の多様な雇用形態、独自の就業規則、複雑な人事制度などの要件にあわせて、柔軟にシステムを構築・カスタマイズでき、既存の業務プロセスを大きく変えることなく導入できます。
複数会社管理機能では、 グループ企業や子会社が多い企業でも、複数会社の労務情報を一元的に管理できる点が魅力です。
高いセキュリティ水準も備えており、導入支援や導入後のサポート体制も充実しています。
月数万円から利用可能。課題を踏まえた上で見積もり・提案をしてくれます。
今回は、現代の企業が直面する労務管理の「見えない課題」とそのリスクを解説し、具体的な解決策を紹介しました。
労務管理の課題は、単なる業務負担の増加にとどまらず、法務リスクの増大、従業員エンゲージメントの低下、経営の停滞にまでつながりかねない、重要度の高い課題です。
従来のような画一的な方法では対応しきれない今だからこそ、自社の課題を明確にし、自社に最適なSaaSを活用した柔軟な労務管理体制を構築しましょう。
最適な労務管理を見つける第一歩として、労務管理システムの資料請求から始めてみませんか?
ぜひお気軽に問い合わせください。
画像出典元:Shutterstock

【2023年最新】賞与に必要な手続きと社会保険料の計算方法を簡単解説

社員管理とは?従業員管理のコツやメリット、おすすめ管理システムも

労務費とは?人件費との違いや計算方法・内訳・労務費率をサクッと解説

SmartHRとジョブカン労務HR徹底比較!料金・機能・使いやすさでわかる違いとは?
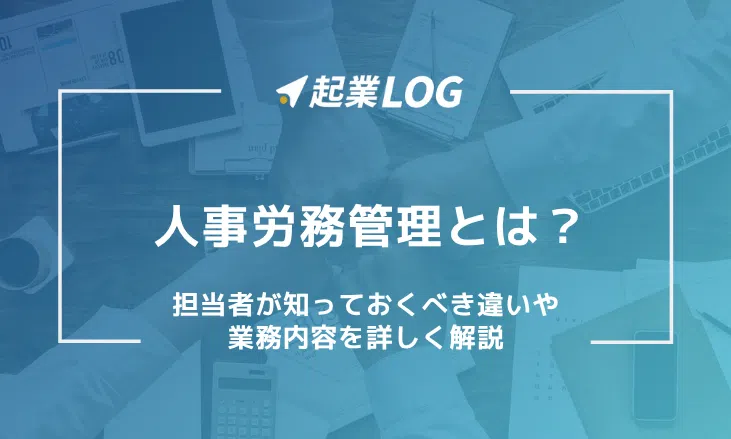
人事労務管理とは?担当者が知っておくべき違いや業務内容を詳しく解説
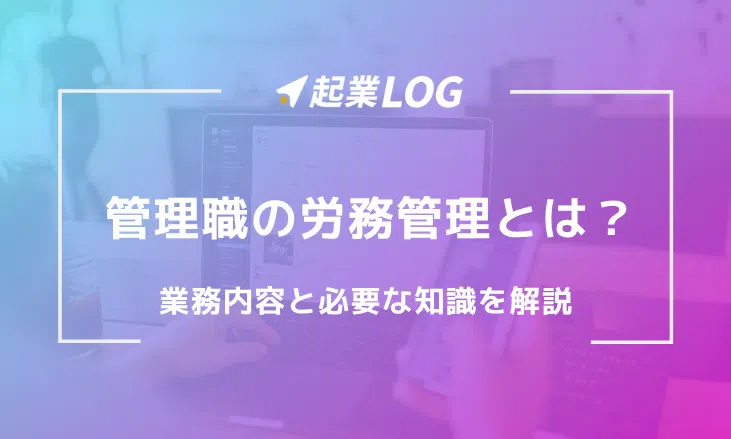
管理職の労務管理とは?業務内容と必要な知識を解説

労務管理システムとは?導入メリットや自社に合った選び方を解説

所定労働時間と法定労働時間とは?違いや残業代について簡単に解説

労務とは?人事との違いや社内での役割・仕事内容を大公開!

就業規則を変更する!変更が必要なケースと手順とは?