
労務管理とは、企業が従業員を雇用する上で必要となる、労働に関するあらゆる管理業務のことです。
適切な労務管理は、従業員のエンゲージメントを高め、企業の生産性や信頼を向上させることにも繋がります。
本記事では、労務管理の基本的な意味や目的、具体的な業務内容、直面しやすい課題について詳しく解説します。
自社の労務管理体制を見つめ直し、課題解決のヒントを得るためにお役立てください。
目次

企業を支える管理業務である、労務管理の基本的な定義と、社内で誰がその役割を担うのかについて詳しく解説します。
労務管理とは、従業員の雇用や労働環境を適切に維持するために、労働に関する全般を管理することです。
具体的には、給与計算や勤怠管理、社会保険・労働保険の手続き、入退社手続き、年末調整などが含まれます。
労務管理は、従業員が安心して働ける環境を整備し、労働基準法などの法令を遵守するために必要不可欠な業務です。
適切な労務管理は、従業員の満足度や法令遵守だけでなく、企業の生産性や社会的信用にも関わる重要な業務です。
労務管理を担う部署は、企業の規模や組織体制により異なります。
| 中規模〜大規模企業 | 中小企業 |
|
「人事部」「総務部」が担当、大規模企業では人事部内に「労務課」という部署が作られる場合も多い。 |
専門部署はなく、「総務担当者」や「バックオフィス担当者」が、経理など他の業務と兼務することも多い。経営者自ら労務管理を担う場合もある。 |
特定の部署だけでなく、現場の管理職がその役割を担う場合もあります。
部下の勤怠承認や時間外労働の管理、ハラスメントのない職場環境の構築、部下からの相談対応など、日々の労務管理の実践は、現場の管理職にも委ねられています。
このように労務管理は、特定の部署だけが担うのではなく、経営者や専門部署、現場の管理職がそれぞれの役割を果たし、連携することで会社全体として適切に機能するものです。
▼労務管理システムの導入を検討したい方はこちらへ
▼労務管理システムの資料請求はこちらから!▼
労務管理の主な目的は、「生産性の向上」と「コンプライアンス強化によるリスク回避」です。
企業が持続的に成長していくための、重要な経営基盤になります。
ここでは労務管理の目的とその必要性について解説していきます。
企業経営を進める上で、労働基準法などの労働関連法令の遵守は、最も基本的な責務の一つです。
代表的な労働関連法令として以下が挙げられます。
これらの法令を軽視した労務管理は、企業に深刻なダメージを与える可能性があります。
労務トラブルが発生すると、罰金や罰則などの法的リスクだけでなく、企業の社会的信用が失墜し、ブランドイメージが大きく損なわれます。
適切な労務管理は、これらのリスクを未然に防ぎ、健全で安定した企業経営の基盤を築きます。
適切な労務管理を通じた働きやすい職場環境の整備は、企業の生産性向上や企業価値の向上に直結します。
適正な労働時間や公正な人事評価などが、会社への貢献意欲である「従業員エンゲージメント」を高め、組織全体の活性化へと繋がるでしょう。
従業員の生産性の向上は、企業の業績向上へ直結します。
さらに、「社員を大切にする企業」という評価は、優秀な人材や社会的信用の獲得、従業員と企業の成長の両立に不可欠な経営機能と言えるのです。

企業における管理業務は、目的や範囲により、「労務管理」「人事管理」「勤怠管理」に分類されます。
これらは密接に関わっていますが、それぞれ役割に違いがあります。
| 労務管理 | 人事管理 | 勤怠管理 | |
| 役割 | 法律やルールに基づき労働環境を整備 | 経営戦略に基づき人材を活用 | 労働時間を正確に把握 |
| 主な業務 |
|
|
|
| 目的 | 法令遵守やリスク回避 | 組織のパフォーマンス力向上 | 正確な給与計算や健康管理 |
労務管理は、従業員の労働に関するあらゆる管理業務です。
組織を整備・運用することが主な役割で、組織全体を管理する側面があります。
また、労務管理の一部として、給与計算などを正確に算出するための、労働時間の実態把握に特化した位置付けが、勤怠管理です。
人事管理は、人材の成長や組織の発展を目的とし、個人の能力を最大限に引き出すための、戦略的な人材活用の役割を担います。
ここでは、労務管理の具体的な業務について解説します。
労務管理への理解が深まるので、ぜひ参考にしてください。
労働基準法により、企業には「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の、作成と保管が義務付けられています。
これらは、「法定三帳簿」と呼ばれ、労働者の労働実態を証明する重要な書類です。
税務調査や労働基準監督署の監査時、また労務トラブルの際などに、事実関係を示す客観的な証拠となるため、適切な管理が求められます。
従業員を雇用する際には、勤務時間や給与など細かい労働条件について合意したことを示す、「労働(雇用)契約書」を交わす必要があります。
さらに契約期間や就業時間、就業場所、従事する業務、休日、賃金など、契約に必要な情報を記載した「労働条件通知書」の交付が、労働基準法で義務付けられています。
労働条件を書面で示すことは、雇用後のトラブルを防ぐ上で特に重要な事項です。
労働条件通知書などのひな形は、厚生労働省のHPからダウンロードできます。
常時10人以上の従業員が働く事業場では、職場のルールブックである「就業規則」を作成し、労働基準監督署へ届ける義務があります。
休憩時間や災害保証などの職場のルールを定め、従業員に周知することも必要な業務です。
従業員の生活を守る「社会保険(健康保険・厚生年金保険)」と「労働保険(雇用保険・労災保険)」に関する手続きも労務管理の業務範囲です。
入社時の資格取得手続きや退職時の喪失手続き、育児休職時の各種給付金申請など、様々なタイミングでの手続きが必要になります。
主に労働時間の管理です。
出勤状況(遅刻・早退・欠席等)の把握から、有給休暇の管理、残業時間の管理等が含まれます。
勤怠管理は長時間労働の是正や、従業員の健康管理に不可欠な情報です。
働き方改革関連法により、客観的な方法による労働時間の把握が厳しく求められています。
勤怠管理を基にした、毎月の給与計算です。
勤務や雇用形態の多様化により、業務が複雑化、増大しているため注意が必要になります。
法律で義務付けられた社会保険などの「法定福利」に加え、企業が独自に設ける、住宅手当や慶弔見舞い金、リフレッシュ休暇などの「法定外福利」の企画や運用を行います。
企業ごとに特徴がある福利厚生は、従業員の満足度やエンゲージメントを高め、人材の確保や定着率に影響を及ぼす重要な業務です。
従業員が安全に、心身ともに健康に働ける職場環境を維持するための業務です。
労働安全衛生法により、職場の安全衛生確保と健康増進が義務付けられています。
健康診断やストレスチェックの実施、産業医との連携、労働安全衛生委員会の設置・実施などを行います。
全ての従業員が意欲的に働ける環境づくりを目指します。
具体的には、ハラスメント防止措置の徹底や円滑なコミュニケーションを促す施策の実施、多様な働き方の導入支援など。
定期的な従業員へのアンケートなどを通じて課題を把握し、継続的に改善していくことが必要です。
従業員が退職すると各種保険の喪失手続き以外に、退職証明書や源泉徴収票の発行、退職金制度のある会社では退職金の支払い等を行います。
従業員の退職後も書類のやり取りが発生するため、連絡先の把握が必要です。
毎月の給与計算に加え、年末に所得税額を確定させるための年末調整業務が必要です。
「給与所得の源泉徴収票」「報酬、料金、契約金及び賞金の支払い調書」などの、法定調書を作成・提出します。
従業員の傷病による休職や自己都合休職、育児、介護休職などに関する保険給付の申請、または人事異動に伴う手続きを行います。
休職者の復職に向けた支援プログラムの運用や、異動辞令の交付、関連部署との情報連携など、個別の状況に応じた対応が必要です。

社会情勢や価値観が変化する中で、労務管理が向き合うべき課題も複雑化してきています。
ここでは、企業が特に注意すべき6つのポイントを挙げ、その具体的な対策について解説します。
労務管理において最も重要な課題の一つが、コンプライアンスの強化です。
労働基準法や労働安全衛生法、育児・介護休業法など、企業が順守すべき法律は多岐にわたりますが、これらの労働関連法令は頻繁に改正されるため、注意が必要です。
法改正の意図や内容を正しく理解し、適切に運用しなければ、意図せずとも法令違反(コンプライアンス違反)を犯すリスクがあります。
特に、時間外労働の時間規制、同一労働同一賃金、有給休暇の取得義務化などは、違反した場合に罰則だけでなく、企業の社会的信用を損なう原因になります。
労務管理システムの導入や専門家への相談を活用し、コンプライアンス違反を未然に防ぐことが重要です。
テレワークやフレックスタイム制度、時短勤務など多様な働き方は生産性の向上や、育児、介護との両立に繋がる一方、労務管理の面では新たな課題を生じさせます。
多様な勤務体系に適したルールを詳細に定め、客観的な勤務時間を把握しましょう。
さらに、働く場所や時間帯が異なっても公平な評価基準を作るため、評価プロセスの見直しも必要です。
チャットツールやWeb会議システムを積極的に活用することで、業務のリアルタイムな進捗状況の把握が可能になります。
孤立感や情報格差が生じないよう、部署内で円滑なコミュニケーションをとりましょう。
近年、政府が副業や兼業を推進しています。
従業員のスキルアップや収入増加に繋がる一方、企業側には新たなリスク管理が求められます。
特に注意するべき点は、自社と副業先の労働時間を通算して管理する必要があることです。
従業員の総労働時間が過度にならないよう、定期的な健康状態のチェックや、必要に応じて業務量の調整や指導を行いましょう。
労務管理は、従業員の氏名や住所などの基本情報に加え、マイナンバーや病歴、人事評価など、機密性の高い個人情報を取り扱う業務です。
これらの情報が外部に漏洩したり、目的外での不適切な利用があれば、従業員の損害だけでなく、企業は法的責任や信用の失墜という深刻なダメージを受けます。
社内での対応に課題がある場合、セキュリティ性が高い労務管理システムを導入することが重要です。
▼セキュリティに定評のあるパッケージ型労務管理システムはこちら
給与計算や社会保険手続きは、労務管理の定型業務ですが、その内容は非常に複雑です。
保険料率の変更や法改正、従業員の個別事情を見落とすことで、計算ミスや手続き漏れが発生しやすくなります。
これらのミスは、従業員の不利益に直結し、会社への信頼を損なうだけでなく、法令違反で労働基準監督署から指導を受けることもあります。
必ず別の担当者がダブルチェックを行うなど複数人での確認を徹底しましょう。
また、手作業によるミスを防ぐ対策として、勤怠管理から給与計算、社会保険手続きまで連動して管理できる、労務管理システムを導入することも有効な手段の一つです。
▼労務管理システムに興味がある方はこちらへ
▼労務管理システムの導入を検討したい方は、まず資料請求から▼
少子高齢化による労働人口減少が予測される日本では、従業員一人ひとりの生産性向上が企業の持続的成長に不可欠です。
紙とハンコを中心としたアナログな手続きは、長時間労働の温床となり、従業員のモチベーションの低下に繋がります。
労務管理システムを導入して、定型業務の自動化や効率化を図りましょう。
各種申請や経費清算なども紙媒体から電子申請に切り替えることで、承認時間の短縮や書類保管に関わる管理コストの削減も可能です。
無駄な報告や重複作業を無くすため、既存の業務フローを定期的に見直す必要があります。
企業の円滑な運営に深く関わる労務管理部門が、進んで生産性を意識した、業務改善のモデルとなることが求められています。
▼労務リスクについて詳しく知りたい方はこちらの記事もおすすめ!
労務管理システムの普及により、複雑な計算や法改正による人的ミスは減少しています。
しかし、法律や社内規程といったルールを扱う正確性と、従業員一人ひとりに向き合う人間性を同時に求められる複雑な業務です。
ここでは、担当者に必要な資質やスキル、業務に役立つ資格について解説します。
労務管理業務は、資格よりも日々の業務を遂行するうえで土台となる、個人の資質やスキルが重要です。
労働関係の法律は、都度改正していますし、労働環境を取り巻く情勢も、刻々と変化しています。
労務管理担当者は、常に法改正の知識をブラッシュアップし、ニュースで労働問題や人々の関心がどこにあるか等、最新の情報を知る必要があるでしょう。
守秘義務を守り、柔軟で向学心のある人物が労務管理の業務には向いています。
労務管理は、必須の資格がなければ出来ない業務ではありませんが、専門知識を証明し、キャリアアップに繋がる資格や検定は数多く存在します。
【国家資格】
【民間資格・公的資格】
これらの資格は、専門性を高めるだけでなく、従業員や経営層からの信頼を得る上でも大きな助けになるでしょう。
特に、国家資格である「社会保険労務士」は、社労士にしか出来ない独占業務があるため、有力な資格です。

労務管理システムの導入は、人的ミスを防ぎ、コンプライアンスの強化に繋がり、労務管理の業務負担を大幅に軽減できます。
労務管理システムを導入すると得られる主なメリットを5つ紹介します。
手作業やExcelで行っていた、勤怠データの集計や給与計算、各種申請などの定型業務を自動化できます。
従業員が、Webやアプリから直接打刻、申請を実行すれば、システムに即座に反映され、転記や集計の手間が不要になります。
担当者は、月末月初の繁忙期に集中していた業務から解放され、業務時間の大幅な短縮が可能です。
業務効率化により生まれた時間を、より付加価値の高い業務に充てることができます。
例えば、従業員のエンゲージメントを高めるような施策、働きやすい職場環境の構築、人事制度の見直し、などの戦略的な業務に注力できるようになります。
また、業務効率化は残業時間の削減にも直結し、人件費の抑制へと繋がるでしょう。
労務管理システムは、最新の法律や保険料率に基づき各種計算を自動で行うため、計算ミスや法改正による手続き漏れなどの、人的ミスを防ぐことができます。
正確な給与計算や社会保険手続きは、従業員との信頼性の向上に貢献します。
業務の属人化は、担当者の急な休職や退職が、業務停滞に直結するリスクになります。
労務管理システムの導入で、誰が担当しても一定の品質で業務を遂行できる体制の構築が可能です。
担当者の急な退職時なども、引き継ぎがスムーズに行われて、安定した組織経営が行えます。
多くの労務管理システムは、法改正に自動でアップデートする機能が備わっているため、コンプライアンス違反のリスクを低減できます。
また、従業員の個人情報などの機密データは、暗号化された安全なクラウドサーバーで管理されるため、情報漏洩や自社管理による紛失のリスクも減らすことが可能です。
▼労務管理システムの導入を検討している方はこちらもおすすめ!
▼労務管理システムの導入を検討中の方は、まず資料請求から!▼労務管理システムの資料を無料ダウンロード
働き方の多様化が進む現代において、労務管理の役割は、従来の定型的な事務処理から企業の持続的成長を支える、戦略的機能へと変化してきています。
これからの労務管理が果たすべき役割について、4つの側面から解説します。
労務管理の根幹は、「企業の健全で持続的な成長を支えること」です。
労務トラブルを未然に防ぎ、法的リスクを回避する、「守りの要」としての役割は、従業員が安心して業務を遂行して、企業の社会的信用を維持する上で、今後ますます重要性を増していくでしょう。
定型業務をいかに正確かつ効率化し、組織全体の生産性を向上させるか、という視点が不可欠です。
労務管理システムの導入や、業務プロセスの見直しを積極的に実行することで、単純作業を効率化し、組織全体の働き方改革をリードしていくことができます。
労働人口の減少が予測され、一人ひとりの従業員の価値が高まる中、個々の事情や価値観に寄り添う姿勢が必要とされます。
メンタルヘルスケアの充実や、育児・介護との両立可能な働き方の支援、従業員のキャリア形成の相談など。
従業員のエンゲージメントを高め、人材の定着を促すことが、組織全体の成長へと繋がります。
これからの労務管理は、日々の業務から得られる人事・労務データを分析して、経営課題の解決に繋げる役割も期待されます。
たとえば、離職率の分析から働きがいの向上策を提案したり、勤怠データより生産性の高い働き方を分析するなど、データに基づいた戦略的な対策が可能です。
また、人材を大切にする企業姿勢は、投資家や社会から高く評価されます。
人材という重要な経営資源を活かし、企業価値の向上に貢献していくことが、これからの労務管理に求められています。
労務管理は、法令を遵守し、従業員が安心して働ける環境を整える、企業の要となる業務です。
さらに労務管理システムを活用すれば、定型業務を大幅に効率化でき、経営的視点をもって企業の成長に貢献することができます。
企業の持続的成長を実現するため、労務管理の役割と重要性を再認識し、強化していくことが求められています。
画像出典元:Pixabay、Pexels

【2023年最新】賞与に必要な手続きと社会保険料の計算方法を簡単解説

社員管理とは?従業員管理のコツやメリット、おすすめ管理システムも

労務費とは?人件費との違いや計算方法・内訳・労務費率をサクッと解説

SmartHRとジョブカン労務HR徹底比較!料金・機能・使いやすさでわかる違いとは?
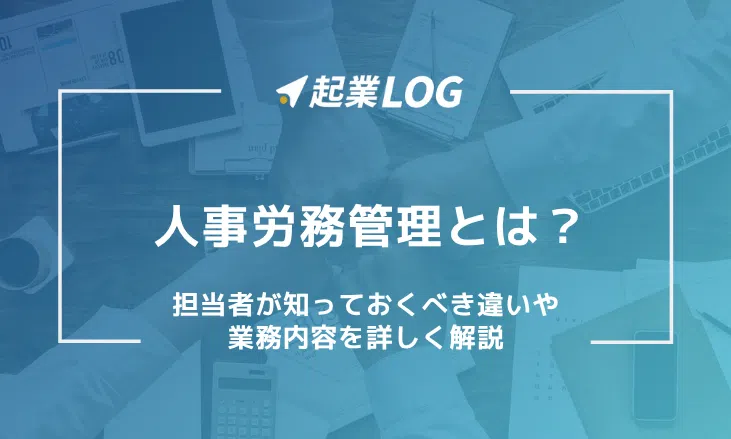
人事労務管理とは?担当者が知っておくべき違いや業務内容を詳しく解説
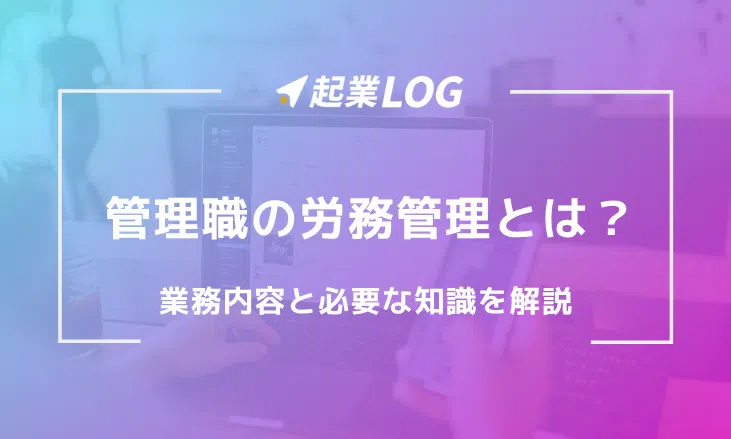
管理職の労務管理とは?業務内容と必要な知識を解説

労務管理システムとは?導入メリットや自社に合った選び方を解説

所定労働時間と法定労働時間とは?違いや残業代について簡単に解説

労務とは?人事との違いや社内での役割・仕事内容を大公開!

就業規則を変更する!変更が必要なケースと手順とは?