TOP > SaaS > マーケティング > webサイト運用 > LLMO対策サービス
TOP > SaaS > マーケティング > webサイト運用 > LLMO対策サービス
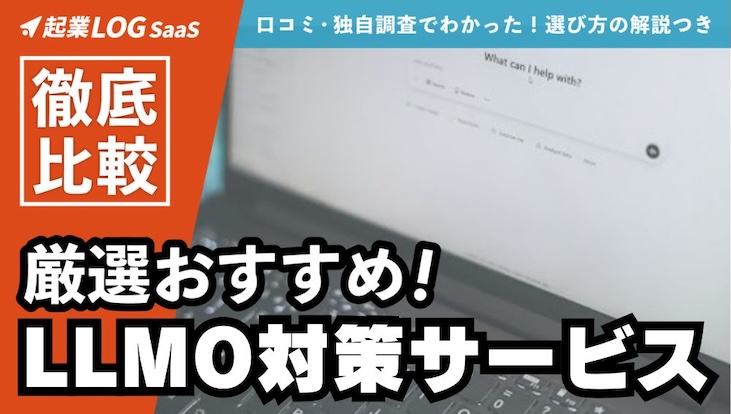
生成AIの普及により、Webマーケティングは大きな転換点を迎えています。
従来のSEOだけではリーチできない「AI検索」時代に対応するには、LLMO(大規模言語モデル最適化)対策が不可欠です。
本記事では、デジタル戦略を強化したい企業におすすめのLLMOサービス12選を紹介します。
LLMO対策のメリット・デメリットから今すぐ実践できる施策、成果の測定指標などまで詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

目次
LLMO対策とは、ChatGPTやGeminiなど生成AIの回答に対し、自社の情報が適切に引用されるよう働きかけるための取り組みです。
AIが生成する回答の中で自社が信頼できる情報源として引用されることで、ブランド認知度の向上や新規顧客の獲得につながります。
特に、専門性の高いBtoBや、購買決定プロセスにおいてAIが活用されるBtoCにとって、競争優位性に直結する重要な施策です。
生成AIが提供する回答や推奨コンテンツにおいて、自社のWebサイトやサービスが適切に参照・表示されるよう最適化するプロセスを指します。
AIアシスタントがユーザーの質問に答える際に、自社の情報が正確かつ信頼できるものとして認識・活用されることが目的です。
具体的には、以下のような要素が含まれます。
AIが理解しやすい自然言語で記述された高品質なコンテンツを作成し、ユーザーの質問や意図に直接応える情報を提供する。
スキーママークアップやJSON-LDを用いて、Webサイト上の情報をAIが正確に解釈・活用できる形式で提供する。
E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識した情報発信を行い、AIから信頼できる情報源として評価されるようにする。
ユーザーがAIアシスタントと会話する際の文脈や意図を想定し、それに応じたトピック設計・回答形式のコンテンツを用意する。
▼対話型AIサービスについて詳しく知りたい方はこちらもおすすめ!

大規模言語モデル(LLM)は、膨大なテキストデータを学習し、自然言語処理(NLP)を通じて人間の言語を理解・生成するAIモデルです。
以下は、その基本的な仕組みです。
LLMは、Webサイト・論文・書籍・ニュース記事・ブログ投稿・SNSの書き込みなど、インターネット上に存在する多様なテキストデータをもとに構築されます。
こうしたデータを通じて、言語パターン、文脈、事実関係、専門知識などを学習し、質問に対して自然かつ適切な回答を行う能力を獲得します。
入力された文章をトークン(単語や句の単位)に分割し、トークン同士の関係性を分析することで文脈を把握します。
この文脈理解により、単なる単語の並びではなく、質問の意図や背景を読み取ることが可能となり、自然で的確な応答が実現されます。
学習した情報と文脈に基づいて、新たなテキストを動的に生成します。
生成の際には、信頼性の高い情報源(例:公的機関、専門サイトなど)やパターンを重視する傾向にあるのが一般的です。
質問の内容に応じて、最もふさわしい形で情報を組み合わせて回答を作り出します。
一般的にLLMは、定期的にモデルの更新が行われ、新しい情報や言語トレンドが反映されるよう設計されています。
一部のモデルでは、対話を通じたフィードバック学習や、外部データのリアルタイム参照機能を取り入れています。
企業としては、質の高い情報を継続的に発信することで、学習プロセスにおいて自社の情報が適切に取り込まれ、回答に反映される可能性が高まるでしょう。
近年、生成AIの台頭によって、ユーザーの情報収集行動や検索エンジンの表示形式が大きく変化しています。
以下では、LLMOが重要視される背景を、3つの視点から解説します。
ChatGPTをはじめとする生成AIが急速に普及したことで、従来の検索エンジンではなく、AIアシスタントに質問して情報を得るケースが増えています。
これにより、AIに自社コンテンツを適切に認識・活用してもらうための最適化=LLMOの重要性が高まっているのです。
Googleは「AI Overview(旧SGE)」を通じて、検索結果ページ上部にAIが生成した要約情報を表示するようになっています。
この変化により、ユーザーはリンクをクリックせずに情報を得る「ゼロクリック」検索が増加。
従来のSEOではカバーしきれない領域への対応が必要で、企業にとってAIに選ばれやすいコンテンツ設計が不可欠となってきています。
ChatGPTやGeminiなど、対話型AIプラットフォームの利用が急速に拡大する中、AIを経由した新たなトラフィックの流れが生まれつつあります。
AI経由のアクセスは、ユーザーが対話を通じて自らの課題を整理・明確化した上で訪問するため意図がはっきりしており、エンゲージメントが高いのが特長。
LLMOは、AIプラットフォーム上で自社の製品・サービスやコンテンツが適切に推奨されるよう最適化し、質の高いトラフィックを獲得するための戦略です。

LLMOとSEOは、いずれもWebサイトの可視性を高めるための戦略ですが、対象とするプラットフォームやアプローチが異なります。
SEOは、GoogleやBingなどの従来の検索エンジンで上位表示を目指す手法で、キーワード最適化やリンク構造の強化が中心です。
LLMOは、生成AIの言語モデルにおいて、どのように情報を伝え、適切に引用・推薦されるかを重視します。
LLMOとSEOの主な違いは、以下のとおりです。
| LLMO | SEO | |
| 対象 | ChatGPT、Geminiなどの対話型AI AI Overviewsをはじめとする検索エンジンに表示されるAI要約 |
Googleなどの検索エンジン |
| 目的 | AIによる回答・推薦の中で自社情報が引用・参照される | 検索結果で上位表示され、クリックを獲得する |
| 露出の仕組み | モデル学習と文脈理解による回答生成 | クローリング・インデックス・ランキングによる表示 |
| 成果指標 | AI内での言及数・推薦頻度・文脈内での引用可視性など | 検索順位・クリック数・CV数など |
▼SEOツールについて詳しく知りたい方はこちらもおすすめです!
LLMO対策は、従来のSEOとは異なるアプローチが必要ですが、すぐに実践できる施策もあります。
以下は、すぐに取り組める具体的な4つの施策です。
また、より本格的な対策をご検討される際は、下の章でご紹介しているLLMO対策サービスの導入をおすすめします。
Schema.orgに基づく構造化マークアップの実装により、AIが自社のコンテンツを正確に理解できるようになります。
特に、組織情報・製品情報・FAQ・レビューなどの構造化データは、AI検索結果での表示率向上に有効です。
JSON-LD形式での記述が推奨されており、比較的容易に導入できます。
ページの読み込み速度やモバイル対応の最適化は、AIクローラーの巡回効率にも大きな影響を与えます。
AIクローラーは、人間よりも高頻度でサイトにアクセスするため、サーバーの負荷を軽減し、安定したパフォーマンスを維持することが不可欠です。
Core Web Vitals(コアウェブバイタル)の改善は、検索エンジンだけでなくAIプラットフォームでの評価向上にも寄与します。
LLMOは、従来のSEOに取って代わるものではなく、むしろ相乗効果を生み出すものです。
検索エンジンでの上位表示を維持することで、AIが参照するソースとしての信頼性が向上し、結果的にAI検索結果での言及率も高くなります。
キーワード最適化、内部リンク構造の改善・定期的なコンテンツ更新などの基本的な施策の継続が重要です。
▼検索順位チェックツールについて詳しく知りたい方はこちらもおすすめ!
社内にLLMO対策の専門知識やリソースが不足している場合は、専門のサービス会社への外注も有効な選択肢となります。
LLMO対策は新しい分野であり、最新の技術動向や効果的な手法を把握するには相当な時間と労力が必要です。
専門サービスを活用することで、効率的かつ効果的にLLMO対策を実施できるでしょう。
以下では、実績豊富なLLMO対策サービスをご紹介します。
ツール名
利用料金
主な機能
サポート体制
導入事例
 AIブログアルケミスト
AIブログアルケミスト
 ナイル株式会社 LLMOコンサルティング
ナイル株式会社 LLMOコンサルティング
 AI Hack
AI Hack
 LLMOコンサルティングサービス
LLMOコンサルティングサービス
 株式会社LANY(記事作成代行サービス)
株式会社LANY(記事作成代行サービス)
 メディアグロース
メディアグロース
(税抜価格)

画像出典元:「AIブログアルケミスト」公式HP
「AIブログアルケミスト」は、SEO・LLMO対策に最適化されたコンテンツを制作する、WordPressに特化した完全自動化ブログ生成システムです。
SEOの専門知識がなくても、AIがサイトURLから自動学習し、LLMO対策に最適化されたコンテンツを継続的に生成します。
初期設定後は、WordPressにログインすることなく、高品質なブログ記事の自動投稿が可能です。
| 主な機能 |
|
| デメリット | 利用がWordPressに限定される |
| サポート体制 | 設定方法から運用に関する疑問まで幅広くサポート |
| 導入実績数 | 具体的な導入実績数は公開されていない |
| 無料トライアル | 利用開始月の月末まで無料 |
月額33,000円(税込)で利用できます。
画像出典元:「ナイル株式会社 LLMOコンサルティング」公式HP
ナイル株式会社の「LLMOコンサルティング」は、SEOとLLMOをセットで最適化できる点が特徴。
主要なLLMで「おすすめのSEOコンサルティング会社」を尋ねた際にも、多くの回答でナイルの名前が挙がります。
戦略設計からKPI設定、効果測定、改善提案、施策実行までを一気通貫で支援し、検索エンジンと生成AIの双方に強いサイトづくりを実現したい方におすすめです。
| 主な機能 |
|
| デメリット | 即効性のある施策を提供するサービスではない |
| サポート体制 | SEO×LLMOのハイブリッド伴走支援 コンサルタント / アナリスト / 編集者など、各領域のスペシャリストが在中 |
| 導入実績数 | 具体的な導入実績数は公開されていない |
| 無料トライアル | なし |
詳細については、お問い合わせが必要です。

画像出典元:「AI Hack」公式HP
「AI Hack」は、複数の生成AIに対してプロンプトを投げかけ、回答内容を可視化・スコア化するAIO(AI Optimization)分析ツールです。
ユーザーの検索行動がAIとの対話型に進化しつつあることに着目し、AI回答の最適化を支援します。
自社サイトのブランド露出度を定量的に評価し、競合との高精度な比較分析が可能です。
| 主な機能 |
|
| デメリット | AIOという比較的新しい概念のサービスのため、実績データや成功事例がまだ蓄積段階である |
| サポート体制 | 具体的なサポート範囲については要確認 |
| 導入実績数 | 具体的な導入実績数は公開されていない |
| 無料トライアル | なし |
詳細については、お問い合わせが必要です。

画像出典元:「LLMOコンサルティングサービス」公式HP
「LLMOコンサルティングサービス」は、株式会社メディアリーチが提供する、生成AI検索に最適化したコンテンツ設計を支援するシステムです。
SEOとLLMOを融合し、検索エンジンとAI双方での成果を追求します。
多言語対応で海外市場やオウンドメディアにも柔軟に適応することが可能です。
| 主な機能 |
|
| デメリット | LLMO診断がスポット30万円~、コンサルティングが月額33万円~など、導入コストが高め |
| サポート体制 | 具体的なサポート範囲については要確認 |
| 導入実績数 | 具体的な導入実績数は公開されていない |
| 無料トライアル | なし |
| サービス内容 | 料金 |
| LLMO診断 | 300,000円~/スポット |
| LLMOコンサルティング | 300,000円~/月 |
| LLMO記事制作 | 60,000円~/本 ※最適10本~ |
| LLMO研修・トレーニング | 200,000円~ |
| サイトリニューアル時のLLMO対策 | 500,000円~ |
| 海外(グローバル)サイトのLLMO対策 | 300,000円~/月 |
(税別)

画像出典元:「LANY」公式HP
株式会社LANYの「LANY診断」は、SEOの深い知見と実績に基づき、AIに選ばれるサイトの健康診断を行うサービスです。
技術的根拠に基づく現状分析と改善策の提案により、表面的な対策ではなく本質的なサイト改善を実現します。
ブランド認知度向上や指名検索の増加を目指す、包括的な視点での戦略が強みです。
| 主な機能 |
|
| デメリット | 個人・フリーランスへの提供は行っていないほか、同業他社への提供も制限されるなど利用対象が限定的 |
| サポート体制 | ヒアリングから診断実施、レポート提出・説明まで専任担当者が一貫してサポート |
| 導入実績数 | 具体的な導入実績数は公開されていない |
| 無料トライアル | なし |
詳細については、お問い合わせが必要です。

画像出典元:「メディアグロース」公式HP
「メディアグロース」は、10年以上のSEOメディア運営実績を基に、AI検索での露出強化を支援するLLMO対策サービスです。
ChatGPTやGoogleのAI Overviewに対応し、自社ブランドやサイトの引用率向上を目指す戦略を展開します。
短期・中長期の施策提案など、土台固めから本格的なLLMO対策まで、企業のニーズに合わせた柔軟な対応が可能です。
| 主な機能 |
|
| デメリット | AIの学習期間を含め、成果が出るまで半年以上の時間がかかる場合がある |
| サポート体制 | LLMO対策の立案から実行まで一貫してサポート |
| 導入実績数 | 具体的な導入実績数は公開されていない |
| 無料トライアル | なし |
| プラン | 料金 |
| 短期施策プラン | 200,000円 |
| サイト全体対策プラン | 要問い合わせ |
| 比較記事プラン | |
| 個別ページ対策プラン |
(税別)

画像出典元:「LLMO最適化サービス」公式HP
株式会社アドメディカルが提供する「LLMO最適化サービス」は、生成AIの特性を考慮しつつ、業種別にカスタマイズされた対応が可能なLLMOサービスです。
通常だと自社対応が難しい設計や検証も、知識と経験が豊富なスタッフが対応し、医療・士業・教育・美容など、専門性の高いジャンルには特に効果的に活かせます。
SEOとLLMO双方の視点からコンテンツを制作するので、より高い成果が期待できます。
| 主な機能 |
|
| デメリット | 詳しい料金情報が開示されていないので問い合わせが必要 |
| サポート体制 | 継続サポートオプションなどで伴走支援 |
| 導入実績数 | 具体的な導入実績数は公開されていない |
| 無料トライアル | なし |
初回導入には、55,000円のワンパッケージプランを提供しています。
最適な戦略設計を提案しているので、詳細については、お問い合わせが必要です。

画像出典元:「DaiLY UP」公式HP
DaiLY UPは、AI時代に求められた検索環境を包括的に構築する伴走型のLLMO対策サービスです。
定期的なディスカッションを行うことで、企業の課題感や改善案の提案まで安定的にサポートできます。
AI検索の重要性が増す昨今の状況を踏まえて、AIによる自然表示を図る施策を多角的に取り入れているのが最大の強みです。
| 主な機能 |
|
| デメリット | サービス開始から間もないため、実績データや導入事例が蓄積段階である |
| サポート体制 | 定期的なディスカッションや包括的なサービスなどで伴走支援 |
| 導入実績数 | 要問合せ |
| 無料トライアル | 要問合せ(無料診断あり) |
基本プランとして、10ページ15万円がかかり、11ページ以降は1万円/1ページが発生します。
基本プランには「現状のサイト構造、AI引用状況の分析」「AIが読める構造化データの作成」「サイトへの反映手順書の作成」が含まれ得ます。
さらにAIに引用されやすくするためのオプションプランもあるので、詳細は問い合わせて確認しましょう。
画像出典元:「SUPER ACT」公式HP
SUPER ACTは、ChatGPTやGeminiなどの生成AIが回答を生成する際に、自社サービスがどの程度推薦され、どのような評価を受けているかを可視化する国内発のLLMO・AIO対策ツールです。
検索からAI対話への移行が進む中、AI内での露出状況や引用元、競合動向を分析し、最適化に向けた具体的な改善アクションの提案までを一気通貫で行うことで、AI時代のマーケティング戦略の立案と実行を支援してくれます。
| 主な機能 |
|
| デメリット | 効果を実感するまでに情報の蓄積と継続的な改善が必要 |
| サポート体制 | 分析結果に基づく具体的な改善アクションの提案・実行支援のサービスプランの提供 |
| 導入実績数 | 具体的な導入実績数は公開されていない |
| 無料トライアル | デモあり |
SUPER ACTの料金プランは次のようになっています。
| Standard | |
| 月額利用料 | 15,000円 |
| 機能 |
|
| 計測プロンプトの追加 10 計測プロンプトの追加 2 ブランドの追加 |
6,800円 |
| プランのカスタマイズ | 要問合せ |
| コンサルティングサービス ※最低契約期間3ヶ月 |
160,000円 |
※税抜

画像出典元:「HODOCK」公式HP
「HODOCK」は、ChatGPTやGeminiなどのAIエージェントに対し、正確かつ好意的に参照されるコンテンツ設計をサポートするLLMO・AIO対策サービスです。
これまでのSEO領域を超えたLLMOとAIOの特化型戦略で、AI検索時代におけるブランド露出を強化します。
体系的な情報整理と信頼性の高いデータ提示により、AIが優先的に参照したくなる情報源へと導く施策が特徴です。
| 主な機能 |
|
| デメリット | 料金が非公開のため、コスト検討や予算計画が立てづらい |
| サポート体制 | 伴走型のパートナーシップ支援 |
| 導入実績数 | 具体的な導入実績数は公開されていない |
| 無料トライアル | なし |
詳細については、お問い合わせが必要です。

画像出典元:「LLMO ANALYZER」公式HP
「LLMO ANALYZER」は、3,000以上のWebサイトから収集した保有データを基に、検索エンジンとLLMからの流入を最適化する総合分析プラットフォームです。
ChatGPTやGeminiなどの生成AIからのトラフィックを独自タグで可視化し、AIに信頼されるコンテンツを構築できます。
データ分析とコンテンツ最適化を融合した戦略で、AI検索で引用される可能性を高める支援が特徴です。
| 主な機能 |
|
| デメリット | サービス開始から間もないため、LLMO効果の実績データや導入事例が限定的である |
| サポート体制 | 有料コンサルティング/月額100,000円~ |
| 導入実績数 | 具体的な導入実績数は公開されていない |
| 無料トライアル | なし |
| スターター | プロフェッショナル | エンタープライズ | |
| 月額利用料 | 50,000円 | 100,000円 | 300,000円~ |
(税表記なし)

画像出典元:「デジタルアイデンティティ」公式HP
「デジタルアイデンティティ」は、15年以上にわたるSEO支援の実績を活かし、AI検索時代に対応した最適化を通じて、先を見据えたLLMOを実現するサービスです。
検索エンジンと生成AIの双方を意識し、SEOと連携した総合的な戦略を提供します。
アクセス解析や広告運用、LP制作、UI/UX改善、バナー・動画制作など、デジタルマーケティングにおける幅広い支援も可能です。
| 主な機能 |
|
| デメリット | ミニマム月額約60万円~と料金設定が高額なため、予算が限られている企業では導入が困難な場合がある |
| サポート体制 | 戦略設計からサイトへの実装まで一貫してサポート |
| 導入実績数 | 具体的な導入実績数は公開されていない |
| 無料トライアル | なし |
サイトの規模や性質などによって変動しますが、ミニマムで月額60万円〜となっています。

AIが生成する検索結果のなかで、企業情報がどれだけ適切に扱われているかを把握することは、今後のWebマーケティング戦力において極めて重要です。
ここでは、LLMO対策の効果を測るうえで注目すべき3つの指標について解説します。
AI回答文への登場回数は、LLMOの最も直接的な成果指標です。
ChatGPTやGeminiなど生成AIが提供する回答で、自社のコンテンツや情報がどの程度引用・参照されているかを測定します。
測定時は単純な登場回数だけでなく、回答文内での位置や扱われ方も重要です。
主要なAIプラットフォームで業界関連キーワードを定期的に検索し、回答内容を分析することで把握できるでしょう。
生成AIが提供した回答やリンクを通じて自社Webサイトに訪れるユーザーのトラフィック量を測定する指標です。
AIが自社のWebページを参照元として提示することで、ユーザーが直接サイトにアクセスするケースが増えています。
このセッション数は、ユーザーに対してAIが自社のコンテンツをどの程度効果的に届けているかを示します。
Google Analyticsや類似のツールを活用するなど、AIからの流入を特定し、どのページやコンテンツがトラフィックを牽引しているかを分析することが重要です。
こうしたデータをもとに、AIが好む構造化されたコンテンツを強化することで、さらなる流入増加が期待できます。
指名検索数は、自社ブランドや企業名、サービス名での検索量の変化を測定する指標です。
AIの回答文に自社情報が頻繁に登場すると、ブランド認知度が向上し、指名検索が増加する傾向が見られます。
AIの情報で興味を持ったユーザーが、より詳しい情報を求めて自社名で検索を行うパターンが典型的です。
Google Search Consoleなどを活用し、自社関連キーワードの検索推移を継続的に監視するとよいでしょう。
LLMOへの対応は、単なるSEOの延長線ではなく、将来のビジネスチャンスを大きく広げる重要な戦略です。
以下に、LLMO対策によって得られる4つの代表的なメリットを紹介します。
最大のメリットは、従来の検索順位に依存しない新たな流入経路を確保できることです。
AIが回答を生成する際、検索順位1位のサイトだけでなく、信頼性や専門性の高い複数のサイトを参照して回答を構築します。
そのため、たとえ検索順位が2位以下であったとしても、AI回答文に自社の情報が引用される可能性があるのです。
この新たな流入経路により、従来のSEOでは獲得できなかった質の高いトラフィックを獲得でき、結果としてコンバージョン率の向上も期待できます。
LLMO市場はまだ発展段階にあり、多くの企業が本格的な対策に着手していない状況です。
この段階でLLMO対策を開始することで、競合他社に先駆けてAI回答文での露出機会を獲得できます。
また、先行者利益として、自社の専門分野におけるAI回答での優位なポジションを確立することが可能です。
競合が後から参入してきた際にも、既に築いた優位性を維持しやすく、長期的な競争優位を構築できるでしょう。
市場が成熟する前の今こそ、LLMO対策に投資する絶好のタイミングといえます。
AIに信頼される情報源として認識されるためには、専門的かつ信頼性のあるコンテンツの整備が重要です。
これらに取り組む過程で、自社サイトの情報の質や構造も改善され、結果として業界内での専門性や信頼性が高まっていきます。
こうした積み重ねが、長期的にはブランドイメージの向上へとつながるのです。
LLMO対策により、従来のキーワード検索では接触できなかった潜在顧客層にアプローチできるようになります。
AIは自然言語での質問に対して包括的な回答を提供するため、これまで想定していなかった検索クエリからの流入が期待できるでしょう。
また、AIは関連性の高い情報を組み合わせて回答を生成します。
そのため、直接的な競合商品を探していないユーザーに対しても、解決策の一つとして自社サービスを提示する可能性が高いです。
LLMO対策を通じて、「まだ知られていないけれど、必要としているユーザー」にリーチできるようになることは、ビジネスにおいて大きな差別化要因となるでしょう。

LLMOは、新たなマーケティングチャネルとして注目を集めていますが、その運用にはいくつか課題も存在します。
これらのデメリットに対して過度に悲観的になる必要はありませんが、適切に向き合い、戦略的に対応していくことが重要です。
以下に、主な4つのリスクとその向き合い方を紹介します。
生成AIは、事実に基づかない情報をもっともらしく出力してしまう、いわゆる「ハルシネーション」と呼ばれる問題があります。
これは、自社や競合、業界全体に関する誤解を招く原因にもなりかねません。
AIが参照しやすい構造化された情報を自社サイト上で整備し、事実ベースのコンテンツを継続的に提供することが大切です。
AIがユーザーに包括的な回答を提示することで、自社サイトへのアクセスが発生しない「ゼロクリック問題」が生じる可能性があります。
この課題には、AIではカバーしきれない独自の付加価値や詳細分析、最新事例を自社サイトで提供することが有効です。
深い洞察を求めるユーザーに向けて、AIを補完する質の高いコンテンツを用意し、クリックを促しましょう。
従来のSEOと比べ、LLMO対策では順位やクリック率といった明確な定量指標が得にくく、効果測定が難しいという課題があります。
けれども、AI回答文への登場頻度や指名検索数、AI経由のセッション数などの間接指標を組み合わせることで、一定の評価は可能です。
現段階では、仮説検証とPDCAの反復により、データの蓄積と解釈を工夫していくことが重要です。
LLMO対策は短期間で成果が出にくく、継続的な取り組みが不可欠です。
AIの学習データは変化し続け、競合も対策を進める中、優位性を維持するには中長期的な戦略と継続的な努力が求められます。
そのためには、予算確保や社内理解の醸成も含めた体制づくりが重要です。
短期的な成果に固執せず、ブランド構築や専門性の確立といった長期目標に基づき、段階的な改善を重ねていく姿勢が鍵となります。
AIの進化により、WebマーケティングはSEO中心からLLMO対策を軸とした新たなフェーズへと移行しつつあります。
構造化マークアップやSEO対策継続などの基本施策から着手し、リソース不足の場合は専門サービスの活用が有効です。
ハルシネーションやゼロクリックなどの課題はあるものの、AI経由の新たな流入経路の確保や、競合に先駆けたブランド露出の拡大が期待できます。
ぜひ、自社に最適なサービスを選定し、AI時代のマーケティング戦略を構築しましょう。
画像出典元:O-dan