
働き方改革による労働基準法の改正により、平成31年4月から「有給休暇の義務化」がスタートしています。この「義務」は「労働者」ではなく「企業」に科せられたものであり、違反した場合には罰則が科せられることもあります。
具体的に、どのような社員に対して、どのくらい有休を取得させる必要があるのか、しっかり理解できていますか?
今回は、有給休暇の義務化について、導入の背景やメリット・デメリットも交えて徹底的に解説していきます。
目次

「有給休暇の義務化」とは、「企業」が「労働者(雇用者)」に対して有給休暇を取得「させる」ことの義務化を意味します。
重要なのは、「労働者」が有給休暇を取得「する」ことの義務ではない、という点。
つまり、義務を課せられているのは「企業」である、という点です。
後述するとおり違反した場合には罰則が科せられる可能性もある「義務」であり、例外なくすべての企業が遵守すべき法令改正でもあるので、企業経営者は具体的な内容をしっかりと確かめて自社の制度変更などに取り組んでいく必要があります。
日本では以前から有給休暇の取得率の低さが問題となっていました。
厚生労働省の「就労条件総合調査」によると、日本の企業における有給休暇の取得率(支給日数20日間あたりの平均取得日数)は51.1%(平成30年)。
「有休を取れない」というイメージからすると「意外と高い」と感じるかもしれませんが、有給休暇取得率は平成3年及び4年の56.1%を頂点として徐々に下がっている傾向にあり、ここ数年でようやく5割を超えるまでに回復した、というのが実状です。
また、世界各国と比較しても、日本の有給休暇取得率の低さは際立っています。
例えばブラジル、フランス、スペイン、ドイツについては支給日数が「30日間」と日本よりも多いのにも関わらず、取得率は100%。支給日数が同じ20日間であるニュージーランドやインド、オーストラリアについてもいずれも取得率は7割を超えており、日本よりも高い結果となっています。
そして昨今、人材不足が深刻化していくのに比例するように、パワーハラスメント等の各種ハラスメントや過労問題などの労働環境に関する問題への風当たりも強くなってきました。
「有給休暇の取得率の低さ」の是正もまた、政府にとっても企業にとっても至上命題となり、「働き方改革関連法の改正」の一部分という形で具現化するに至ったのです。

有給休暇の義務化について具体的に説明すると、「法定の年次有給休暇付与日数が10日以上」の労働者すべてに対して、企業側が最低でも年5日の有休を取得させなければいけない、ということになります。
まず重要なのは、義務化の対象となっているのが「法定の年次有給休暇付与日数が10日以上」の労働者である、という点です。
つまり対象となっているのは「正社員」だけではありません。
下表の条件を満たした「契約社員」や「アルバイト・パート」も対象に含まれる点に注意が必要です。

有給休暇は、有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に取得させる必要があります。
例えば4月1日に入社した新入社員の場合は、6か月後の10月1日が基準日となり、そこから1年以内つまり翌年の9月30日までの1年間が付与期間となります。
日本では、有給休暇は労働者からの請求により取得手続きがスタートするのが一般的でした。
しかし、有給休暇の義務化に伴い、義務となっている「年5日」までの分については、企業から労働者の意見を聴取した上で、有給休暇を取得する時季を指定しなければなりません。
これを「時季指定義務」といいます。
今回の法改正による有給休暇の義務化に関係なく、従来から有給休暇を5日以上取得させる制度(計画的付与制度)を整えている場合、もしくは新たに計画的付与制度を整備する場合には、時季指定を行う必要はありません(ただし、計画的付与制度の整備には労使協定の締結が必要となります)。
そうでない場合は企業として「時季指定」をしなければいけない、ということを必ず押さえておきましょう。
労働者への意見聴取の方法は、面談やメール、あるいは社内の業務管理システムを介した意思疎通など、任意の方法で構いません。
また、1年間の付与期間中であればどの時期に行なっても問題ありません。
ただし、確実に年5日の有休取得義務が履行されるよう、意見聴取のタイミングには配慮する必要があります。
なお、労働者の方から先に請求があった場合には、その日数分が時季指定義務から控除されます。
有給休暇の取得は基本的には「1日単位」ですが、「半日単位」であっても差し支えないとされています。
この場合、日数は「0.5日」と換算することになります。
ただし、例えば「2時間」など「時間単位」で取得した有休については、義務となる「5日間」の有休にカウントすることができません。
また、すでに決まった有休の日程を事後に変更したい場合には、それが企業もしくは労働者の希望どちらの場合であっても、再度意見聴取の手続きを行うことで、変更することが可能となります。
有給休暇の義務化にともない、以下のような場合には就業規則を改定しなければなりません。
・時季指定を行う必要がある場合には、その方法などについて規定する
・時季指定ではなく新たに計画的付与を行う場合には、その内容について規定する
就業規則を改定する必要がないのは、あらかじめ計画的付与制度を整えている場合のみです。
企業は、有給休暇を付与を取得した基準日、取得日数、実際に有給休暇を取得した日付について明らかにした書類「年次有給休暇管理簿」を、労働者毎に作成し、3年間保存しなければいけません。
ただし、必ずしも紙面で作成しておく必要はなく、必要なときにいつでも出力できるように、システム上で管理する形でも問題ありません。
ここまで、有給休暇の義務化に関する具体的な内容について述べてきましたが、ではもし有給休暇を取得させなかったなどの場合には、どうなってしまうのでしょうか。
具体的には、下表のような罰則が科せられることになります。

なお、罰則による違反は、対象となる労働者1人につき1罪として取り扱われます。
つまり、労働者3人について違反してしまった場合には3つの罪として扱われる、ということです。

最後に、有給休暇の義務化によるメリットとデメリットについて、企業側の視点に立って解説していきましょう。
まず先にデメリットについて述べておくと、有給休暇が義務化されることで、今後は企業内の有休消化率が上昇することにつながります。
すると、企業側としては労働者の働いていない時間に対して支払う給料の金額が大きくなります。
そういった意味で、コストが大きくなるというデメリットが発生します。
このデメリットは、これまでの有休消化率が低ければ低いほど、企業にとって大きな負担となるでしょう。
また、特に規模が小さい企業の場合は、労働者1人が休むことによる企業全体の業務量への影響は大きいでしょう。
場合によっては納期に間に合わなくなるなどの問題が生じたり、あるいは他の労働者への負担が大きくなってしまう、もしくは後日残業などにより対応せざるを得なくなる等の影響も出てしまいます。
有給休暇の義務化が企業にもたらすのは、デメリットだけではありません。
そもそも、労働者にとって休暇は、心身の疲労回復やリフレッシュの効果をもたらし、生活の質を高めてくれるものです。
それにより仕事をするうえでのパフォーマンスも向上することが期待できますし、企業全体での生産性の向上につなげることもできるでしょう。
また、有給休暇の取得率向上は、企業にポジティブなイメージを与えてくれます。
人材不足が加速している昨今、企業のイメージは採用率や離職率を左右する重要なファクターとなっていますから、「義務だから仕方ない」ということではなく、積極的に有給休暇の取得率を上げていくよう取り組むことが望ましいです。

今回は、有給休暇の義務化について、導入の背景やメリット・デメリットも交えて徹底的に解説してきました。
有給休暇の義務化は、正社員であるないに関わらず、「10日以上」の有給休暇を支給される資格のあるすべての労働者に付与されるべきものです。
労働者が「5日」以上の有給休暇を取得できるよう、会社の方から働きかけることを求められるという点で、これまでの有給休暇に対するイメージからは大きく変化しています。
もちろん、労働者が有休を取得することでコスト面でのデメリットがあるかも、と危惧する気持ちを持つのは、企業経営者の立場からいえば致し方ないことといえます。
しかし、労働者がしっかりと休みをとり心身をリフレッシュすることは、ひいては会社全体の生産性向上にもつながる、という意識を持って、積極的に有給休暇の義務化に取り組んでいくと良いでしょう。
画像出典元:pixabay、Unsplash、Pexels 、O-DAN

【2023年最新】賞与に必要な手続きと社会保険料の計算方法を簡単解説

社員管理とは?従業員管理のコツやメリット、おすすめ管理システムも

労務費とは?人件費との違いや計算方法・内訳・労務費率をサクッと解説

SmartHRとジョブカン労務HR徹底比較!料金・機能・使いやすさでわかる違いとは?

人事労務管理とは?担当者が知っておくべき違いや業務内容を詳しく解説
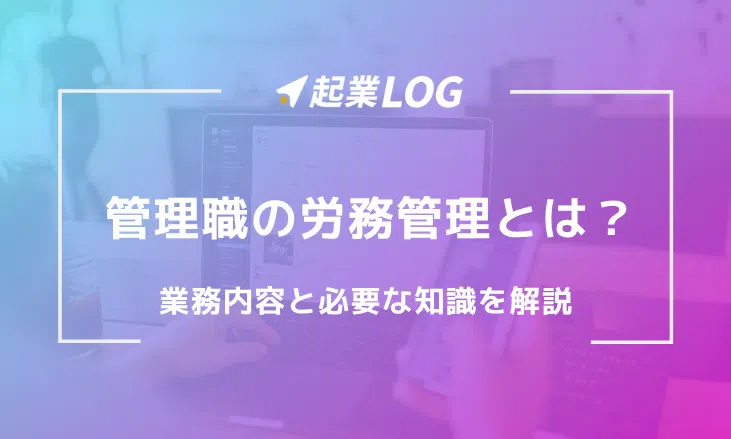
管理職の労務管理とは?業務内容と必要な知識を解説

労務管理システムとは?導入メリットや自社に合った選び方を解説

所定労働時間と法定労働時間とは?違いや残業代について簡単に解説

労務とは?人事との違いや社内での役割・仕事内容を大公開!

就業規則を変更する!変更が必要なケースと手順とは?