
従業員の福利厚生の一環として、社食の導入を検討している企業は多いのではないでしょうか。
社食には様々な種類があり、自社に合った種類・サービスを導入することで従業員の満足度向上や健康増進を実現できます。
この記事では、「社食とは?」といった基礎知識から、メリット・デメリット、サービスの種類、選び方などを詳しく解説します。
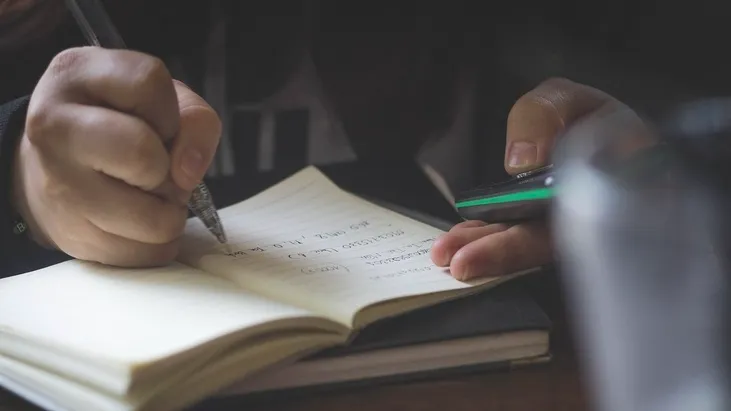
社食とは、企業が従業員向けに提供する食事施設やサービスのことを指します。
かつては食堂スタイルが一般的でしたが、近年は設置型やデリバリー型など様々な形態のサービスが導入されています。
食生活のサポートや健康増進、福利厚生の充実などの目的で導入する企業が多く、コミュニケーション促進や企業への満足度向上などが期待できます。
さらに詳しいメリットや種類に関しては、この後の章で解説していきます。
社食には、従業員側・企業側それぞれにメリットとデメリットがあります。
しっかりと理解したうえで導入を検討しましょう。
従業員側のメリットは、主に以下の点が挙げられます。
社食は、従業員の健康的な食生活をサポートし、休憩時間の有効活用を促せる点が大きなメリットです。
一方で、従業員側には以下のデメリットも考えられます。
メニューが固定されていると、毎日の利用に飽きてしまう可能性があります。
また、時間帯によっては食堂が混雑し、時間に余裕がない場合は不便に感じることもあるでしょう。
企業側のメリットとしては、以下のような点が挙げられます。
基本的には、従業員満足度の向上が企業にもメリットをもたらす、という流れです。
これらのメリットは、結果的に従業員エンゲージメントの向上、健康経営の推進、組織の一体感醸成、そして優秀な人材の確保へとつながります。
一方で、企業側には以下のデメリットも考えられます。
企業にとってコスト面・運営面での負担が増し、規模によっては経営を圧迫する可能性があります。
また、従業員の多様な嗜好を考えると、全員を満足させるメニューを提供し続けるのは難しいという課題も出てきます。

「社食」と聞くと、社内に厨房を設ける「社員食堂」をイメージする方も多いでしょう。
この食堂型は、多額の初期費用や運営費用がかかるため、コストが高くなります。
しかし近年では、より手軽に導入できる新しいサービスが増えています。
本章では、それらの種類と特徴などについて解説します。
| 設置型 | 代行型 | 提供型 | デリバリー型 | |
| 特徴 | 社内に冷蔵庫を設置 | 提携店を利用 | 弁当・惣菜を社内で提供 | 社員が注文した食事を配達 |
| 向いている企業 | 休憩時間がバラバラな企業 | 多様なニーズに対応したい企業 | 食事時間が統一されている企業 | 社内でスペースを取れない企業 |
| メリット | いつでも食事がとれる | 選択肢が多い | 出来立てを提供できる | メニューの自由度が高い |
| デメリット | 出来立ては提供できない | 外出が必要 | メニューの自由度が低い | 対応エリアは限定的 |
| コスト | 低 | 低〜中 | 中 | 中 |
なお、表内のコスト評価は、本格的な社員食堂を「高」とした場合の相対的な目安です。
設置型は、企業が自社内に専用の冷蔵庫を設置し、食事やお菓子などを提供するタイプのサービスです。
時間に関係なくいつでも食事がとれる点や、一食あたりの費用がリーズナブルに済む点などがメリットです。
一方で、出来立ての食事を提供することが難しい、冷蔵庫の設置スペースが必要になるといった注意点もあります。
代行型は、サービス提供側が提携する飲食店やコンビニなどを従業員が安価に利用できるサービスです。
他のサービスと比べて従業員側の選択肢が多いほか、企業側の負担額(福利厚生の範囲)を設定できるのもメリットです。
一方で、外出が必要になるため、社食のメリットがやや薄くなるのはデメリットです。
提供型は、ランチタイムをはじめ、決まった時間に弁当や惣菜などを社内で提供してもらえるサービスです。
社内に設備を儲ける必要がなく、出来立ての食事を提供できる点がメリットで、休憩時間が決まっている企業に最適です。
一方で、メニューの自由度が低いため、満足度が低くなる可能性もあります。
デリバリー型は、社員が各自で注文した弁当や惣菜などが職場に配達されるサービスです。
提供型と同様に設備なしで温かい食事がとれるほか、提供型と比べてややメニューの自由度が高く、それぞれが食べたいものを選択できます。
一方で、対応エリアが限られることや、配達時間に左右される点がデメリットです。
社食サービスを選ぶ際には、押さえておくべき重要なポイントがあります。
自社に合った最適なサービスを見つけるために、しっかり理解しておきましょう。
社食サービスは、大規模な食堂の導入から設備投資のいらないサービスまで、様々な提供形態があります。
形態によって費用面の負担も異なり、食堂を設置するのと設置型サービスでは何十倍ものコスト差があります。
単に高額なサービスを選ぶのではなく、従業員にとってメリットが大きく、かつ自社に合った運用方法・コストのサービスを選びましょう。
社食サービスの運用方法は、導入するサービスによって大きく異なります。
自社で調理スタッフや担当者を置く必要があるケースもあれば、それらが必要ないケースもあります。
実際に運用できなければ意味がないため、必要な人的リソースが確保できるかどうかも、サービス選びの重要な基準です。
社食の導入における最大の目的は「従業員の健康増進・満足度の向上」です。
採用に役立つ見栄えの良い社食を導入しても、実際に働いている従業員が満足していなければ目的は果たせません。
そのため、あらかじめアンケートや食事のお試しなどを通じて従業員のニーズを把握し、それを満たせるサービスを導入することが重要です。
前の章で解説したように、社食サービスは、「設置型」「代行型」「提供型」「デリバリー型」の4種類がおもな選択肢になります。
それぞれにメリット・デメリットがあり、コストはもちろん、運用に必要なリソースも異なります。
事前に調査したニーズとあわせて吟味したうえで、自社に合った種類を選びましょう。

社食サービスの導入は、計画的に進めることで最速で成果を出すことができます。
一般的な導入ステップは以下の通りですが、自社の状況に応じて最適なステップで導入を行いましょう。
まず、福利厚生として、社食や昼食補助が本当に自社に合っているかを検討しましょう。
企業のフェーズや状況によっては、家賃補助や育児関連など他の福利厚生の方が効果的な場合もあります。
社食が最適と判断できた場合は、社内でプロジェクトチームを立ち上げ、予算、対象人数、提供方法などを検討してひとつずつ進めていきます。
社食は従業員の満足度を向上させるための取り組みであるため、ニーズを把握することが非常に重要です。
アンケートやヒアリングを実施し、現状の食事スタイル、希望する種類(デリバリー型、設置型など)やメニューを把握しましょう。
そのうえで、企業側の予算やリソースとあわせて、ある程度制度の枠を明確化していきます。
従業員ニーズの調査結果を念頭に、社食制度の具体的なゴールも設定しておきます。
社食の利用人数や、満足度に関するアンケート項目の検討などを行い、定期的に明確な効果測定ができるようにしておきましょう。
ここでしっかりと評価軸を設定しておかないと、後々の振り返りが難しくなってしまいます。
社食サービスの提供方法や運営方法を決定します。
すでに解説した設置型・代行型・提供型・デリバリー型の中から条件に合った提供方法を選び、さらに細かいオペレーションや担当者などの具体的な部分を決めます。
どのサービスを導入するかを、従業員アンケートの結果や予算などを含めて検討しましょう。
導入する社食サービスの種類や規模に応じて、初期費用や運営費用をシミュレーションします。
人件費、食材費、設備費、委託費用など、必要なコストを細かく洗い出し、予算内で実現可能なサービス内容を検討しましょう。
また、補助金や助成金制度の活用も視野に入れることで、コストを抑えることができる場合があります。
社食の導入は、従業員満足度の向上や健康増進など多くのメリットが得られる取り組みです。
一方で、様々な種類があり、それぞれの特徴を理解したうえで最適なものを選ぶことが成功のためには欠かせません。
まずは自社に社食が必要か、従業員がどんな制度を望んでいるかを調査して、それに合うサービスを導入することが重要です。
画像出典元:O-DAN