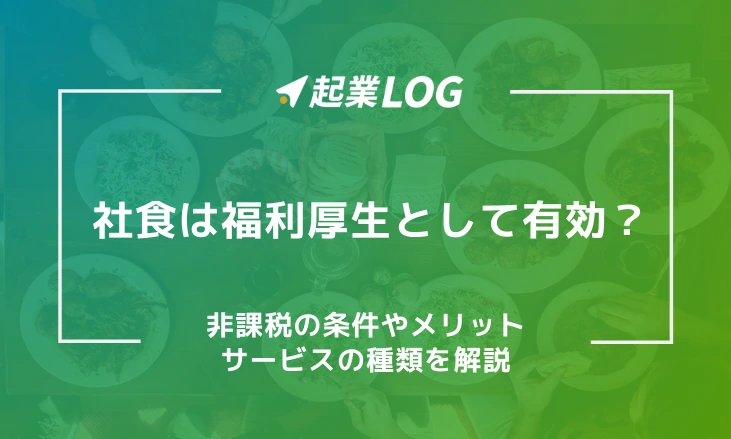
社食は、企業と社員の双方にメリットがある制度として、再評価が進んでいます。
一定の条件を満たせば、社食の費用を福利厚生費として計上することも可能です。
近年は、低コストで導入できるサービスも増えており、中小企業でも取り入れやすくなってきました。
この記事では、福利厚生として社食が注目される理由や導入メリットをわかりやすく解説します。
▼ 社食サービスについて知りたい方はこちらへ ▼
目次

社員の満足度向上や健康支援、離職防止を目的に社員食堂 (社食) の導入を検討する企業が増えています。
しかし、「社食って福利厚生になるの?」「無料にしたら課税対象になるのか?」といった疑問は導入前にしっかり確認しておきたいところです。
実は、社食にかかる費用は、一定の条件を満たしていれば、福利厚生費として処理できます。
主な条件は以下の3点です。
これらの条件のいずれか一つでも満たさない場合、会社が負担した費用は原則として社員の「給与」とみなされ、所得税の課税対象となってしまうため、注意が必要です。
では、それぞれのポイントをもう少し詳しく見ていきましょう。
社食を福利厚生費として計上するためには、すべての従業員に対して、利用の機会が公平に提供されなければなりません。
本社に勤務する正社員のみが対象など、一部の従業員しか利用できない場合は「給与」とみなされる可能性が高まります。
この公平性は、食事補助に限らず、あらゆる福利厚生に共通する基本的な考え方です。
会社が食事代を全額負担してしまうと、給与とみなされてしまう可能性があります。
非課税の福利厚生とするには、会社が負担する50%以上を社員が自己負担する必要があります。
たとえば、1食の価額が500円の場合、社員が250円(500円の50%)以上を負担していれば、この条件はクリアです。
会社が食事代を補助できる金額には、税法上の上限が設けられています。
福利厚生費として非課税で計上できるのは、会社の負担額が1ヶ月1人あたり3,500円以下の場合です(消費税および地方消費税の額を除く)。
もし、上限を超えて会社が補助した場合、超えた部分だけが課税されるのではなく、その月の補助額すべてが給与として課税対象となってしまいます。
なお、現在、この月額3,500円という基準については、物価上昇に対応するための見直しが進められており、6,000円ほどへの引き上げが検討されています(2025年7月現在)。
なぜ今、社食が注目を集めているのでしょうか?
その理由として、以下のような社会的・経済的な流れが挙げられます。
健康への意識は年々高まっており、社員の健康管理は企業にとっても重要な経営課題です。
健康経営という言葉も浸透し、社員の体調管理は生産性向上に直結すると認識されています。
外食やコンビニ弁当ばかりでは栄養が偏ってしまいますが、社食であれば栄養バランスのよい食事を提供することが可能です。
リモートワークやフレックスタイム制の普及により、社員がオフィスに集まる機会や、同僚と食事をとる機会が減りました。
そんな中、社食は部署を越えたコミュニケーションやチームの一体感を促す場として再評価されています。
物価高騰は、社員のランチ事情にも大きな影響を与えています。
このような状況下で、社食は社員の食事代を目に見える形でサポートできる福利厚生です。
また、企業にとっても、社員の満足度向上と福利厚生の効果を両立できる有効な手段として、価値が再認識されています。
福利厚生の充実は、採用活動において、他社との差別化になります。
中でも社食は、求職者への訴求力が高く、社員の健康と働きやすさを追求する企業であるといったメッセージを発信できます。
また、戦略的に運営できれば、社員の満足度を大きく引き上げ、生産性向上や定着率改善にもつながる重要な要素です。

ここでは、社食を福利厚生として導入することで、企業が得られる具体的な4つのメリットを紹介します。
社食が利用できれば、昼食の準備や外出に費やす時間と労力を省けるため、社員は休憩時間をうまく活用できるようになります。
また、健康を意識したバランスの取れた食事を手軽にとれるようになり、午後の業務へのモチベーションや集中力が高まります。
結果として、社員の満足度や組織全体の生産性向上につながります。
優秀な人材を確保し、企業を成長させていくためには、会社で働くこと自体がメリットと感じられる環境づくりが欠かせません。
社食の導入は、そうした魅力あるオフィス環境の1つとして、働く人にとって大きな価値となります。
特に、バランスの取れた食事を安価に提供できる社食は、日々の生活を支える福利厚生として求職者に好印象を与え、採用活動の競争力を高める要素になります。
また、社員にとっても昼食の心配がいらない職場は働きやすさを実感できるポイントであり、定着率の向上にもつながります。
企業にとって、社員の健康維持は重要な経営課題の1つです。
社食は、栄養バランスの取れたメニューを提供することで、社員の健康をサポートする仕組みにもなります。
長期的な視点で見れば、体調の改善によるトラブルの予防や、体調不良からの早期回復にもつながり、業績や医療コストの抑制にも良い影響をもたらします。
社食は、食事の提供だけでなく、社員同士の自然な交流を促すコミュニケーションの場としても機能します。
ランチタイムの何気ない会話や部署を越えた交流が、チーム間の連携強化や情報共有の促進へとつながるのです。
また最近では、社員食堂を懇親会やイベントのスペースとして活用する企業も見られます。
▼社食サービスをもっと知りたい方はこちらをご覧ください▼
社食は魅力的な福利厚生ですが、導入後に「こんなはずじゃなかった!」とならないよう、事前に知っておくべき注意点があります。
ここでは、導入後の運用やコストに関する具体的な懸念点について解説します。
せっかく社食を導入しても、利用されなければ意味がありません。
そのためには、導入前後の工夫がとても重要です。
具体的には、導入前にどんなメニューが求められているかなどをアンケートで確認することから始めましょう。
また導入後は、全社員に利用の方法やメリットを分かりやすく伝えたり、社員からのリクエストを反映させたりすると、飽きずに利用してもらえるようになります。
社食サービスの種類によって、オフィス内で食事をするスペースや、サービスに必要な設備を置く場所を確保する必要があります。
また、社員がリラックスして食事ができるテーブルや椅子、ゴミ箱などが整備されているかどうかも利用率に影響するため、とても重要です。
オフィスに勤務する社員だけでなく、多様な働き方をする社員にも公平にメリットを提供できるかを検討しましょう。
たとえば、リモートワーク社員には、自宅に食事が届くデリバリー型の社食などが適しています。
また、複数のサービスを組み合わせて導入し、オフィスとリモートワークの社員をカバーするのも一案です。
社食の導入・運用には、設備費や人件費、光熱費など目に見えないコストが発生します。
たとえば、サービスによっては導入時に初期費用や機器の設置費用がかかる場合があります。
また、冷蔵庫や電子レンジを使用する場合の電気代といったランニングコストも考慮する必要があります。
特に注文数と実際の利用数に大きな差が出ると、フードロスによる無駄なコストが発生する可能性があるため注意しましょう。
社食サービスにはさまざまなタイプがあり、それぞれ特徴や費用感が異なります。
ここでは、主な社食サービスを比較していきましょう。
設置型は、オフィス内に専用の冷蔵庫や冷凍庫を設置し、弁当・惣菜・ドリンクなどを常備するタイプの社食サービスです。
社員は好きなタイミングで食事をとることができ、柔軟な働き方にも対応できます。
多くのサービスでは、商品の補充や在庫管理を代行してくれるため、企業側の運用負担が少ないのが特徴です。
メリット
デメリット
代行型は、食事券や電子マネーを支給し、提携する飲食店やコンビニなどを社員食堂として利用できる社食サービスです。
オフィス内にスペースや機材を設置する必要がなく、出社していない社員も利用できます。
最近では、カフェ・定食屋・コンビニ・ファストフードなど、加盟店舗の業態も増えており、社員が気分や好みに応じて自由に選べるようになっています。
メリット
デメリット
デリバリー型は、決まった時間にオフィスへお弁当を配達してくれる社食サービスです。
また、販売員が対面で販売してくれるタイプもあります。
温かい状態で食事を届けてくれるサービスが多いのが特徴です。
メリット
デメリット
提供型は、つくり立ての食事をケータリング形式で決まった時間に提供する社食サービスです。
調理スペースは不要で、会議室や休憩室などを活用できます。
社員が同じ時間に集まるため、自然な交流が生まれるのも特徴です。
メリット
デメリット
| 設置型 | 代行型 | デリバリー型 | 提供型 | |
| 初期費用 | 1万円~10万円ほど(冷蔵庫などの設置費用を含む場合あり) | ほとんどかからない場合が多い | ほとんどかからない場合が多い | ほとんどかからない(スペース準備のみ) |
| 月額費用 | 5,000円~5万円ほど(基本料金+利用量に応じて変動) | サービスによっては月額利用料あり | 最低注文数が設定されている場合がある | 利用する人数や提供の回数に応じて変動 |
▼ 社食サービスをもっと知りたい方はこちらもご覧ください ▼

社食サービスを検討する際によく聞かれる質問をまとめました。
あなたの疑問もここで解決するかもしれません。
サービスを選べば、少人数の会社でも導入が可能です。
設置型の社食サービスには利用数に応じた柔軟なプランが用意されています。
まずは、気になるサービスの資料を取り寄せて、自社の人数規模に合ったプランがあるか確認してみましょう。
社食サービスの運用にかかる手間は、選ぶサービスの種類や提供会社によって異なります。
特に設置型の社食サービスは、サービスを提供する会社が商品の補充や賞味期限の管理などを行うため、担当者の手間は少ないです。
一方、デリバリー型では注文の取りまとめなどの運用管理が必要な場合もあります。
導入する前に、各サービスのサポート体制について詳しく確認しておくことが重要ですし、無料トライアルで試してみるのも良い方法です。
リモートワーク社員には以下のような社食サービスが適しています。
また、オフィスとリモートワークの社員をカバーするには、複数の社食サービスを組み合わせて導入することも効果的です。
社食は、企業にとっても社員にとってもメリットの大きい福利厚生です。
条件を満たせば、企業は費用を経費として計上でき、社員も非課税で補助を受けられます。
加えて、社員の健康促進や採用力アップ、社内の交流促進といった効果も見込めるため、今あらためて注目が集まっています。
「うちの会社でも導入できるのかな?」「どんなサービスが合っているんだろう?」と感じた方は、まずは社員のニーズを把握し、気になるサービスの資料請求や無料相談から始めてみましょう。
画像出典元:Pixabay、Pexels、O-DAN