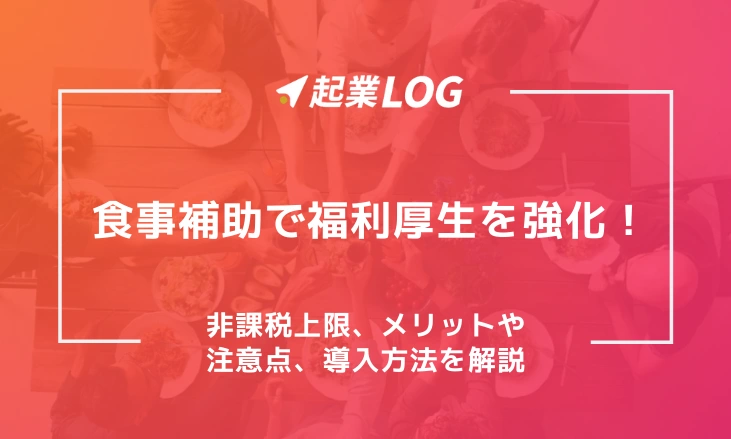
「食事補助」は、従業員の健康促進やモチベーション向上、人材定着や採用活動でのアピールにも役立つ、いま注目の福利厚生です。
さらに国税庁が定める条件を満たせば非課税扱いとなり、企業・従業員の双方に税制上のメリットが生まれます。
本記事では、「食事補助」の非課税ルールや「食事手当」「まかない」との違い、コンビニで使える人気の食事補助サービスについても解説します。
このページの目次

食事補助とは、企業が従業員の食事代の一部を負担する福利厚生制度です。
「健康経営」や「人材定着」につながる施策として、多くの企業が導入を進めています。
食事補助には、給与として課税される「食事手当」や、主に飲食店などで提供される「まかない」とは異なる税務上のメリットがあります。
では、混同されやすいこれらの制度との違いを詳しく見てみましょう。
食事補助と食事手当は、支給する方法と税務上の扱いに違いがあります。
食事補助
食事手当
夜勤などで食事の提供が難しい場合は、例外的に現金支給も可能です。
その場合、1食あたり300円(税抜)以下であれば非課税として扱われます。
食事補助とまかないは、税務上のルールは基本的に同じです。
どちらも国税庁が定める条件を満たせば、非課税として扱われます。
ただし、制度の導入対象や利用できる範囲には違いがあります。
食事補助
まかない
食事補助は、国税庁が定める条件を満たせば福利厚生費として計上できます。
もし、条件から外れると、補助額の全額が給与として扱われ課税対象となるため、導入前の確認が必要です。
では、条件について詳しく見ていきましょう。
食事補助を非課税にするためには、以下の条件を満たす必要があります。
企業が提供する食事の価格(原価)のうち、50%以上は従業員が負担する必要があります。
たとえば、 1食700円の弁当を支給する場合、従業員は350円以上を負担しなければなりません。
企業が従業員1人あたりに補助する金額の上限は、1ヶ月3,500円(税抜)までです。
もし企業の補助額が3,500円を超えた場合、超えた分だけでなく補助した金額の全額が給与として課税対象になります。
たとえば、月4,000円を補助した場合は、4,000円全額が課税対象となるので注意が必要です。
実は、月3,500円という非課税の上限額は、1984年の物価水準をもとに設定されたものです。
その後40年以上が経ち、物価や食費が大きく上昇しているにもかかわらず、上限額は据え置かれています。
このため近年では、非課税限度額を6,000円以上に引き上げるべきだという議論も出ています。
もし上限が引き上げられれば、従業員の負担軽減だけでなく、企業の健康経営推進や飲食業界の需要拡大にもつながり、社会全体にメリットが循環すると期待されています。
参考:食品産業新聞社ニュースWEB 経産省が「税制改正要望」に食事補助制度の見直しを明記

食事補助は、企業と従業員の双方にとって大きなメリットがある、費用対効果の高い福利厚生制度です。
ここでは、それぞれの立場から具体的なメリットを解説します。
従業員の健康は、企業の生産性に直結する大切な経営資源です。
食事補助を通じて栄養バランスの取れた食事を提供すれば、従業員の健康維持をサポートできるだけでなく、食生活への意識を高めるきっかけにもなります。
結果として、欠勤率の低下やパフォーマンスの向上にもつながります。
福利厚生は、就職や転職の際に重要視される要素の一つです。
中でも食事補助は、従業員が日常的に利用できるため、恩恵を実感しやすい制度といえます。
継続的に利用できる仕組みは従業員満足度を高め、離職防止にもつながります。
さらに従業員の健康や働きやすさを大切にする企業として、求職者に良い印象を与えるため、採用活動における強力なアピールポイントとなるでしょう。
非課税の条件を満たした食事補助は、福利厚生費として経費計上できるため、企業の法人税の課税所得を減らすことが可能です。さらに、食事補助は給与に加算されない非課税扱いとなるため、企業が負担する社会保険料を増やすことなく、従業員へ還元できます。
食事補助を利用することで、外食やコンビニ弁当に比べて月々の食費を大幅に抑えられます。
たとえば、オフィスに設置した冷蔵庫や冷凍庫で提供される設置型サービスでは、1食100円〜で栄養バランスの取れた食事を利用可能です。
外食で毎日700〜1,000円かかる場合と比べると、1か月で約12,000〜18,000円も節約できる計算になります。
一人暮らしや外食が中心で栄養が偏りがちな従業員も、食事補助を活用すれば手軽に必要な栄養をとることができます。
食事補助のサービスには、不足しがちな栄養素を補える商品や、栄養バランスの良い商品も豊富です。
バランスの良い食事は、午後の業務パフォーマンスの向上だけでなく、生活習慣病の予防や健康維持にもつながります。
お弁当のデリバリーやオフィス設置型の食事補助を利用すれば、外に出て飲食店を探したり、混雑した店内で待ったりする時間を節約できます。
ランチタイムにゆとりが生まれ、午後の仕事をより効率的に進めることが可能です。
また、忙しいときやコンビニに行くのも面倒な場合にも、社内で手軽に食事を済ませられます。
▼ 社食サービスについて詳しく知りたい方はこちらもご覧ください ▼
企業の規模や働き方の多様化に合わせ、さまざまな食事補助サービスが登場しています。
かつて主流だった社員食堂だけでなく、手軽に始められる「オフィス設置型」や、公平に従業員へ福利厚生を届けられる「食事券・カード型」など、選択肢は豊富です。
ここでは、主な食事補助の提供方法について、特徴やメリット・デメリットを解説します。
オフィス内に冷蔵庫や専用の什器を設置し、惣菜・おにぎり・サラダなどを常備しておく方法です。
大規模なスペースは不要で、調理スタッフもいりません。
メリット
デメリット
▼ オフィス設置型ならこちらがおすすめ! ▼
提携する弁当業者が、毎日決まった時間にオフィスへお弁当を届けてくれるサービスを利用する方法です。
事前にオンラインなどで注文する形式が一般的で、できたての温かい食事を食べられます。
メリット
デメリット
▼ 宅配弁当・デリバリー型ならこちらがおすすめ! ▼
全国のコンビニや主要なチェーン店などで利用できるチケットや専用カードを従業員に配布する方法です。
従業員1人から利用できるため、中小企業やスタートアップも導入しやすい食事補助となっています。
メリット
デメリット
▼ 食事券・カード型ならこちらがおすすめ! ▼
企業が自社内に専用の厨房と食事スペースを設け、従業員に食事を提供するスタイルです。
大規模オフィスや工場で導入されるケースが多く、昔からある食事補助の代表例です。
運営は自社で行う「直営方式」と、外部に委託する「準直営方式」があります。
メリット
デメリット
▼ 社員食堂の導入コストについて詳しく知りたい方はこちらもおすすめ! ▼

食事補助にはさまざまな種類があり、自社の状況に合わないサービスを選んでしまうと「誰も利用しない」「管理が大変」といった事態に陥りかねません。
導入を成功させるために、以下の3つのポイントで自社に最適なサービスはどれか、比較検討しましょう。
従業員数や勤務形態など、自社の状況に応じて最適なサービスを選ぶことが重要です。
たとえば、従業員数が少ない企業やリモートワーカーが多い場合は、公平に利用できる食事券・カード型が適しています。
逆に、オフィスへの出社率が高いなら、コミュニケーションの活性化にもつながるオフィス設置型や宅配弁当型もおすすめです。
福利厚生は、導入時だけでなく、その後の管理担当者の負担も考慮することが大切です。
食事券・カード型はWeb上で管理が完結するため手間が少ない一方、宅配弁当型は毎日の注文管理が発生する場合があります。
自社のリソースで無理なく運用できるか、管理システムの使いやすさやサポート体制を確認しましょう。
制度を導入しても、従業員に使ってもらえなければ意味がありません。
メニューの選択肢は豊富か、オフィスの近くに利用できる加盟店はあるかなど、従業員の目線で評価することが重要です。
オフィス設置型や宅配弁当・デリバリー型を検討する際は、メニューの豊富さや、試食が可能かどうかを確認しましょう。
事前に従業員へアンケートを実施し、どのような食事補助を求めているかニーズを把握することも大切です。
▼人気のサービスを比較したい方はこちらもご覧ください ▼
では、ここで食事補助を導入した会社の例をいくつかご紹介します。
会社概要と食事補助の内容をまとめましたので、「会社の特色」と「食事補助」をどう掛け合わせているかに注目してください。
IT・医療・介護などの事業を展開するレバレジーズ株式会社では、食事補助制度「レバカフェ」が人気です。
無料のコーヒーや白米に加え、栄養バランスの良い惣菜も手頃な価格で購入でき、従業員の声を反映してメニューが更新されるのが特徴です。
こうした取り組みにより、従業員同士が自然にコミュニケーションを取るきっかけが生まれ、仕事中のちょっとした息抜きや交流の場としても活用されています。
レバレジーズの食事補助制度は、福利厚生を通じたコミュニケーション促進やエンゲージメント向上にもつながる好事例といえます。
Looopは、再生可能エネルギーを扱う会社です。太陽光発電所システムや電力小売り事業を手がけており、その特質から従業員のワークスタイルは外回りが中心になっています。
そんなLooopが導入したのはチケット型の食事補助!外回りの際に好きなお店・好きなタイミングでチケットを使えるため、任意加入だったにも関わらず、導入から1カ月でほとんどの従業員が加入したのだとか。
チケット・クーポンを支給する食事補助と、外回り中心の会社はマッチしやすいことが分かる、いい例ではないでしょうか。
歴史の長い生命保険会社の1つ、明治安田生命。保険サービスを展開している明治安田生命には「社員食堂」があるのですが、こちらの食堂が大変評判になっています。
食堂には約10mにも及ぶ吹き抜けがあり、清潔感に包まれた空間が魅力的!メニューは食堂の管理栄養士が計画・作成し、従業員の好みを取り入れながらメニューに飽きてしまわないよう工夫されています。
内勤メインの会社である場合、社員食堂の導入を検討するかと思います。社員食堂を導入する際は、明治安田生命のように空間と食事の内容どちらにも配慮し、心地よい空間を作ることが大切です。
参考:明治安田生命新東陽町ビル
▼ 社食サービスの資料を一括請求したい方はこちらから! ▼
▼ 社食サービスについてもっと知りたい方はこちらもご覧ください ▼
本記事では、多くの企業で導入が進む福利厚生「食事補助」について解説しました。
課税対象となる食事手当の現金支給と異なり、国税庁が定める「月3,500円の上限」と「従業員負担分の給料天引き」という条件を満たすことで、非課税メリットを得られるのが特徴です。
また、コンビニなどで使える食事券タイプからオフィス設置型まで、さまざまなサービスも登場しています。
この機会に、自社に最適な福利厚生として食事補助の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
画像出典元:o-dan