
株式会社クリスクアジア 取締役 金城 弘二郎氏
日本政府観光局の発表によると、2025年8月の訪日外国人旅行者数は342万人を突破。インバウンド需要は急速な高まりを見せています。その一方で、深刻化する少子高齢化は、国内市場の縮小に直結しています。日本企業にとって、海外マーケティングの強化はもはや必須といえるでしょう。
しかし、国内市場に精通したマーケターであっても、既存の手法をそのまま持ち込んで失敗するケースは少なくありません。
国内のノウハウが通用しないグローバル市場で、企業はどのような戦略を描くべきなのでしょうか。今回、海外マーケティングを専門とする株式会社クリスクアジア 取締役の金城 弘二郎氏に、その具体的な手法について詳しく伺いました。
目次
[PR]

──国内マーケティングと海外マーケティングの手法では具体的にどのような点が異なるのでしょうか?
根本的な違いは、大きく分けて3点あります。
まず第一に、文化的背景や価値観です。言語は当然として、宗教観や国民性、価値観が根本から異なります。これにより、同じ商品でもターゲット国によって「価値の感じ方」が全く変わってくるため、国内と同じインサイト分析は通用しません。
第二に、購買行動のパターンです。 特にインバウンド領域では、顧客のフェーズが「旅前・旅中・旅後」で明確に分かれます。
フェーズごとに顧客が求める情報やタッチポイントは変化するため、企業側が提供すべき訴求内容もフェーズに応じて最適化する必要があります。
国内の購買行動と訪日旅行者の購買行動のパターンは、当然ながら異なります。この認識の欠如も失敗につながる大きな要因です。
そして第三に、主要なプラットフォームです。日本ではX(旧Twitter)がリーチを多く獲得できる媒体ですが、国が変われば主流のSNSは全く異なります。タイではFacebook、次にTikTok、インドネシアではInstagram、中国ではWeChat(微信)や小紅書(RED)、抖音(Douyin)といった具合です。使用プラットフォームが違えば、当然「伝え方」が変わるため、媒体に合わせた最適化が必須となります。
──各国でSNSの投稿内容も異なる印象があります。
そうですね。たとえば、日本の場合は世界的に見ても特殊で、匿名性が好まれる傾向にあります。キャンペーンの当選者発表一つをとっても、アカウント名の公表は好まれません。実際にSNSのキャンペーンを見ると、当選者の発表はDM(ダイレクトメッセージ)を通じた個別で連絡されるケースがほとんどです。
しかし、タイでは真逆の対応が求められます。当選者のFacebookアカウント名を公式ページで公表し、本人からの連絡を促す方式が主流です。
このように、国民性によってSNSの「あり方」自体が異なるのです。
──プラットフォームの特性のみでなく、文化的背景や価値観についての深い理解が必要ですね。
おっしゃる通りです。これらの本質的な差異を把握せずに国内の成功体験をそのまま持ち込んでも、そもそも情報がターゲットに届きません。
ターゲットが外国人である以上、「日本人の延長」という考え方で進めるべきではありません。
「外国人の視点」を中心とした発想転換が前提となります。
自社やサービスの価値を「伝わる」ようにするためには、現地の目線や価値観を捉え、表現を変えたり、訴求する角度を変えたりすることが不可欠です。単に「伝える」のではなく、「伝える」と「伝わるものを作る」をセットで考える必要があります。
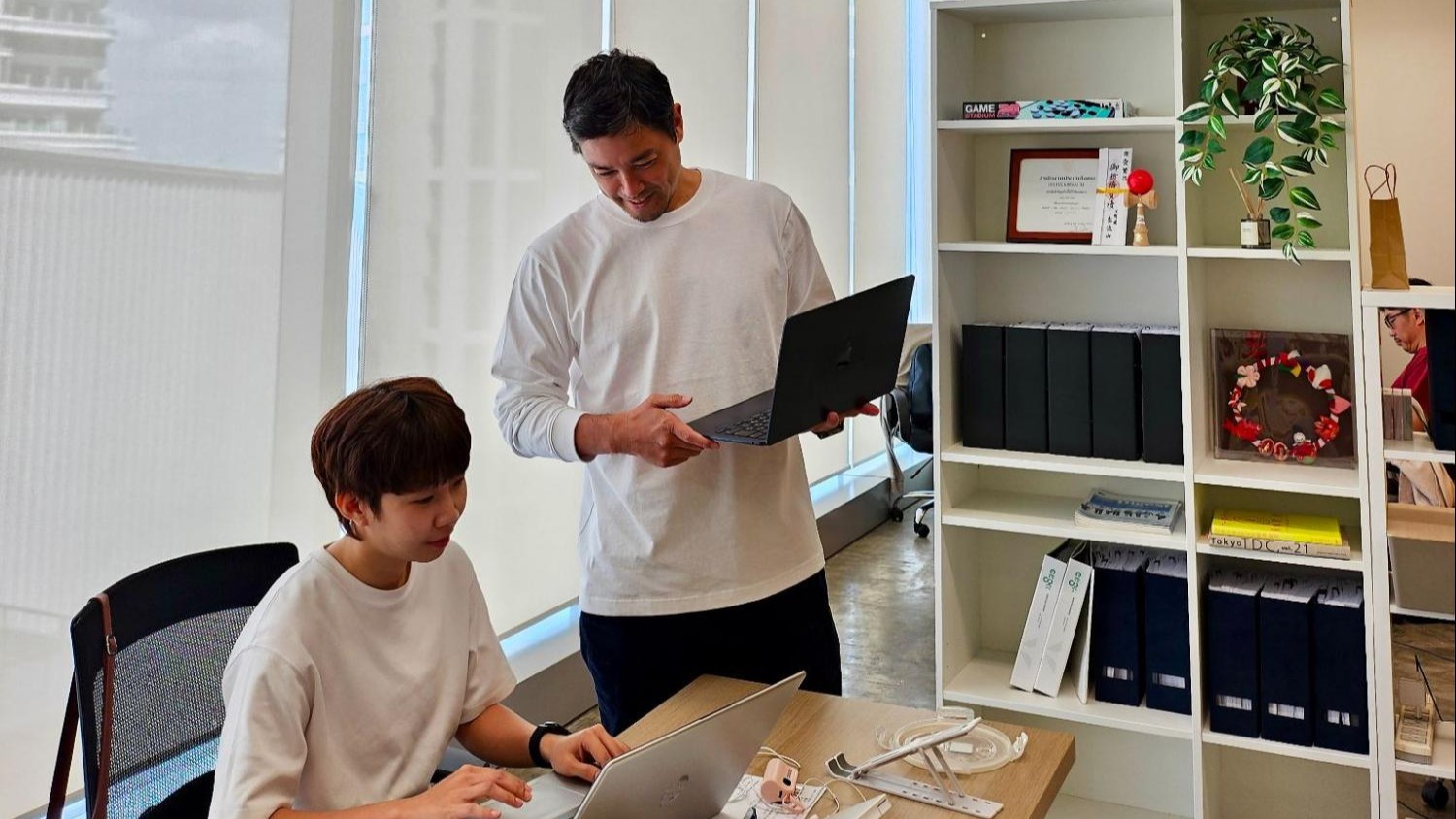
──国内と海外では、顧客インサイトや文化的背景が根本的に異なると理解できました。そうした現地の特性を把握しきれないまま進めると、どのような「失敗」につながるのでしょうか?「失敗パターン」を教えてください。
まず、日本国内で反応の良かった広告コピーを「ただ翻訳してそのまま出稿する」パターンです。
機械翻訳はもちろん、単純な直訳では、その国が持つ独自の文化や絶妙な言語的ニュアンスを反映できません。現地の生活者のインサイト(深層心理)を捉え、感情に訴えかけなければ、期待するエンゲージメントを獲得できないのです。
その結果、盛り上がりに欠け、何の成果も得られないままプロモーションが終了する。そのようなケースは少なくありません。
次に、「オーガニック投稿だけでリーチしようとする」パターンです。
国内で高い認知度を持つブランドの場合、オーガニック投稿でもある程度の拡散が見込めます。しかし、海外市場では日本ほどの認知がないケースがほとんどであり、同様の拡散は期待できません。
そのため、初期段階においては、明確なターゲットにリーチできる広告配信や、現地のインフルエンサーとタイアップし、戦略的に初期認知を獲得する取り組みが不可欠です。
この初期戦略を設計せず、ただ良質なコンテンツ制作にリソースを投下するだけでは、投資対効果(ROI)が見合わず、プロジェクトが頓挫してしまいます。
最後は、「ジャパンブランドへの過信」です。
私が海外市場に関わり始めた10年以上前は、確かに「メイドインジャパン」や日本のブランドに対する信用は非常に高く、特に東南アジアでは絶大な信頼がありました。「日本でNo.1」と謳うだけで一定の信頼が得られた時代でした。
しかし、中国、韓国、欧米諸国の製品・サービスの影響力が飛躍的に向上したことにより、消費者の選択肢は激増しています。その結果、昔の感覚で「日本のブランドだから反応が取れるだろう」と期待しても通用しません。
その商品自体がどう特別なのか、どういった価値があるのかを、論理的・感情的にきちんと説明することが大前提です。「高品質です」といったジャパンブランドに頼った訴求をそのまま使っているだけでは、現在の海外でポジションを確立するのは難しいでしょう。
──海外マーケティング、特に東南アジアにおいてSNS戦略が成功の鍵を握る理由について、日本の消費者との比較も交えながらお聞かせいただけますでしょうか?
東南アジアと日本の市場特性で決定的に異なるのが、SNSの利用時間です。 東南アジアではSNSの平均接触時間が2〜3時間台と長く、いずれの国も日本の約3〜4倍に達しています。※。
さらに重要なのが、「ソーシャルコマース」(SNS経由での購買行動)の活発さです。 データによれば、SNSの口コミを参考に商品を購入する日本の生活者は30%以下なのに対し、ベトナムでは57%、マレーシアでは53%を超えています※。
このようにデータから、購買行動におけるSNSの影響力が、日本市場とは比較にならないほど大きいことがわかります。
※参考:DataReportal(2025年)
インバウンドの場合でも、旅前の情報源として最も信頼されているのはFacebookやYouTubeです。マスメディアによる発信ではなく、友人やインフルエンサーによる「体験コンテンツ」が情報収集の中心であり、カスタマージャーニーの各フェーズでSNSが強い影響力を持ちます。
「誰かが実際に体験したもの」を含めたコンテンツが重要視される。これが、SNSの影響力における日本との大きな違いです。
この特異な市場環境は、インターネットが普及した経緯に起因します。タイでは2012年頃、安価なスマートフォンとプリペイドSIMの普及により、インターネット接続のハードルが一気に下がりました。このタイミングとFacebookの普及が重なった結果、「インターネットユーザーのほぼ100%がFacebookアカウントを持つ」という強固な下地が形成されたのです。
現在、ネット普及率は日本と遜色ない約80%に達しましたが、その基盤は変わりません。日本のFacebook普及率が約13%であるのに対し、タイではMeta(Facebook・Instagram)だけで、ほぼすべてのターゲット層にリーチが可能です。この圧倒的なリーチ力こそが、東南アジア戦略でSNSを最優先すべき明確な理由です。
※参考:DataReportal(2025年)
──東南アジア4カ国にネイティブマーケティングスタッフが在籍されているとのことですが、この体制によって、具体的にどのような戦略や施策が可能になるか教えていただけますでしょうか?
弊社はタイ、ベトナム、マレーシア、インドネシアに専属の現地メンバーを配置しています。彼らはネイティブであると同時に、ほぼ全員が日本への留学や生活の経験者です。日本の文化を深く理解していることが、日系企業のサービスを展開する上で決定的な強みとなります。
これにより、翻訳に留まらず、サービスの理解と現地の視点を併せ持つ、「発想転換」が可能になります。たとえばインフルエンサー施策では、炎上リスクをはじめ、日本側からは見えない現地のリアルタイムな情報をネイティブが把握し、ミスマッチやブランド毀損のリスクを回避します。
また、日本とは異なる現地のカスタマージャーニーを理解しているため、各フェーズに最適化されたコミュニケーションプランの設計・運用も可能です。
この「現地の視点」はSNS以外でも不可欠です。Google検索は東南アジアでシェア95%を占める重要な施策です。しかし、戦略のコアとなるキーワード設計が日本と根本的に異なります。
たとえば、日本では「東京 旅行」といったビッグワードの組み合わせで検索されますが、タイではワンフレーズで検索される傾向があります。現地での実践データを持つメンバーだからこそ、こうしたローカルな特性を的確に把握し、戦略設計に活かせるのです。

──各国に最適化された現地体制が重要なのですね。そうした体制に加えて、貴社が培ってきた「独自のノウハウ」や「強み」についても教えていただけますか?
弊社の強みは、SNS黎明期である15年前から現地で培ってきた実績そのものです。現地の文化や文脈に最適化されたコミュニケーションのノウハウが蓄積されています。
最大の特徴は、各国への施策を「1つの窓口」で一元管理できる点です。通常は各国で代理店を探す必要がありますが、弊社は日本語の窓口一本で対応し、クライアントのコミュニケーションコストを大幅に削減します。
さらに、日本側のディレクターが現地メンバーと連携し、複数国の特性を理解した上でコンテンツの共通化を図るなど、制作コストの効率化も実現します。長年のPDCA実績に基づき、施策実行前に精度の高いシミュレーションをご提示できる点も、専門代理店としての強みです。
また、東南アジアでの実績を基盤に、約3年前に中華圏の専門家が加わりました。さらに欧米も専門パートナーとの協業体制を確立し、訪日上位国すべてへの一括対応が可能です。
──つまり、東南アジアから中華圏、欧米を含む主要国すべてに対し、「現地の視点」を取り入れたマーケティング支援を依頼できるということですね。
はい。成果にコミットしてきた実績と経験はもちろん、そして現地専属メンバーがいることによる「安心感」を評価いただいています。専属メンバーがいるからこそ、提案段階から、各国のメンバーに「この訴求は現地でどう受け止められるか」といった簡易的なヒアリングも可能です。
加えて、専門代理店だからこそ実現できる「柔軟な対応力」も弊社の強みです。現地メンバーの意見を踏まえ「これはポテンシャルが高い」と判断できれば、最低予算に縛られず「まず一度試す」というスピーディな実行が可能です。
 訪日上位国全ての国でのマーケティング支援を実現するクリスクアジア社
訪日上位国全ての国でのマーケティング支援を実現するクリスクアジア社
──柔軟な対応を実現できるのも「現地の視点」を持つ各国の専属メンバーがいるからこそですね。海外マーケティングには、表面的な理解ではなく、現地への深い理解が不可欠であることがよくわかりました。本日はありがとうございました。
画像出典元:O-DAN


“裸眼のVR”で新しいバーチャル表現で池袋のカルチャーとコラボレーションするkiwamiの取り組みとは

日本のHR市場がこれから目指すべき、TalentXが描く「タレント・アクイジション」の世界
TalentX代表 鈴木貴史氏

「上場=目的達成のための手段」Kaizen Platformの創業者が語る“上場”とは

ビジネス書大賞『売上最小化、利益最大化の法則』の作家に聞く 「利益率29%の⾼収益企業を作る方法」

資金調達に新しい選択肢を。ブリッジファイナンスとしてのファクタリングを「PAY TODAY」が解説

【令和の渋沢栄一になる】エンジェル投資で日本にイノベーションを

米国新興市場上場を経て10億円を調達 「代替肉」で社会課題に取り組むネクストミーツの歩み

海外で活躍する女性起業家の実態 〜2児のママがシンガポールで起業した理由とは?株式会社ハニーベアーズ〜

湊 雅之が見る欧米と日本のSaaS業界の違い | 注目海外SaaS 6選
BtoB/SaaSベンチャー投資家 湊 雅之

広告事業だったのにコロナ禍で売り上げ上昇! 〜売り上げ90%減からの巻き返し〜
代表取締役 羅 悠鴻