TOP > インタビュー一覧 > 起業経験者の「再挑戦」にこそ光を──TOKYO Re:STARTER キックオフレポート

TOKYO Re:STARTER
「TOKYO Re:STARTER」は起業経験者の多様なセカンドキャリアに関する情報発信をすると共に、再起業や転職といったリスタートを目指す起業家を支援する東京都の取り組みだ。
2025年6月14日(土)、東京・有楽町にて開催されたキックオフイベントには起業経験者やこれからの挑戦を志す人々、企業や支援団体の関係者など、100名を超える参加者が集結。初挑戦のサポートではなく、起業経験者の“再挑戦”の支援をあえて掲げるこのプログラムが、なぜ今必要なのか――その問いに答えるかのように、熱気とリアルな言葉が飛び交う一日となった。
本レポートでは、TOKYO Re:STARTERの全体像とともに、当日展開されたパネルディスカッションやリバースピッチを通じて語られた「挑戦と失敗、そして再出発」の実像を紐解いていく。
目次

イベント冒頭に登壇したのは、TOKYO Re:STARTER事務局の株式会社ガイアックス 田村 悠馬氏。自らも起業を経験した”リスターター”である田村さんは、この取り組みに込めた想いを、自身の経験を交えながら語った。
田村:創業支援は全国的に増えていますが、初めての挑戦でうまくいく人はごくわずか。多くの人は、失敗と再挑戦を繰り返しながら成長していく。そんな起業経験者たちの“次の一歩”や“起業経験の価値”に、もっと光を当てたいと思ったんです。
TOKYO Re:STARTERでは、再起業に挑戦したい人を対象とした「アクセラレータープログラム」に加えて、再起業検討層や起業経験を活かして別のキャリアを築こうとする人たちがつながる場としての「コミュニティ」も提供される。
アクセラレータープログラムについてはこの日から募集を開始したことがアナウンスされた。本プログラムは事業アイデアが固まっていなくても応募できる柔軟な設計となっており、「再挑戦したい」という意志そのものが歓迎される。
またコミュニティの取り組みとしては、起業経験者同士が出会い、情報交換ができる交流イベントが7月から月に1回程度開催される予定であることが発表された。
TOKYO Re:STARTERについての最新情報はこちらから

「失敗をどう乗り越え、次の挑戦へと変えていくか」。
そんなテーマで行われたパネルディスカッションには、異なるフィールドで挑戦する2人の起業家が登壇した。
ひとりは、音声配信サービス「Voicy」を立ち上げた株式会社Voicy代表取締役CEO 緒方 憲太郎氏。もうひとりは、研究者として大学に籍を置きながら、昆虫食のスタートアップを立ち上げ、惜しくも倒産を経験した徳島大学バイオイノベーション研究所・講師 渡邉 崇人氏。モデレーターは、TOKYO Re:STARTER事務局の株式会社ガイアックス 亀岡 愛弥氏が務めた。
外部の意見に振り回され、自分のやり方を通すことができずに逆に組織運営が難しくなってしまった事例や、思いがけない外的要因で事業を閉じる決断に至った失敗経験が語られた。
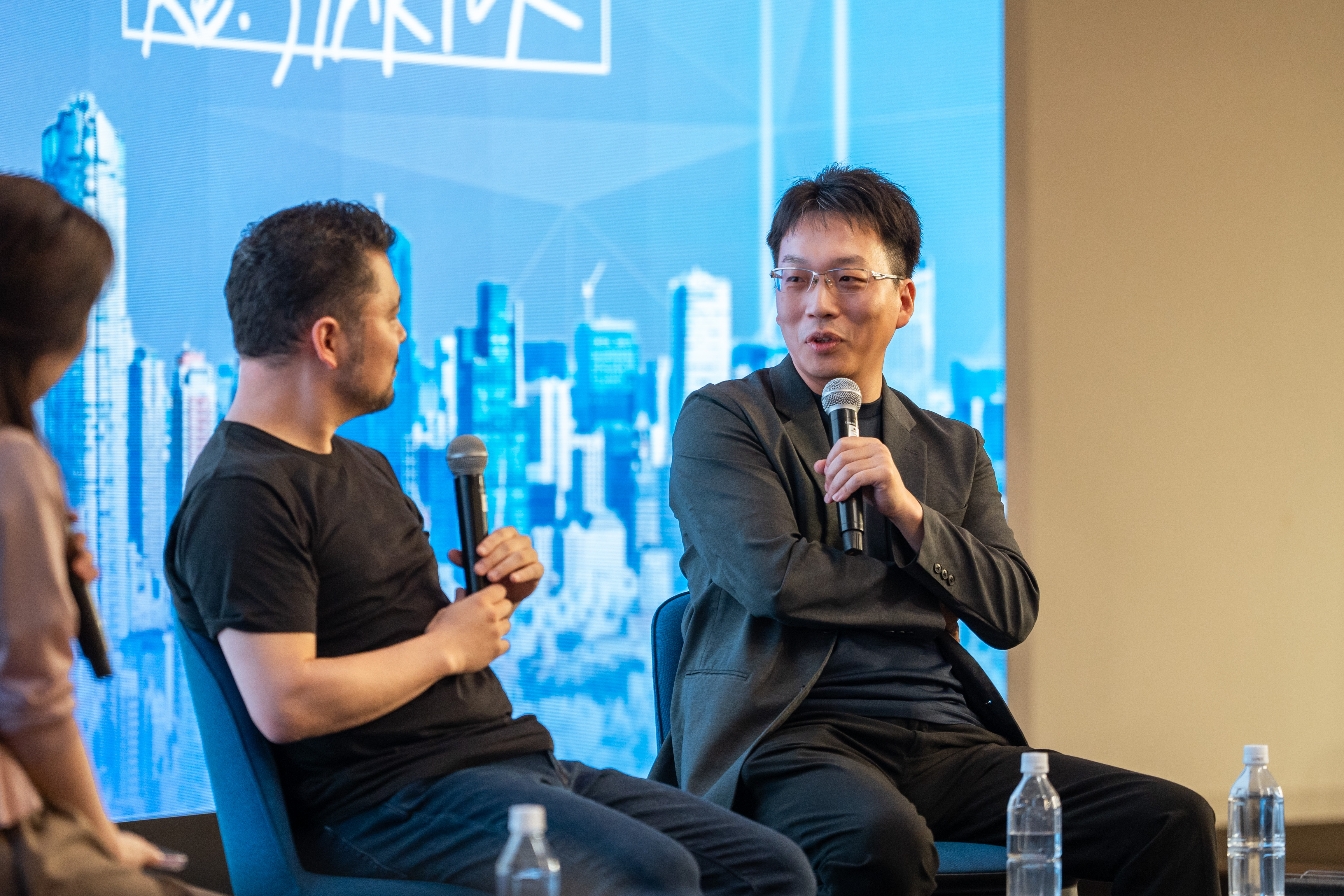
一方で、失敗そのものではなくそのあとどうしたかということも話題に上がった。
「撤退」や「倒産」という決断に向き合う中で問われたのは、「どう終わらせるか」という姿勢だったという。誠実に事業に向き合い、ちゃんとやっていればいくらでも次のチャンスはある。その”次の一歩”を踏み出すためには終わり方も大事という言葉には実感のこもった重みがあった。
語られたのは、「失敗しても、終わりじゃない」という単純なメッセージではない。
むしろ、失敗のあとにどう向き合い、その経験をもとに事業やキャリアをどう再構築していくのか。その過程にこそ挑戦の本質があるということ。登壇者の言葉には、自身の挑戦のプロセスを丁寧に振り返ってきたからこそ滲み出るリアルがあった。

パネルディスカッション後半のテーマは、「起業家としてのメンタルマネジメント」。
経営や起業という営みが、極めてパーソナルで孤独な戦いであることはこれまでも多くの人の口から語られてきた。では失敗や撤退が視野に入ったとき、プレッシャーが極限まで高まったとき、いかに心を保ち、前を向き続けるか。それぞれの経験をもとにしたリアルな話に、会場では誰もが息を詰めるように耳を傾けていた。

重要なのは、事業の困難の原因を「スキル不足」として捉えるスタンスだという。現状に対して過度に感情的にならず、冷静に受け止めることで足りなかった点が見えてくる。「今の自分にとっては難易度が高くてできなかっただけ」と考えることで、必要以上に自分や他人を責めることもなくなる。
また、自分への期待値が高すぎることが苦しさにつながるケースも多い。だからこそ、「自分は思っているより優秀ではない」と一度引いた目で自分を見ることが気持ちを整える助けになると語られた。
そして何より、「失敗は学びのきっかけであり、次に挑戦しなければ本当の意味では学びにならない」という前向きな姿勢。逃げず、誠実に対応することで再起の可能性が開ける――そんな、地に足のついた知恵が交わされた時間となった。
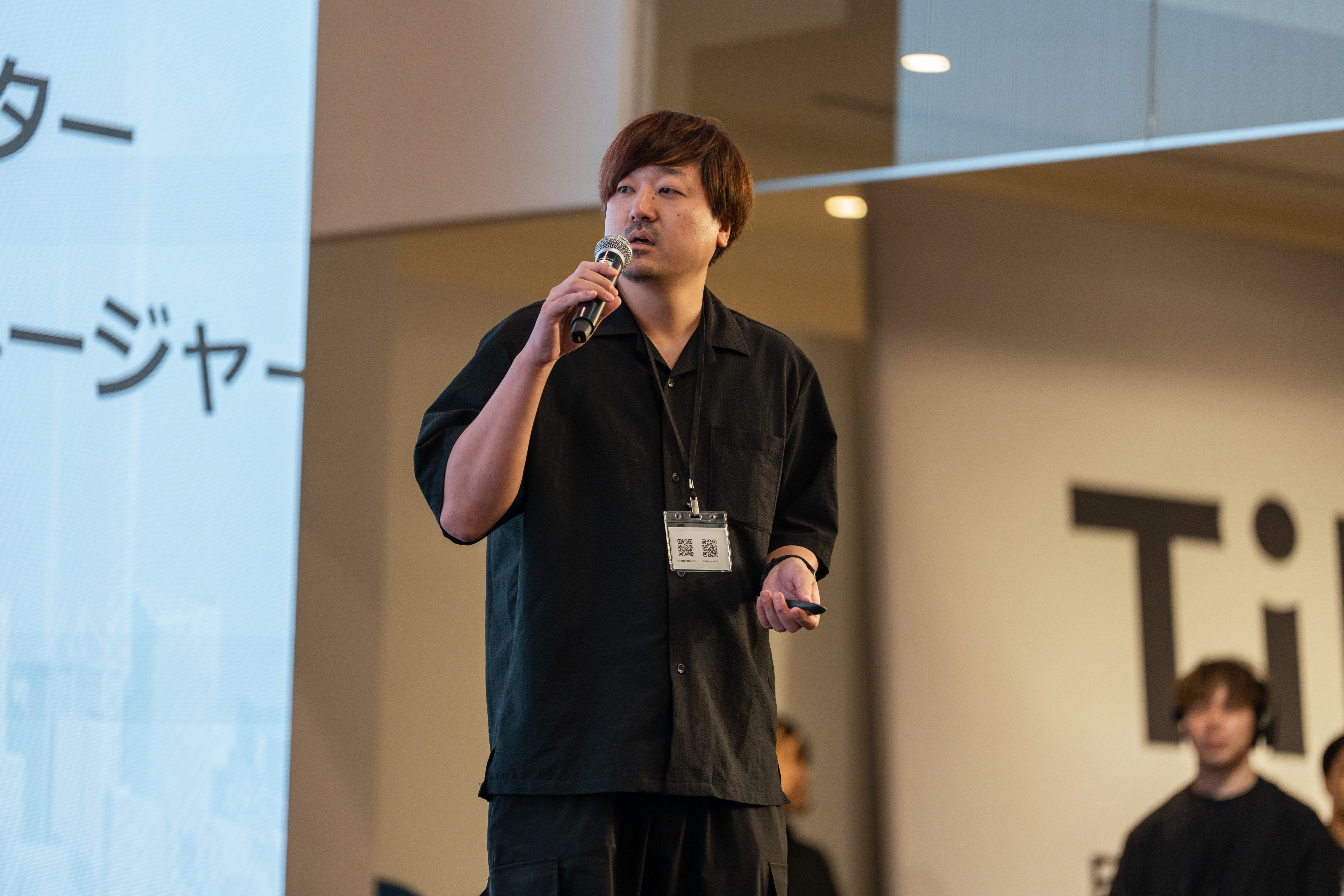
続いて行われたのは、ベンチャーキャピタルや事業会社6社からのリバースピッチ。それぞれの視点から、起業経験者──特に再挑戦を志す人材──の価値が語られた。立場や支援方法は異なるものの、共通していたのは、失敗を含む起業経験は資産であるという確信だ。
一度事業を創った経験がある人は、「うまくいかなかった理由を客観的に分析できる力」や「逆境から立ち上がる回復力」、そして「利害関係者との関係構築力」など、実戦でしか得られないスキルをすでに備えている。こうした能力は、スタートアップに限らず、大企業の新規事業開発や経営層にも強く求められているという。

失敗経験をネガティブに捉えるのではなく、むしろ「次の成功の種」として受け止める姿勢も印象的だった。実際に過去の苦い経験を糧に、新たな挑戦の場で活躍している起業経験者の事例も紹介された。
再起業を後押しするアクセラレータープログラム、さらには起業経験者を企業の中核メンバー候補として迎える採用制度など、起業経験者の再スタートに向けた選択肢は広がっている。
組織やビジネスモデルの変革が求められる今、変化のエンジンとなるのは、まさに起業経験を持つ人材である。そんな期待が登壇者の発言の端々に宿っていたこのピッチは、参加者にとって自身の再起業やキャリアを前向きに再構築するための強い後押しになったはずだ。

TOKYO Re:STARTERのキックオフイベントは、「再挑戦」を軸に、起業経験者、支援者、企業の採用担当者など、多様な立場の参加者が集う機会となった。
一貫して、いわゆる成功談よりも、むしろ失敗や葛藤にどう向き合って次の一手に繋げたかといった実践的な視点が共有された。結果の成否にかかわらず、それをいかに咀嚼し、次のキャリアや行動に結びつけていくかという点に多くの関心が寄せられていたように思う。
イベント終了後も、登壇者と参加者、あるいは参加者同士の間で名刺交換や意見交換が活発に行われていた。再挑戦に関心を持つ人々にとって、この場は単なる情報提供にとどまらず、次に向けた関係性や視点を得るための接点として機能していたのではないだろうか。
今後、TOKYO Re:STARTERでは起業経験者を対象としたイベントや支援プログラムが継続的に展開されていく予定だ。最新情報については公式サイトにて随時更新されていくので、ぜひチェックしてみてほしい。
TOKYO Re:STARTERについての最新情報はこちらから


“裸眼のVR”で新しいバーチャル表現で池袋のカルチャーとコラボレーションするkiwamiの取り組みとは

日本のHR市場がこれから目指すべき、TalentXが描く「タレント・アクイジション」の世界
TalentX代表 鈴木貴史氏

「上場=目的達成のための手段」Kaizen Platformの創業者が語る“上場”とは

ビジネス書大賞『売上最小化、利益最大化の法則』の作家に聞く 「利益率29%の⾼収益企業を作る方法」

資金調達に新しい選択肢を。ブリッジファイナンスとしてのファクタリングを「PAY TODAY」が解説

【令和の渋沢栄一になる】エンジェル投資で日本にイノベーションを

米国新興市場上場を経て10億円を調達 「代替肉」で社会課題に取り組むネクストミーツの歩み

海外で活躍する女性起業家の実態 〜2児のママがシンガポールで起業した理由とは?株式会社ハニーベアーズ〜

湊 雅之が見る欧米と日本のSaaS業界の違い | 注目海外SaaS 6選
BtoB/SaaSベンチャー投資家 湊 雅之

広告事業だったのにコロナ禍で売り上げ上昇! 〜売り上げ90%減からの巻き返し〜
代表取締役 羅 悠鴻