TOP > SaaS AI > SaaSの未来 > 欧州企業で起こったSaaSの解約。AIによるシステム内製化は日本でも起こるのか?

欧州フィンテック大手Klarna(クラーナ)が2024年、主要なSaaSを解約し、AIを活用した自社システムへ移行する計画を発表。この発表はSaaS業界に大きな波紋を広げている。
では、日本でも同様の「SaaS離れ」は加速するのか。本記事では、国内企業のAI導入事例を分析し、その現実的な可能性を探っていく。

Klarnaは、Salesforce(セールスフォース)をはじめとする主要なSaaS契約を打ち切り、AIを活用した自社開発のテクノロジー・スタックに統合。同社はいち早くAIを積極的に導入し、結果として、AIが業務効率化をもたらしている。
顧客とのコミュニケーションにAIアシスタントを活用した結果、わずか1ヶ月間で230万件の会話に対応し、顧客対応業務全体の約3分の2を担うに至った。平均応答時間は11分から2分未満へと大幅に短縮され、再問い合わせ率も25%減少。35言語での24時間対応が実現し、年間4,000万ドル規模の利益改善につながると試算されている。
参考:フルタイムの担当者700人分の仕事量をこなすKlarnaのAIアシスタント|OpenAI
KlarnaのAI内製化という動きは「もはやSalesforceは不要なのでは」という議論を業界に巻き起こした。
この風潮に対し、CEOであるセバスチャン・シェミャトコフスキ氏は2025年3月4日、自身のSNSで「Salesforceの終焉だとは思わない」と否定。同氏は、Salesforceを含む約1,200のSaaS契約を解約した事実を認めつつ、その真の目的を次のように説明している。
シェミャトコフスキ氏は、当初の目的は、SaaSをAIに置き換えることではないと主張。社内に散在・断片化した「知識(データ)」を、AIが最大限に活用できる形に一元化・標準化することこそが狙いであった。AIは断片化された質の低いデータを与えても、質の低い結果しか生まないという問題意識から、同社は独自の技術基盤を構築。その結果として、多くの既存SaaSが不要になったのである。
つまり、データの一元化が目的であり、上述した効率化は副次的なものだったのだ。
この一連の経緯は「Salesforceの終焉」を意図したものではない、とシェミャトコフスキ氏は強調する。
むしろ、今後はSalesforceのような大手SaaSこそが、Klarnaが今回内製したような、情報を集約した「知識のハブ」へと進化する可能性が高いと見ている。
ただし、そのためにはSaaS企業が「AIファースト」の思想に適応し、単なるデータの格納庫(データベース)に留まらない、「意見のあるソフトウェア(Opinionated Software)」としての価値を磨き続ける必要がある、と課題を提示した。

SaaSは役割を変えるが、終焉ではない。AIを最大限活用するには、データの一元化と標準化が不可欠である。その目的において、内製システムは有効な選択肢となる。Klarnaのように内製化へ舵を切る企業は、今後増える可能性が高い。
日本でも、大手企業の中には脱SaaSや内製化を進める動きがある。そうした企業にとって、AI活用を前提とした内製化は現実的な選択肢となり得るのではないか。
そこで、日本国内のAI導入現状を調査した。今回の調査範囲では、SaaSを解約して全面的に内製化した事例は見つからなかった。
しかし、自社開発のAIツールを活用し、業務改善を進めている企業は少なくないことが分かった。以下では、そうした具体的な取り組みの一部を紹介する。
KDDIは、国内でAI導入が本格化する以前の2023年5月、従業員向けAIチャットサービス「KDDI AI-Chat」をいち早くリリースした。現在では、約1万人の社員が日常業務で活用しているという。
同サービスは、資料作成やQ&A検索を安全な環境で行えるのが特長だ。リリース当初はWebアプリ版として提供され、同年12月にはMicrosoft Teams上でも利用可能に拡張。わずか半年余りで機能拡張を実現できたのは、内製化の体制が整っているKDDIならではの強みだろう。
SMBCグループは、Azure OpenAI Serviceを基盤に社内専用AIアシスタント「SMBC-GAI」を開発した。Microsoft Teams上で利用でき、参照元URLの表示やガイドラインの整備によって、金融機関として求められる高い安全性を確保している。
現在、1日あたりの利用件数は約1.2万件にのぼり、2秒に1回のペースで活用されている計算だ。今後は、従業員のプロンプト入力スキル向上を支援する取り組みも進めていくという。金融機関ならではの厳格なセキュリティ要件という課題を、内製化によって乗り越えた事例だ。
参考:SMBCグループが独自に生み出したAIアシスタント「SMBC-GAI」開発秘話
SHIFTは、社内FAQ対応の非効率を解消するため、Azure OpenAI ServiceとDifyプラットフォームを活用したAIチャットボットを自社開発した。これにより、約1.8万件のFAQ対応を自動化し、40人月分に相当する工数削減を実現。
狙いを絞ったAI活用が、業務改善に直結する好例となっている。
参考:「探す手間」に終止符を打つAIボット。SHIFTの哲学が息づく、内製開発の舞台裏
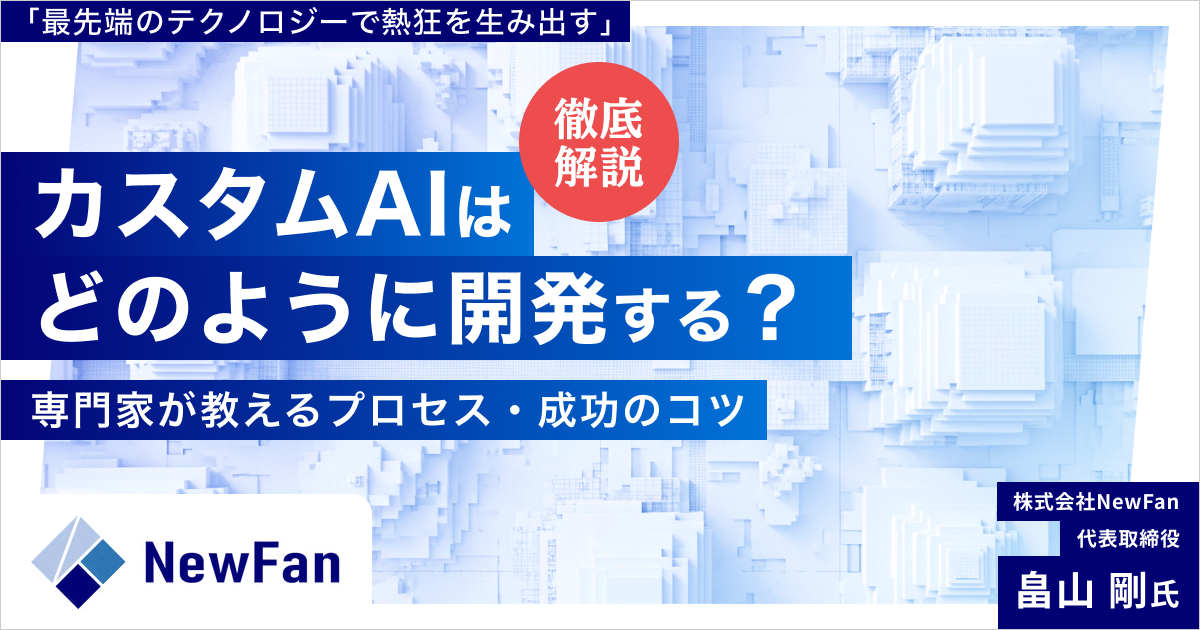
日本国内において、SaaSを全面的に解約する動きは観測されない。しかしその一方で、特定業務に特化したAIツールを内製化する流れは一部で進展している。このアプローチは、安全性やガバナンス(企業統治)を重視する日本企業の経営方針と親和性が高い。
ただし、深刻な人手不足や開発リソースの制約を鑑みると、「現時点」では急速な内製化が広がる可能性は低いと見られる。
画像出典元:O-DAN
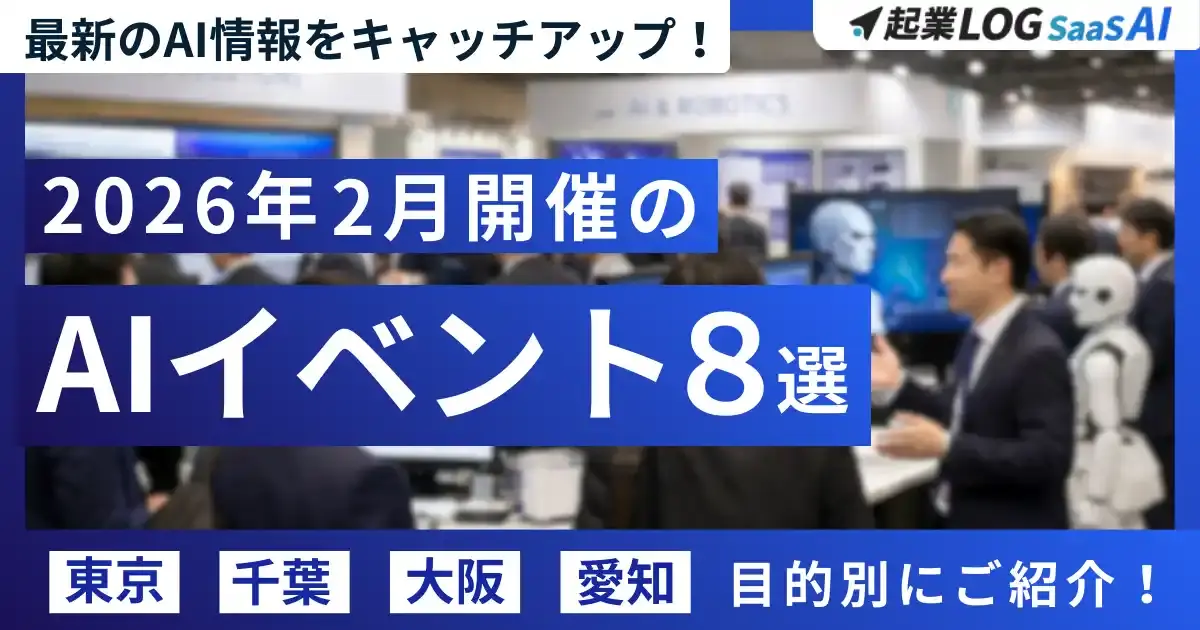
2026年2月開催!注目のAIイベントを目的別に紹介
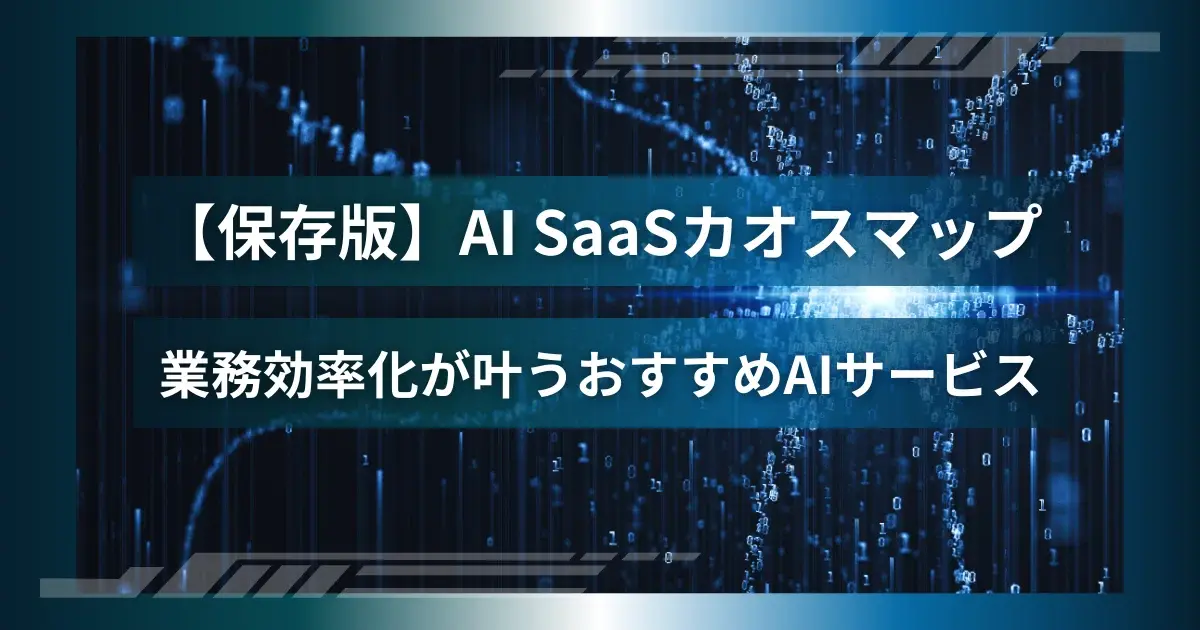
【保存版】AI SaaSカオスマップ|業務効率化が叶うおすすめAIサービス
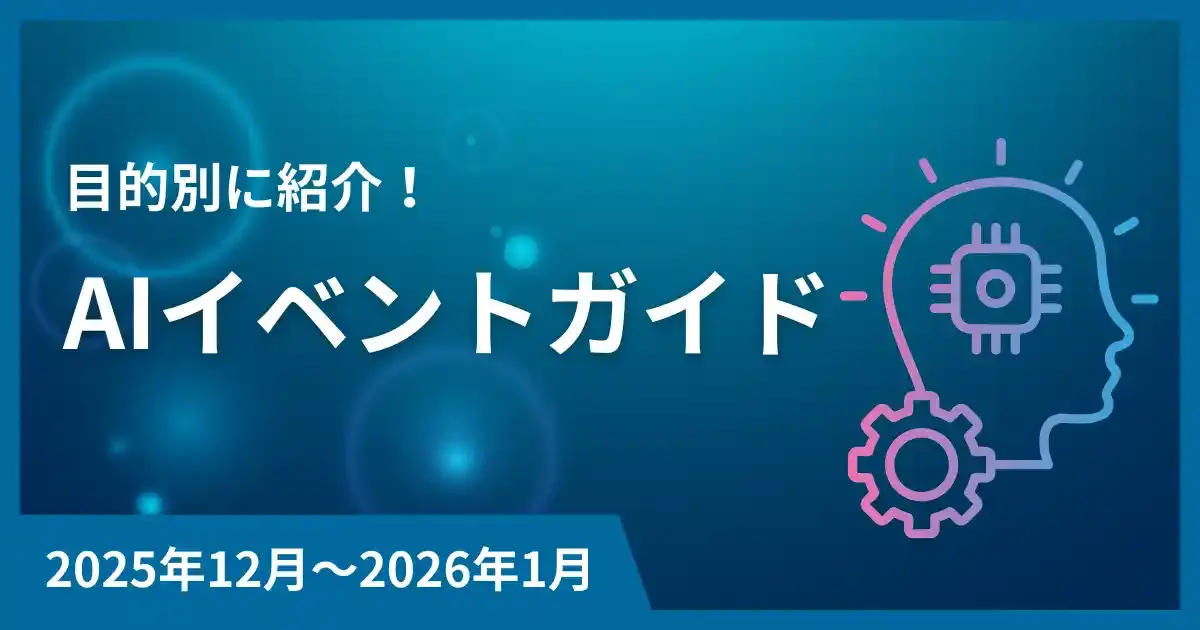
2025年12月~2026年1月開催!注目のAIイベントを目的別に紹介

建築業界のDXはどう変わる?アンドパッド代表・稲田氏が明かす「AI戦略の現在地」

コンプラ遵守は“無理ゲー”?労務課題を社労士とAIが解決したワケ

契約を「守る」から「活かす」へ、AI時代の経営を「データの正確性」で革新するContract Oneの挑戦
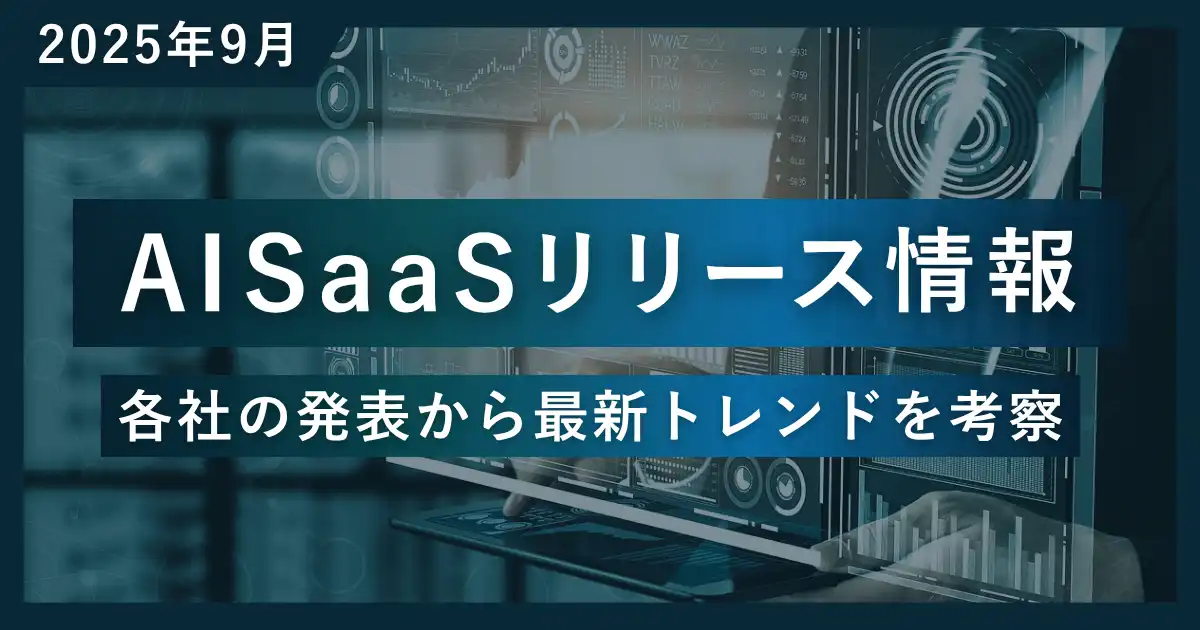
【速報】AI SaaSリリースラッシュ!2026年9月に見る最新トレンド
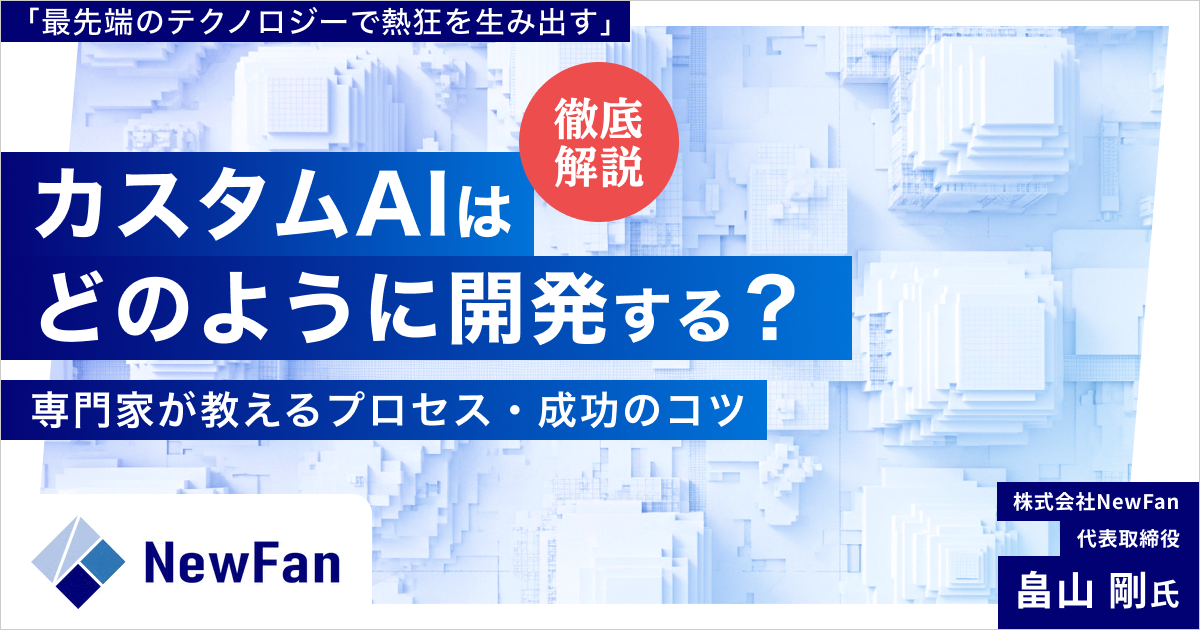
AI開発の進め方を専門家が解説!業務効率化・ナレッジ活用に役立つ、カスタムAIの第一歩
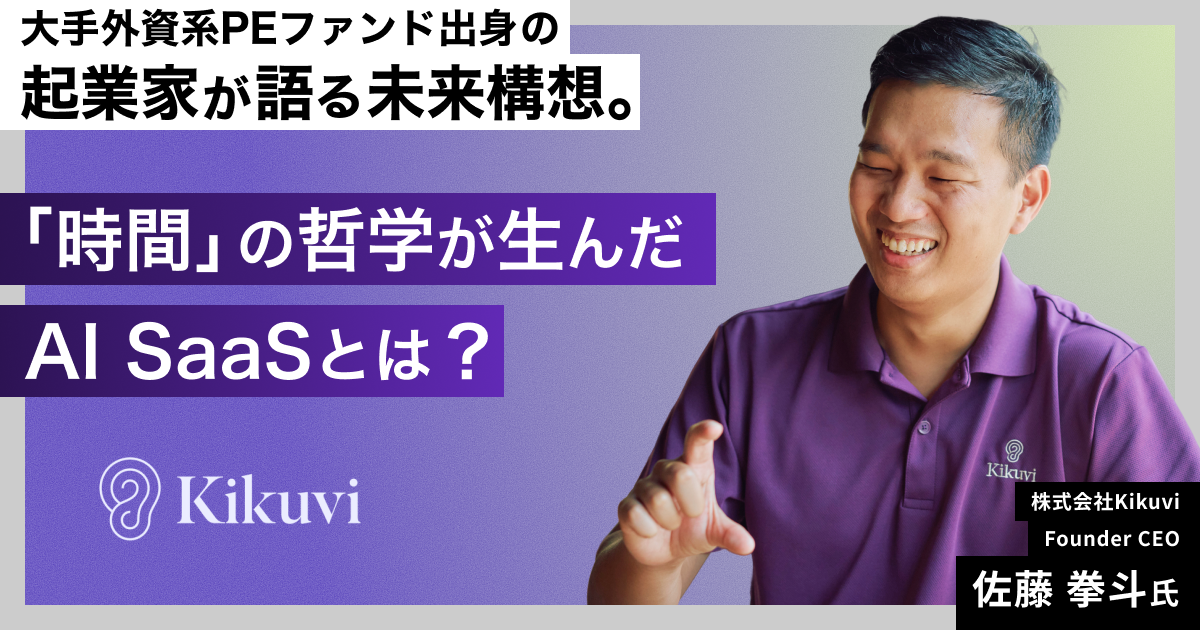
大手外資系PEファンド出身の起業家が語る未来構想。「時間」の哲学が生んだAI SaaSとは?

AIでSaaS営業の働き方は変化する。業界を俯瞰して「営業担当の未来」を考察